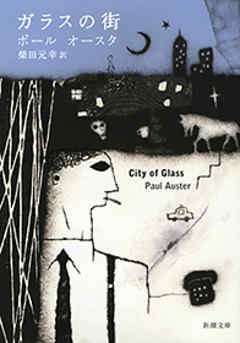あらすじ
「そもそものはじまりは間違い電話だった」。深夜の電話をきっかけに主人公は私立探偵になり、ニューヨークの街の迷路へ入りこんでゆく。探偵小説を思わせる構成と透明感あふれる音楽的な文章、そして意表をつく鮮やかな物語展開――。この作品で一躍脚光を浴びた現代アメリカ文学の旗手の記念すべき小説第一作。オースター翻訳の第一人者・柴田元幸氏による新訳!
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
物語の中に著者が出てくるメタ要素がある中で、同じくメタ要素のあるドン=キホーテをとりあげるというユーモアさもありつつ、妻と息子を失った主人公の虚無感ゆえの自己の抽象化と、そこから起こる探偵物語のような展開に惹き込まれる。
どうなっていくんだろうと没入するほど、奇妙に歪められた世界を見ることになった。
結論から言うと解決はされていない。
俎上に載せられた問題は何もわからないまま、物語の幕は閉じる。
真実の物語なのだから、常に答えが用意されているとは限らないよね、という感じなのか。
それでも、面白い。
個人的な読字体験として、プルーストとイカ〜読字は脳をどのように変えるか〜を併読していて、文字や言葉を人間がどのように習得していくのかについて考えていたので、作中のスティルマンが犯した実験や考察については興味深く読めた。
読書を通じて得られる、別の物語が別の物語とシンクロする体験は大好きだ。
Posted by ブクログ
ニューヨーク三部作の一作目。
ポール・オースターに間違われた作家クインが、他人に成り代わり探偵の真似事を始める。
自分がクインであるという事実が、気が付かないうちに次第に薄れていく。肌身はなさず持っていた赤いノートだけが証拠に。まさか、こんなに儚い話だとは思わなかった。
オースターの文だから?それとも柴田さんの訳だから?流れるような文体が心地良かった。
Posted by ブクログ
そもそも、最後の視点は誰?
途中も急に視点が変わって、え?ってなった(笑)んで、駅でなんでピーターが2人いたんだろう、これはクインの書いた小説か?
ちょっとわからないことが沢山あるけど、間違い電話から始まって、興味本位で探偵することにした設定は物凄くいいよね。
ニューヨーク3部作、全部読んでみよう。
Posted by ブクログ
ある小説家クインがポール・オースターという探偵に間違えられた電話が来て、演じ切ることを決意する。幼少期から言葉を与えずに監禁された子供と、そうすることで神の言語が現れるとした父親に関する事件だ。数年前に父親から殺害予告じみた手紙がきて、もうすぐ精神病院から父親が帰ってくるから監視及び警告してくれという依頼だ。クインはそれに則り数週間スティルマンをつけることにする。最初にスティルマンをみつけ駅でつけていた時に、スディルマンは2人に分裂していた。クインは直感的に古びたように見える方のスディルマンを選ぶ。そこから奇妙な歩き方をし、ガラクタをひろうスディルマンを、赤いノートにしるしながらつける。ストーキングというものは相手と一体になることだ。しかし一切怪しさがなく、2週間が経った時とうとう接触してみることにした。最初にはベンチで、次は喫茶店、最後に大岩の上?(うろ覚え)。話しかける度にスティルマンはクインのことを忘れていた。最後の時には息子を名乗ってみたら信じ込み、格言と謝罪と愛を与えてくれた。
ここから話が急カーブ。スティルマンを1晩のうちに見失ってしまった。それをヴァージニア(依頼人の嫁)に伝えることを渋り、本来のオースターという探偵を探すことにする。同姓同名の人物がいたので尋ねてみると、自分の本を読んでいる作家だった。ここで劣等感を感じ、さらにはヴァージニアからのでうわを無視してしまい転落し絶望。何とか気を取り戻して、ヴァージニア夫妻の家を衣食住を犠牲にしながら2ヶ月見張り続けた。ある日金が尽きてそれも終わり、オースターに依頼金の譲渡を取り消す用取り測ろうと電話をしたところ、スティルマンの自殺を告げられる。自室呆然としつつもなんとか我が家に帰ると、そこは取り払われ、新しい女が住んでいて、今は亡き息子と嫁の写真諸共すてられていた。最後にヴァージニア夫妻の家を尋ねるも又もぬけの殻。そこで、スティルマンをつけていた時にや事件記録として最初から使っていた赤いノートに思考を書きながら、終わる。オースターの友人がこの赤いノートを発見し、このガラスの街という本を書いた。
ものすごい急展開。ポール・オースターの本は前半と後半で内容がうってかわり驚く。神の言語やスティルマンの不気味さは後半には消えていて、1度の間違いや怠慢自己欺瞞が招く悲劇や、オースターによく見られる父性愛がでてきた。これを味わいたいので良し。たださすがに前半後半どちらも不完全燃焼感がある。1連の物語を読むと言うよりも、文章や断片的な情景を楽しんだ方が良さそう。探偵小説は全てに意味があるからいい、だとか、言語についての言及や、神の言語だとか、放浪だとか、なにより老人と中年男性の親愛だ