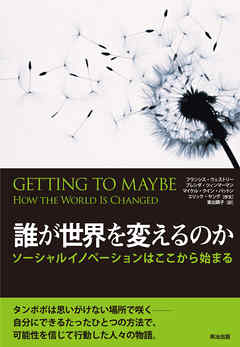あらすじ
ひとりの一歩が、こうしてすべてを変えていく
人は誰でも、世の中の現実に不満や疑問を抱くことがある。身のまわりの世界を、よりよいものにしたいと望む瞬間がある。だが、私たちは、社会を変えるのは一握りの偉大な人々だと考えがちだ――が、そうではない。世の中の変化は、時代の流れは、意外なところで生まれるのだ。
ソーシャルイノベーション――劇的な社会変革は、物事を個別に見ることをやめ、社会のシステムを構成するさまざまな要素間の関係をつかむことから始まる。この「システムと関係」のレンズを通して、本書は人と人、個人と集団、人と社会の間にひそむ関係性のルールを明らかにする。
犯罪を激減させた“ボストンの奇跡”、HIV/AIDSとの草の根の闘い、いじめを防ぐ共感教育プログラム、失業・貧困対策、自然保護、障害者支援……それぞれの夢の軌跡から、コミュニティを、ビジネスを、世界を変える方法が見えてくる。インスピレーションと希望に満ちた一冊。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
2020.31
改めて読み直し
・「Getting to Maybe」というタイトル。直訳なら、かもしれないを目指す。
その日本語タイトルは、「誰が世界を変えるのか?」というオシャレさ。
・発展的評価指標なるものがある
Posted by ブクログ
ソーシャルイノベーションを起こした事例がたくさん書いてある。ソーシャルイノベーションが起こるところ、持っている課題なども赤裸々に綴ってあるので、そこの潔さも面白かった。ソーシャルビジネスをして、それがイノベーションになるのか本当に迷ったときにもう一度読みたい。大事なのは信じるこころ。Maybeの領域でもいかに信じきれるか。まぁそんなことが伝えたいところなのかも。
Posted by ブクログ
Getting To Maybe
不確かな世界で、ただ立ち竦むのではなく、不確実性をも呑み込んで、一歩前に踏み出してみよう‼…と思わせてくれる一冊。
■書評ではない自分史的散文
レビューを書こうと思ったが、もう既に多くの方がまとめているので、私は、私自身がこの本から、何を感じ、何を考え、どう動いているのか⁈…について書いていきたいと思う。
この本とは、約4年前、友人の結婚式で横浜に行ったとき、待ち時間にふらりと立ち寄った駅中の本屋さんで出逢った。
駅前の大きな木の下のベンチに座り、風に吹かれながら、時を忘れて読み進めた。都会の青空の下、久々に凄まじい解放感を味わった…気持ち良かった。
当時の私は漠然とした理想にもれなく付いてくる、漠然とした不安の中で、夜はひとりの世界で万能感に浸り、朝は現実を突き付けれ、打ちのめされる…そんな日々を送っていた。※1
何かを変えたい‼…という思いはあるが、何をどう変えればいいのか分からない…自分の進むべき道など皆目検討が付かず途方に暮れていた。※2
そんな時に出逢ったのがこの一冊だった。この本には、世界に翻弄されながらも、自身の情熱と向き合い、思考し、動き続ける人々の姿が描かれてた。
動いてみても何も変わらないかもしれない、だけど、もしかしたら何かが動き出すかもしれない…と私は感じた。
単なる頭デッカチで、悶々としていた私は、そろそろ現実と向き合い、逃げることなく、自分の足でフィールドに降り立ち、具体的に動き出してみよう‼…この世界に打って出よう‼…何かに挑戦してみよう‼…と思った。※3
こうして、私のソーシャルアクションがむくり&始動‼したのだ。
つづく
※1
その頃、まちづくりに携わりたい、と思い地元に帰って来た私は、消防という仕事をしながら、社協主催の災害ボランティア講座に参加した有志と「災害につよい足利つくる会」という市民活動団体を立ち上げ、防災に関わる展示会や公民館などでワークショップを開催していた。
当時から防災に関わるワークショップの意義や可能性について認識しつつも、具体的に何かが変わる…という感覚が感じられず、この動きは本当に意味があるのか⁈これが俺のやるべきことなのか⁈…と悶々とした日々を送っていた。
※2
理想と現実とのギャップに立ち竦む…という表現の場合、課題が明確になっているので、何からどう手を付ければいいのか⁈…ということを考えればいいので、比較的、建設的な思考回路を発動させやすいのだが、当時はそれ以前の段階だった。
※3
この本を読んでいて、ふたりの恩師の言葉を思い出した。
「可能性への挑戦」・・・小学校の担任の先生が卒業式に、和紙に墨で綴り、額に入れて送ってくれた言葉。
「フィールドを持たない学者はただのバカだ」
・・・学生時代にお世話になった教授の言葉。彼は脳梗塞で一度倒れてからもフィールドに立ち続け、臨場感ある言葉で語り、我々学生の心に火をつける天才だった。
Posted by ブクログ
トリガーワード:今ここ、「かもしれない」、単純なルール、変化、思考は行動の一部、つながり、ソーシャルイノベーション
この本のポイントは、「思考は行動の一形態である」ということだと思う。個人個人の思いが世界を形作っている、そしてその思いが行動となってイノベーションを起こす、そして世界が変わっていく、という流れだ。「どうせ思い通りにならない」とふてくされてないで、「思いも行動」「『かもしれない』を目指す」と思えば、気軽に行動につなげられるように思った。勇気が出る一冊。
Posted by ブクログ
カール・ロジャーズの「エンカウンター・グループ」論と同じほどの感銘を受けた。両者には明らかに通低するものがある。
多数の事例から得られる知見の紹介は卓抜な箴言にあふれる。
ここ数年間抱えていた組織と個人にかかわるさまざまな課題に対する多くの洞察だけでなく、自分の生き方にまで指針を与えられた。
このような素晴らしい本を教えてくれたYに感謝。
Posted by ブクログ
小さな変化が世界を変えるほどの影響を及ぼす。
社会起業家の実例を踏まえながら複雑に入り組む要素を丁寧に解説しており、結論がなく混沌としがちな複雑系の本の中でもダントツに分かりやすく、スラスラ読める。
各章の冒頭に載っている詩も含蓄があって考えさせられる。終始惹きつけられたが特に自分に影響を与えてくれそうな言葉はこれ
・「世界があなたを見つけるのだ」
変化のフローを見つけ出せば自分でも思いもよらなか った劇的効果を生み出す。
変容を生み出すエネルギーが社会起業家に利用される のを待っているのだ
Posted by ブクログ
第1章 暮れ始めの灯り
・複雑性は可能性を意味する
第2章「かもしれない」をめざす
・世界は驚くほど単純なルールで動く
・社会起業家はルールを変える
第3章 静思の時
・社会起業家は行動しながら考える
第4章 強力な他者
・権力と巧みにわたり合う
第5章 世界があなたを見つける
・自己組織化
第6章 冷たい天国を生き抜く
・孤独と絶望に屈することなく
第7章 歴史と希望が韻を踏む時
・ソーシャルイノベーションが日常になる
第8章 ドアは開く
・ドアはただのドア
・結局、だれが社会を変えるのか
Posted by ブクログ
誰が世界を変えるのか
変えたいという思いを持ちそれをなんとしても実現させる強さをもったごく普通の人たち
次はあなたの番だ!的な
行動するだけ!的な
たくさんのいい言葉に会えた
Posted by ブクログ
「誰が世界を変えるのか」その言葉に胸がドキドキした。
純粋にその答えが知りたくて本を読んでいた。しかし、正解はないのかもしれない。
本書には、「かもしれない」という不確実なものに対して立ち向かっていく世界中の様々な人たちが描かれている。その人たちは、のちに社会起業家といわれる有名人というより、「この状態を何とかしたい!」という使命感に駆られた勇気ある一般人の姿だ。
私は、紹介されていた方への敬意と感謝の気持ちでいっぱいになったが、一方で「果たしてソーシャルイノベーションを起こしてきた人自身の人生は幸せであったのか?」という問いを持たずにはいられなかった。その理由は、きっとこの本を最後まで読めば分かってくれると思う。社会起業家と呼ばれる彼らにスポットライトが当てられがちだが、その周りにいる人たちの姿にも目を向けて読んで見て欲しいと思った。
そして、ソーシャルイノベーションの定義について本書ではこう述べている。
”社会起業家は、絶望と可能性、悲鳴と産声、始まりと終わりを同時に経験するかもしれない。はっきりいえば、この経験が、ソーシャルイノベーションの成功の定義なのだ。”
成功をも障害として、傲慢にならずに淡々と道を切り開いていく。その道筋が見えてくる一冊だった。
内容があまりにも濃かったので、この本をもう一度読んで、考えを整理したいと思う。
Posted by ブクログ
複雑系を踏まえたリーダーシップのあり方について、つぎつぎと良書を翻訳、出版している英治出版からの1冊。
「社会変革に取り組む人たちの感動の物語が沢山、入っているのかな。たまには、そういう話も読んで、元気をもらおう」という感じで、読み始めたのだが、書き方は非常に客観的、理論的である。
そういう意味では予想と違ったのだが、個人的には、これは結構、最近の関心事にぴったりの本だった。
つまり、「複雑系的な世界のなかで、支援的なリーダーシップによって、創発的な変化が生じる」という本は最近結構多いし、共感するところも多いのだが、「そういうことをいったって、いつもそんなにうまく行く訳でないでしょ。うまく行く可能性をあげるためにはどうするのだろうか。理想主義的なアプローチだけでは、世の中は変えられないので、政治的なものとどう折り合って行くのか。うまくいっても、すぐ悪くなることは多いよね」などなどの疑問もわだかまっていた。
という疑問にストレートに答えてくれる本である。
この本の原題は、getting to "maybe"である。つまり、maybeにかけてみるという生き方なのだ。can-beやwill-beではないのだ。それでも、世界の悲惨を見たときに、思わずドアを開けてそこに出てしまう、いや、閉じていると思っていたドアは開いているのだ。その先にまっているのは、奇跡のようなプロセスであったり、絶望であったり。。。。
そんな苦しい道を何故歩むのか?彼らが英雄だから?
いや、calling、呼ばれるからなのだ。あなたが使命を見つけるのではなく、使命、いや世界があなたを見出すのだ。
社会変革は、「あなた」なしにはないと同時に、「あなた」なしでも自然に起こる物である。
内容的には、★5つなのだが、書き方がもう少し物語風だったら、良かったかな、と思う。
Posted by ブクログ
ミラツク・西村さんのオススメで読んでみた。まだ私には分からないところもいろいろあったけれど、なるほど!と共感・納得するところがたくさんあった1冊。
巻末の『「かもしれない」を目指すには、HOW TO GET TO MAYBE』がすごくよくまとまっていてわかりやすい。
Posted by ブクログ
冷たい天国・
直接ほんの内容にはあまりかかわりがないけれども
ホテル・ルワンダで国連軍!おい!って思った。
ものごとの一面しか見ないとはこのことか、と実感している。
Posted by ブクログ
今ではすっかり有名になったグラミン銀行を含め、ソーシャルイノベーションの事例を丁寧に掘り下げながら、社会的な課題を「複雑系」として捉え、学習と創発を伴うイノベーションこそがその解決手段であるとする著者達の主張は納得感が高い。
チクセントミハイの「フロー体験」やミンツバーグからの引用、さらには「学習する組織」や「U理論」にも通じる部分があり、複雑さのレベルに違いはあれど、何らかの「変革」に携わる人なら、誰もが多くの気づきを得られるに違いない。
Posted by ブクログ
「かも知れない」を目指す。Getting to Maybe.
ごく普通の人が、想いを抱き、ちょっとしたタイミングに恵まれ、世界を少しだけ変える大いなる動きの中心となる。また、その部分となる。
自分のビジネス、ソーシャル活動の両方に活かす事の出来る考えを得られました。なんか背中を押された気持ち!!
Posted by ブクログ
正直期待外れ
社会企業家を目指す人がモチベーションを上げるために読むのならば、
アリかもしれない
だけど、この本から社会企業家を目指す上での何かを学ぼうとするのならば、対して意味はないように思われた
なぜなら、社会企業家を目指そうと思った時点で、
この本に書いてある内容くらいのことは、すでに考えているのが当然だと思うからだ
なので、何か知識とか、実際に役立つスキルとかセオリーみたいなものを知りたいのであれば、読む必要はないかと感じた
Posted by ブクログ
やっぱり、自分の振る舞いが世界を変えるきっかけになったら、興奮するんだろうな、なんて思って買ってみた。必ずしもソーシャルイノベーションという手段に何か感情を持っているというわけではないんですが、最近はこういうアプローチが必要なんだな、と改めて実感。
Posted by ブクログ
具体例が散乱していて、わかりにくい。
しかし、何となく社会企業家について分かる。
各章の最後にまとめが載せてあったらもっと良かったと思う。
おしいので星3つ!
Posted by ブクログ
Referred by Nikkeinews 20080928 日曜書評
本書は、社会起業家の思索と行動が他の人々を突き動かしていく過程を描きつつ、社会変革が起こる力学を複雑系の理論で解き明かそうとしている。
本書には、ムハマド・ユヌス氏などが登場するが、その目的はリーダーを称賛することではなく、社会を変えたいと考える人々に羅針盤を示すことにある。著者は「単純」「煩雑」「複雑」の三つを区別し、それぞれ例として「ケーキを焼く」「月にロケットを送る」「子供を育てる」をあげる。子育てが複雑なのは、「親と子が互いに影響を与えあう関係にあり、子供の個性も一人ひとり異なるからだ。育児書通りにしてもうまくいく保証はない」と指摘する。
それと同様なのが、社会変革。事前に描いた綿密な戦略も成功を保障するものではない。著者は、社会起業家は、「不確実性を恐れない使命感がいる」という。日本の代表格は、ヤマト運輸の小倉昌男氏。障害者の賃金の低さに憤り、月給を十万円に引き上げる目標を掲げて奔走し、実現された。口癖は、「やればわかる。やらなければ分からない。失敗したらやり直せばいい」だった。
社会変革が実現するのは、多くの人が「世の中は変わらない」とあきらめ顔をしながら、心底では「変えるべきだ」と感じているからなのだろう。社会起業家が行動で変革の方向を示せば、他の人々も少しずつ「変えられるかもしれない」と思いだす。
共感する人々とのネットワークづくりも重要なカギだ。