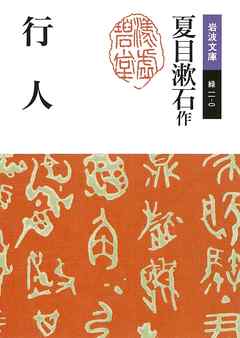あらすじ
妻お直と弟二郎の仲を疑う一郎は妻を試すために二郎にお直と二人で一つ所へ行って一つ宿に泊ってくれと頼む……。知性の孤独地獄に生き人を信じえぬ一郎は、やがて「死ぬか、気が違うか、それでなければ宗教に入るか」と言い出すのである。だが、宗教に入れぬことは当の一郎が誰よりもよく知っていた。 (解説・注 三好行雄)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
漱石の手に心臓を掴まれた気がした。
第四章『塵労』は読んでいて苦しい。
「ああおれはどうしても信じられない。どうしても信じられない。ただ考えて、考えて、考えるだけだ。二郎、どうかおれを信じられるようにしてくれ」
「僕は死んだ神より生きた人間の方が好きだ」
「死ぬか、気が違うか、それでなければ宗教に入るか。僕の前途にはこの三つのものしかない」
「僕は迂濶なのだ。僕は矛盾なのだ。しかし迂濶と知り矛盾と知りながら、依然としてもがいている。僕は馬鹿だ。人間としての君は遥に僕よりも偉大だ」
「どうかして香厳になりたい」
ああ、苦しい。
駄目だ。
泣く。
Posted by ブクログ
弟の二郎と妻お直との仲を疑う、学者である兄の一郎の苦悩を綴った作品。
高校時代の国語教師は「漱石は女を不可解な存在と感じていた」と論じたのを覚えている。
本作や「彼岸過迄」を読むと、漱石が「不可解」だったのはおそらく、女のみならず全ての他者、特に、最も近しいはずの身内ですら、その「不可解」の対象だったのではないかとすら感じる。
他の方のレビューに目を通すと、その感想には、概して一郎へ共感したかどうかの分かれ目があるように思える。
だがそれは、他の方々が一郎へ共感したかどうかを重要視したのではなく、個人的には、はたして他人は一郎のような苦悩を抱えたことがあるのかどうか、が気にかかったのだ。
正直に記せば、子どものころからぼんやりと、大人となったいまではより明確に、本作の一郎や「彼岸過迄」の須永のような苦悩を感じることがたびたびある。
ただ、その苦悩の原因はおそらく、他人に受け入れてもらえないということではなく、他人を受け入れない性質のせいか、どこか他人も自らを受け入れないのではないかという懐疑を基にしているではないかと、最近つくづく思う。
本作や他の漱石作品から感じられるのは、自らと同様に、彼自身もそのような苦痛を抱えていたんだろうということ。
そしてそれは、「近代人の苦悩」と簡単な言葉で片付けられるほどではなく、彼自身とともに自らもいまだ苛まれている重要な命題なのだと思う。
また、自分自身にとっては、明治の世から自らと同じ悩みにとらわれている人間がいたことを慰みとするわけでもなく、結局、これから先も、この苦悩を抱えていくしかないことに気づかされたに過ぎないのかもしれない。
10年以上前、学生のころ読んだのだが、最近、青空文庫のものを再読した。
なので本来は再読かもしれないが、以前読破してからだいぶ月日が経つので、改めてこちらに感想を記した。
Posted by ブクログ
聡明な頭脳を持つ哲学者である兄。それゆえに思考のみが先走り、本人が望んでいる行動に移せない。行動に移るなら愚鈍でなければならない。それにもなれないという哀れさ。
中盤で、兄が自分の妻の貞操を確かめる場面があるが、あの時どちらに転んでも兄は同じ反応を起こしたのではないだろうか。
自分で妻に対して聞きただしたかった。しかしそれができずに弟に頼む。結局何もないにも関わらず、兄は弟に対して癇癪を起こしてしまう。
「自己本位」という漱石について使い古された言葉を念頭において考えれば、ここでは「受身な我儘」がテーマになっていたのではないか。
妻に何も言えず、弟に任せる兄、ふと縁談が勝手にまとまってくれれば良いと思う私、兄を疎ましく思うもなんら処置を下せない家族、自然のままに流そうとする三沢、これら全員が受身な我儘を持っている。その根底にあるのは決定に伴う責任を回避したいという甘えではないか。
「君は山を呼び寄せる男だ。呼び寄せて来ないと怒る男だ。地団太を踏んで口惜しがる男だ。そうして山を悪く批判する事だけを考える男だ。なぜ山の方へ歩いて行かない」
Hのこの言葉がそれを表していると思う。
唯一自己の愚鈍を主張している嫂の直とHはこれとは違うと思った。
「今の日本の社会は――ことによったら西洋もそうかも知れないけれども――皆な上滑りの御上手ものだけが存在し得るように出来上がっているんだから仕方がない」
この言葉がそれを代弁している。
長々と愚説を書きましたが、読み物として普通に面白いです。一読あれ。
Posted by ブクログ
非常に思いテーマを扱っている小説だった。一郎のように、知識や研究に生きる人にしか理解できない苦悩があるのだろう。なにもかもを分析して研究して理解することはすばらしい事だけど、人の心はそうはいかないものだと思う。それでも、理解して解釈しないでは居られないということ自体、どれほど苦痛だろうか。決して、解決されるような問題ではないのだから。
知識人ゆえ、一つのところに留まれない苦痛は、死ぬか狂うか宗教に入るかというところまで一郎を追いつめている。私自身は一郎のように知識人ではなく平凡な人間で、一郎ほど思い詰める事も無いから理解しがたい部分もあるけど、ただ、ひとところに留まれないような感覚、焦燥感に近いもの、そういうのは分かる気がした。それは誰でも、どこかで感じることなのかもしれないなって思う。何も考えずに生きるという事のほうが、実は難しいのかもしれない。
Posted by ブクログ
聡明な頭脳を持つ哲学者である兄。それゆえに思考のみが先走り、本人が望んでいる行動に移せない。行動に移るなら愚鈍でなければならない。それにもなれないという哀れさ。
中盤で、兄が自分の妻の貞操を確かめる場面があるが、あの時どちらに転んでも兄は同じ反応を起こしたのではないだろうか。
自分で妻に対して聞きただしたかった。しかしそれができずに弟に頼む。結局何もないにも関わらず、兄は弟に対して癇癪を起こしてしまう。
「自己本位」という漱石について使い古された言葉を念頭において考えれば、ここでは「受身な我儘」がテーマになっていたのではないか。
妻に何も言えず、弟に任せる兄、ふと縁談が勝手にまとまってくれれば良いと思う私、兄を疎ましく思うもなんら処置を下せない家族、自然のままに流そうとする三沢、これら全員が受身な我儘を持っている。その根底にあるのは決定に伴う責任を回避したいという甘えではないか。
「君は山を呼び寄せる男だ。呼び寄せて来ないと怒る男だ。地団太を踏んで口惜しがる男だ。そうして山を悪く批判する事だけを考える男だ。なぜ山の方へ歩いて行かない」
Hのこの言葉がそれを表していると思う。
唯一自己の愚鈍を主張している嫂の直とHはこれとは違うと思った。
「今の日本の社会は――ことによったら西洋もそうかも知れないけれども――皆な上滑りの御上手ものだけが存在し得るように出来上がっているんだから仕方がない」
この言葉がそれを代弁している。
長々と愚説を書きましたが、読み物として普通に面白いです。一読あれ。
Posted by ブクログ
「君は結婚前の女と、結婚後の女と同じ女だと思っているのか」という一郎のセリフが、この作品の恋愛感を端的に示しているような気がします。一妻と弟の二郎の間を疑う一郎は、ついに妻を試そうと決心をする。そして最後に、一郎は孤独な悩みを抱え込むようにんっていきます。新三部作の第二作目です。
Posted by ブクログ
非常に印象深い作品。
絶対と相対と依存と矛盾と葛藤。
そういうものの存在に、人生で初めて直視させられました。ラストの描かれ方がものすごく、好きです。
Posted by ブクログ
涼しい顔して平気でニートが不倫する話ばっかり書いてる漱石先生には毎回やられっぱなしっすわー!このチョビヒゲ!
ごめんこの話の主人公はちゃんと働いてたわ。珍しいことに。
「キミは山を呼び寄せる男だ。呼び寄せて来ないと怒る男だ。地団太を踏んで口惜しがる男だ。そうして山を悪く批判する事だけを考える男だ。何故山の方へ歩いて行かない」
いやー、そう言われっちゃうとなー。
Posted by ブクログ
後期三部作『彼岸過迄』と『こころ』の間を埋めるニ作目。
『行人(こうじん)』は、道を行く人=旅人という意味。読み終わってみると、物語の終盤を暗示しているタイトルかな。
前作『彼岸過迄』同様に、「友達」「兄」「帰ってから」「塵労(じんろう)」の四篇から構成されていますが、「帰ってから」と最後の「塵労」との間が半年近く空いています。これは、胃潰瘍の再発のせいですが、中断する前後で話しの構成が変化しています。語り手が変わるところなどは、後の『こころ』に繋がるプロットが、この『行人』で試みられたのかなと思いました。
内容は、語り手である次男が、兄から「はたして妻はじぶんを愛しているのだろうか」という疑問を投げかけられたことから、本筋が動き出します。
そんな事には頓着しない嫂のクールなところが、激しやすい兄と真逆ゆえに、話しがもつれながら進んでいきます。
終盤には、禅問答の『無門関』第二十三則が後半に出てくるなど、頭が良すぎる兄の苦悩が描かれて、はっきりとした結末が示されないまま、静かに幕を閉じます。ただ、どうにもならない結末ともいえ、これで良かったのかもと思いました。
余談ですが、読書家の坂本龍一さんが、亡くなる数年前に読んでいた本に『行人』が入っていたとのこと。『無門関』も読まれていたようです(『婦人画報』2023年11月号の巻頭特集記事)。
Posted by ブクログ
後期三部作の2作目。
後期三部作は話としてつながるように意図された作品ではなく、各作品で方向性は違うのですが共通のテーマを持った作品となっています。
彼岸過迄では、須永がその気もない女性であるはずの千代子に縁談が上がるや否や嫉妬の炎に身を燃やすというエゴイズムと、そんな己の感情に苦しめられる様が描かれていましたが、本作においても自分と外界のギャップを許容できず苦しむ男が描かれています。
彼岸過迄では須永がコントロールできない感情からエゴにまみれた嫉妬をしてしまう話でしたが、本作は彼岸過迄よりテーマとしてはもう少し昇華していると感じました。
主人公の兄・長野一郎は学者で、何事も深く考える性質があり、聡明さ故に不器用で、頭ではわかっているが受け入れることができない、現代においても持ちうる悩みを持っています。
考えさせられると同時にまた、自分は他者とは異なるという当然の事実を再認識させられるような作品でした。
内容は4つの短編に別れています。
彼岸過迄とは違い、各短編によって主人公が異なるということはなく、主人公は同一です。
ただ、実際的には長野一郎に関する物語であり、主人公である長野二郎は狂言回し的なポジションとなっています。
一章では、「長野二郎」が友人の三沢と落ち合う約束をし、大阪を訪れる。親戚の岡田の元に身を寄せて三沢を待つのですが、なかなか連絡が来ない、そんなある日、三沢が大阪の病院に入院しているという手紙を受け取るという話。
一章は導入としてのようなストーリーで、二章より長野一郎が登場します。
二章は長野二郎とその兄「長野一郎」、二人の母、そして嫂の「直」が大阪に訪れる。自分に対する態度とは違い、二郎に親しげな直を信用できない一郎は、二郎に直と二人で一泊して貞操を試してほしいと頼むという話。
以降は一郎がメインキャラとして描かれており、一郎の性質、苦悩にスポットされた展開となっています。
感情の起伏が比較的激しい一郎と異なり、嫂の直はクールなキャラクターとして描かれていて、二郎もまた感情を読みにくい彼女に翻弄されるのですが、個人的にはそこが楽しかったです。
直はクールですが傲慢さはなく、神秘性の高い女性として描かれており、私的には、恐らく夏目先生も予期しなかった艶っぽさのようなものを感じました。
一郎は端的にいうと面倒な性格で、人が感じていながらもうまくやっていく部分を許容できずに狂ってしまうのですが、本作中にはそのアンサーのようなものはなく、物語は静かに終幕します。
結局のところその問に答えはなく、深く考えることをどこかで放棄するしかないのですが、その終わらない問を投げかけてくるような作品でした。
Posted by ブクログ
「こころ」と同様、最後は不自然なくらい厚い手紙を主人公が受け取り、
その中身を長々と綴って物語は終わる。
「行人」は「こころ」の前作であるから、同じ手法を連続で用いて
幕引きを行ったことになる。漱石にマンネリがあったとは考えにくい。
一体、そこにはどのような理由があったのだろうか。
また、登場人物が精神異常になる展開は漱石にとって珍しい。
ある意味、自殺よりも衝撃的な顛末である。
Posted by ブクログ
本当は裏でこう思っているのではないか。そう疑い始めたら、人付き合いは苦しくて仕方ない。普段そういうことを考えない習慣を自然と身に付けているんだろう。一郎のように突き詰めたいという衝動とそれに向かって行けば行くほど幸福から遠ざかる。ではどこまで妥協すればいいのか。どこまで見て見ぬ振り、意識的な「思い込み」をすればいいのかー。そういう煩悶を共感してくれる者もいない。ただ、三沢という受け止めてくれる人がいてくれたことが、ものすごく救いになってるように思えた。
Posted by ブクログ
「死ぬか気違うか、そうでなければ宗教に入るか」
学問をやりすぎたために、人を信じられず、妻さえも自分を愛していないのでは無いかと疑い出した一郎。
その弟の二郎は兄や友人、下女など様々な人の使いとして結婚とは何か、愛とは何かの現実を見る。そんななか、どうしようもないほどに精神衰弱な兄の影響を受け、二郎も結婚について疑問を抱き始める。
この作品の底にあるテーマは結婚に関すること、人を信じること。明治以前の家が関わる旧式の結婚制度、恋愛結婚などなど様々な形で夫婦になり、こどもが生まれ、年をとる。
そうした、夫婦間の関係について、疑問を投げかける作品です。
漱石作品として相変わらず、登場人物に起こる出来事に方を付けないで終わりますが、ストーリーとしてもなかなか面白い。一郎の精神衰弱ぶりには辟易する人もいるかも知れませんが、頭の良い人特有の悩みに共感を覚える人も少なくないはずです。
胃を痛め精神を病みながら漱石が書いただけあり、彼の作品の中でもなかなかの読み応えでした。
Posted by ブクログ
【概要・粗筋】
学者である一郎は、妻・直の本当の気持ちがわからず、信じることができず、夫婦の間は冷え切っていた。直はそのようなこと気にするそぶりもなく冷淡であった。しかし、一郎は妻の本心が知りたくてたまらない。そして、一郎は妻の貞操を試すために、弟である「自分」に嫂と二人きりになるよう依頼する。知識人の孤独と狂気を描いた小説。
【感想】
第一章「友達」から第三章「帰ってから」までと第四章「塵労」では作品の雰囲気ががらりと変わった。三章までは長男夫婦の不和に周りの家族が巻き込まれていくというある平凡な家族の姿を描いていたのに、四章からは一郎の内面が掘り下げられて家庭小説の枠をはみ出した。雰囲気ががらりとかわった。私としては三章までの雰囲気が好きだ。
周りからは冷淡と見られ、何ごとにも動じない強さを持った女性である直が、二郎に時折見せる淋しげな微笑みや砕けた態度が魅力的である。うっちゃっておけず、その本心を知りたいと思う一郎の気持ちがよくわかる。
憎からず思っている相手同士が突然の嵐で帰れなくなり、一晩を共に過ごすという場面は恋愛もののお約束としてあるけれど、この作品にもそれがある。二郎と直の間には一郎に報告するようなことは何も起きなかったけれど、それでも一郎が疑いを持つのも仕方がないような何かが二人の間にあるのは確か。この場面で、嵐で停電にもかかわらず、直が湯上がりに二郎に気づかれずに薄化粧をしていたところ(P167)が、特に印象的だった。
Posted by ブクログ
兄一郎が弟二郎に妻の節操を試して貰いたいというところは狂気であり作中の圧巻である。 直の本心は謎のままである。一郎も二郎も直に翻弄されている。直は恐れない女である。
Posted by ブクログ
ドン・キホーテ前編の「愚かな物好きの話」がモチーフになっているようだ。
お直の心境は書かれていないがやはり二郎に好意を持っていたんだろうか。手紙の最期に暗示してあるように兄は死んでしまうのだろうか。二郎は結婚せずに外国に行き戻ってこないのだろうか。自分の中に神がいて苦しむさまは近代人の苦悩を表現しているように思う。
Posted by ブクログ
一郎の妻、直のような女性が好きだ。そう思って最後まで読んでいたら、解説で酷くこきおろされていていらっとした。ただ、たしかにそういわれればそうだと納得もした。
晩年の漱石の小説は、執拗に孤独を、我執を主題として追い求めていく。ただ、それは紹介の帯がいうような「近代知識人の苦悩」に回収されてしまうのだろうか。仮にそうだとしたら、漱石の小説は過去の廃墟にすぎない。廃墟を好きなひとがいるように、それが過去であり、痕跡であるからこそ価値を持つような、そんな代物にすぎない。
ぼくが漱石を好きなのは、そのような懐古主義からではない。彼の魅力は、彼が本格的に小説を書き始めてから一貫して、三角関係のなかで人間を捉えようとしていたところにある。『行人』では、近代知識人の苦悩ではなく、ひとの心のはかりがたさを、だれしもが共有している。そのつらさを訴えようとすれば、心をはかりがたい当の相手ではなく、第三者に向かうのは必然だ。そうしてかたちどられた三角形が、この物語のなかではいくつも生成し、重なり合って社会を形成している。
あとひとつ、付け加えておけば、やはり日本語のための日本語は美しい。
Posted by ブクログ
<女性というものに哲学的な懐疑をもつ一郎は、弟に対する妻の愛情を疑うあまり、弟に自分の妻と一と晩他所で泊ってくれと頼む。知に煩わされて、人を信ずる事の出来ない主人公の、苦悩と悲哀と、寂莫と、それにさいなまれる運命的生活が描かれる。漱石の実人生と作品との交渉が問題にされる作品。大正元―2年作。>一郎の友人のHさんの手紙にはかなり心を打たれた。Hさんの登場は物語の後半部分なので、そこを待つまでが長いなあと思ってしまうかもしれないけれど、ほんとそこまで頑張って読む価値がある。上のあらすじを読むといかにも難しそうでなかなか手が出しがたいかんじがするけれど、読んでみると全然そんなことはない。漱石さんの文章は美しくてちょっとはまった。あんなふうな文章でものを考えたり喋ったりしたらおもしろそう。
Posted by ブクログ
漱石の精神が衰弱していた頃に書かれたといわれている作品。人の何を疑い、何を信じれば良いのか。この作品こそ人間本来の姿を描いているのではないだろうか?その心理描写に圧倒されます。“自分は女の容貌に満足する人を見ると羨ましい。女の肉に満足する人を見ても羨ましい。自分はどうあっても女の霊というか魂というか、いわゆるスピリットを攫まなければ満足ができない。それだからどうしても自分には恋愛事件が起こらないのだ。(行人より)”
Posted by ブクログ
夏目さんが、病んでうっかり実体験を書いてしまったようなきわどい小説。勿論面白いんですが、ちょっとハムレットっぽいかも…ああ今ものすごくいい加減なことを言ったかも…
Posted by ブクログ
寝る前の文学シリーズ。夏目漱石は比較的読みやすいけど、高尚な一郎ワールドはなかなか理解に苦しむ。他人からみた家族を手紙の中で描くという構成が面白い。
Posted by ブクログ
他の夏目先生の作品の主人公に比べてかなり色々なことに巻き込まれる主人公だなと思いました。最後まで一郎さんのことはよくわからなかったです。
Posted by ブクログ
後期三部作の2冊目。修禅寺の大患を挟んで書かれたもの。構成上の問題もあるが、とても難解な印象。とくに嫂の心情が明確に描かれていないことが難解さに拍車をかける。とはいえ止まらない面白さは相変わらず。
Posted by ブクログ
勉強だけを生き甲斐とする兄・一郎と彼を敬遠するその家族や親族の様子が登場人物の心情を深く描きながら記された作品。
なんか勉強ばかりに没頭する人って周りにもよくいるけど、その人たちも一郎のように実は心の中は言葉では言い表せないような悲観的な物を感じているのかなと。
でも二郎も早く結婚したらたぶん気持ち的にも落ち着くんじゃないかなとか。笑
Posted by ブクログ
語り手二郎の兄、一郎は旅先で自分に嫂の不貞を試してほしいと持ちかけてきた。結局、嫂とは何もなかったのだが、そのことの報告をするのが進まなかった二郎は結局それを後延ばしにしてしまう。それが原因で兄と喧嘩をし、家の空気が気まずくなったため、家を出ることにした。その後もしばしば実家を訪れる二郎の耳に、兄は最近では他の者ともあまり口を利かなくなったということを耳にする。元来、学者であった兄は自分の頭で考え続けた結果、ついに他人と共に生活をすることができなくなったほどにやりこまれてしまったのであった。最終的に二郎は兄の親友Hに彼を旅行に連れてってもらったのだが、彼からの書簡によって、現在の兄の実態が明らかになる。 と、まず考えすぎはよくないってことですね。しかし私みたいにあまりに考えなさすぎなのもどうかと思いますが(゚∀゚)アフォが一番です^^