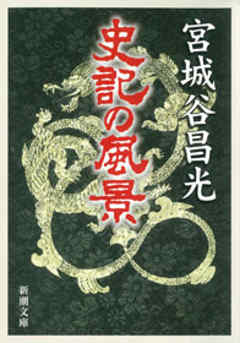あらすじ
古代中国二千年のドラマをたたえて読み継がれる『史記』。中国歴史小説屈指の名手が、そこに溢れる人間の英知を探り、高名な成句、熟語のルーツをたどりながら、斬新な解釈を提示する。この大古典は日本においても、清少納言、織田信長、水戸光圀、坂本龍馬にと、大きな影響を与えていたことに驚愕させられる。世のしがらみに立ち向かった先人の苦闘が甦る101章。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
司馬遷『史記』を素材に、古代中国の習俗、文化、歴史について述べたエッセイ集。
一篇に一テーマ、文庫2~3ページくらいにまとまっており、読みやすい。
以下、各文章から、興味を持った点を覚書に。
「酒の霊力」
紂王の「酒池肉林」のエピソード。肉は干し肉を木々の枝にかけた、と一般には言われているが、宮城谷さんは裸の男女を立たせた、としていて驚いた。神霊を招く行為というが・・・
「商民族の出自」
上甲以来、商の王には十干が名前に入るとか。甲は「一」を表すのでなく、「十」が石棺に入った形だという指摘が面白い。
「氷の利用」
古代では貴族の遺骸をきよめるのに氷を使っていた、という話に驚いた。
「新年の吉凶」
『史記』の「天官書」にある、魏鮮が正月に行ったその年の吉凶を占う方法が紹介されている。さまざまなものが列挙されていたが、町の人の声が宮(ド)に聞こえればよい年、商(レ)なら戦争、徴(ソ)なら旱害、羽(ラ)なら水害、角(ミ)だとわるい年だそうだ。
「鶴鳴」
鶴を好んで身を滅ぼした衛の懿公のエピソードが紹介されている。
「空前絶後の道」
春秋時代の戦争は、戦車(兵車)が主力だそうだ。平地で大軍の兵士を送るのに向いていたからだという。もっとも、北方の異民族との戦いではあまり効果がないそうで、戦国時代には歩兵と騎兵中心に変化してきているらしい。始皇帝は軍事用道路を建設し、兵車を「数十乗」横並びで走らせられる、幅約百六十メートルの道を作ったという話もあった。それを北方へ600キロ作るとは・・・。
「古代中国の気象」
昔の気象条件については、なかなか知りえないことなので、貴重だと思った。春秋時代は黄河以南は雪もあまり降らず、むしろ夏の大雨の方を憂慮していたとか。
「鳥の陣形」
今まで古代の戦争がどのようなものかさえ、考えたことがなかったため、気象の話と並んで興味深かった。魚鱗、鶴翼、長蛇、偃月、鋒光矢、方円、衡軛、雁行の八陣のことが出ている。
「子路の冠」
本題の子路の話より、なぜ十二歳、または二十歳に加冠の儀を行うのかという話が面白かった。満数「十」に、陰を表す「二」を添えた数であるというところが重要で、陰陽の思想で陽を表す男性は、陰をもって完成するということを表しているのだとか。
「数の単位」
紂王が撃たれるときのことを書いた『詩経』の表現にある、「受(=紂)の臣億万有るも・・・」の話から、この頃の「億」は現在の十万または百万のことだと書かれていた。知らないととんでもない誤読をしかねないことになる。
「王侯の一人称」
『史記』では、王侯が「孤」や「寡人」と称するとき、凶事が起こる。そのように司馬遷が使い分けている、と。「予小子」は即位したてで、喪に服している君主の一人称と紹介されていたが、これは他の文書でも共通する意味合いか?ちょっと判然としなかった。
「仙人杖」
『史記』にはエピソードはあるものの、そのいでたちについてはあまり触れていない聖人原憲。藜の杖をついていたことから、後にそれは聖人のシンボルになったとか。
「靴の出現」
はきものを表す言葉に、「靴(かわぐつ)」「舃(二重底のくつ)」「履(かわぐつ)」「屨(麻のくつ)」「蹻・鞋(わらじ)」があるという。匈奴との戦いに臨み、兵車戦から騎馬戦に切り替えざるをえなくなった趙で、「履」を捨て、「靴」に変わった、というが・・・靴はブーツ型のものらしい。「履」がどんな「かわぐつ」だったのかは、よくわからなかった。
「呂后の治世」
身内や臣下を殺戮したという劉邦の妻、呂后。しかし彼女が実験を持っていた間、庶民は安らかな生活を送ることができたという。
他にもたくさんあるが、これくらいにしておくことにする。
Posted by ブクログ
つまらない漢文の授業は、いらない!
漢文は、漢字の羅列に頭が痛くなる人もいるだろう。
苦労して読み下して、意味が分かったとしても、結局、「?」になるのがオチだ。
漢文の最高峰、「史記」。
中国歴史小説の第一人者の著者がエッセイでそれを優しく教えてくれる。
この人の小説を読んでから、「史記」を読むと、面白い。
長編が無理という人は、このエッセイから入ろう。
Posted by ブクログ
中国の古典「史記」を題材にしたショートエッセイ集。
よくこんな細かいところに疑問を持つな、というところから始まってしっかり話を広げるところはさすが。あとがきにもあるが、「小説家は一種無責任な立場から、想像や空想を広げ」て自由自在に話題を展開している。
Posted by ブクログ
2013年02月 05/09
史記にまつわることを新聞で連載していたものです。
かなりマニアックで、半分くらいしかきちんと理解できませんでしたが、おもしろかったです。
史記が現代にもさまざまに影響を与えていることを教えてくれます。過去の中国ってすごい。
「晏子」を読みたくなりました。
Posted by ブクログ
中国史に傾く人間はまず読んでいるといっても過言ではない「史記」について、の説明書的な本。史記の歴史観、雑学的な文章から、難解な文章をより読みやすくするようにされている。これを読んだあとにもう一度史記を読むならさらに、内容を把握しやすいと思う。
Posted by ブクログ
連載モノを集めているので、読みやすさと読みにくさが同居しているのは仕方ないとして、宮城谷昌光という作家の背景が見える一冊。それなりに面白かった。
Posted by ブクログ
中国の歴史は嫌いではないにしても、にしても一般人向けに常にフリガナがあると助かるのう。こんな感じは覚えられんよ。。戻って確かめてもよいけどね、なんなテンポ悪くなるし。
というわけで名前とか地名の漢字は見た目のイメージというか象形文字と思って読んでしまったよ。
内容としてはちょっとしたトリビアを挟みながら、妙にあっさりとエピソードを語っていくので、教科書っぽいとでも言おうか。なんだけど、教科書はこうかも知れんけど疑わしいよね、みたいな個人の見解がちょいちょい入ってきて、いや歴史を語るならこういう姿勢が良いよな。まぁぶっちゃけ何を言ってるかはよく分からんのだけどもさ。
Posted by ブクログ
古代中華の世界を静謐な筆で著してきた著者が、平成五年から産経新聞夕刊文化面に連載を始めた『史記の地平』。一年が過ぎ連載が終了するとその評判から、新潮社の雑誌「波」に『史記の風景』として連載が引き継がれた。
一話原稿用紙三枚に、司馬遷の『史記』から話を引くという独特な手法を用いている。
「管仲と晏嬰」では、生きた時代が違う二人に対話をさせている。『列子』には、晏嬰が長生きの秘訣を問うと、自分の思った通りに生きれば良いと答える。管仲が葬式はどうすれば良いかと問うと、六種類あり、火で焚く、水に沈める、土に埋める、野晒しにする、谷に棄てる、石棺に 斂める、そのどれでもよくその人のめぐり合わせだ、と晏嬰は言う。管仲が生について知り、晏嬰が死について知っていたとするのは、管仲は君主桓公より先に死に、晏嬰は霊公、荘公の二君主の死を見送ったからではないかと、著者は解釈している。
「大うつけ」では、『史記』の「田敬仲完世家」に斉の威王が、即位後九年の間国政をほったらかしにし、うつけを決め込んた挿話がある。九年後に突然即墨の 邑を治めていた大夫を呼び「汝の悪口が毎日聞こえるが、調べてみると即墨は良く治めている。それは汝がわしの側近に取り入らなかったせいであろう」て褒美を取らせた。逆に阿の邑の大夫には「汝の評判は極めて良いが、調べてみると阿の民は貧苦におり、汝は怠け者よ。わしの側近に賄賂を贈ったな」と、責めこの大夫と賄賂を受け取った側近どもを鼎で煮殺した。『信長公記』には作者太田牛一が、信長は十六・七・八歳に突然うつけになったと記しているが、これは父信秀の死が関係していると著者は考える。独創的な改革を次々に打ち出した信長は頭脳明晰であり、多分に中華の書籍を熱心に学習していたのではないか、と結論づけている。いや〜、中華の書籍は知見に富むなぁ。
Posted by ブクログ
史記にまつわる101のお話
漢字や言葉の成り立ち、日本の歴史上の人々に影響を与えたこと、解釈が不明なことへの宮城谷さんの思い、古代中国の習慣や風俗などなど史記が身近に感じるおもしろいお話の数々でした
史記が書かれたのは日本の弥生時代中期、「日本の歴史がこれからはじまろうとするころに、中国ではその歴史が集大成されるということも、脅威にあたいする。」という宮城谷さんの言葉。
まさに私もこの思いでどんどん中国史にはまってしまいしまた
Posted by ブクログ
宮城谷氏の新聞連載をまとめたもの。
移動中の読書に向いてるかも?
コラムなのでひとつひとつは短いけど
『史記』のサイドディッシュ的に楽しめます。
勉強家の氏のいろいろな視点を借りるのは面白い。
いろんな疑問点や着眼を膨らませていくことで
お話ができていく過程も垣間見る感じ。
Posted by ブクログ
日本がこれから歴史が始まろうとする弥生時代の頃、中国では司馬遷が歴史の集大成として「史記」を編纂(紀元前91年頃)している。
その史記を題材として、色んな話が2,3頁程度で語られている。
ある程度詳しくないと分からない。また1話が非常に短いので、知らない話だと理解できないまま終わってしまう。
Posted by ブクログ
小ネタ集。気持ちとしては、「中国古典ことわざを読む」とか、そんな感じ。史記に関しての小ネタだったので、史記の横に置いて、雑学補助的に読んだら面白かったのかもしれません。