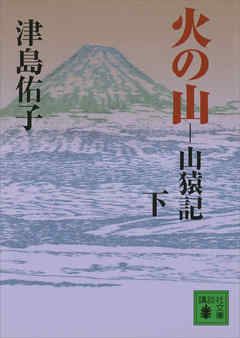あらすじ
死ぬ時に、ああ、私にはもっと別の人生があった筈なのに、と自分の生涯を後悔しなければならない程不幸な事があるだろうか、と今まで私は思い続け、それで死ぬのも怖れ続けていた。でもこうした後悔は随分傲慢な思いなのかもしれない。――始まりがあれば、終りがある。死とはそうしたもの。――<本文より>(講談社文庫)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
6代の物語である。下巻は山梨で空襲にあい、その先祖代々の家がなくなり、東京の江古田やそれ以外の所に移るという家の問題である。記録を書いている勇太郎が妻と一緒に米国に行っているが、そこのところの記録は書かず、米国に旅立つところで記録は終わっている。生まれては死にまた生まれては死にの繰り返しである。
Posted by ブクログ
凄まじい大作だった。
上巻では、津島佑子らしくない創造力で意外性を見たが、後半は正に女性讃歌の一冊だった。
有森家の女衆の1人、桜子の魅力が物語を牽引している。彼女の顛末に関しては本作はおろかここ最近数作の中のハイライトだと思った。
Posted by ブクログ
投げ出してしまいたくなるほどではないものの、少々味気ない話が続き、下巻の中頃までは作品の意図を掴みかねた。しかし、桜子によるメモが挿入されることでこの作品が持つ意義が分かりやすくなった。石を巡る作品であったことに改めて気が付かされたのである。石にもそれぞれ名前がある。同じ土地から産出したものでも、含有成分や構成によって異なる輝きを、美しさを見せる。そうしたこまごまとした石の美しさを再発見すること、それによって有森家(石原家)の生を後世に残るかたちで復元することがこの作品の達成であると言えるだろう。
中上紀氏による解説は作品のあらすじや構成、特徴などについて十分に整理されているが、通読した前と後ではかなり違った印象を受ける。
Posted by ブクログ
読むのに苦労した上巻とは打って変わって、随分と読みやすく感じた。
富士の裾野に住む有森家の年代記とはいえ、物語のほとんどは語り手である勇太郎の父である源一郎と、彼の子どもたちについてである。
上巻は父・源一郎を中心に、何の不安もなく過ごした故郷での子ども時代の幸福な日々に大きくページを費やしているため、その後の家族の闘病や死別が続く下巻が、敗戦の混乱も含めて理不尽に感じられる。
だが、大きく時代が変わるときに、精神的支柱の父を喪い、今まで通りの生活が送れるわけはない。
最終的に有森家の人間はだれ一人として甲府に住み続けることはなかったのだ。
そして、勇太郎自身アメリカで生涯を過ごし、その娘はパリで子どもを産み育てる。
有森の血は世界を舞台に流れているとも言えるし、甲府に足を据えて生きてきた一族の血は薄まったともいえる。
命をつなぐというのは、そういうことなのだ。
甲府を離れながら甲府を思い、時に、亡くなったはずの父や兄姉たちが青空の中を馬で駆っていく姿を見たり、過去を思い出していると亡くなった姉たちの会話が聞こえてきたりと、軽くマジックリアリズムを思い起こさせる部分がある。
そう言えば土地に住み続ける一族の話だし、似たような名前が繰り返し出てくるし、おさすりさんのような科学では解明できない力を持つ者がいたり、自然災害の脅威にさらされたりと「百年の孤独」を彷彿させる箇所が多々ある。
かと思えば、姉の一人で、一番勇太郎には厳しかった笛子の夫・杉冬吾は、明らかに作者の父である太宰治がモデルであるとわかる。
津軽の大地主の息子でありながら、生活能力が全くなく、ただ酒と煙草と芸術と女に依存して生きる男。
現実の太宰がどこまでそうだったのかは知らないが、心身があまりにも脆弱で、自分のなしたことに責任を取ることなどできない無責任な臆病者でも、芸術の才能さえあればすべてが赦されるものなのだろうか。
文章や構成に色々と工夫が凝らされているのだけど、それがどれほど作品によい影響を与えているのかは疑問。
もっとシンプルな方が断然読みやすいのに。
例えば
”桜子はまだ二、三時間、麻酔からさめないと言われたので、私たちはインキュベイタアに入った赤ん坊を見届けに新生児室に行った。人間の赤ん坊とは思えないほど小さな赤ん坊がいろいろなテュウブを取りつけられ、巨大なオムツをつけただけの姿で、ガラスの箱のなかでゆるやかにうごめいていた。”
書いていることが理解できないわけではないが、カタカナがいちいち障害となって立ちはだかり、読書に急ブレーキがかかるんだよね。
つるつる読める文章がいいのかと言えば、そういうわけでもないけれど、これはあまりにも甚だしくて、もう少し日本語に寄せた標記にして欲しかったわ。
Posted by ブクログ
書き手は姉弟の間を移り、思い出は膨大だけれど、何か一本貫かれたものを感じるのは、姉弟の血か、故郷の名残か。人間を描き切る著書の真摯さに、読者である私は姿勢を正したくなる。人間の命は引き継がれていく。一生懸命に、あるいは無心に。
Posted by ブクログ
勇太郎は大学で物理学を専攻し、学問の世界に生きることをめざすものの、日本を取り巻く国際情勢が悪化していくなかで将来の見通しを立てることができません。さらに終戦後も、大学に居場所はあるものの、急激なインフレのために生活がままならず、悩みは尽きません。
勇太郎のすぐ上の姉である桜子は、婚約者の松井達彦が軍に召集されて連絡がとれないまま、勇太郎を支えます。そんななか、思いがけず達彦が帰還し、桜子は松井家に嫁いで子どもをさずかるものの、病に犯されてこの世を去ります。
国語教師だった笛子は、画家の杉冬吾のもとに嫁ぎ、彼を献身的に愛するようになります。戦中から戦後にかけて日本中が物質的に窮乏していた時代にも、勇太郎には乱費とも思える冬吾の生活ぶりは変わらず、その作品が評価されたことで冬吾の暮らしぶりはますます乱脈をきわめ、死へと突き進んでいきます。
激動の時代を生き抜いてきた家族の物語としてまとまろうとする、求心性の強さが印象的です。本作は、連続テレビ小説『純情きらり』の原案ということで、そこで要求されていることに的確におうじる著者の技量には関心させられますが、比較的数すくない主題をじっくり追求する著者の作品群のなかにおいて見ると、刺激に乏しいという感想をいだいてしまいます。