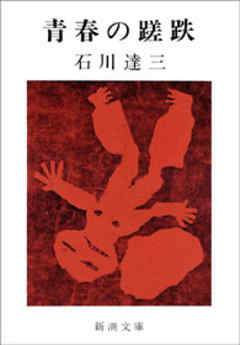あらすじ
生きることは闘いだ。他人はみな敵だ。平和なんてありはしない。人を押しのけ、奪い、人生の勝利者となるのだ――貧しさゆえに充たされぬ野望をもって社会に挑戦し、挫折した法律学生江藤賢一郎。成績抜群でありながら専攻以外は無知に等しく、人格的道徳的に未発達きわまるという、あまりにも現代的な頭脳を持った青年の悲劇を、鋭敏な時代感覚に捉え、新生面を開いた問題作。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
5.0/5.0
共産運動や、学生運動が吹きあられる時代に極めて現実主義の姿勢を貫く青年、江藤の破滅の物語。静かに狂っていく展開と、凛々しい文体。
素晴らしかった。
Posted by ブクログ
できるだけ若いうちに読まなければ意味がない作品ではある。
ミステリーとして読めばあらすじにすでに書いているため面白くないが、人間が持つエゴイズムが悲劇につながっているということを念頭に置いて読むと頭が冷える作品ではある。
主人公の青年、江藤賢一郎は何事も打算的に考えてしまう性格であるがゆえに、法律を盲信しそれ以外を無駄だと切り捨ててきた。そして、自分の人生設計が崩れることを恐れ、教え子を殺し、母の声にも耳を傾けなかった。
現代で言えば何事も効率を重視する価値観に似ているかもしれない。
もしかしたら、何事も計算し、自分自身の人生を重視する結果、誰もが人間関係、社会生活の崩壊につながるのではと怖くなった。
Posted by ブクログ
とても好きな作品。
立身出世のために選んだ道、それは全てを狂わせてしまった。
「愛」などという不確かな物を信じない主人公、最後はその「愛」によって、足元をすくわれたのかもしれない。
Posted by ブクログ
終盤にかけて非常に衝撃を受けた。
主人公江藤は法律学生であり、専攻のもの以外については無知に近いほどの変わった人間である。
それ故に教え子の女の妊娠の月が合わないことに対しても気づいても、それ以上は追求しなかったが為に、不必要な殺人を犯してしまった。
この作品を読んで、エゴイズムと女性の恐ろしさを感じた。
江藤が哀れでならない。
Posted by ブクログ
高校生の時、読書感想文を書くために読んだ。
それから30年後、実家にあった文庫本を見つけもう一度読んでみた。
とても衝撃を受けた記憶はあったが、内容は忘れていた。
高校時代の自分は頭脳明晰な江藤に憧れ、エリートに憧れたと思う。
そして「女は怖い」「女で失敗してはいけない」と思った。
高校・大学時代の自分を思い返すと、この小説の影響を受けていたなと思う。
今読み返して思うことは、エゴイズム、未熟さ…
高校生の自分とは違う視点で楽しめたと思う。
高校生時代に自分が引いたアンダーラインに?を感じながら、高校時代の自分と対話しながら読み進めるという不思議な体験ができた。
読書感想文もどんなこと書いたか…
読んでみたい。
Posted by ブクログ
めっちゃ面白かったー!!一気読み。
しかも沢山メモとりながら読んだ。
なんなら結末はあらすじから容易に想像できるのだけど、それに至るまでの主人公の考え方や過程に読み応えがあった。
最低な男というのが一般的な感想だと思うけど、男とか女とか超越した視点で楽しめた。
「誘惑とは結局、相手にあるのではなくて、自分の情感の中にあるものだった。」など、名言ばかりじゃないの・・。
主人公の江藤が法学生ということで、ところどころに法律やそれに基づいた論理的な思考が出てくる。が、自分の都合の悪い時だけ論理が崩壊する。
なるほど、そう来るか、、!と笑
それにしても法律には「愛」という字は一つも出てこないというのは成る程と思った。
非嫡子についての表現も興味深い。
解説にも書いてあったけど、いくら優秀で将来有望な学生とはいえ、世間知らずというか、幼稚というか、ある意味純情なところが彼を躓させている。
なんだかんだ言って母ちゃんの方がよく分かっていた…。
古い作品だけど読みやすいので是非若い人にもよんでほしい。
男女の駆け引きという点で東野圭吾の何某かや、名作・◯◯器を思い出した。切り札を使わないといけない関係というのは切ない…。
1966年に佐賀県で起こった事件がモデルになっています 数年前、モデルとされた事件が新聞で取り上げられていました 犯人を知る地元の人は犯人に同情的だったと書いてありました
人を裁く事の難しさを痛感させられた事件だったと思います 本書では主人公を法学部の学生に変えてあり、それがかえって幸せとは何かなどいろいろと考えさせられる内容になっています 勝ち組、負け組が叫ばれている昨今、是非読んでおきたい本です
Posted by ブクログ
学生どうしの痴情のもつれ話ほど醜いものはないと考える私だが、この学生どうしの痴情のもつれを見事に表現しきった作品が本作である。
しかも片方は司法試験にパスするほどのスーパーエリート。
そんなスーパーエリートの思考が、一人の女により突き崩されていくおぞましさが見事に描かれている。
元・法学徒の私には、「あーこういう思考の法学部生いるわー」と思えるセリフも多々ありました。
結末はあまりにおぞましいので書かないが、おぞましい結末がやがてくるとわかっていてもページをめくる手が止まらないはず!
Posted by ブクログ
江藤は精神面であまりに幼かったのだろう。追い詰められて観念的になってしまった。そういう意味では冒頭に出てきた左翼学生の三宅と同じであった。
まったくもって,人間は危うい期間を,人生の中で過ごさなくてはいけないのだなあと思った。
Posted by ブクログ
鼻持ちならない自信家の秀才が女を二股したあげく
のっぴきならない状況に追い込まれて道を踏み外す…
そう書くと、なんだか溜飲の下がるような話だが
実際の読後感は、吹雪の夜に裸で外へ放り出されたようなものだった
彼はみずからの力を信じ、世界の秩序を信じていた
世界は己の意思による働きかけで変えてゆけるものだと、
素直に信じてしまったんだ
その一方で彼は、人を疑うということをよくわかっていなかった
考えたくなかったんだと思う、自分が他人にあざむかれ、踊らされている
ただの滑稽な人形かもしれない、なんてことは
だからこそ、逆に彼は
他者を人形のように扱い、始末をつけることで
世界に対するみずからの誠実さを証明しようとしたんではなかろうか
Posted by ブクログ
本屋で平積みされていて手にとった本
大学生 江藤は貧しいが野心があり、現実主義者だ。
非常に優秀で司法試験に合格、資産家の伯父の娘(康子)との縁談と社会的地位、ブルジョワへの階段を上っていくかに見えた彼の目の前に現われたのは妊娠した教え子(登美子)だった。
彼女に対して彼は死んでくれればいいと思う。
人生設計が崩れることを恐れた彼は彼女を殺してしまう。
無能で受け継ぐべきものがないが、江藤を愛し心底尽くす姿勢の登美子
プライドは高く、愛情を感じないが、受け継ぐべき資産のある康子
警察の取り調べの中で、彼は何もないが登美子となら幸せになれたのではないかと感じる。最後に待ち受ける衝撃の事実とは… (このあたりの江藤の心情は個人的にもわかる気がする。)
現代が生み出した江藤というエゴイズムの塊は特別な存在ではない。ごくありふれた人間の一人だ。世間を法という視点から見る偏狂さ、しかし、それ以外のことになるとまるで何も知らない学生。 現代(これは作品ができた当時だけでなく今も含めて)を鋭く見ている筆者の眼のつけどころに驚いた。
男女のエゴが丸出しの本作からは現代の資本主義社会の闇の一面も見える。資本主義の規律の中で生きるとはどういうことなのかを説いているようにも思えた。
Posted by ブクログ
大学生のころ、初めて読んで、強い衝撃を受けました。
人間のエゴを見事に描いた作品です。
ラストがなんとも・・・・。
「容疑者Xの献身」なみの大どんでんがえしです。
Posted by ブクログ
昭和46年の作品。学生の頃に話題になった本で読んでいたが、記憶が曖昧なので再読してみた。
読み始めてわかるが、たぶん初読でも、ストーリーがどう運ばれていくか、ある程度予想できる内容になっている。そのわかりやすさが逆に、先へ先へと読み進めさせる原動力になっている。立身出世欲が強い主人公、母親ひとつ手で育てられ、周囲の期待のなか、司法試験合格を当面の目標に見据えている。家庭教師での教え子(登美子)と愛情を持たない関係を続けている。登美子は母親をなくし、父親とその妾と同居する形で、心の荒んだ生活を送っており、主人公だけが心の拠り所となっている。一方、主人公は資産家の叔父さんの援助のもと、司法試験合格が期待され、いずれはその娘(康子)との縁談への思いがある。この二人の女性を軸に、緊張感を伴って進行していく。登美子にも康子にも、愛情をだくことなく、ひたすら自身の社会的成功のため、打算的な考えで均衡をとる主人公。司法試験に合格してからは、康子に収斂すべく進んでいくが、登美子の妊娠という思わぬ事態に直面する。自分勝手な判断が抜け出せない迷路を作り出し、最後のクライマックスへと急降下する。予測される展開ではあるが、最後の刑事の一言が、主人公の誤算を浮き彫りにして余韻を残しつつ、物語が閉じる。
Posted by ブクログ
時代背景は1960年代後半どっぷり昭和に漬かった、しかし古びていない題材。
いつの世も経済的に不如意な青年が、勉学、容姿に自信あり、上昇志向があるとすると、手っ取り早いのは後ろ盾を見つけること。いわゆる「逆玉の輿」を狙うのもその一つ。
法律を学んで国家試験を目指している青年が、学費を援助してもらい、その支援者の娘と結婚の運びの実現となったところで、その道は安易ではなくなった。そのつまずきはこっそり付き合っていた元カノが妊娠「生みたい」と言われ、万策尽きて・・・そしてどんでん返し。斎藤美奈子氏が文学論『妊娠小説』で「妊娠サスペンス」と名付けているほどの緊迫感だ。
石川氏はけっこう結婚つまずき小説を書いていて(『薔薇と荊の細道』『僕たちの失敗』など)、石川達三の特徴は堅苦しく理詰めと言うけれど、法律を学んでいる青年が主人公のこの小説では、それがよく発揮されていてなかなか読ませるものである。
古いからもう読む人もいないのではと思っていたら、昭和4年5月初版のこの文庫本、令和2年3月に76刷だというから。見つけたわたしもびっくり。たぶんこういう状況はこの超現代にも転がっているだろう、だから読み継がれているのだと。
Posted by ブクログ
打算的な賢一郎くんに「いつか天罰が下れ」と思いながら読んでいた。エゴイズムは仕方がない。みんな自分をいちばん大事にするのは当然。とはいえ、それを正当化するための屁理屈みたいな理論にむかつきますよね。たしかに「よく考えている」とも言えるけれど、ほとんどが保身のための言い訳なのだから。男が女に対してこういう屁理屈をぶつときは、たいてい「オレは言ったよ」「お前は頷いて聞いていた」という言質をとるためなのではないかしら。本当に自信のある生き方をしているのなら、こんなに無理くりな屁理屈はこねないでしょう。「いうまでもなく、それは彼のエゴイズムだった。あるいは臆病さ、または狡猾さ、そして小さな賢明さでもあった。」というところは、「まさに」なんだけれど、賢明さが最後に来るのがいかんとも。野心を持つのもいいけれど、人には分相応というものがあり、適当なところで折り合いをつけながら生きているというのが現実なのでは。理想と現実についても、恋愛と結婚についても。登美子も保身のために必死であるけど、妊娠出産の当事者だから賢一郎くんよりは同情の余地がある気がする。少なくとも殺されるほどは罪深くはないのでは。
お母さんがお弁当や着替えを差し入れたり、それを「ありがたいな」という刑事さんの、ふつうの人情のようなものに最後に触れられるのは、救いみたいな気がした。登美子が主人公の『裏・青春の蹉跌』が読みたい(存在しません)。
Posted by ブクログ
江藤賢一郎の行動はエゴイズムそのものだが登美子の行動もまたエゴイズムであった。康子の行動も然り。エゴイズムが概念的思想から実存的暴力に変換されたとき、江藤の敗北は喫したのかもしれない。最後の数ページまでは江藤の身勝手さや自惚れ、過信に憤慨と好奇をしつつも、結末(特に最後の段落)は『羅生門』的な人間の闇と業を感じさせる。
江藤をひとりの青年として捉えた場合、若気の立身出世を夢みる気持ちや優位的な逢瀬、知略の綻びに対する焦りは男性諸君には多少通ずるものがあるかもしれない。(女性には失礼を承知ながら)それを題材に行動と事件に変え、結局は男性の稚拙さや浅はかさを描いているのが何とも面白い。『青春の蹉跌』というタイトルから純文学かと思ったら一流のミステリーであった。★5に近い★4。
Posted by ブクログ
金持ちのいとこと結婚するため邪魔になった恋人と別れようとするが彼女が妊娠してしまい……、というありがちなプロットながら司法試験に合格するエリート法科学生である主人公のあまりに冷めたリアリストの視点が面白く、読みごたえはありました。また、叙述トリックものというわけではないですが、『イニシエーション・ラブ』を彷彿させるような「女こわっ」ってなるラストのどんでん返し(?)もヒヤッとしました。
Posted by ブクログ
社会、結婚、資本主義、罪、死、幸せ、これらは一体何なのか考えさせられた。完璧なんてないんだから、できることなら蹉跌につまづいても「つまづいちゃったよー」ってヘラヘラしていたいなー、と。
Posted by ブクログ
【本の内容】
生きることは闘いだ、他人はみな敵だ――貧しさゆえに充たされぬ野望をもって社会に挑戦し、挫折していく青年の悲劇を描く長編。
[ 目次 ]
[ POP ]
生きることは闘争だ。
平和を叫ぶやつの大部分は敗北者だ。
頭脳明晰で野心家の法学生江藤は、司法試験に合格し、資産家の娘との結婚話を進める。
だが、愛人の登美子との関係をやめられず、ある悲劇を招いた。
大学紛争の激しかった1968年に出版された一冊は、萩原健一主演で映画化され、文庫は累計208万部を数える。
テレビ朝日系の「スーパーモーニング」で先月紹介され、増刷された。
番組の中で作家の吉永みち子さんは「登場人物と同じ年ごろに読み、恋愛観が変わった」と語った。
政財官の癒着に切り込む『金環蝕』や『蒼氓』などで知られる著者(1905~85年)の作品は今年3月、中年会社員の危機を描く『四十八歳の抵抗』も復刊された。
人間の内面を描くその言葉は稠密だ。
「あなたは犯人の男と被害者の女の、どちらに同情しますか」と、宣伝文に書かれている。
ちなみに記者は、13年前、女の愛欲の気高さと怖さに共感した。
34歳の今は、男の幼さにもひかれる。
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
司法試験に挑まんとする大学生の賢一郎。家庭教師の教え子である登美子と、裕福な家庭に育つ伯父の娘・康子、どちらと結婚すれば有利に働くか算段するが…
Posted by ブクログ
自分はエリートになり、他の人間とは違うのだと思いあがった学生の転落する様。思い上がりや嘘や不義理、計略によって自らが破滅していく。
古い本なので、ちょっと読みにくいかなと思ったけれど、後半に行くにつれて面白く、意外とさらりと読めました。
面白かった。
Posted by ブクログ
学生運動の中、貧しい生活を抜け出すべく野心に燃え、司法試験合格を目指す主人公。令嬢との縁談と教え子の女生徒との関係は、司法試験の進捗と共に複雑かつ深刻になっていく。
主人公が必死に周りとの関係に対し、冷静に論理的思考でいようと、もがき苦しむ様は、読む方の胸を締め付け、ある種の共感すら覚えてしまう。
周囲の人間をひたすらエゴと判断する法律的、論理的展開も読みどころの一つ。
Posted by ブクログ
心ではなく、頭で生きている学生が愛人を殺めてしまう、そんな話。
昭和46年発行。
あの終わり方から、打算的に生きていても、
罪を犯さない限り処罰されない社会性の限界を感じた。
誰も歪んだ社会を直しちゃくれない。
正直江藤みたいな人はうじゃうじゃいるし、
増えている一方なんじゃないかと思う。
大きな変化は起こせないが、これを読んだ人が
自分はそうなるまいと思えればいいんじゃないかと思った一冊。
Posted by ブクログ
何きっかけで読もうと思ったのか、さっぱり思い出せない…。とりあえず、とても時代を感じる小説。そしてストーリーも予想がつく。ただ、エリート大学生の傲慢さや自分勝手さは、自分のときも、たぶん今も大差ないと思われるので…(まだ人生経験も少なく幼いがゆえ)。大学生のときに読むと身につまされてよいのかも。
Posted by ブクログ
うーん何というか、こういう自分の内面と向き合わざるを得ない本を読むと、いつも複雑な読後感を味わうことになる。きっと江藤に感情移入しながら読んでいるからだと思う。彼のエゴや傲慢さや浅はかさや、一方で生真面目さや肝の小ささや。
フィクションとして読んでいたものが、いつの間にか〝自分ならどうだろう、自分も同種の人間かもしれない〟などと考えている自分に気がつき、来し方に思いを馳せていたりする。それがこの本の優れたところなんだろうな、とも思う。
Posted by ブクログ
中国人の友人から、読んだことがある日本の小説として紹介されたので読む。問題の当事者になると、周りが見えなくなり、判断を誤り、過ちを犯してしまう、難しい。
Posted by ブクログ
(30年ぶりの再読)
正に自分が見てきた風景、自分が過ごした時代。
「法律を味方につけ、法律を楯にとって、他人の愛情も善意も踏みにじって、自分の欲望を合理化し合法化しながら、世の中を押しわたって行こう」とした主人公の青春の蹉跌が描かれています。
重く積もった雪を掻き分け掻き分け進むような重さを感じながら読みました。