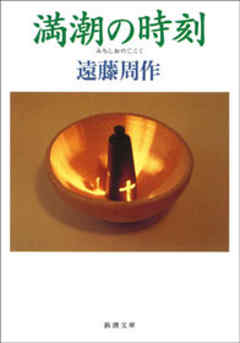あらすじ
突然の喀血により結核に冒されていることを知った明石。四十代の働き盛りで療養生活を余儀なくされ消沈する明石が入院先で出会ったのは、自分よりもさらに死に近い病人たちと、その儚い命の終焉だった。結核がまだ致命的な病であった時代、死の淵を彷徨い絶望と虚無に陥った男の心はどこへ向かったのか。生と死、信仰と救済。遠藤文学を貫くすべてのテーマが凝縮された感動の長編。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
看護婦さんが手を握ってくれると、信じられないようなことだけど、実際に不安や痛みが和らぐ。
病気をすると、遠い風景を俯瞰しているような気持ちになる。
本間さんのセリフ「手術を受けた日から、何もかもが変わっていく」「もっと心の上で」
主人公明石は、自分が日常に戻ると、人生をどれだけ持続できるのか心配しているが、退院してもまだ俯瞰の眼をしている。そして、忘れずに長崎の踏み絵を見に行って、キリストの「沈黙の声」を聞いた。
心に浮かぶ疑問に答えられないもどかしさ。
明石は、弱いものに寄り添い、手を握ってくれる存在を見つけて、強く前向きになれた。
Posted by ブクログ
40代の働き盛りの男性が、結核により療養生活を送ることになることから物語は始まり、淡々とした療養生活と、その心境の機微が描かれている。
今の医療技術からは考えられない治療法、入院期間だが、当時多くの人々が命を落とした結核という病気の恐ろしさを垣間見た気がした。
その苦痛、死の淵に立たされたときの模写が妙にリアルなのは、作者自身結核を患っていたからなんですね。
病院のなんとも言えないあの重い空気感も、読んでいるだけで気が滅入るよう。
ケムリハナゼ、ノボルノカ。
わたしは今まで大きな病気も事故もしたことがない。
本当の苦痛、不幸、孤独感を味わったとき、何を考えるのだろう。誰か、そばで手を握ってくれる人間がいてくれたらいいなあ。