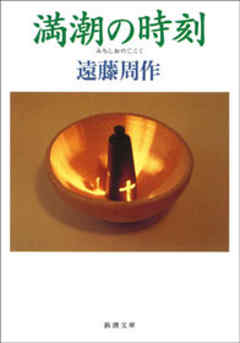あらすじ
突然の喀血により結核に冒されていることを知った明石。四十代の働き盛りで療養生活を余儀なくされ消沈する明石が入院先で出会ったのは、自分よりもさらに死に近い病人たちと、その儚い命の終焉だった。結核がまだ致命的な病であった時代、死の淵を彷徨い絶望と虚無に陥った男の心はどこへ向かったのか。生と死、信仰と救済。遠藤文学を貫くすべてのテーマが凝縮された感動の長編。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
★5つ
読みながらリアル感があると関してましたが、解説を読み納得。
自分自身も短い期間だけど入院したこともあり、術後で声が出ない時、医師から言われた期間でドレンが外れない時など色々と思い出しました。
本作でも「生活」と「人生」が表現されており、奥深いテーマだなと、、
2024年のベスト本に遠藤さんは入ってきそうですが、どの小説を選ぶか悩みます。
Posted by ブクログ
看護婦さんが手を握ってくれると、信じられないようなことだけど、実際に不安や痛みが和らぐ。
病気をすると、遠い風景を俯瞰しているような気持ちになる。
本間さんのセリフ「手術を受けた日から、何もかもが変わっていく」「もっと心の上で」
主人公明石は、自分が日常に戻ると、人生をどれだけ持続できるのか心配しているが、退院してもまだ俯瞰の眼をしている。そして、忘れずに長崎の踏み絵を見に行って、キリストの「沈黙の声」を聞いた。
心に浮かぶ疑問に答えられないもどかしさ。
明石は、弱いものに寄り添い、手を握ってくれる存在を見つけて、強く前向きになれた。
Posted by ブクログ
著者自らの闘病生活をそのまま綴ったかのような内容。主人公の明石が入院中に見た「あの目」が彼に訴えようとしていたのは人生の本質とも思われるそれ。「人生」と「生活」、その両方を行き来する時に人は何を見るのか。
きっと読む誰しもが「共感」を感じる一冊だと思います。とても満足でした。
Posted by ブクログ
初めて読んだ遠藤周作の本。
すごく丁寧に主人公が描写してあり、物語に没頭しやすい。
17年ぶりに肋膜炎を再発した男性の、病気を克服するまでの日々を描いた小説。闘病というよりは、病気との共存を通して、生きる意味を静かに問いかけている。
多分、人によって好き嫌いが分かれたり、読む時期も選びそうな本。自分が感動できる時期に読めて、本当に良かった。
特に気に入った部分はこれ。
「手術をやめる自由はまだ残されているのだと思いながら、掌の上の丸薬を見ると、言いようのない快感がこみあげてくる。それは自分の自由を弄んでいるという快感だった。」
Posted by ブクログ
あらすじを見て、読んでみたいと思った作品。
テーマは興味深いのだが、「導入」「起承転結」「終わり方」「題名」がそれぞれ別の方向を向いているような、長編なのにチグハグさを感じた一冊で、
一つ一つのものはとても興味を持てるのに、全てを線で繋げられていないような不安定さを感じた。
しかし遠藤周作自身が伝えようと思ったテーマはしっかりと書かれており、読み進めることで考えさせる本だったと思う。
チグハグさを感じたが、それは逆にいえば全てを集中して記憶するように読まなくても楽しめるということなので、病院内のことが多く明るくはない内容だが興味がある人は手に取ってもらいたい一冊。
Posted by ブクログ
遠藤周作の作品をいくつか読んだ上で、この作品が完成度の高い作品とは思わなかったものの、病気を通じて人生の悲哀を感じるという感覚は、現状健康な自分は持ち合わせていないので良い読書体験。
Posted by ブクログ
静かな気持ちになりました。
静かに静かに進みながらも、気づけば最高潮に。まさに満ち潮のよう。感情の大波が訪れていました。
生きることを見つめていく明石の、たった一人と九官鳥一話の深夜の対話。溢れる彼の涙。
明石の心を捉えた、病室の夫婦。手を握り合った2人の情景が忘れられない。
良書でした。
Posted by ブクログ
小説のところどころに「沈黙」の一場面を思い出させる描写があって、遠藤作品そして遠藤周作さんのつながりを感じました。そのほかの作品にも流れる「人間をありのままに受け入れる」ものについての遠藤さんの強い確信を感じるよい小説でした。
Posted by ブクログ
40代の働き盛りの男性が、結核により療養生活を送ることになることから物語は始まり、淡々とした療養生活と、その心境の機微が描かれている。
今の医療技術からは考えられない治療法、入院期間だが、当時多くの人々が命を落とした結核という病気の恐ろしさを垣間見た気がした。
その苦痛、死の淵に立たされたときの模写が妙にリアルなのは、作者自身結核を患っていたからなんですね。
病院のなんとも言えないあの重い空気感も、読んでいるだけで気が滅入るよう。
ケムリハナゼ、ノボルノカ。
わたしは今まで大きな病気も事故もしたことがない。
本当の苦痛、不幸、孤独感を味わったとき、何を考えるのだろう。誰か、そばで手を握ってくれる人間がいてくれたらいいなあ。
Posted by ブクログ
生を見つめる眼、沈黙の声。著者の訴えたいことが、じわりと伝わってくる。生活と人生は違う。なので日常から離れた入院生活で実感できたのだろう。14.1.8
Posted by ブクログ
死の淵に立った男の人の話。
人生万事が塞翁が馬っていうことばが常に頭から離れなかった。
悪いことをすればどこかでしっぺ返しが来る。
いいことをすればどこかで返ってくる。
戦争から逃れたものは・・・という感じで。
生きるか死ぬかの瀬戸際みたいなぎりぎりの状態ではなくて、水が地面にしみこんでいくようにじわじわと病に蝕まれていく。
ひとつひとつの行動の意味を考えて、どうあるべきかを考えずにはいられない作品。
Posted by ブクログ
人は死に近づくとき、普段の生活の中で何を考え、何を感じるのか。この作品は遠藤周作自らの体験を元に描かれているのだが、夫婦のつながりに関して涙した。遠藤周作が息を引き取るときも、妻の手を握っていたのがすごいと思った。
Posted by ブクログ
結核がまだ致命的な病であった時代、
死の淵を彷徨い絶望と虚無に陥った男の心はどこへ向かったのか。
生と死、信仰と救済。
遠藤文学を貫くすべてのテーマが凝縮された感動の長編。
(--紹介文より抜粋)
もしも自分が死の淵に出くわしたとき
それまでこういう本を一冊も読んだことがなかったのなら
きっとあっさり気が狂うと思う
Posted by ブクログ
病院。生死。内なるもの。キリスト。遠藤周作のキーワードがしっかり出ている本。ただ、キリスト教あたりは無理やり突っ込んだ感が否めず、違和感があります。
Posted by ブクログ
今までできるだけ多くの遠藤周作作品を読んできましたけれども、「感動」というか「感慨」を一番つよく感じた作品はこれかもしれません。
遠藤自身が病気に伏せる時期が長くあった時に実体験した内容をそのまま作品に投影しているようです。キリスト教信者の視点から見た死と生を病院にいる状況下での視点から描いていきます。
自分よりも病状の悪い患者の部屋を気にするようになったり、その病室が突然片付けられていることを遠目ながらに気づきその人の死を実感すること。遠藤周作の言葉がとても重たい説得力をもって生死に関わる重要な視点を記していきます。
ここから先は、本を読む予定の人は読んで欲しくないのですがこの作品の主人公・明石(つまりは遠藤自身)は病気から回復して退院し、妻と一緒に行くはずだった長崎を自分一人で旅することにします。そこで重たい体を引きずりながら生きて長崎をもう一度みたときの作者の感激を読むと、感動します。この作品が21世紀になってやっと発表されたということにも何か意味があるのではないかと思ってしまいます。
この作品が持つ大きな意味合いは、解説にも示されているとおり、作者の死後発表された作品であるということ。この解説文だけでも一読の価値有りです。
一番最初の「海と毒薬」を読んだときの遠藤文学の怖さというか人間の行動がいかにひどくむごたらしいものになりえるかを読んだときは衝撃的でしたし、その後に「死海のほとり」や「影法師」なども読みましたが、この「満潮の時刻」には遠藤作品全てに共通するテーマと人間の根元と宗教と絡んでいる数少ない作品です。ぜひ読んでみて下さい。
Posted by ブクログ
結核に冒された男がおくる闘病生活を淡々と描き出した作品だが、入院している人々の様子や、病院の窓から見える数々の情景、そして三回に及ぶ手術に望む男の意思の動きといったシーンは、決して平坦ではなく、ドラマティックですらある。
男の内面は期待と絶望の間を行き来し、一旦は無気力に陥ったりする。その動きは決して他者と共有することは出来ない。一人きりで屋上から眺める風景や、真夜中に思う絶望はあくまで個人のものであり、悲しみを分け合うことは出来ない。
しかし、男の妻は男のために様々な努力をしてくれる。絶望の種類は違ったとしても、悲しい出来事によって絶望するのは、本人だけではないのだ。悲しみを見守る視点は常に周囲から優しく注がれている。注ぐ対象は、まるきりの他人であるとしても。
内面や感情や絶望はあくまで個人のものであるが、人は見つめること、手を繋ぐことで、その一端を分け合うことが出来る。
辛いテーマだけれど、根底に流れる優しさに、酷くせつなくなった。
ちなみに、突然、長崎やキリスト教といったモチーフが出てきたのには少々驚いたが、遠藤周作の作品であることを考えると、それも納得。
いつも思うのだが、遠藤周作の作品は、視点が透徹で温かいように思う。
どの作品を読んでも、どんな人にも、隣を歩いてくれる人がいるということを、改めて教えて貰える気がする。
読み終わった後、この作者がもうお亡くなりになっていることを考えると、時々、なんだか侘びしい感じがする。けっこう作品はたくさんあるけれど、もっと書いて欲しかった。新作を楽しみに待ってみたかった。
Posted by ブクログ
結核にかかった明石という男の入院生活をえがいた作品です。
肋膜炎にかかったため、召集を受けることのないまま終戦を迎えた明石は、四十代という働き盛りの年に結核で一年以上の入院を余儀なくされたことによって、同世代のなかで自分だけが戦場に行かなかったというコンプレックスを解消することができるのではないかという考えます。しかし、長くつづく入院生活にそうした決意は揺らぎ、妻に不平をこぼします。
ところが、思いもかけず手術によって早く退院することができるかもしれないという医者の話がもたらされ、明石は手術を受けることを決意します。しかし、彼の病状は医者の予想をはずれて悪化の一途をたどり、退院のめどが立たなくなってしまいます。明石はそうした自分の運命を嘆きつつも、あたりまえだった日常の「生活」から離れて病院で長い時間を過ごしていくなかで、「人生」に思いをめぐらせます。
『沈黙』と同時期に執筆され、著者自身は改稿の計画をもっていたものの、そのままになってしまった作品ということもあって、構成に多少難があるようにも感じられますが、入院生活という即物的な条件によってさまざまな思いが去来して心が揺れ動く展開になっており、興味深く読むことができました。
Posted by ブクログ
「沈黙」「海と毒薬」と比較すると軽い印象。
九官鳥や四十雀の目と踏み絵のキリストの目が「煙はなぜ立ちのぼるのか」について答えを暗示する。生とは何かについて、肺を患ったことでひとつの答えに到達する。
Posted by ブクログ
病院独特の希望とは遠い場所にある暗い雰囲気が重たかったです。そこにいる人たちの日常なので陰鬱な感じではないですが、やっぱり異質ではあるかなと思います。
あたしも病院なんて歯医者くらいしか縁がないので、想像するだけで恐怖の場所です。医学のことはよく分からないですが今はきっと手術するのに骨を切ったりしないですよね……「海と毒薬」でも出てきたシーンですが、怖い以外のなんでもない。物語よりその医療的な部分の方が印象的でした。
どことなく中途半端な感じがしたのは、明石の長崎旅行のせいじゃないかと思います。
遠藤作品と長崎は切っても切れない関係ですが、この作品に限ってはなんだか唐突なような気がします。奥さんと行くかと思ったら明石一人だったし。
なんとなく尻すぼみな感じがしてしまいました。
Posted by ブクログ
『沈黙』と同時に執筆されながら、未完のまま作者の死後出版された作品です。未完成であるだけに、修正されていない作者のダイレクトな思いが伝わってきます。