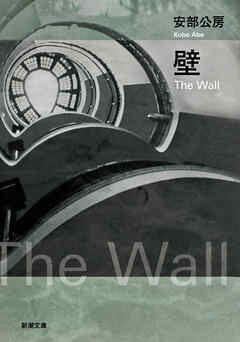あらすじ
ある朝、突然自分の名前を喪失してしまった男。以来彼は慣習に塗り固められた現実での存在権を失った。自らの帰属すべき場所を持たぬ彼の眼には、現実が奇怪な不条理の塊とうつる。他人との接触に支障を来たし、マネキン人形やラクダに奇妙な愛情を抱く。そして……。独特の寓意とユーモアで、孤独な人間の実存的体験を描き、その底に価値逆転の方向を探った野心作。(解説・佐々木基一)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
あまり理解できたとは言いがたい。安部公房のいう壁というものがなんなのか。
第一部の壁は主人公が胸に吸収してぐんぐん大きくなる壁、第二部の壁は本筋からずれているかもしれないが、透明人間になった主人公の、皮膚としての壁、第三部の壁はいろいろあるが、魔法のチョークという話からだと、太陽光に当たらない範囲で絵を本物にする壁という感じだと思う。
正直それが何を意味しているのかわからない。ただ解説に壁の中も外も同質みたいなことが書いてあったからそれがヒントになりそう。また読み直すしかない気がする。
しかし、文章自体とても面白かった。ゾクゾクするような面白さがあった。安部公房は初めてだったから、こんな世界もあるのかと驚いた。
チャットGPTの勧めで、カフカの変身の後に続けて読んだが、カフカのような不条理さがある。解説でもちゃんとカフカを扱ってるし、他の方の感想でもカフカの影響が語られている。チャットGPTって案外正しいこと言うんだって思った。
これから同じく安部公房の箱男を読もうと思うけど不安でしかない
Posted by ブクログ
シュールレアリスム的小説でカフカと似たる作風。
読者によって作品イメージが異なるであろう。
安部公房は繰り広げる世界観は狭いけれど、そこには想像を掻き立てる仕掛けがあり飽きさせない。
安部公房満載の作品である。
Posted by ブクログ
この頃の作品が好き。
抽象化と具体化に富んでいて、まるでモジュールが組み込まれてるのかというような試みが感じられる。
プログラミングされてるのか?と思うくらい発明家っぽいこの頃の作品達はとてもよい。
Posted by ブクログ
20年振りの再読。安部作品の中では今作が最も理解しにくい。第3部しか感覚としての理解が追い付かなかったが、20年前にはその感覚すら味わえなかったのだから多少進歩したのだろう。第3部「洪水」は貧困層(低所得者)からの逆襲と呼んでも良かろう。搾取する富裕層への逆襲。きっかけは嫉妬心ではなく貧乏人から順に液体へと変わる点が問答無用の冷たさをはらんでいて現実的。嗚呼、貧困から抜け出したいな。誰もが願う事が容赦なくコミカルに描写されているので、やはり安部公房は現実的で冷たい観察眼を持つ独特な作家だ。
Posted by ブクログ
「目を覚ましました」から始まる。何かしら変だと思う。まるでカフカの変身の毒虫のお話のような失われた自分の名前。
自分の中に砂漠を宿して、いや からっぽになった自分もどきをもてあまして悪あがきをする。
不思議な世界を冒険している童話のようであり、かなりシュールな旅をしているような気分を味わう。
「バベルの塔の狸」は、もっと冒険する。
はたして自分の中の葛藤なのか?様々な要素が絡まる。世界にのめり込んでしまった!
楽しすぎるし、ゾワゾワと鳥肌がたつ!あーでもないこーでもないと頭を巡らせる事ができる。
何度でも読めるし、何度でも違う感想を持てそう。そしていろいろな学び直しをしたくなる
壁はさまざま、物質的にも、精神的にも!壁と思えばすべてが壁
Posted by ブクログ
第一部「S・カマル氏の犯罪」と第二部「バベルの塔の狸」を読んだとき、まるでピカソの絵のようだと思った。どこまでもどこまでも突き進む想像力が紡ぐ奇々怪々な世界。その「なんじゃこりゃ」と叫びたくなるような世界は、ピカソの絵がそうであったように、演繹という論理的な思考の展開によって極めて理性的に導出されているものだ。ただ、論理の出発点となる公理が、我々の常識の及ばぬ破天荒なものであるから、演繹の帰結としてとんでもないものが導き出される。あるいは出口のない堂々巡りを続ける。特に両作品の登場人物たち(「S・カマル氏の犯罪」で言えば裁判官を務める経済学者や数学者、「バベルの塔の狸」なら狸など)の会話は、本人たちが尤もらしい口調と論理展開でハチャメチャなことを言っているだけに思わず笑みがこぼれる。とても面白い。
第三部「赤い繭」には「赤い繭」「洪水」「魔法のチョーク」「事業」の短編が収録されている。こちらは直接話法で語られる部分が少ない分、前二部に比べてソフトな感じがする。
Posted by ブクログ
初・安部公房。難しい。短編でかろうじて飲み込めたかも。
バベルの塔の狸は視覚的に面白くて、理解が追いつかないなりに楽しかった。
S・カルマ氏の犯罪はよく分からない!
Posted by ブクログ
鬼才・安部公房の芥川賞受賞作。
第一部、S・カルマ氏の犯罪は、名前を失った男が、社会での存在権や帰属集団を無くし、現実世界を不条理でグロテクスなものに感じるようになるという物語である。
社会との接点を無くした人間にとって、社会とは何と残酷な世界であり、不安定なものに映るのかが鋭く抉り出されており、現実から外部世界へと自然に誘って行く安部公房の筆致が際立つ名作であると感じた。
最後にカルマ氏は砂漠の中に佇む壁と化してしまうが、それは何の暗喩なのであろう?社会から疎外され、もはや人間ですら無くなったカルマ氏への鎮魂碑であろうか。
Posted by ブクログ
安部公房の創造性が爆発した作品。
不気味さやブラックユーモアに溢れ、真骨頂が発揮されている。
何を考えていたらこんなストーリーや設定を思いつくのか。
一見荒唐無稽な内容に思えるが、一つ一つの展開には繋がりがあり、破綻していない。
Posted by ブクログ
安部公房先生を読むのは2作目。正直最初から最後まで壁がわからなかった。独創性についていけず、文学を深く理解できていないように感じた。しかし、現実世界でもないけど空想世界としてほんの少し理解できる独創性は、安部公房先生ならではかなと思った。
いつか再読しよう。
Posted by ブクログ
シュールで独特な設定が面白かった。作家は若い頃極貧生活だったらしく、壁ばかり見つめていたのだろう、多種多様な壁のイメージが全てリアルでユニークだった。時々女性が主人公の男性の前に現れ、抽象的なような名を失った語り手に「名前ある個人としての」人生があったことを思い出させてくれる。第一部では1ページかけて主人公の男が目の前の女を理解できず、捕まえ損ねてしまう体験が描かれている。その瑞々しさは束の間の潤いであった。だが、そんな希望の見えた人生の分岐ルートも、押し寄せてくる不条理にすぐ潰されてしまう(その不条理というのは、大体が「自分の問題」という種の奴で、カフカの不条理とは違う)。
Posted by ブクログ
物語の初めまでは理解できるんだけど気がついたら理解の範疇を超えちゃう。名前を名詞に奪われたあたりまでは理解できるんだけど壁調査団のところはもうわからない。ラクダを針の糸に通すより金持ちが天国に行くのが難しいことを逆転の発想にするところは好き。目に入ろうとしてぐんぐん体が小さくなっていくところはなぜか爽快だった。涙が溢れてその洪水に巻き込まれるのは理解を超えてくる。けど好きな場面。ノアが出てくるけどノアも洪水に巻き込まれる。最終的に主人公は壁となる。どういうこと?なんかの比喩だとしてもよくわからん。
バベルの塔の狸もいい。なんだかワクワクしながら読んだ。影を取られたらその結果の原因である身体まで透明になるという説得力。過去の賢人たちの狸がどうしようもなく低俗なもののように書かれている。面白い。
赤い繭の連作が好き。
主人公の衣服と身体が解けて赤い繭を形成し、自身の自宅を作り上げる。最終的にはその自宅に住まう身体がなくなっているという皮肉。
赤いチョークのお話も好き。
Posted by ブクログ
中・短編集。
3話すべてに「壁」が登場するが、最初の『S・カルマ氏の犯罪』がもっとも壁との関わりが深い。
名前を奪われたカルマは人権も失い、裁かれ、監視される存在となる。
心の空洞には砂漠が広がり、そこに成長していく「壁」がある。
それは自由を守る壁ではなく、束縛の壁?
やがてカルマ自身が壁になってしまう。
そこには感情が描かれず、ただの壁、ただの物質と化したということなのだろうか。
結末にどんな意図が隠されているのか正直わからない。
それでも、不思議と強い印象を残す、面白い作品だった。
Posted by ブクログ
あまりに奇妙。5作あって、1作目は慣習的に生きていた男が名前を名刺に奪われ、それぞれの役割を無機物に奪われる。慣習から外れると無機物が有機物になるための蜂起、不条理な裁判、ガールフレンドのマネキン化、など様々な困難に巻き込まれる。途中雑誌の1ページの荒野を胸の穴に吸い込んでしまって(恐らく名刺に奪い取られたものの隙間)荒野に生息している動物に魅入られ魅入るようになる。その胸の穴に次は壁を吸い込んでしまい、父親がラクダと裁判に関与していた病院の先生と共に"探検家"という名称で主人公を解体しようとする。最終的に主人公は胸の中の荒野で壁そのものになってしまった。
2作目は詩人がタヌキに陰を奪われ透明になり、そのタヌキが知能を手に入れる。たぬきに、たぬきだらけの異世界に連れていかれるも、詩人は"たぬきは人間の影を手に入れて人間を空へ送る"という不条理だが何故か説得力のある理由で塔の中で死ななければいけなかった。なんやかんやありタイムマシーンで影を取られる前に戻り影を奪われることを阻止する。
3作目はその辺の家全てが自分の家かのように思えるが、聞くとそれは他人の所有物であり混乱しながら自分の家を探し求める男の話。そのうち足から順に頭まで糸のように解けていき主人公を包む中が赤い繭になった。外装という家を手に入れたけど今度は中身が無くなってしまった。
4作目労働者階級から富裕層まで順に水人間になってしまう世界の話。富裕層は巨大な壁を作り水人間から逃げるが、その巨大な壁を作るために労働者を用いてるので意味が無かった。
5作目壁に書いたものが太陽に当たらない限りは実物になるという魔法のチョークを手に入れた貧乏な画家が、食べ物、ドア、女、などさまざまなものを書き出す。ドアの向こうの世界はまっさらだったので、新聞で見つけた女をアダムとイブのイブに見立てて新世界を創造しようとするも女に殺されかける。女はドアを開けた瞬間太陽にあたり壁に戻ってしまうが、その直後、いまや壁の食べ物でできている主人公も女にかさなるようにして壁に戻った。
それぞれの物語に共通してるのは、壁が分節化の境界線であることだと思う。第2作目で透明化した詩人が壁があることで自分の存在や定義を再確認し安心してる描写と、3作目の赤い繭で壁を手に入れて分節を手に入れるような描写もあったことからも読み取れる。4作目の洪水に関しては労働者階級と富裕層を壁によって分節化しようとするも全員水になって同一化してしまうという皮肉的なもの。絶望的で、不思議な世界なのに完成されていておもしろかった。
Posted by ブクログ
これぞ安部公房!といった感じの意味不明な設定(いい意味で)の物語が盛り込まれている。宗教観のようなものも含まれていたため、宗教(特に旧約聖書)の知識があるともっと違った見方もできるのかもしれないと思った。意味がわからず、1文を何度も読み返しながら頭をひねらせてくる安部公房、さすが。
Posted by ブクログ
壁。人間とは壁なのだ。
いや、ちょっとこれは、挫折するよ。
と言う難解な小説。
意味わからん。。。なんなの荒野を吸い込むとか、名刺に名前を奪われるとか。。
とっても安部公房らしい、文体とリズムではあるし、短編ではあるけど、難しかった。。Sカルマ氏という名前はなんだったの。
でも、これ、この時代に書いてるのやばいな。
ベルリンの壁崩壊のだいぶ前なんよね。
壁というのは、人と人の境とも読める。
真理に対しては大衆はいつもかたくなな壁である。(引用)
Posted by ブクログ
Podcast「夜ふかしの読み明かし」の読書会で取り上げられていた一編、第一部の「S・カルマ氏の犯罪」を読んだ。
見渡す限りの荒野、静かに果てしなく成長してゆく名前を奪われた壁による、問わず語りの「おかしなことばかり多くて、普通のことがほとんどない」多分“ぼく”にはあまりむかないのだと思った”現実“の数日間。
名刺に名前を奪われたり、身のまわりの品に存在理由をかけた闘争を仕掛けられたり、永遠に続く裁判にかけられたりする現実に向いている人はまあいないと思うし、そのわりに冷静に話しますよね、と思いながらも、これは現実をあきらめ、自由を奪われた独房の孤独のなかで、それ故に語らざる得ない哀しい物語のような気がしてくる。
とはいいつつ「構想が熟したと思ったとたん、とつぜん自由になった感じがした。ペンが躍り出し、四十時間ほど一睡もせずに一気に書上げることができた。」と阿部公房自身のちょっとボーストも入っているぽい発言の通り、語りは丁寧でテンションも抑えられているけれど、物語、“現実”はまさに踊るようにあちこちに自由にステップを踏んでいく。わたしも遅れないように頁をめくっていく。「難しいんでしょう?」という事前のイメージが溶け出して、「何を言っているんだか、きっと、自分にも分かっていないんだわ。」というセリフに、まさか公房さんも、と多少の勘繰り(バーナード嬢曰く。の神林のイーガン的な)を入れつつ、驚くべき出来事や不条理な状況、わたしにも絶対に向いてない“現実”を理解、解釈する前に純粋に自由に楽しみながら読み進めていたのだった。
こういう小説(古典、かつ難解な作家のイメージ)を読むときには構えて、理解や解釈をしようとしてしまうのだけれど、自分なりにグルーヴを掴めたなら、ただ楽しめば良いのだ、と思い始める。そうやって読んでも、引っ掛かりや残るものは確実にあって、それは後から考えたり話したりしたくなるものだから。そう考えると読書会って思っていた以上に重要かつ楽しそう、と冒頭に書いたPodcastを聞き直しながらわたしの思いつきも口からも溢れそうになるのだった。ああ、わたしのお気に入りのシーンや解釈の前の思いつき、死にやすい法学者やロールパン氏のキャッチャーな魅力、登場時によってマネキン〜生身にグラデーションする彼女の状態は“ぼく”の心情の表れなのか、壁は隔たり拘束するものでもあるけれど、逆に護るためのものでもあって、その壁自体になることとは…など、あと阿部真知(パートナーなんですね)による本文中のカットの不気味カッコよさも少し高めのテンションで誰かに聴いてもらいたいところです。読書会良いなあ。
Posted by ブクログ
ずっと途切れることのない不条理の連発に読書の快楽を感じた。
こちらに考える猶予すら与えずに繰り出されると、それは受け入れざるを得ない上に予想もできないのだからひたすらに驚き、それが娯楽性に繋がっていた
Posted by ブクログ
バベルの塔の狸
魔法のチョーク
事業
現実とは事実なのか、改めて考えさせられる。
シュルレアリスムによって非現実を現実化する方法を学んだとされる安部工房。
夢や無意識、偶然と言った意識でコントロール出来ないものが現実を凌駕するような感覚は今だからこそわかる。我々が普段当たり前に区別しているであろう現実⇄非現実の区別が曖昧になる。そればかりか、今の自分には非現実の精神世界の方が不可欠な物のような気がしている。
世界観が好き。文体が海外作家っぽい。
Posted by ブクログ
見たことあるはずが無いのにありありとヴィジョンが浮かぶ圧倒的な描写力と自分でも気が付かなかった心情をピッタリ同値な比喩で表現されて、ヤバババ〜
Posted by ブクログ
1、児童文学を読んでいたなら意外にも、サクサク読めると思います。
何故ならば、物が喋りだすといった非日常的設定を自然に取り込むことができるからです。
2、シュールな出来事のボケだけでなく、掛け合い等のボケもあって、そこが特に面白いと思った。
3、S・カルマ氏の犯罪のあとに続く短編はもう少しわかりやすく、短いので読みやすい。
Posted by ブクログ
不思議な物語である
話の筋がメチャクチャだか
テンポがいいので心地よく読める
キュビズムみたいに誰でも書けそうだか
安部公房しか書けない言葉
裁判のシーンは水ダウの小峠が出演した
「どんなにバレバレのダメドッキリでも芸人ならつい乗っかっちゃう説」を思い出しクスリとしてしまう
Posted by ブクログ
新潮文庫、昭和44年発行版を読んだ。
収録作は「S·カルマ氏の犯罪」、「バベルの塔の狸」、「赤い繭」(赤い繭、洪水、魔法のチョーク、事業)。
全編を通して悪い夢でも見ているような感覚であったが、面白かった。
「赤い繭」は国語の教科書にも載せられているが、なるほど一番まとまりがよく、短い中に安部公房のエッセンスの詰め込まれた作品であると気付かされた。
Posted by ブクログ
本書は『砂の女』で知られる安部公房の芥川賞受賞作。
ある日、名前を失ってしまったことで、
社会の外に放り出されることになった主人公。
その世界は奇妙さを増していき、
ある意味で支離滅裂な夢のようなイビツなものとなっていく表題作の『壁』と、
他、二章からなる作品です。
非現実的なタイプの小説です。
現実性からかなり高くジャンプしています。
そこには、現実性の強い重力から逃れながらも、
現実性から逃れたがゆえの、
孤独による、よるべなさのようなものがあります。
しかし、その世界観といい、文体といい、
何故かとても心地よくもあるのです。
その幻想世界にある、現実社会を照らすするどい寓意。
それはメインに表だって飾られたものではなく、
うっすらと感じる程度に内包されているというか、
抽出的に読解してみることで感じられるものだったりします。
また、村上春樹の『世界の終りとハードボイルドワンダーランド』の
「世界の終わり」の部分はこの『壁』から大きな着想を得ている感じがしました。
もう、アンサーソングみたいに書いたんでしょう?ってくらいです。
「世界の終わり」で街を取り囲む「壁」というモチーフといい、
主人公とはがされた「影」の存在といい、この『壁』と共通しますね。
科学が、先達たちの業績の上に積み上げていく形で
少しずつ発展しているものであるのと同じように、
作家も、先達たちの切り拓いた先をさらに切り拓くように、
バトンを受け取って仕事をするのが、こういうところからわかりますよね。
数年前に『砂の女』を読んだ時には、
まだピンとくるものが弱かったように思うのですが、
今回、安倍公房の本作品を読んで、
皮膚感覚といったような自分と近い感覚での読書体験をすることができ、
おもしろかったので、また、彼の作品をそのうち読んでみようと思います。
Posted by ブクログ
・起きたら名前がなくなってたり、服が喋り出したりとファンタジーな世界のようで、何故か現実に起こりえそうな気がするリアル感、緊迫感を持って展開される、安倍公房の不思議な世界観の物語。
・「壁」がテーマになっており、主人公によって色んな壁の解釈をしていた。第一部にあった「遥か彼方に見渡す地平線と、目の前のある壁は同じ」という主張が、分かりそうで分かり得なかった。
・物語として読みやすい内容ではあったが、その一歩先の安倍公房の主張や考えを読み解くことができなかった。砂の女の方がその辺りは読み取りやすかったように思う。壁はデビュー作である一方、その10年後に砂の女は書かれているからかな。ただ、安倍公房の主義主張が色濃く記されていることはひしひしと感じ取った。もう一度時間を置いて読み直してみたい気持ちはある。
Posted by ブクログ
皆がまず真っ先に思うのはとてもカフカ的だということ。カフカからの絶大な影響を受けた影が、己の背後から忍び出て目の前で踊り出すぐらいには前面に出ている作品。
安部公房の作品はストーリー性のある砂の女や密会、哲学的な方向へ重心を置いた箱男、など前衛的な作品でいっぱいだが、その中でも哲学的に軸を置いた作品のように感じた。
Posted by ブクログ
一部はシュールレアリズム文学としてまだついていけたけど、二部はもうダメだった、意味わからんすぎる、不条理の果ての果て。三部の短編集は薄っすら既読感があった(『赤い繭』と『魔法のチョーク』)。星新一を哲学方向に完成させたというような印象。『事業』は面白かった。表現こそ安部公房的な言い回しだらけなんだけど、構成は筒井康隆ぽいし内容は星新一グロ増しといったところか。他の作家の名前出さないとなんか言えないなんて、感想文としては三流も三流だろうけど、物語の枠組み自体が崩壊したようなものばかりで、そのままでは私にはとても受け止めきれない。だから既知の枠に無理矢理にでも収めて安心したくなっちゃうんだろうな。文学を多少かじった人間の逃避本能出てんのかも、知らんけど。