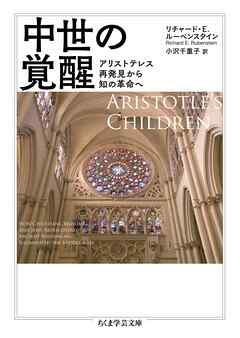あらすじ
12世紀の中世ヨーロッパ、一人の哲学者の著作が再発見され、社会に類例のない衝撃を与えた。そこに記された知識体系が、西ヨーロッパの人々の思考様式を根底から変えてしまったのである。「アリストテレス革命」というべきこの出来事は、変貌する世界に道徳的秩序と知的秩序―信仰と理性の調和―を与えるべく、トマス・アクィナスをはじめ、キリスト教思想家たちを激しい論争の渦へと巻き込んでいった。彼らの知的遺産は、現代にどのような意義を持つのであろうか。政治活動の発展と文化的覚醒が進んだ時代の思想を物語性豊かに描いた名著。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
12世紀のイスラミック・スペインでアリストテレスらの古代ギリシャ哲学が再発見されたことを契機として、当時の西欧社会が神や被造世界などの信仰上の概念について理性的な立場から理解を深めていく様を描いた書。アリストテレスのテクストには当然にキリスト教信仰と明確に対立する点があったが、宗教的世界観と理性的世界観が、度重なる論争の中で相互に変容を見せてゆく姿がスリリングに描写されている。
その相互変容を媒介したアリストテレス哲学も、近代以降の啓蒙哲学の発展の中で、次第に過去のものとして否定的に語られるようになる。近代以降の西欧社会が大量消費と大量生産に向かう中で、それまで支配的であったカトリック協会が押し付けていた社会的くびきを否定する必要にかられ、そこで「中世的なるもの」を全て排除するついでに、カトリック協会が権威を保つべく利用していたアリストテレスの思想までも排除してしまったのだ。
著者は、宗教と理性が分断して久しい今こそ、中世のアリストテレス再発見が媒介したような宗教的思想と科学的思想の「統合」が必要だと説く。安易なアイデンティティの確立でなく、信仰と理性の創造的な緊張こそが、自文化中心的な固定観念を脱しグローバル世界を生き抜く重要な手段だというのだ。現在の世界情勢はほぼ逆のベクトルに沿った動きを見せているのは、著者にとってはさぞ残念なことだろう。
スコラ哲学の歴史と主要概念を概観するのに極めて有用だが、それ以上に、相容れない思考様式同士の相剋と対話こそが新たな価値を切り拓くという著者の主張は、ある意味ヘーゲル的でもあり興味深く読めた。
Posted by ブクログ
中世は暗黒ではなく現代科学に連なる葛藤の時代。プラトン思想を取り入れたアウグストゥティヌス的なキリスト教思想が下地にあるなか、アリストテレスの自然哲学が西洋に流れ込んだ。神学と自然哲学の間にある矛盾を調停しようと、信徒たちが様々に思想を展開する。革新的な思想は慣習からの距離ゆえに忌避され、時を待って政治的社会的文化的な土壌が整って初めて受け入れられる。そうして時間をかけて、理性と信仰は棲み分けが進んだ。社会に通底する正しさは宗教から科学に取って代わり、信仰は個人的な領域に追いやられた。しかし、科学と宗教の境界に位置する心の領域には、未だ科学では手が届いていない。共通の理念が失われ、科学が十分に及んでいない範囲にある政治や法や倫理の分野には、信仰を復活させる必要があるのではないか。個人個人が持つ信条を対話により互いに折衷していくことで、共通理念を形成することはできないか。そのためには、各人がそれぞれの持つ理念を自ら分析して科学や他者の理念と調和させる、すなわち、個人の領域内に神学的な態度を持ち込む必要があるのではないか。中世の思想家たちの歴史に胸を打たれるだけでなく、現代を生きる自分にとっても大きな学びが得られる本だった。
Posted by ブクログ
本屋で見かけて。「一四一七年、その一冊がすべてを変えた」に似ていると思って読んでみたが似ていた。ルクレティウス再発見の代わりにアリストテレス再発見。ただし1417よりさらに壮大で上を行くおもしろさ。
中世は無知の暗黒時代と言われるがそうではなかった。アリストテレスの理性とキリスト教の信仰を調和させる中世の努力が近代科学の道を拓いた。現代の人間科学(道徳、政治、社会関係など)の課題は理性だけでも信仰だけでも解決できず、中世のような理性と信仰を調和させる活動が今こそ必要である、という主張。
ドゥンス・スコトゥスやオッカム(の剃刀)によって理性と信仰が分離していく転換点が印象的。理性を追求すればいずれ神を理解できるとしたトマス・アクィナスに対し、いやいや神は理性では理解できない、信仰によってのみ理解できるとして分離した。キリストでなくロバでもよいとかわざわざ過激に主張するオッカムが好き。結果、早くも14世紀にはビュリダンのインペトゥス理論やオレームの地動説まで出ていた。日本ではまだ足利尊氏の時代なのに。
西洋だけが知の革命を成し遂げた理由に興味がわいた。イスラム文明のアリストテレス主義者は一般の知識人だったのに対して西洋文明のアリストテレス主義者は聖職者でもあったので社会変革に至ったとの説明があったが、それだけとも思えない。なぜ唯名論が実在論に勝てたか。また一神教でない中国や日本で知の革命はなぜできなかったか。
Posted by ブクログ
これは面白い!中世ヨーロッパにおけるアリストテレスの再発見と受容の話なんだけど、中世と聞いてイメージするステレオタイプの「信仰と迷信に支配され、合理的・科学的思考のない時代」を覆すストーリーを展開する本。あまりに魅力的で異端的だったアリストテレスの自然哲学を、あくまで教会内で、信仰という土台の上でどう消化し、カトリックの中のものとするのかという数百年にわたる論戦(ときに暴力)を時々の登場人物にフォーカスして語る。異端思想の源泉として警戒・禁止されつつも、押したり引いたりを繰り返しながらカトリック神学の中心に咲き誇り、そして時代の権力や経済力が教皇の手を離れていくに従い、教会の枠を離れていく複雑な流れをわかりやすく書いてくれてとても面白かった。翻訳も自然で読みやすくて良かったと思う。著者は中世も神学も専門でないのに、こんなに書けるなんてすごいなあ。
Posted by ブクログ
ヨーロッパ中世において教会からの抑圧、弾圧が強烈だったのはイメージ通り。しかし決して知的、思想史的にに停滞した時代ではなかったことがよくわかった。ただし各思想の読解は簡単ではない。何度か再読したい本。
Posted by ブクログ
500ページでものすごいボリューム
でも、とても楽しかった
カトリックしかなかったところに、全く違う完成した価値体系がある日突然、現れる
プラトン・プロティノス 的なキリスト教と言ってもいいのか、アウグスティヌスからの伝統である「信仰」という方法に、アリストテレス的な価値体系である「理性」が出会う。
まずは2つの調和が目指されるが、最初は読み解かれるのに1世紀くらいかかったものの、そこからは新たな考えがどんどんとうまれ、そこに驚異を感じたカトリックからは異端とされたりもし、でも、理性と戦うにはカトリックにも理性が必要として推奨されもし。
カトリック体制、ドミニコ会、フランチェスコ会と、パリ大学などの大学のそれぞれで、アリストテレスをいかに援用していくか、試みられる。
そこにはしかし、二重真実の萌芽が芽生え、最初は、理性と信仰がぶつかるところでは信仰をとるべき、と、二重真実をひとつにまとめる階層があったもののオッカムによって明確に自覚、分離され、そこで理性と信仰というものが排他的になることで純化、独立していくことで、理性を拒否した信仰としてマルティン・ルター的な宗教改革が芽生えていき、信仰を拒否した理性として近代科学が立ち上がる。
そしてその分離は今も残っているという感覚が常識であるが、そこかしこで実は半端に混ざってもいる。
アインシュタインが、神はサイコロをふらない、と、量子力学を否定しようとしたように。
でも、科学の時代は、倫理を欠いて、中絶の問題には答えられない。
再び、理性と信仰が調和するところに、アリストテレス的な方法を考えなおすべきでは、という話。
たしかに、自然学、形而上学と、論理学だけでなく、そこに二コマコス倫理学があるようなアリストテレス的な知的体系こそ、今日の知者の全てが基本とすべき広さなのかもしれない。
だから、理性か、信仰か、よりも、専門分化の危険が今日的危険なのかもしれない。倫理観を学んでない人達が人工知能を開発している、というような。