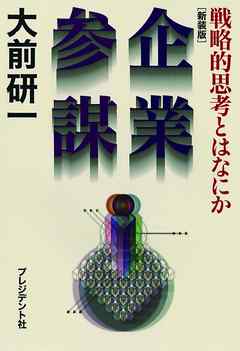あらすじ
世界中のビジネススクールで読まれている大前流戦略論の原点。ビジネスの現場、もしくは日常生活の中で直面する問題に対し、最善策を得るために必要な戦略的思考とは、常に物事の本質に迫るための方法論とは何か。新しい時代の企業戦争を生き残る鍵を握るのは、評論家になり下がったスタッフ集団でも、アイデアを花火のように打ち上げるだけの一匹狼でもない。組織の中にあって、企業の頭取脳中枢として戦略的行動方針をつくりだし、それをラインに実行させる独特の力をもつ「企業参謀」集団だ。29歳でマッキンゼーに入り、その無名時代に取り続けた著者の私的なメモは、いまなおビジネスマンの戦略的思考の入門書として読まれ続けている。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
戦略的思考とは、既存のシステムをものの本質に基づいて分解した上で、各々の持つ意味合いを自らにとって最も有利になるように再構築、攻勢に転じるやり方である
戦略の基本は、世の趨勢を見極め、うまく利用し、競争相手との差が最大になるよう自社のケイパビリティを最大限活用する
そのため、製品・市場分析は肝要
Posted by ブクログ
・ものの本質を考えるために、設問のしかたを解決志向的に行うこと。
×「残業を減らすにはどうすればよいか?」
→ありきたりな回答しか出てこない。
○「当社は仕事量に対して十分な人がいるのか?」
○「当社は仕事の量と質に対して人間の能力がマッチしているのか?」
×「売り上げを伸ばすためにどうしたら良いか?」
→ありきたりな回答しか出てこない。
○「シェアが伸びていないのか、マーケットサイズは増大しないのか、シェアを増やす方法ないか、シェアの決定要因は何か」
・現象から実行計画を立案しないこと。正しくは、現象→グルーピング→抽象化→アプローチ設定→解決策と思われる仮説設定→分析により仮説の立証または反証→結論→具象化→実行計画立案→実行。
52マーケの強い会社は分析をルーチンワークで行えるよう、一定間隔で情報収集をやっている。
分析のための情報収集を断片的に、思い出したようにやっている会社はマーケティングがあまり得意ではないはずで、断片的な分析や知識では正しい経営戦略は出てこない。万一できてもそれは運。必勝を期す戦略的思考家のものではない。
183 KFSについては徹底的に挑戦する
189何ができないか?と考えるかわりに何ができるか?と最初に考えること。そして、その「できる」ことを「できなく」している制約条件を一つずつ執拗にはぎとる戦略を考えていく
(まだ途中)
Posted by ブクログ
レジェンドコンサルタント大前研一の代表作にして、コンサル界の古典とも評される本著。
著者の若手時代のメモ書きがベースになっているだけあり、内容は抽象的な思考姿勢から、実践的な理論とケーススタディまで多岐にわたり、ジャンルレスな一冊と言える。
理論自体は高度なものもあるが、図解も多く、何より非常にロジカルな論理展開なので自分は理解しやすかった。特にPIMS、PPT、戦略策定プロセスは興味深い。
また読み返して、内容を身につけたいと思える一冊だった。非常に良書。
Posted by ブクログ
再読。
ずいぶん歳をとってから改めて読んでみると、若い頃には読み取れなかったことがらが思いの外多く、大変勉強になった。
KFSの大切さ、それは名前自体から自明のことだが、戦略的思考家とは、常にKFSが何であるかという認識を忘れない人のことであり、その人は、全面戦争ではなく、KFSに対する限定戦争に徹底的に挑む、
という。
そして経営とは常に相対的にみた状況判断から始まるということ。市場があって、コンペティターがいて、産業があって。そういう情景を見渡せられる人が参謀たりえる資格があるということだろうか。
Posted by ブクログ
もはや説明不要の戦略本。
とにかく内容は奥が深く、本を読みなれていないヒトが読むとおそらく最後まで読めないと思います。
難しい内容も多いです。ただ、読むべき箇所は
第3章『戦略的思考に基づいた企業戦略』
だと思う。
・企業活動ステップと、ステップごとのKFS
・競合との相対的優位性に基づいた戦略
・新機軸に基づいた戦略および戦略自由度
・戦略設定時のプロテクション(守り)の必要性
この部分が一番読んで仕事に生かせると思った。
この本はたまに読み返すために手元に置いておきます。
おそらく自分が経営層になった場合は必ず役に立つと思う。
Posted by ブクログ
時代を超えて語り継がれる伝統的戦略論、という感じ。
伝統的大企業が、どのように考え、問題解決にあたるかについて説明するもの。
自分のポジションによって、読み返すごとに新しい知見が得られるのではないか。
Posted by ブクログ
企業の全社戦略に関する本。
全社戦略、中期経営戦略を考える視点が網羅されている。
今では当然のようになった考え方やフレームワークが多い。
しかし、これは今だからそう感じること。
この本が書かれたのは約20年前。
30年前からこの域に達していたことを評価すべきだと思う。
しかし逆に言うと、20年経っても変わっていない戦略手法は評価できないのでは。。。
一つの真理にたどり着いているのだろうか?
以下メモ
戦略的思考とは、物事を本質的に分解する作業と、それを別の形に組み合わせ、ソリューションを導き出す行為を指す。
本質に迫るためには、解決策的な問いを立てる必要がある。問いを立てるためには、事象を抽象化するプロセスを経る必要がある。
抽象化のプロセスを経るためのフレームワークとして
・イシューツリー
・プロフィットツリー → イシューツリーよりも収益に特化したツリー、そもそも論を展開出来る。ただし、経営に関する問題に限定される。
中期経営計画策定にあたり、登場する考え方
・PPM
・プロダクトライフサイクル
・製品市場戦略 → かなり良いのでまた読み直す
・SWOT
・What If → もし状況がこうなったら、どの様に考え、あるいは行動、反応したら良いのか?
参謀五ヶ条
・Ifを考える
・完璧主義を捨てるKFS(Key Factors for Success)を徹底的に
・物事に影響を与える
・制約条件に制約されない
・記憶に頼らず分析
PPMの象限、マトリックスのマス一つずつに対して標準戦略を考える必要あり。
Posted by ブクログ
大前研一さんが若かりし頃マッキンゼーに入社したての時期に、メモ書きしていたものをまとめたものだと冒頭に紹介されています。コンサル会社に入社してまもない社員が本を出版し、またそれがマッキンゼーの売り上げにも貢献していたようで、本国からも色々と横槍が入ったようです。内容は、ビジネスの本質を捉えるための手法などが、理路整然とわかりやすく書かれています。今ではフレームワークが構築され当たり前になっているものも、当時の大前さんの言葉で説明がされています。
私の読んだものは、2003年の第11版なので(表紙がクリーム色)、新装版とは多少違うものかもしれません。
Posted by ブクログ
変革しなければならないのは個人であり企業だが,個人や企業が変わるには「こうすれば変わるのだ」という「気概」が必要になる。ポイントは
(1)目的地に達した場合,守り抜けるものでなくてはならない
(2)己の強さと弱さを常に知り抜いていなければならない
(3)リスクをあえてとる局面がなくてはならない
(4)戦略に魂を吹き込むのは人であり,マネジメントのスタイルである
である。経営者が備えるべき先見性の必要条件として事業領域の規定と明確なストーリーの作成だけでは不十分で,自らの経営資源の配分にムダがなく,また原則に忠実で,かつ世の中の変化に対しては原則の変更をも遅滞なくやっていくという十分条件が備わっていなければならない。
内容については素人にはちょっと難しい。
Posted by ブクログ
企業参謀 (講談社文庫)
著:大前 研一
企業や公共機関には、戦略的問題解決者のグループが必要である。このグループは、問題をいかにしてとらえ、いかに解決してゆくかということに対する専門家である。問題の解決ではなく、評論家の集団に成り下がってしまった今日のスタッフ部門にたんにとって代わるだけでなく、組織の最高意思決定者のための真の戦略参謀である。
こうした機能は、ほとんどの組織に欠けている機能である。日本をとりまく客観情勢の変化は、「おみこし経営」から「コントロールタワー経営」への変革を迫っている。著者の意図は、この遷移の一助となるような戦略的思考家の像を描いてみることであった。
本書の構成は以下の5章から成る。
①戦略的思考入門
②企業における戦略的思考
③戦略的思考方法の国政への応用
④戦略的思考を阻害するもの
⑤戦略的思考グループの形成
数年前に読んだものの、非常に難解であったため、時間をおいて再読。やはり難しい。しかし、その難しさの中に本質を垣間見れ、光を感じる。
本書が記されたのは1985年。インターネットはもちろんスマホもない時代にこれだけの「知」が入り乱れ、飛び交い、著者の中で体系的に持論として展開されている。
時代は違えども、芯を食った歯に衣着せぬ物言いそのままの文体は、今でも輝き、今だからより輝いている。今の日本にない、今の日本に求められている、言い切る。そんな、力強さが文字からもその熱量として伝わってくる。
難しいがまた触れたくなる。
数年後にも再度読み直し、再度教えを請いたくなるような病みつきになりそうな一冊。
Posted by ブクログ
・マーケットサイズは再び増大することはないか
・当製品市場におけるシェアの決定要因は何か。当社がその決定要因を十分持っているか
・プロフィットツリー
・現状の延長線上に解がない場合の戦略的代替案
1)新規事業へ参入:多角化
2)新市場への転出:海外進出など
3)上方、下方または双方へのインテグレーション(垂直統合):石油精製から上方に行けば輸送、採掘などがあり、下方へいけば有機合成化学、ガソリンスタンド業などがある
4)合併、吸収:3)の統合の目的のためだけではなく、単に製品系列を拡充したり、マネジメント力の強化を図るために行う場合もある
5)業務提携:販売網の共有化、部品の共同購入、技術提携など
6)事業分離:別会社設立による専業化による効率経営など
7)撤退、縮小、売却:事業の切り売りから退却まで、全体のために部分を放棄する
・たとえば耐熱ガラスは、用途から見るとアルミ鍋などと競合しているし、贈答品としてみれば化学調味料や角砂糖と競合しているのである。だからこの場合には500円から1万円までの贈答品市場を関連マーケットとしてとらえなくてはならない、そして砂糖ではなく、耐熱ガラス製品を購入する決定的要因を分析し、この要因に影響を及ぼすような販売方法や製品開発をしなくてはならない
・業種の付加価値マトリックス
国内付加価値率/国内付加価値率に占める単純労働人件費の割合
・アプローチ
第一段階:必要性の確立
第二段階:潜在力の評価
第三段階:代替案の選考
第四段階:実施計画を立案、実行
・この業界で成功する秘訣は何か = KSF
・戦略家は頭脳の明晰さではなく、結果のみを問われる淋しい職業である。しかも将軍であれば臨機応変にアドリブで切るのであろうが、参謀は将軍のアドリブが少なくて済むように考え抜いてあげなくてはならない。将軍と、その兵の力量と判断力を評価できなくてはならない
・状況が悪くなるほど、広く見なくてはならないのに、余計狭く見て、もう選択の余地はない、と思い始めてしまう。しかし、万一、目標を「成功」から「最悪の事態を避ける」ことに置換した場合には、様々な選択が自ら出てくる
・大企業で事業部制を取っているところは、形態的に官僚組織を持っている。一方、自由体としての私企業の本来の特徴は、“組織よりは発想”が重視され、予算のうちの可変部分が著しく大きく、状況変化に迅速に対応するという特質を持っている
・戦略という言葉は、戦争における勝利に至る計画をさしているのであろうから、第一に相手がいなくてはならない。したがって企業における戦略計画においても、当然その大前提は競争相手が存在し、その競争相手に対し相対的に有利になるような、かつ、その有利になり方が最も効率的であるような方法を模索しなくてはならない。
・お客様の要望に沿って製品系列を拡充し、少ない経営資源をさらに薄く広げてすべての前線で敗退することは極めて常識的な帰結なのである
・インスタントカメラのフィルム数を20枚から24枚に増やすことにより「なんとはなしにフジ」のイメージに対して少なくとも一瞬のためらいを注入することになった
・戦略的自由度(強化できるオプションの軸)を整理し、打ち手を実現するための費用とその効果をプロットすることで、単細胞的に一つのことばかりを考えずに、それぞれの方向に対して対策ができる
・戦略事業ユニットの究極の姿は、戦略的自由度に沿って存在している既存の組織の軸を、すべて束ねた形でくくってしまうこと。逆にいえば、戦略的自由度が最も大きくなるように事業単位を包み込んでやる必要がある
・いかなる勇者といえども、市場の構造変化を予知し、対処するためには、己の強さと弱さを常に知り抜いていなければならない
・どんなに成功している事業でも、かならずその由ってきたる理由というものがあるはずで、これを見失って経営者の欲望の赴くままに進み始めれば崩壊は疑いない。このため、先見性のある経営者なら、自分はどのような顧客のために、どのようなサービスを提供し、どのようなメカニズムで収益を上げているのか、ということを寸時も忘れることはしないだろう
Posted by ブクログ
〈書評〉
戦略とは何であるか、参謀とはどうあるべきか、企業はどのような体制で企業戦略を作り実行していくべきかというテーマについて、考え方のエッセンスと、エッセンスを具体的なケーススタディに落とし込んだノウハウが書かれている。しかし、著者も言及しているように前者(エッセンス)が重要であり、後者はケースバイケースのため枠組みとしては利用できるが、紹介している型をそのまま当てはめる既製服のよう使い方は想定されていない。
本書が書かれた時代と今では社会背景などは大きく異なるものの、問題解決/戦略的思考の手引きとしては、現代でも充分に活用できるエッセンスが散りばめられていると思う。
〈メモ〉
・「戦略的」=事象を本質的な境界線を頼りにバラバラに分離させ、自身の目的達成に有利になるように組み直し、攻めに転ずること。
→「本質的」な分解と再構築とは何かを考える
・企業戦略の立案において、自社状況などの内部に目を向けるのはもちろん、市場や競合他者などの外部にも目を向けて、分解と再構築の見通しを立てる必要がある。
・特に、市場における「KFS」が何にであるかを掴むことが最重要事項の一つである。
・参謀心得
→「If」を恐れない:常に代替案を探り、どんな状況にも対応できる構えを取るべき。(※日本人は古くは中国、近代では西洋などの先行事例への依存、そして言霊的なシャーマニズムに由来して、「もしも」に対する準備をする慣習が薄い)
→完璧主義を捨てる:完璧な戦略は存在しない(無限の資源が必要)。競合相手より一枚上手を行くだけで充分。
→KFSには徹底的に挑戦する:二項の完璧主義を捨てるに反するように見えるが、KFS、戦争におけるセンターピンが何であるかに関しては、妥協せず試行錯誤を繰り返して探り続ける。
→制約条件に制約されない:「何ができないか」ではなく、制約条件を取り払った状態で「何ができるのか」を考えた上で、制約条件を突破するためにはどうしたら良いかを考える。
→記憶にたよらず分析をする:惰性や常識にとらわれず、本質的な分解と再構築に向き合う。
Posted by ブクログ
経営者として、企業戦略の定義(他社と差別化できる目的地から逆算した、競争力を活かした攻め方)を顧みたのと、改めて自社の分解とKFSの言語化をしたくなった本。
Posted by ブクログ
オリジナルの本は40年以上前に書かれたものであるが、それでも今なお、変わらない企業戦略の本質が描かれている。 企業がどういう戦略を取るかを考える上での考え方についてまとめられている。
Posted by ブクログ
理解できないことが多かった。印象的なことはKFS。これを考えることは今後社会人とて、ゲームとて何でも重要なことと思える。また読み直したい。次は理解できるように。
Posted by ブクログ
戦略的思考家のKFS=Key Factor for Success=成功のカギ思考が、とても為になり、どのレベルのビジネスマンにも共通する必須な思考法だと感じた。
Posted by ブクログ
企業分析や市場分析の観点で大変勉強になる本だった。
ただ、一回では読み解ききれなかった部分も多いので、もう一回読みたい。
特に、市場の見方についてはとても構造的にまとめられている本だった。
Posted by ブクログ
20代で読んだが正直難しかった印象。
30代になり流し読みで再読すると今ちまたに出ている戦略やフレームワークなど
1970年の内容としては大変先駆けだったのだなと思いました。
この書をきっかけに大前さんの本を読むようになった現在です。
Posted by ブクログ
戦略コンサルティングという仕事が一体何なのかを非常に分かりやすく書いてくれてる。
しかも、かなり多くのケースを使って思考のプロセスやら可視化の手段やらを説明してくれているので、テクニック的な部分も学びが多かった。
個人的には情報収集の仕方にも結構興味があるので、その辺りに触れてる本も探してみたい。
Posted by ブクログ
なかなか難しい内容だった。戦略的思考とはどう言うものか、企業·事業がどのポジションにおいて、経営·意志決定すべきかが述べられている。他にも重要なポイントは何か、留意点は何かということなども。
プロダクト·ポートフォリオ·マネジメント(PPM)についてがメインだったと思うので、たくさんの製品や事業を扱っている企業、つまり大企業向けの話っぽいなと思った。
戦略の立案や分析のプロセスについてはどの企業にも参考になるので、実践してみたいなと思う。
とにかく、一読では理解しきれない内容であるから、何度も読み返して、実践して、(出版されてから時間も経過しているので)最新のベストプラクティスを考慮しながら、思考とその実行力を身につけていきたい。
Posted by ブクログ
古い本だったが特に時代遅れではなかった
一読では全てを理解するのは難しいが、なるほどと思える所が多々あった
戦略的思考
非線型思考
設問のしかたを解決策志向的に行うこと
そのためには、問題の絞り方を現象追随的に行うこと
製品系列のポートフォリオ管理(PPM)
製品・市場戦略とは、実に分析的な仕事なので最初は専門家の助けが必要
参謀五戒
戎1:参謀たるもの「イフ」という言葉に対する本能的恐れを捨てよ
戎2:参謀たるもの完全主義を捨てよ
戎3:KFS(成功のカギ)については徹底的に挑戦せよ
戎4:制約条件に制約されるな
戎5:記憶に頼らず分析を
世の中の「営みごと」はすべて、オン=オフというバイナリー系(二者択一)ではなく、灰色のアナログ系である
新機軸展開方法
1.考え方の転換
2.戦略的自由度
3.技術的ポートフォリオ
戦略的に意味のある計画は、ひとたび目的地に達した場合、守りぬけるものでなくてはならない(プロテクション)
いかなる勇者といえでも、市場の構造変化を予知し、対処するために、己の強さと弱さを常に知りぬいていなければならない
真の戦略家は、リスクを避けるのではなく、リスクをあえてとる局面がなくてはならない
最後に戦略に魂を吹き込むものは人であり、マネジメントのスタイルである
Posted by ブクログ
大前研一30代にして、この企業分析、社会分析をしていたことに大変驚いた。世の中をよく観察し、問題点を見つけ、自分ならどうするのか?どう変革することが将来必要なのかを日々研鑽することで、大前研一にちょっとでも近づけるのかなと感じた。
Posted by ブクログ
経営戦略の教科書。巷にあふれる戦略系のビジネス書に書かれていることは、40年前に上梓された本書に、既に全てが書かれている。
とにかく、『現状分析から現在置かれているポジションと、進むべき方向性を導き出し、具体的な実施プランに落とし込んでいく』という戦略策定〜プランニングまでのベーシックな在り方が、これでもかという程細かく、具体的に記されている。その熱量に圧倒される。
本書は『企業参謀』と『続・企業参謀』が一冊となった本でボリュームがあるため、最後の方はちょっとお腹いっぱいになってくる。が、ビジネスマンは読んでおくべきだ。
本書とドラッガー『経営者の条件』、コヴィー博士の『7つの習慣』の3冊を読んでいれば、ビジネスマンとして基本的なマインドはセットされるように思う。
Posted by ブクログ
1975年出版てすごいな。32歳だったらしい。
なにかで「コンサルをセールスするための営業資料」を狙ってたのじゃないかと読んだが、そんなに胡散臭さもなく、大前健一節みたいなものも胡散臭くない程度に入っていて、とても面白かった。(料理に物を例えるケースはよく見るが、食品の腐敗を未回収投資と呼んだり、償却損と呼んだりする、異様な具体性に笑った)
Posted by ブクログ
かなりの古典にしては今読んでも納得感はある。先見の明とはこういうことかと感心するが、如何せんちと難しすぎて、というか実践に取り入れづらく、挫折。
Posted by ブクログ
上司オススメの一冊
【ざっと内容】
大前研一当時の経済の見方や組織運営の仕方がギュッと詰まった一冊。抽象的な考え方から具体的な指標の見方まで幅広く触れられている。初版は1999年でそれ以来29刷もされておりロングセラーとなっている。
【こんな人にオススメ】
・組織の中心人物、特にNo.1,2の人
【感想】
正直、自分にはまだちょっと難しかった……逆に本作をしっかり理解するためには普段からもっと大観的に組織を見る必要があるなと改めて感じた。
戦略的な組織運営における考え方は参考になることが多かったので、組織のトップを目指す方々は是非一読してみては?
数年後読んだら全く違うところに線を引いてそう。
Posted by ブクログ
『企業参謀』は不朽の名作だと思う。通算3度目の読書だが、自分自身の戦略思考度が上がったと感じるとともに(初読では論理展開力に圧倒された「イカ漁」も今はやや強引で多少の稚拙と感じるまでになった)、本書を32歳のときに書き上げた大前研一氏の知的水準の高さに驚かされる。
『企業参謀』『続・企業参謀』は間違いなく良い本だが、特に改変もせず合体して単行本化というのは芸がない。文庫化もされているのに。ということで星は3つである。
Posted by ブクログ
企業参謀
経営戦略の本
戦略的思考:事象を分析し、ものの本質に基づいて分解したうえで、自分にとって有利なように組み立てていく思考方法
・問題点の摘出と解決のプロセス
①問題点の絞り方を現象追随的に実行
①現象→②グルーピング→③抽象化→④アプローチ設定、必要な手段
→具体的な手段に落とし込む
Posted by ブクログ
ポートフォリオを利用した企業戦略、事業戦略に触れられている。
1975年に売られ、その時から低成長が問題に成っていたんだなって改めて思い知らされる。
戦略というのはどうやって立てていくのかといったアプローチが記載されており、一読の価値はあるように思う。
・what if この場合どう考えるを徹底
・完全主義を捨てる
・kfsを徹底
・制約条件に制約されないこと
・記憶に頼らず分析すること