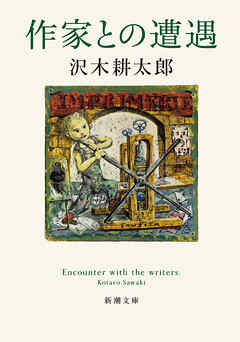あらすじ
少年の頃に開いた書物の森で、あるいは「学校」のようだった酒場の片隅で、沢木耕太郎が心奪われるように出会ってきた作家たち。山本周五郎、向田邦子、山口瞳、色川武大、吉村昭、吉行淳之介、小林秀雄、瀬戸内寂聴など、書くことが即ち生きることだった19人の作家に正面から相対し、その本質を描き出す。誰も知らなかった顔に辿り着き、緊張感さえ孕むスリリングな刺激あふれる作家論!
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
思えば、沢木幸太郎の本を読んだことってほとんどなかった。
今回読んだのは、いろんな作家のことで、紹介分には作家論とある。あとがきを読むと、文庫の解説を集めたものだという。
どれもこれも、するどく個性的だと思った。もちろん、作家それぞれが個性的であるわけだけれど、この本を読むと、登場する本たちも読んでみたくなる。
特に印象的なのは、向田邦子。読み進めていくうちに、あれこれは?と思い、やはり、そうだったか、とはっとする。書かれた年月をじっと見る。
Posted by ブクログ
少女は小説を書く愉しみを覚えた。それは、『しんこ細工の猿や雉』の中の「おとなしい子に御褒美」という言葉を借りれば、物語を愛し、物語の力を信じた少女に、物語の神様が「御褒美」としてひとつの美しい手鏡を与えた、ということと同じであったろう。そこに映せばどのようにでも姿かたちを変えることができる、という美しい手鏡だ。少女は、思うがままに変容させつつ、そこに自分を映し、外界を映していく……。
だが、小説を書くという行為には、たとえそれがどれほど幼くつたないものであっても、どこかに「自らを視つめる」という契機を避けがたく含んでしまうところがある。手鏡は自惚れ鏡にもなりうるが、鏡台の前に座った少女には合わせ鏡にもなりうるのだ。合わせ鏡として自分の見たくない自分を見せてしまうことがある。虚構に夢を織るということを覚えてしまった少女は、好むと好まざるとにかかわらず、常に合わせ鏡で自分を見ているような、自己相対化の視線を持たざるを得なくなる。
ここに「距離の感覚」の萌芽を見出すことはそう難しいことではない。
少女は虚構という手鏡に映すことで自分を見つめることに慣れていったにちがいない。やがて少女は成長するが、しだいにその手鏡なしに自分を見ることができにくくなる。大阪文学学校に入学し、生活記録を書けといわれて戸惑うのは、虚構という仕掛けなしに自分を書く、詰まり手鏡なしに自分を見ることを要求されたためではないか、と思われるのだ。いや、自分だけでなく、外界に対してもその手鏡を通して眺める癖が抜けなくなってしまったのではないか、という気さえする。
『生家へ』の中に、受賞第一作を書こうとして、「夏には水をガブガブ呑む。それが弥助の健康法である」という一行を書いただけで行きづまってしまう挿話が出てくる。その一行から推測するかぎりでは、彼は自分から離れた外部に物語を作り出そうとしていたかに見える。だが、『黒い布』が力のある作品になったのは、父親という圧倒的なモデルが存在していたからであり、もしそれに匹敵するものを書こうとすれば、当時の若い彼にとっては自分自身を素材とする以外はなかったはずである。父親と同じかそれ以上に綿密に見つづけている存在がいたとすれば、それは彼自身しかいなかったからである。しかし、彼の視線は内に向かわず外に向かった。多分、若い色川武大には自分自身を書く準備ができていなかったのだろう。準備とは、自分をどう書くかという方法を探り当てることであり、それ以上に、曖昧なままで済んでいる周囲の人間との関係を明確にしていく覚悟を決めることである。陽の光にさらされた「関係」は、自分だけでなく他人をも傷つける。当然それは現実の生活の中で返り血を浴びることにもなるのだ。『黒い布』では、父の視点から自分を見させることで自身の内面の表白を巧みに避け、しかもそれが卓抜な自己批評にもなっているという効果を上げることになったが、真正面から自分を書こうとすれば、どういう形であれ内面が露出していき、「関係」に新たな緊張を加えることになる。だが当時の彼は、生活自体が極めて流動的であり、「関係」を明確にすることで自分が座らなければならない位置をはっきりさせてしまうことを、どこかで恐れていたのではないかという気がする。とにかく《爾来十六七年、私は小説というものから逃げるようにばかりして来た。小説ばかりでなく、あいかわらず、自分自身からも遠ざかろうとしていた》(『生家へ』)のである。それが色川武大としての筆を鈍らせた。