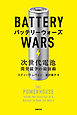田沢恭子のレビュー一覧
-
-
Posted by ブクログ
著者のツァイリンガー博士は実験物理学者で、量子テレポーテーションの実験などの功績で2022年にノーベル物理学賞を受賞している。
本書は学生に実験をさせて、観測されたデータが意味することを議論させるという形式で説明が進む。
博士自身が、実験を通して試行錯誤してきた様子を表しているのだと思う。
「世界一わかりやすい量子力学」という日本語タイトルは、本書の内容を的確に示していない。
原書タイトルは、「Dance of the photons : from Einstein to quantum teleportation」で、
直訳すると「光子のダンス:アインシュタインから量子テレポーテーション -
Posted by ブクログ
最初にひとこと言わせてもらう。「どこが『世界一わかりやすい』ねん!!」です。以上。
と、これではレビューにならないのでもう少し。著者は実験物理学者で、2022年にノーベル物理学賞を受賞している。
本書の肝は「量子もつれ」「量子テレポーテーション」「ベルの不等式の破れ」であると、私は解釈しました。「量子もつれ」に関しては、私は一応存じ上げているつもりなのですが、後の2つについては正直よくわかりません。いや、「ベルの不等式」がそもそも知らない。
それぞれの言葉の説明については、本書を読めば書いてあるのですが、私の理解の範囲を今のところは超えています。著者が実験物理学者なので、実際に行った実験をモデ -
Posted by ブクログ
私たちが量子という言葉を作り、発見し、研究し、実用可能な現代(2025)まで長い月日を経過した。これもひとえに量子力学視点からすると量子という存在が発見して確定した時から今日や未来の先までが創られているのだろう。
本著はとても図解を通してわかりやすく教えてくれる。量子力学とは何か、それがどういうことが出来るのか。私たちが知っている通常のパソコンとは次元が異なる演算能力を持っていることは確かだろう。
本著を読んで思ったことは、量子や量子もつれという存在は人間に似ているなと思った。量子力学では観測した瞬間に確定するという。人間も何か意識して行動した瞬間に確定すると似ていると思うのだ。私たちは120 -
Posted by ブクログ
ネタバレ核融合は、投入エネルギーよりも高い出力があるか、が問題。ブレークイーブンを目指している。ここに到達するか、はライト兄弟の飛行機の発明くらい革命的。あとは改良すればいい。
地場閉じ込め核融合と慣性閉じ込め核融合の2つの方法がある。
水素がヘリウムになる核融合のほかに、大きな構成は炭素窒素酸素(CNO)サイクルもある。
恒星は安定化装置があって、概ね同じ大きさを保てる。質量が増えるとサイズが収縮する。密度が上がるので各有業反応が高速に起きる。温度が上がるので、重力に逆らって膨張する。密度が下がって核融合の速度が落ちる。温度が下がる。再び収縮する。
欧州のJET、トーラス共同研究施設。地場でプラ -
-
-
- カート
-
試し読み
Posted by ブクログ
「物」を手に入れてウットリした経験がある。
キラキラするものや精巧なもの、自分自身のステイタスを上げてくれるようなもの。人は物を何故愛するのか。その前に、何故、物を必要とするのかを考えてみたい。
それは生存のための日用品だったり、帰属や権威を示すためのものや自己表現のためのものだったり。生活必需品、家電、玩具、ファッションアイテム、書籍、ガジェット、家や車。それに留まらない。飛躍するが、ペットや他者を所有品としてみたり、自らの身体の一部、能力や集団だってモノ化して見る事さえある。
所有の対象を「モノ」とする。しかし、私自身も「モノ」化する事で、所有の対象になり得る。人間社会は人間以外と人 -
- カート
-
試し読み
-
購入済み
2巻目
2巻目では、冷戦の初期からキューバ危機、そしてケネディ政権の政策やその後のジョンソン・ニクソン政権下でのベトナム戦争までを詳細に取り上げており、特に、キューバ危機を中心にケネディのリーダーシップとその背景にある歴史的文脈が非常に詳しく描かれている。ストーンはケネディにかなりの比重を置いており、その決断や政策が世界の平和にどのように影響を与えたかを掘り下げ、ケネディの歴史的役割を再評価するうえでの新たな視点を示している。
-
3.3 (3)
-
3.3 (3)
-
Posted by ブクログ
訳者後書きにあるように、薄い小冊子ながら知識の細切れというよりは著者のユーモアも交えながら天文学の歴史を感じることができた。
一貫して著者の念頭にあったのは
「地球でのふつうは宇宙でのふつうではない」
という言葉に集約できるだろう。
ただ、最終章には著者の想いが強く出てしまったのだろう。読んでいて非常に違和感を感じてしまった。
本書のタイトルが著者の想いであることから主旨としては良いのだが、これまでの宇宙スケールの話が極端に一個人のスケールにまで収束してしまい(書いてある内容は宇宙視点の話なのが皮肉である)、言い方は悪いが著者がアメリカ人気質が全面に出てしまった感が否めず、残念であった。 -
Posted by ブクログ
単行本『忙しすぎる人のための宇宙講座』から改題されたそうだけど、元のタイトルの方が良かったんじゃないか?しつこくつっこむなら「忙しい人のための」が。
確かに最後の部分は、価値観というか近視眼的なものの見方の変革を迫る感はあるけど、そこに辿り着くまでは、どうにもタイトルへの違和感がつきまとう。
このレベルの内容をさらっと理解できる人には、目新しいこと書いてるわけでもないし、この内容が人生変わるほど新しく感じる人は、多分内容を理解できない気がする。
あと、薄さから「このくらいなら読めるかも」と思うと、それなりに時間かかるかも。読みやすいことは読みやすいけど。
-
-
-