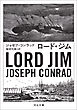ジョゼフ・コンラッドのレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
大自然の雄大さと人間の心の闇を世界に曝け出した問題作。
世は植民地時代、主人公が血生臭い経験をしながら、アフリカ大陸奥地にある貿易会社の拠点に赴くと悍ましい光景が広がっていた。
おおまかなあらすじはこの小説に辿り着いた読書人なら誰でも知っているかもしれない。
しかし、その中の一定層は、この手の小説に冷ややかな視線を向けるのではないだろうか。
「そういう重たい話は現実世界で十分だ」
「読んでいて疲れるのにはうんざりしている」
私はこのような気持ちから、発売直後に購入したにも関わらず、約三年もの間積読していた。
重い腰を上げたキッカケは些細なものだった。なんとなく近代の海外文学を読みたく -
Posted by ブクログ
大英帝国の繁栄を担う貿易商社員がコンゴの奥地のジャングルで目にしたものは、誰もが目を背けたくなるのような現実だった。19世紀のヨーロッパの植民地主義は、文明的、人間的に劣後した地域をキリスト教的な理想主義のもとに啓蒙するという高邁な使命によって、貿易利益の独占、資源的搾取を覆い隠すような陳腐なショーであった。クルツというヨーロッパ人を象徴として、人間性の闇、文明人が未開人になり、未開人が文明的になるその皮肉を、陰鬱で明快な表現で書き上げている極めて歴史的価値が高い一冊。ヨーロッパの植民地主義を人文的に一考する上で、欠かせない一冊であろう。
-
Posted by ブクログ
植民地支配の醜悪さがきつい。
何度かヨーロッパに戻れる機会があったのに、思いとどまったクルツの心情を考えながら読む。
未開の地に西洋文明を教示、ついでに象牙で一儲けのつもりが、身も心も自らが軽蔑する蛮人以下になってしまう。身を守るために残忍にならざるを得ない、ジャングルの圧倒的な自然と、そこに住む人たちのわけのわからなさ。
多面的でいろんな読み方ができる本だと思うけれど、逐一、対比がはっきりしているのでストーリーや会話の意図はとりあえずは読み取りやすい。
例えば船に乗組員として乗せた食人族が、白人のマーロウ達を飢えていたとしても襲わなかったこと。それに比べてクルツが奥の駐在所の入り口に無数の生 -
Posted by ブクログ
古典を読まなくなって何年にもなる。十代、二十代の頃は、向学心も強かったためか古典ばかり読んでいたのに、今は新作の追っかけに四苦八苦してそれで済ませている自分がいる。でも古典は、今も時に気になる。未読の古典はずっと心の片隅で消化されることなく遺り、燻り続ける熾火である。
本作は多くの方とおそらく同様に映画『地獄の黙示録』を契機に知ることになったものだ。コンラッドという作家は冒険小説作家の起源みたいなものである。ぼくはパソコン通信時代<冒険小説フォーラム>に入りびたり、ついにはSYSOP(システム・オペレーターの略でフォーラム運営者を言う)にもなりゆき上なってしまったが、恥ずかしながら冒険小 -
Posted by ブクログ
雑誌BRUTUSの村上春樹特集で、本人が選んだ51冊のブックガイドの中でまだ未読だったものの1冊。コンラッドの名作『闇の奥』は読んでいたのだが、同じ語り手マーロウが登場する他作品ある、というのはそもそも知らなかった。
コンラッドの作品は、基本的に植民地支配がテーマであり、本書ではインドネシアのスマトラ島が舞台となる。主人公は、多くのイスラム教巡礼者を乗せた客船が沈没寸前となったことから客船を見捨ててボートで逃げ出したイギリス人航海士のジムという男である。彼が自らの名誉を回復せんがごとく、スマトラ島の未開の地を開拓し、現地人のリーダーとしてコミュニティを作っていく・・・というのが大まかなあらす -
Posted by ブクログ
ノルウェイの森の永沢が敬愛する作家の一人として挙げていたジョゼフ・コンラッド。漠然とした興味で手に取ったのが本作。既訳が何個か出ているが柴田訳を見つけるまでに何度も挫折。最初から柴田訳を見つけておけばよかった。。
訳文を読んだだけで原文のコンラッドの英語の硬質そうな感じが伝わってくる。感情の描写では一読しただけでは理解に苦しむ部分も多く、なかなか噛み砕けなかったが風景の描写自体はかなり克明というかリアルで海原を進む船の様子がはっきりとイメージできた。
爆笑問題の太田が本作を「線路に倒れた人を助ける勇気がないのが人間だが自問自答を続けることで助けられるようになるのも人間なのだと教えてくれる作品」 -
Posted by ブクログ
ネタバレ脚注25 "十九世紀の世界地図では、諸大国の領土を赤(イギリス)、青(フランス)、オレンジ(ポルトガル)、緑(イタリア)、紫(ドイツ)、黄色(ベルギー)の各色で色分けしていた。" p.204
"油のようにねっとりとした波が大儀そうに艦をもち上げては下ろし、細いマストを揺らしている。" p.35
これぞ目の当たりにしたものの描写と思える。想像では、こうはいかない。
" この黒人たちが緩慢な死をとげつつあるのは、ひと目でわかった。彼らは敵でもなければ犯罪者でもなく、もはやこの世の者でもない――病いと飢えにからみとられ、緑がかった薄暗闇のなかに -
Posted by ブクログ
日本縦断サイクリングに持ち込んだ本のうちの1冊が本書だ。面白く、かつ、サクサク読み進められない、というのが選択基準だ。結果、本書と『ホモ・デウス』を持ち込んだが、サイクリング中は主に『ホモ・デウス』を読んでいたので、本書は帰宅後読み進めることになった。
映画『地獄の黙示録』の原案として知られる本書だが、私も中学生の時に観た『地獄の黙示録』が忘れられず、いつか本書『闇の奥』を読みたいと思っていた。新潮社のStar Classicsシリーズの新訳が発刊されたので、手に取ってみた。
1800年代の欧州とアフリカの象牙交易の様子がよくわかる。なんと命の価値の低いことかと感じ入る。
コンゴ -
Posted by ブクログ
19世紀末のアフリカ大陸
植民地化を進める西洋人の、想像を越える未知の世界が広がる。
小説『闇の奥』は、コッポラが映画「地獄の黙示録」を作る際の原型とした物語。
19世紀末のアフリカ、コンゴを舞台とした探検記録のような、それでいて、全編にわたりまとわりつくような熱帯雨林の世界を描き綴っており、ページごと進むのがかなり難儀。
(舞台をベトナム戦争としたコッポラの映画の方が、まだ分かりやすい?)
冒険を求めて、主人公マーロウは何が飛び出すかわからない密林のなかの川を遡上する。
そして、行き着いた“奥”で、不思議な集団を率いていたクルツという人物と出会う。
幽霊の運び手
従順な崇拝者ども
鬱然 -
Posted by ブクログ
うーん
まずこれを飲んだ一番の理由は、コンゴで起きた歴史的人間の蛮行を知りたいと思ったから。つまり、小説というより、ノンフィクション?或いは歴史書的な目的で読んだ。結果として、そういうのというよりは随分と人間の内面を描いた哲学的な小説といった意味合いが強かった。もちろん、「蛮族」達の悲惨さは艶やかな筆記から伝わってはきたが、描写がもの足りなかったというのが正直なところ。つまり、国王のことと、或いは手足の切断についてまるで描写がなかったのは、あれれ?という感じだった。更に言えば、哲学的小説としての話だが、これは私が未熟だからなのか?クルト?にも語り部にもいまいち移入できなかった。およそ現代日本に