学術・語学 - オーム社作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 全国の多くの大学のカリキュラムやシラバスに合った、「光エレクトロニクス」の新たな定番テキスト 電気・電子・通信系学科の専門課目である「光エレクトロニクス」の講義用教科書。基礎となる光の波としての性質についての解説からはじめ、光ファイバやレーザの原理・特性、さまざまな光制御と実際の装置や現在欠かせないものとなってきている各種光応用などについてわかりやすく解説するものです。全体は1コマの講義の回数に合った15章構成をとっており、各章末とも理解度をチェックする演習問題を配しています。 目次 1章 光波の性質 2章 回折と干渉 3章 媒質中の光波の伝播 4章 ガウスビーム 5章 光ファイバの原理 6章 レーザの動作原理 7章 パルスレーザ 8章 半導体レーザの基本構造と特性 9章 非線形波長変換 10章 光制御(電気光学効果) 11章 その他の光制御 12章 光検出器 13章 イメージセンサ 14章 分光器 15章 光波の時空間数値解析法 演習問題略解 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 全国の多くの大学のカリキュラムやシラバスに合った、「集積回路(工学)」の新たな定番テキスト 電気・電子・通信系の大学学部向け2単位用のテキストシリーズの一巻。 本書は、電気・電子・通信系学科の専門課目である「集積回路(工学)」の教科書。MOSトランジスタの基本的動作の解説からはじめ、CMOSを中心として集積回路の原理、特性、設計、実装などをわかりやすく解説するものです。全体は1コマの講義の回数に合った15章構成をとっており、各章末とも理解度をチェックする演習問題を配しています。 目次 1章 集積回路とは 2章 MOSトランジスタの動作原理 3章 CMOSインバータ 4章 CMOSスタティック基本ゲート 5章 プロセスフローとCMOSレイアウト設計 6章 CMOS組合せ論理回路 7章 ラッチとフリップフロップ 8章 スイッチング特性 9章 同期設計 10章 演算回路 11章 メモリ回路 12章 ディジタル回路の設計フロー 13章 CMOS回路の消費電力 14章 寄生素子と2次効果 15章 比例縮小則と微細化の課題 演習問題略解 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 全国の多くの大学のカリキュラムやシラバスに合った、「情報(・符号)理論」の新たな定番テキスト 電気・電子・通信系の大学学部向け2単位用のテキストシリーズの一巻。 本書は、情報通信系学科の専門課目である「情報(・符号)理論」の講義用教科書。情報の数量的な定義や符号化とその限界を解説して、情報量、エントロピー、マルコフ情報源、通信路容量などの重要な概念について理解できるようわかりやすく解説するものです。全体は1コマの講義の回数に合った15章構成をとっており、各章末とも理解度をチェックする演習問題を配しています。 目次 1章 情報理論の概要 2章 事象の情報量 3章 1個の確率変数のエントロピー 4章 2個の確率変数のエントロピー 5章 相互情報量およびn個の確率変数のエントロピー 6章 情報源と符号化 7章 平均符号語長の下界 8章 理想符号語長とエントロピー 9章 情報源符号化定理 10章 マルコフ情報源 11章 通信路と符号化 12章 線形符号 13章 線形符号の具体例 14章 通信路容量と通信路符号化定理 15章 情報理論の発展と応用 演習問題略解 参考文献 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 全国の多くの大学のカリキュラムやシラバスに合った、「コンピュータアーキテクチャ」の新たな定番テキスト 電気電子通信系の大学学部向け2単位用のテキストシリーズの一巻。 電気・電子・情報系学科の専門課目である「コンピュータアーキテクチャ」「計算機工学(概論)」の講義用教科書。情報の表現方法、論理演算を実現する方法を学ぶとともに、演算回路、レジスタファイル、メモリなどのハードウェアの基本部品に関する知識、またそれらのC言語との関係について解説。また、パイプライン処理方式、記憶階層の考え方および実現方法、OSの基本機能、プロセスとその管理の実際、代表的なI/O装置の仕組みなどをわかりやすく解説するものです。全体は1コマの講義の回数に合った15章構成をとっており、各章末とも理解度をチェックする演習問題を配しています。 目次 1章 基本素子と情報の表現 2章 演算器と記憶機構 3章 プログラミング 4章 パイプライン 5章 浮動小数点演算とマルチメディア命令 6章 プログラムとメモリ 7章 キャッシュと予測 8章 スーパスカラとVLIW 9章 アクセラレータ 10章 オペレーティングシステム(OS)の役割 11章 プロセス 12章 記憶階層 13章 I/O装置 14章 仮想化技術 15章 マルチコア向けOS 演習問題解答 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、SAGE社発行の「対応分析(コレスポンデンス分析)」と呼ばれる統計分析手法の初学者向けの書籍「APPLIED CORRESPONDENCE ANALYSIS: An Introduction」の全訳に、訳者が解説及びRを利用する環境構築を加えた構成で発行するものです。 全訳に加え、訳者がRを使って「検算」をしながら解説を行うことで、より理解が深まる構成となっています。また、このプロセスを経ることで、読者はRで提供されている対応分析パッケージを使いこなすことが可能となります。
-
3.0数学は、問題に対するアプローチそのものが、特にコンピュータとの関係では学ぶべき価値がある分野です。 本書は、“A Geek's Guide to the Beauty of Numbers, Logic, and Computation”の翻訳書です。現代数学における「問題のとらえ方」に慣れ親しみながら、本格的な数学を用いてプログラミングの理論や計算機科学の深い内容を楽しく学んでいきます。数とは何かから始まり、一階の述語論理、公理的集合論、群論、有限状態機械、ラムダ計算、型システム、停止問題にいたるまで、計算機がいかに数学と密接に結びついているかを27 のトピックを通じて噛みしめてみましょう。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本電子書籍はA5サイズの書籍より固定レイアウトで作成しました。 ■豊富な写真・図によって測定の基本を徹底理解!! 自家用電気設備の保守・管理を行う電気技術者は、常に電気設備の状態を把握しておき、不具合や異常あるいは故障の兆候が発見された場合には、適切に対応して電気の保安確保に努めなければなりません。本書では、自家用電気設備の保守・管理の現場で使用する基本的な測定器や便利な測定器をとり上げ、その測定原理から取扱い方法、測定上の注意点などを具体的に説明しています。また、測定のポイントや注意点が理解しやすいように、写真や図表を数多く載せています。 ★このような方におすすめ 自家用電気設備の電気管理技術者 ★主要目次 第1章 測定の基礎 第2章 電流測定 第3章 絶縁抵抗測定 第4章 接地抵抗測定 第5章 温度測定 第6章 電源品質測定 第7章 ブレーカ・ケーブルの事故点探査 第8章 環境・省エネ測定 第9章 電気安全・その他 第10章 測定器の管理
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 FAや物流の作業軽減・時間短縮など効率化が図れる!RFIDを導入したい方におすすめの書! RFID(Radio Frequency Identification)とは、電波を用いて非接触によりデータの読み取り、書き込みなどができる技術で、特にFAや物流の分野での効率化に大いに役立つものです。 本書は、RFIDの原理や特徴、標準化の動向、アプリケーション、法令や規制への対応、応用例など、RFIDをとりまくさまざまな情報を収録しています。RFIDを検討・導入するにあたって知っておきたいことが簡潔にまとまっている一冊です。 第1章 RFIDとは 第2章 RFID の基礎用語 第3章 RFIDの原理と特徴 第4章 RFタグ 第5章 リーダ・ライタ 第6章 電波法とその他の法規・規格 第7章 使用上の留意点と活用法 第8章 RFID国際標準化の動向 第9章 RFIDアプリケーションの標準化の動向 第10章 RFIDの応用例 付録
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 機械製図の知識・技能の基礎をわかりやすく解説! 本書は、機械製図法/機械設計の初学者に向け、機械製図の知識・技能の基礎をわかりやすく解説した書籍です。 JIS(日本産業規格)が定める製図規約を十分に理解し、設計者の意図が製作者に正しく伝えられる図面の描き方、また設計者の意図を正しく理解できる図面の読み取り方など、機械製図の基礎を学ぶ際に最適な書籍となるよう内容を絞り込んでいます。また、重要な点は吹き出しで表示する、作図問題を設ける等、ワークブックの要素を盛り込んでいますので、楽しく機械製図法/機械設計の基礎を身に付けることができます。 第2版では、実際に授業で使用した実績を取り込み、学生等の理解が薄かった/質問が多かった項目などに加筆を施しています。 第1章 製図の基礎 第2章 機械製図法 第3章 公差と表面性状 第4章 材料記号 第5章 検 図 第6章 ね じ 第7章 転がり軸受 第8章 歯 車 第9章 ば ね 第10章 溶 接 第11章 スケッチ 第12章 CAD 第13章 図面集 第14章 作図問題 付 表
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 「電気回路」全般をわかりやすく解説した教科書. 大学や高専で学ぶ「電気回路」全般をわかりやすく解説した教科書. 初めて当分野を学ぶ人のために完全に理解できるよう, 多数の例題や演習を併用し,また体系立てて構成. ※本書籍は、日本理工出版会から発行されていた『電気回路テキスト』(1994年9月)をオーム社から発行するものです。 第1章 直流電圧-電流 1-1 電流の種類 1-2 オームの法則 1-3 抵抗の直並列接続 1-4 キルヒホッフの法則 1-5 電力 1-6 定電圧源,定電流源表示 1-7 供給電力最大の法則 1章 演習問題 第2章 交流電圧-電流の大きさ 2-1 正弦波起電力の発生 2-2 瞬時値 2-3 平均値と実効値 2章 演習問題 第3章 回路素子 3-1 抵抗R 3-2 インダクタンスL 3-3 静電容量C 3章 演習問題 第4章 基本回路 4-1 RL 直列回路 4-2 RC 直列回路 4-3 RL 並列回路 4-4 RC 並列回路 4-5 RLC 直列回路 4-6 電力 4章 演習問題 第5章 ベクトル記号法 5-1 複素数計算 5-2 交流回路への複素数の導入 5-3 イミタンスへの導入 5-4 時間因子εjωt 5-5 基準ベクトル 5-6 基本回路への適用 5-7 電力のベクトル表示 5-8 ベクトル軌跡 5章 演習問題 第6章 回路の基礎 6-1 直列回路 6-2 並列回路 6-3 直並列回路 6-4 直並列回路の変換 6-5 △-Y,Y-△変換 6-6 キルヒホッフの法則 6-7 重ね合わせの理 6-8 鳳-テブナンの定理とノートンの定理 6-9 交流ブリッジ回路 6-10 共振現象 6-11 条件付き回路の計算 6章 演習問題 第7章 相互誘導回路 7-1 相互誘導係数 7-2 相互インダクタンスM を含む回路 7-3 M で結合された回路の導電的等価回路 7章 演習問題 第8章 2端子対回路 8-1 2端子対回路の関係式 8-2 2端子対回路の接続 8章 演習問題 第9章 影像パラメータとLC フィルタ 9-1 影像パラメータ 9-2 LC フィルタ 9章 演習問題 第10章 三相交流回路 10-1 多相方式 10-2 対称三相交流 10-3 三相起電力の結合方式 10-4 三相負荷の結合方式 10-5 対称三相の交流電力 10-6 対称三相回路 10-7 非対称三相回路 10-8 三相回路の電力測定 10章 演習問題 第11章 対称座標法 11-1 非対称三相電圧および電流の対称分 11-2 非対称三相電圧のY-△変換 11-3 非対称三相電流の△-Y変換 11-4 三相交流発電機の基本式 11章 演習問題 第12章 ひずみ波交流 12-1 フーリエ級数とフーリエ係数 12-2 フーリエ級数の回路への応用 12-3 ひずみ波の実効値と電力 12-4 ひずみ波の皮相電力と力率 12章 演習問題 参考文献 演習問題 略解 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 無線通信工学、移動通信工学を基本から図解で解説したわかりやすい教科書 電気・電子・情報通信系学科の選択・専門科目「無線通信工学」「移動通信工学」の学部生向けの教科書です。 通信工学の基礎科目の履修を前提として、これに接続する内容として、無線通信で用いる電波の性質、送信電力、通信路の伝搬損失、アンテナ特性、受信電力の基本や、ディジタル信号の無線信号への変換・変調などについてわかりやすく解説しています。 1章 0,1のディジタル信号を無線通信で伝送する方法とは 1-1 電波法 1-2 電波の周波数,波長,及び速度 1-3 波形整形とフィルタ 1-4 雑音と歪 1-5 アナログ変調 1-6 ディジタル変調 演習問題 2章 電波のエネルギーはどのように表現すればよいか 2-1 電場と磁場 2-2 ポインティングベクトル 2-3 マクスウェルの方程式 2-4 マクスウェルの方程式と電磁波のエネルギーの関係 演習問題 3章 電波が距離の2乗に反比例して減衰するのはなぜか 3-1 アンテナの放射特性 3-2 フリスの伝達公式 3-3 アンテナの基本性能 演習問題 4章 電波の受信電力が刻々変化すのはなぜか 4-1 固定通信,放送におけるフェージング 4-2 移動通信におけるフェージング 演習問題 5章 移動通信はセルラーとも呼ばれる,その理由は 5-1 セル方式と位置登録 5-2 つながる仕組み 5-3 ハンドオーバー 演習問題 6章 基地局が多数のユーザ端末と通信できるのはなぜか 6-1 多重化と多重分離 6-2 OFDM 6-3 多元接続 演習問題 7章 双方向通信でデータが衝突しない理由は 7-1 FDD 7-2 TDD 7-3 全二重無線通信 演習問題 8章 複数アンテナの利用ですべてが変わる 8-1 受信アンテナダイバーシチ 8-2 送信アンテナダイバーシチ 8-3 MIMO空間多重 8-4 ビームフォーミング 8-5 送信パラメータの設定 演習問題 9章 ネットワーク技術とは 9-1 ヘテロジーニアスネットワーク 9-2 リレー通信 9-3 基地局連携技術 演習問題 10章 無線信号は光ファイバで伝送できるか 10-1 光ファイバ通信の基本 10-2 無線信号の光ファイバ伝送 演習問題 参考文献 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 3Dスキャナ,LiDARなどの3次元計測技術がゼロからわかる 本書は,物理空間中にある物体の3次元形状を映像データとして取り込む技術である3次元計測技術について,読者の方々に手を動かしながら,その原理を理解してもらう本です. 3次元計測技術を理解するために必要な知識を最初の一歩から順を追って解説しています.物体の3次元情報をコンピュータにインプットするためにはどういったことが必要なのか,そのためにはどのような方法が使われているのか,その数理モデルはどうやって導かれるのか,そして,簡単に実践してみるところまでを説明しています. 本書にひととおり目を通し,実際に手を動かしてみることで,さまざまな場面で応用できる基礎力を養っていただけるはずです. 第1章 3次元計測技術の基礎 1.1 カメラのみによる計測 1.2 光パターン投影で高精度計測 1.3 反射光の到達時間で計測(TOF) 第2章 アクティブ型三角測量による3次元計測 2.1 カメラとプロジェクタのプロパティ設定 2.2 カメラとプロジェクタの設置 2.3 正弦波位相シフト法による3次元計測 第3章 LiDARを使って手軽に3次元計測実験 3.1 LiDAR搭載タブレットによる3次元計測 3.2 市販の3次元計測装置の活用 3.3 レーダ型LiDARを試作する 3.4 3次元計測装置を動かしながらRGB-Dデータを取得 3.5 時系列RGB-Dデータの統合 第4章 3次元計測装置の設計と開発 4.1 3次元計測装置の要件を洗い出す 4.2 アクティブ型三角測量の設計と開発 4.3 TOF センサ/ LiDARの設計と開発 4.4 将来の3次元計測技術
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 最新事例まで含めてメカトロニクスを概観できる定番教科書。さらなる充実の改訂3版! ロボット・メカトロニクス関連学科を対象とした教科書シリーズの1巻として発行し、好評を博した教科書の改訂3版。 改訂2版発行から7年が経過し,この間ヒューマノイドロボットやEV技術などの技術進展には著しいものがあります。また、5Gや人工知能などの周辺分野との関連についても学ぶことが必要となってきました。今回の改訂では、図や写真を多用した解説、各章冒頭の「学習のポイント」、章末の「理解度チェック」「演習問題」など、読者が理解度を確認しながら読み進められる構成は活かしつつ、前記の事項を踏まえて全体的な内容の見直しを図り、より時代に即した教科書となるようまとめました。 1章 序 論 1.1 私たちのメカトロニクス社会 1.2 メカトロニクスの関連技術 1.3 メカトロニクスシステムの見方と本書の構成 理解度Check 2章 メカトロニクスのためのシステム論 2.1 システムとは 2.2 モデリング 2.3 システムのアナロジー 2.4 システムの特性と解析 理解度Check 演習問題 3章 センサ 3.1 ロボット・メカトロニクスシステムとセンサ 3.2 国際単位系 3.3 ロボット・メカトロニクスに使われる代表的なセンサ 3.4 センサの変換方式 3.5 センサの信号処理 理解度Check 演習問題 4章 アクチュエータ 4.1 ロボット・メカトロニクスシステムとアクチュエータ 4.2 ロボット・メカトロニクスに使われるアクチュエータ 4.3 アクチュエータの応用技術 理解度Check 演習問題 5章 コンピュータ 5.1 コンピュータのハードウェア 5.2 コンピュータのソフトウェア 5.3 プログラムの実行 5.4 データの表現 5.5 論理演算と組合せ回路 理解度Check 演習問題 6章 機械設計 6.1 機械要素 6.2 加工法と工作機械の種類 6.3 CAD/CAM/CAE 6.4 設計および製図 理解度Check 演習問題 7章 制御器設計 7.1 制御系の設計手順 7.2 制御理論の歴史 7.3 ブロック線図 7.4 システム構造ム 7.5 周波数における制御系設計 理解度Check 演習問題 8章 制御器の実装 8.1 ロボット制御に必要な信号処理 8.2 組込みマイコン 8.3 実時間制御 8.4 制御器のシステム化 理解度Check 演習問題 9章 解 析 9.1 信号からの情報抽出 9.2 信号解析 9.3 周波数解析の応用 理解度Check 演習問題 10章 上位システムの設計 10.1 ロボットのタスクプランニング 10.2 ロボットのモーションコントロール 10.3 ヒューマノイドロボットの設計 10.4 自動車開発 理解度Check 演習問題 11章 UMLとシステム開発 11.1 UMLとは 11.2 組込みシステムの開発事例 理解度Check 演習問題 演習問題解答 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 私たちの「食をめぐる環境」とその「問題点」とは? 日本の食料・農業問題を多角的・体系的にまとめ、 「SDGs」、「TPP」、企業の農業参入、食品表示、 食料自給力、エンゲル係数の上昇、「中食」のさらなる拡大など、 新たな動向についてデータとともにわかりやすく解説。 農学系・栄養学系・経済学系の大学・短大・専門学校1・2 年生、 公務員をめざす農学系の学生、「食の将来」に関心のある社会人に最適。 ※本書は2016年7月発行『食料経済(第5版)-フードシステムからみた食料問題』の改訂第6版です。 prologue 食料経済で何を学ぶか ─食卓からさかのぼってそのフードシステムのしくみをたずねる─ 1 “豊かな食卓”から思い浮かべるもの 2 “ご飯”,“米”,“稲” 3 ひろがる“食”と“農”の距離 4 フードシステムとその基本数値 1編 “豊かな食卓”を解析すれば 1章 食生活の変遷と特徴 1 わが国の食生活小史 2 第二次世界大戦後の食生活の変化 3 食生活変化の背景および現代食生活の特徴と問題点 4 食の外部化と簡便化 5 “食”の国際比較─日本食文化の特徴─ 2章 成熟期にきた食の需給 1 食料の需給システム 2 食料の供給市場構造 3 成熟期にきたわが国の食料需要 4 日本人の食品購買行動の特徴 2編 農場から食卓を結ぶ食料・食品産業 3章 農畜水産物の生産 1 フードシステムの“川上”:農業 2 農業生産をめぐる環境の変化 3 SDGsと漁業 4章 食品企業の役割と食品製造業の展開 1 食品企業の目的 2 フードシステムにおける食品製造業の位置 3 食品製造業の国民経済の中での役割 4 食品製造業の構造的特徴 5 食品製造業の原料調達とフードバリューチェーン構築 5章 食品流通とマーケティング 1 卸売市場流通を中心とした生鮮食品の流通経路 2 加工食品の流通経路 3 食品流通業における構造変化の諸形態 4 商品のライフサイクルと食品小売業のマーケティング 6章 外食・中食産業の展開 1 飲食業と外食産業・中食産業 2 外食産業の経営戦略の特徴 3 中食産業の多様性 4 外食・中食産業の食材調達─農産物の需要者としての食品産業─ 7章 貿易自由化の進展と食料・食品の輸出入 1 グローバル化と食料貿易の転換点 2 高度化・多様化する食料・食品輸入 3 世界規模での食料の需要増大と食料貿易の将来 3編 国民食料の安定確保 8章 世界の食料問題 1 “過剰”と“不足”の併存 2 地球規模の食料需要の増大 3 成長の限界が懸念される食料供給 4 世界食料の需給バランスと新たな要因 5 世界の食料需給の展望 9章 日本の食料政策 1 食料政策の課題 2 「主食」政策─おもに米政策を対象として─ 3 食料をめぐる貿易政策 4 食料産業政策 5 食料自給の確保─食料安全保障の確立に向けて─ 10章 食品の安全政策と消費者対応 1 食料に求められる基本的な性格─安定供給と安全性─ 2 なぜ食の安全・安心が保たれないか 3 安全性確保のための政策対応 4 環境問題から食料問題へ 5 安全な食料共有と安心な食生活のためのフードシステムの構築 epilogue 日本の食料問題を考える─真の豊かさを求めて─ 1 他国に例をみない食料自給率の低さ 2 基本は“風土に見合った食生活” 3 真の豊かさを求めて,21世紀の食生活を展望する 参考文献/索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 18年ぶりの改訂! 本書は計測や自動制御技術を学ぶ学生やセンサを扱う他分野の技術者、研究者を対象として、センサ工学の基礎を解説した入門書です。センサのすべてを網羅するのではなく、計測対象や状況に応じて千差万別な技術の中に共通の手法と技術が存在することを述べ、センサ技術の全体像がわかるように解説しています。 【第3版にあたって】 ・IoTやAI技術の活用など、社会システムの変化に応じて内容を見直した ・国際単位系(SI)の改訂にあたって、計測標準や量の定義を見直した ・自学自習を鑑み、演習問題を追加し、解答も掲載した 第1章 センサとは何か 第2章 信号変換のしくみ 第3章 物理測定と標準 第4章 力,圧力のセンサ 第5章 長さ,速度センサ 第6章 流速・流量センサ 第7章 固体センサデバイス 第8章 温度測定と温度センサ 第9章 成分センサ 第10章 センシング技術の進歩と方向性
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 建築環境工学の基礎知識が、図解でわかりやすく学べる! 専門学校、職業訓練校、大学などで建築士を目指す学生の方々を主な読者とした教科書シリーズ「図解建築シリーズ」の1冊です。 「建築における環境」をテーマに、初学者にもわかりやすい図やイラストを多用して解説しています。また、各章末には建築士試験で出題された問題を中心にした演習問題を設けていますので、知識の定着を図ることができます。 初めて建築環境工学について学ぶ方から、実務者の方まで、おすすめの1冊です。 Ⅰ編 建築環境工学概論 1章 建築環境の用語 2章 人間や建物に影響する環境 Ⅱ編 環境工学 1章 換気 2章 伝熱 3章 日照・日射 4章 光 5章 色 6章 音 7章 振動と防振 8章 腐食 9章 その他建築を取り巻く環境
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 必要最小限をまとめた急性期エコー検査の入門書 エコー検査は、すぐれた非侵襲性検査であり、腹部、乳房、産婦人科でよく使われていましたが、ポータブルエコーの開発・普及、プローブの高性能化等々により救急分野や整形外科でも積極的に使用されるようになってきました。 特に救急分野では、いつでもどこでも繰り返し検査が可能であり、今後さらに普及のすそ野が広がりそうです。また、重要所見の有無に絞って短時間に行うポイントオブケア(point-of-care)エコーが広がりつつあり、最新の救急分野のエコー検査をまとめた一冊です。なお本書は、救急の際のエコー検査が中心ですが、急性期の一次診断として使用されるエコー検査も考慮した構成になっています。 第1章 基礎 第2章 外傷 第3章 ショック 第4章 心臓 第5章 急性期 第6章 体表エコー
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 これからのエンジニア、研究者にとって必須となる離散数学の知見をわかりやすくまとめたテキスト。 本書は、長年にわたって研究の第一線にある著者が、これからのエンジニア、研究者にとって必須となる離散数学の知見をわかりやすくまとめたテキストです。 現在、AI、ICTの活用は全分野で必須となっていますが、AIやICTが実際どのようなものであり、何が実現できるかを正しく理解することが活用の第一歩となり、それには基礎となる数学(離散数学)の知識が不可欠です. 本書は離散数学の中でも、現在、特に重要となっている論理関数(ブール関数)、ニューラルネットワーク(ディープラーニング)、グラフ理論とネットワーク最適化、組合せ論等について、大学学部生が理解できるよう懇切に、かつ、詳しく解説を行っています。 第1章 基礎概念 第2章 論理関数とその応用 第3章 しきい関数とディープラーニング 第4章 グラフ理論 第5章 ネットワーク最適化 第6章 組合せ論の基礎 練習問題:ヒントと略解
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 理工系の学生にとって基礎となる内容がしっかり身に付く良問を数多く掲載した微分積分、線形代数、ベクトル解析の演習書 本書は理工系の学生にとって基礎となる内容がしっかり身に付く良問を数多く掲載した微分積分、線形代数、ベクトル解析の演習書です。 高校数学で学んだ内容を起点に、丁寧にわかりやすく解説したうえ、読者が自ら手を動かして確かなスキルが身に付けられるよう、数多くの例題、問題を掲載しています。 第1章 三角関数および指数関数,対数関数 第2章 微分積分 第3章 線形代数 第4章 ベクトル解析 第5章 電気数学 章末問題の解答例
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ディジタル電子回路の定番教科書、待望の改訂! 「ディジタル電子回路」の基本となる内容こそ変わらないものの、1988年の初版発行から30年以上が経過し、一部の記述に古さを感じられるようになりました。また、フィルムの劣化によって印刷に傷が見られるようにもなってきています。ここで新たに、題材や記述の現代化など内容の見直しを行い、第2版として発行するものです。 第1章 アナログ回路からディジタル回路へ 第2章 ディジタル回路の論理関数による表現 第3章 集積化基本ゲート 第4章 組合せ論理回路 第5章 フリップフロップ 第6章 順序回路 第7章 A/D・D/A変換回路 問題解答
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 Excelを使って回帰分析を使いこなせるようになる!! 本書は、回帰分析の理論を、その前提となる相関関係から基本の単回帰分析、重回帰分析、線形判別分析、そして類書ではあまり触れられていないロジスティック回帰まで、豊富な実例を絡めながら、わかりやすくじっくりと解き明かしていきます。本書はExcel を用い、実際に手を動かしながら進めていくよう構成しています。 はじめに 序 章 回帰分析とは 第1日 データ活用と予測をする上で知っておくべきこと 第2日 散布図と相関関係 第3日 単回帰分析 第4日 重回帰分析 第5日 カテゴリーデータを含む重回帰分析 第6日 線形判別分析 第7日 ロジスティック回帰分析 付 録 回帰分析の補足資料 A 累乗・√・log の解説 B 回帰分析について C アドインプログラムの利用 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 Excelで熱学のシミュレーションができる!! 本書は、Excelを使いながら物理のテーマである熱力学(高校カリキュラムでは熱)と統計力学を勉強するものです。 熱という身近だけどエントロピーという不思議なものを扱う熱力学とかなり抽象的でわかりにくい分布関数を扱う統計力学をExcelでシミュレーションしながら学ぶことができます。例題や章末問題も用意して、自習できるようにします。 第1章 熱力学と統計力学 第2章 温度と熱平衡状態(熱力学の第0法則) 第3章 内部エネルギーとエネルギー保存則(熱力学の第1法則) 第4章 不可逆過程とエントロピー(熱力学の第2法則) 第5章 熱力学関数と相変化 第6章 統計力学の考え方 第7章 ミクロカノニカル分布(断熱系) 第8章 カノニカル分布(熱交換系)とグランドカノニカル分布(熱.粒子交換系) 第9章 フェルミ分布とボーズ分布
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 全国の多くの大学のカリキュラムに適合した、「高電圧工学」「高電圧・絶縁工学」の新たなテキスト 電気・電子系学科の専門課目である「高電圧工学」「高電圧・絶縁工学」の教科書です。各相における放電と絶縁のしくみ、(高)電界の解析に用いられる手法の基礎的事項をおさえたうえで、実際の過電圧対策やサージ解析、高電圧・大電流の方法などをわかりやすく解説するものです。全体は15章構成をとっており、各章末には理解度をチェックする演習問題を配しています。 目次 1章 放電の基礎過程 2章 気体放電の開始 3章 機中放電の形態・特性 4章 気体絶縁 5章 固体の放電と絶縁 6章 液体の放電と絶縁 7章 真空中の放電開始と絶縁 8章 破壊統計 9章 電界解析手法 10章 電力系統における過電圧の種類と発生機構 11章 雷過電圧対策 12章 サージ解析手法 13章 高電圧機器 14章 高電圧発生装置と試験方法 15章 高電圧・大電流の測定 演習問題解答 参考文献 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 統計解析は最強のツールである! Excelの統計解析機能の活用術を学べる『Excelで学ぶ統計解析入門』のExcel 2016/2013対応版登場!! Excel関数を使った例題をとおして学ぶことで統計の基礎知識が身に付くロングセラー『Excelで学ぶ統計解析入門 Excel2013/l2010対応版』のExcel2016/2013対応版です。本書は例題を設け、この例題に対して、分析の仕方と、Excelを使っての解法の両面を取り上げ解説しています。Excelの機能で対応できないものは、著者が開発したExcelアドインで対応できます。本書に掲載されているExcelアドインは、(株)アイスタットのホームページからダウンロードできます。 主要目次 第1章 統計解析の基礎 第2章 相関分析 第3章 確率分布 第4章 統計的推定と統計的仮説検定の基礎 第5章 母集団の平均と割合に関する推定 第6章 一つの母集団の平均と割合に関する検定 第7章 二つの母集団の平均と割合に関する検定 第8章 統計的推定、統計的仮説検定の理論と公式の導き方 第9章 母集団の分散・正規性・相関に関する検定 第10章 標本平均の分布、検定統計量T値の分布 第11章 Excelの統計解析機能 第12章 Excelのアドインソフトウェア
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 電気機器設計の定番教科書の改訂3版 電気機器設計の基本書として、大学の教科書としてはもちろん、広く電気技術者にも親しまれてきた『大学課程 電機設計学(改訂2版)』(1993年発行)の改訂版です。 1993年の発行後20年あまりが経過したいまも電気機器設計の基礎理論は変わるものではありません。しかしながらこの間、電気機器を取り巻く材料技術やパワーエレクトロニクスといった分野は目覚ましい成長を見せ、また関連する規格についてもいくつか改訂されています。 本書は、時代に即した電気機器設計の教科書として、また、電機メーカの若手エンジニアの座右の書となるように、データの見直し、内容の加筆修正をはかり、まとめたものです。 主要目次 第1章 電気機器の本質とその内容 第2章 電気機器設計の基礎原理 第3章 三相同期発電機の設計 第4章 三相誘導電動機の設計 第5章 永久磁石同期電動機(PMモータ)の設計 第6章 直流機の設計 第7章 変圧器の設計 第8章 電機設計総論 第9章 パワーエレクトロニクスと電機設計 付録 コンピュータによる利用 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 「機械設計技術者試験」にチャレンジする人を応援! 令和5年度1級、2級、3級[試験問題]と書き下ろし[解答・解説]を完全収録! 本書は(一社)日本機械設計工業会が実施・認定する技術力認定試験(民間の資格)「機械設計技術者試験」 1級、2級、3級について、令和5年度(2023年)11月に実施された試験問題の原本を掲載し、機械系各専門分野の 執筆者が解答・解説を書き下ろして、(一社)日本機械設計工業会が編者としてまとめた公認問題集です。 合格への足がかりとして、試験対策の学習・研修にお役立てください。 ※「機械設計技術者試験」の詳細は、主催の(一社)日本機械設計工業会へお問合せください。 https://www.kogyokai.com/exam/ ※本書は2021年6月発行『令和3年版 機械設計技術者試験問題集』(日本理工出版会)の『2024年版』をオーム社から発行するものです。過去の「元号版」のタイトルは、弊社に引継ぎされておりませんのでご留意願います。 機械設計技術者資格認定制度について 機械設計技術者認定制度概要 令和6年度(2024年)機械設計技術者試験案内 ※受験申請期間:7/19~9/30 令和5年度 機械設計技術者試験 3級 試験問題 I/試験問題 II 3級 問題 I 解答・解説 3級 問題 II 解答・解説 令和5年度 機械設計技術者試験 2級 試験問題 I/試験問題 II/試験問題 III 2級 問題 I 解答・解説 2級 問題 II 解答・解説 2級 問題 III 解答・解説 令和5年度 機械設計技術者試験 1級 試験問題 I/試験問題 II/試験問題 III 1級 問題 I 解答・解説 1級 問題 II 解答・解説 1級 問題 III 小論文作成の手引き
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 情報理論の基盤をなす離散数学がしっかり学べる教科書、待望の改訂! 離散数学は、ディジタル時計の数値のように「とびとび」の値をもつ量や現象を扱う数学であり、情報理論の基盤をなします。例えば、次の問いに正確に答えるには、いずれも離散数学の知識を要します。 ・コンピュータを使って計算するとはどういうことか ・コンピュータの設計を見通し良く行うにはどうすべきか ・コンピュータを効率良く使うにはどうすべきか ・コンピュータネットワークにはどのような性質があるか 本書は、情報系の学部・学科の学生が確実に押さえておくべき離散数学の基礎を効率良くしっかり学べる教科書として発行された『IT Text 離散数学』の改訂版です。改訂にあたり、グラフ理論やネットワークの内容を充実させたほか、オートマトンの分野を中心として問題演習量の増加、古い記述の見直し、情報科学の理解を深めるコラムの追加など、本書の特長「丁寧でわかりやすい解説」「豊富な図表と問題演習」がさらに実感いただける内容としました。 情報科学を学ぶ学生や若手社会人におすすめの教科書です。 第1章 集合・写像・関係 第2章 論理と証明 第3章 数え上げ 第4章 グラフと木 第5章 オートマトン 第6章 アルゴリズムと計算量 第7章 数論
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 水環境工学の基本が学べる! 大学の2~3年次生程度を対象とした教科書として好評の『大学土木 水環境工学』の改訂版です。上・下水道や河川流域などの水環境について、工学的側面および実用的側面から適切・簡素に記述しています。 今回の改訂にあたって施設基準などの見直しを行うだけでなく、読者がより理解を深められるよう、従来の内容に記述を追加するほか、熱力学の基礎や微生物活動についての解説を補強しています。 序章 水環境技術の歴史的展開 第1章 水環境の基礎科学 第2章 上水道 第3章 下水道 第4章 水環境計画と水処理技術 付表 演習問題略解・ヒント 参考文献
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 現場で直面する50の疑問の回答で、電気の基礎が確認できる! 電気エンジニアのみならず、電気に関する知識を必要としている機械、化学、建築系のエンジニアの方々に電気の全般にわたる実務的な知識を得るための書籍として、2007年に発行した「現場エンジニアが読む 電気の本」の改訂企画。 前版同様、現場で直面する50の疑問(Question)を設定、これに回答(Answer)していく構成で、内容的にも電気の基本的なテーマを取り上げています。なお、7章については、世界的な脱炭素社会実現を目指す動きを念頭においた内容構成としています。 第1章 やさしい電気の基本 Q01 直流と交流の違いは? Q01 電圧の種別は? Q03 抵抗、インピーダンスとは? Q04 位相の遅れ、進みとは? Q05 電力はどのように表すのか? Q06 単相3線式とはどのような給電方式か? Q07 三相3線式とはどのような給電方式か? Q08 変圧器の原理は? Q09 高調波はなぜ問題になるのか? Q10 接地(アース)はなぜ必要か? 第2章 現場で必要な電気の測定 Q11 測定の正しさとは? Q12 アナログ測定器とデジタル測定器の違いは? Q13 電圧の測定方法は? Q14 電流の測定方法は? Q15 ホイートストン・ブリッジってなに? Q16 電力の測定方法は? Q17 絶縁抵抗とは? Q18 接地抵抗とは? Q19 漏電の検出は? Q20 波形の観測は? 第3章 機械を制御する半導体 Q21 半導体が機械を動かす? Q22 半導体部品の中身は? Q23 ダイオードってなに? Q24 半導体スイッチってなに? Q25 オペアンプってなに? Q26 半導体の弱点は? 第4章 縁の下で活躍する制御部品と制御機器 Q27 スイッチ、リレーの接点機能は? Q28 リレーの選択方法は? Q29 センサの原理と種類は? Q30 光電センサ、近接センサを教えて? Q31 調節器とは? Q32 温度調節の実際は? Q33 直流パワーサプライってなに? Q34 停電の時に必要な電気はどうする? 第5章 自動化の頭脳 シーケンス制御 Q35 シーケンス制御とは? Q36 リレーシーケンスの基本回路は? Q37 リレーシーケンス回路設計-1 モータの起動、停止階路の設計 Q38 リレーシーケンス回路設計-2 早押しクイズのランプ転炉迂回路の設計 Q39 リレーシーケンス回路設計-3 交通信号回路の設計 Q40 PLCとは? 第6章 意外と知らないモータとインバータ Q41 交流モータはなぜまわる? Q42 トルクとは? Q43 インバートとは? Q44 インバータのV/f制御、ベクトル制御とは? Q45 サーボモータとは? 第7章 脱炭素化社会実現に貢献する電気の省エネ Q46 脱炭素社会と電気の省エネの関係は? Q47 電気の省エネの効果はどう表す? Q48 電気の省エネの進め方は? Q49 投資効果の評価の実例は? Q50 ZEBって何のこと?
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 急速に進化する分析化学の新潮流、LC/MSおよびLC/MS/MSがわかる! 高性能分離能と高感度・高選択的検出能を具備したLC/MSとLC/MS/MSは、最も急速に進化しつつある分析法として着目されています。 本書は、LC/MSとLC/MS/MSの入門者、また、すでに実務を担当している初級・中級技術者などを対象として、分析化学的な観点から基本的な知識と技術の習得に必須な内容をまとめた書籍として発行するものです。 1章 概論 1-1 LC/MS,LC/MS/MSにおける用語と基礎理論 1-2 LC/MS,LC/MS/MSの原理と可能性 2章 LC/MS,LC/MS/MS用の溶媒・試薬・器具 2-1 水 2-1-1 LC/MS,LC/MS/MS用水の製造法 2-1-2 LC/MS,LC/MS/MS用水の使用法 2-2 溶媒 2-3 試薬 2-4 器具 3章 LC/MS,LC/MS/MS分析のための前処理 3-1 固相抽出 3-2 カラムスイッチング 3-3 超臨界流体抽出 3-4 MS検出用誘導体化 4章 LC/MS,LC/MS/MSにおけるLC分離 4-1 HPLC・UHPLC装置 4-1-1 HPLC装置 4-1-2 UHPLC装置 4-2 分離モードとカラム分離 4-2-1 逆走分配 4-2-2 順相分配・吸着 4-2-3 HILIC 4-2-4 イオン交換 4-2-5 サイズ排除 4-2-6 アフィニティー 4-2-7 キラル 5章 LC/MS 5-1 LC/MSにおけるイオン化法 5-1-1 エレクトロスプレーイオン化法 5-1-2 大気圧化学イオン化法 5-1-3 大気圧光イオン化法 5-1-4 誘導結合プラズマイオン化 5-1-5 その他 5-2 MS装置 5-2-1 四重極質量分析計 5-2-2 飛行時間質量分析計 5-2-3 イオントラップ質量分析計 5-2-4 フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計 6章 LC/MS/MS 6-1 装置 6-1-1 トリプル四重極質量分析計 6-1-2 四重極-イオンモビリティ-飛行時間形質量分析計 6-1-3 イオントラップ/TOF 7章 LC/MS,LC/MS/MSの応用 7-1 LC/MSの応用例 7-1-1 内因性物質(アンジオテンシン,プロスタグランジン) 7-1-2 グリコヘモグロビン 7-1-3 米中ヒ素の化学形態別分析 7-1-4 アミノ酸 7-1-5 食品中の機能性成分分析 7-2 LC/MS/MSの応用例 7-2-1 生体試料中のプロスタグラジン類の定量 7-2-2 食品中のリスク物質の微量分析 7-2-3 アミロイドβペプチド 7-2-4 合成カンナビノイド 7-2-5 MS/MSの化学物質連続モニタリング装置への応用 7-2-6 生薬のLD/MS/MS分析
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 はじめて学ぶ建築材料のポイントを図解でわかりやすく解説! はじめて建築材料を学ぶ方や建築材料を知りたい方を主な対象に、建築材料全般について、わかりやすく解説しています。 現在のニーズにあうように内容を全面的に見直し、授業でも使いやすいよう〇×式の練習問題を新たに追加しました。 建築材料を理解するために必要な知識について、基本的な80テーマに絞り、2色刷り・絵とき・見開き2ページ構成で解説しています。 1 建築と材料 【木材】 2 木材と日本建築 3 木材の特徴と構造 4 木材の種類 5 伐採と製材 6 木材の性質 7 合板・集成材 【石材】 8 石材の歴史 9 石材の特徴 10 石材の採石と加工 【セメン卜・コンクリー卜】 11 セメント・コンクリートの歴史 12 セメントと骨材の特徴 13 コンクリートの特徴と種類 14 まだ固まらないコンクリートの特徴 15 コンクリートの調合 16 コンクリートの混和材料 17 コンクリートの物性 18 コンクリートの施工と養生 19 コンクリート製品 20 コンクリートブロック 【金属】 21 金属の歴史 22 鉄・鋼の特徴 23 鋼の加工と腐食 24 形鋼・鋼板・棒鋼 25 鉄管・接合金物 26 アルミニウム・ステンレス 27 その他の金属 【焼成品】 28 陶磁器の歴史 29 タイル 30 かわら 31 れんが・セラミックブロック 32 衛生陶器・陶管 【プラスチックス】 33 プラスチックスの特徴と種類 【防水材料】 34 防水の歴史とアスファルト 35 アスファルト防水 36 合成高分子ルーフィング・塗膜防水 【ガラス】 37 ガラスの歴史と特徴 38 ガラスの種類 39 各種のガラス 40 ガラス製品とチッェックポイント 【屋根材】 41 セメントかわら・スレート 42 金属板・とい 【ボード・合板】 43 壁下地材 44 繊維板・パーティクルボード 【左官材料】 45 左官の歴史 46 モルタル塗 47 プラスター塗・しっくい塗 48 土壁(珪藻土を含む) 49 人造石塗・積層石材 【内・外装材】 50 断熱材 51 外壁材 52 カーテンウォール 53 壁紙類 54 カーテン・ブラインド 【天井・床仕上】 55 天井仕上材 56 床仕上材(1) 57 床仕上材(2) 58 畳・カーペット 59 各種の床仕上材 【塗料・接着剤】 60 塗料 61 接着剤 【建具】 62 木製建具 63 金属製建具 【設備機器】 64 システム家具・システムキッチン 65 浴槽・洗面化粧台 66 照明器具 67 空気調和設備 68 消防設備 69 エレベータ・エスカレータ 【外構・仮設】 70 門・扉・カーポート 71 仮設資材 【現代社会と建築材料のかかわり,今後の課題】 72 環境と建築 73 木質材料のリサイクル 74 コンクリートのリサイクル 75 金属・その他のリサイクル 76 高齢者対応とバリアフリー 77 バリアフリー設計のポイント 78 シックハウス 79 品確法・PL法・LCA 80 SDGs(持続可能な開発目標) 〇×式練習問題 解答・解説 用語解説
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 鋼構造の設計が絵ときでわかる! 初めて土木を学ぶ方が楽しく学習できるように、土木のさまざまな分野をイラストや図でわかりやすく説明する「絵とき」入門書の一巻です。 本書は、橋梁設計の基礎となる各種鋼構造の設計について、基礎からやさしく学べるように、具体例をまじえて解説し、章末に演習問題を掲載しています。また、道路橋示方書の改定に伴い、全体の数値および用語の見直しを行い、紙面を刷新しました。 第1章 鋼構造の基礎 1-1 鋼の性質と役割 1-2 許容応力度設計法と限界状態設計法 1-3 橋設計の大前提 1-4 設計作用の特性値 第1章のまとめの問題 第2章 部材 2-1 部材の種類 2-2 引張りを受ける部材 2-3 圧縮を受ける部材 2-4 曲げモーメントを受ける部材 第2章のまとめの問題 第3章 部材の接合 3-1 接合の方法 3-2 溶接 3-3 開先溶接 3-4 すみ肉溶接 3-5 溶接の強さ 3-6 高力ボルト接合の種類と継手の種類 3-7 摩擦接合 3-8 支圧接合 第3章のまとめの問題 第4章 プレートガーダー橋の設計 4-1 構造と設計手順 4-2 設計条件 4-3 概略設計 4-4 床版の設計 4-5 主桁に作用する力 4-6 主桁断面の設計 4-7 主桁断面の変化 4-8 主桁の連結 4-9 補剛材の設計 4-10 対傾構の設計 4-11 横構の設計 4-12 支承の設計 第4章のまとめの問題 第5章 トラス橋の設計 5-1 構造と設計手順 5-2 設計条件 5-3 概略設計 5-4 影響線による主構の応力解析 5-5 上弦材の設計 5-6 下弦材の設計 5-7 斜材の設計 5-8 連結部の設計 第5章のまとめの問題 第6章 その他の橋の特徴 6-1 アーチ橋 6-2 ラーメン橋 6-3 格子桁橋 6-4 合成桁橋 6-5 斜張橋 6-6 吊橋 第6章のまとめの問題
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 出題傾向に沿って要点を押さえたテキスト&実戦問題解説で合格最短コース! 本書は、1級土木施工管理技術検定(第一次検定)の受験対策書です。最近の出題傾向をふまえた演習問題(過去問題が中心)を豊富に盛り込んだほか、テキスト解説は試験に出題されやすい重要事項を主として、わかりやすく、かつ、コンパクトにまとめました。多忙な読者のみなさんが望む「より短時間で効率的な学習」を可能にする「テキスト+問題集」一体型の実戦的な1冊です。姉妹書の「これだけマスター 1級土木施工管理技士 第二次検定」(4月発行予定)とあわせて学習すれば効果は絶大です。 受験ガイダンス Ⅰ部(選択問題) 土木一般 第1章 土工 1 土質調査・土質試験 2 土工量計算 3 土工作業と建設機械 4 盛土の施工 5 法面工 6 軟弱地盤対策工法 過去問チャレンジ(章末問題) 第2章 コンクリート 1 コンクリートの品質 2 コンクリートの材料 3 コンクリートの施工 4 各種コンクリート 過去問チャレンジ(章末問題) 第3章 基礎工 1 基礎工法全般 2 既製杭の施工 3 場所打ち杭 4 直接基礎 5 土留め(土止め)工 過去問チャレンジ(章末問題) Ⅱ部(選択問題) 専門土木 第1章 構造物一般 1 耐候性鋼材 2 鋼橋の架設 3 鋼材の溶接 4 高力ボルト 5 コンクリート構造物 過去問チャレンジ(章末問題) 第2章 河川 1 河川堤防 2 河川護岸 3 柔構造樋門 過去問チャレンジ(章末問題) 第3章 砂防 1 砂防えん堤 2 砂防施設 3 地すべり防止工 過去問チャレンジ(章末問題) 第4章 道路・舗装 1 アスファルト舗装の路床・路体 2 アスファルト舗装の上層・下層路盤 3 アスファルト舗装の表層・基層 4 アスファルト舗装の補修・維持 5 コンクリート舗装 過去問チャレンジ(章末問題) 第5章 ダム 1 ダムの形式 2 ダムの基礎処理 3 ダムの施工 過去問チャレンジ(章末問題) 第6章 トンネル 1 トンネルの掘削方法 2 トンネルの支保工 3 トンネルの施工 過去問チャレンジ(章末問題) 第7章 海岸・港湾 1 海岸堤防 2 港湾工事 3 消波工・海岸浸食対策 4 浚渫 過去問チャレンジ(章末問題) 第8章 鉄道・地下構造物 1 鉄道:鉄道工事 2 鉄道:営業線の近接工事 3 地下構造物:シールド工法 4 地下構造物:シールド工事 過去問チャレンジ(章末問題) 第9章 鋼橋塗装・推進工 1 鋼橋塗装 2 小口径推進工 3 薬液注入工 過去問チャレンジ(章末問題) 第10章 上・下水道 1 上水道の施工 2 下水道の施工 過去問チャレンジ(章末問題) Ⅲ部(選択問題) 建設法規・法令 第1章 労働基準法 1 労働契約・雑則 2 労働時間 3 年少者・妊産婦等 4 賃金 過去問チャレンジ(章末問題) 第2章 労働安全衛生法 1 安全衛生管理体制 2 作業主任者 3 工事計画の届出 過去問チャレンジ(章末問題) 第3章 建設業法 1 許可制度 2 技術者制度 3 元請負人の義務 過去問チャレンジ(章末問題) 第4章 道路関係法規 1 道路の占有 2 車両の通行制限 過去問チャレンジ(章末問題) 第5章 河川法 1 河川管理者の許可 過去問チャレンジ(章末問題) 第6章 建築基準法 1 仮設建築物に対する制限の緩和 過去問チャレンジ(章末問題) 第7章 火薬類取締法 1 火薬類の取扱い 2 火薬庫・火薬類取扱所・火工所 3 発破・不発 過去問チャレンジ(章末問題) 第8章 騒音規制法及び振動規制法 1 特定建設作業 2 届出 3 規制基準 過去問チャレンジ(章末問題) 第9章 港湾・海洋関係法規 1 航路・航法 2 許可・届出 過去問チャレンジ(章末問題) Ⅳ部(必須問題) 工事共通 第1章 測量 1 トータルステーション(TS) 2 GNSS測量(旧GPS測量) 3 水準測量 4 公共測量 過去問チャレンジ(章末問題) 第2章 契約 1 公共工事標準請負契約約款 2 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 過去問チャレンジ(章末問題) 第3章 設計 1 設計図 過去問チャレンジ(章末問題) 第4章 建設機械 1 建設機械の種類と特徴 2 工事用電力設備及び原動機 過去問チャレンジ(章末問題) 第5章 施工計画 1 施工計画作成の基本事項 2 施工体制台帳・施工体系図 3 事前調査検討事項 4 仮
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 これ1冊で、建築構造力学の建築士試験レベルに到達できる! 充実の296問収録! 本書は、建築構造力学を学ぶ学生向けて、基本習得から単位取得、さらには建築士試験対策レベルまでを網羅した問題集です。 講義に出てくる演習問題はもちろん、実際の1・2級建築士試験に出題されたレベルの問題までを取り上げ、計算を解きながら重要な点や陥りやすいミスのポイントなどがズバリ学べるように構成されています。 充実の296問を収録しています。 *なお、本書は『ズバッと解ける 建築構造力学問題集220』(2011/02)の内容を大幅に見直し、加筆・修正等を行った上で、改題改訂し発行するものです。 第1章 力の計算とつりあい 第2章 反力の計算 第3章 ある点の応力 第4章 応力図 第5章 断面と応力度 第6章 変形と座屈 第7章 静定ラーメン 第8章 静定トラス 第9章 不静定ばり 第10章 不静定ラーメン 第11章 崩壊機構 第12章 固有周期 実力UP問題解答 演習問題解答 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 出題傾向に沿った豊富な問題と「これだけは押さえたい」ポイント解説で最短合格! 待望の改訂2版登場! 本書は、2級管工事施工管理技士試験の受験対策書です。 学科試験+実地試験の両方をカバーした内容構成になっています。また、最近の出題傾向をふまえた演習問題を豊富に盛り込んだうえ、テキスト解説は試験に出題されやすい重要事項を主とし、『マスターPOINT』としてわかりやすく、かつ、コンパクトにまとめました。さらには、実地試験対策の章を充実させ、記述対応が苦手な受験者が実戦力アップできる工夫を随所に配しています。多忙な読者のみなさんが望む「より短時間で効率的な学習」を可能にする(テキスト+問題集)型の実戦的な1冊です。 著者の方々が講師を務めた講習会での受講生からの声を取り込むことで、前版より充実した内容にとなっています。 1章 原 論【必須問題】 1 環境工学 2 流体工学 3 熱工学 2章 空 調【選択問題】 1 空気調和 2 冷暖房 3 換気・排煙 3章 建築学【必須問題】 1 建築構造 4章 電気工学【必須問題】 1 電気工学 5章 衛生設備【選択問題】 1 上下水道 2 給水・給湯 3 排水・通気 4 消火設備 5 ガス設備 6 浄化槽 6章 設備に関する知識【必須問題】 1 機 材 2 配管・ダクト 7章 設計図書に関する知識【必須問題】 1 設計図書 2 JIS規格 8章 施工管理法【必須問題】 1 施工計画 2 工程管理 3 品質管理 4 安全管理 5 工事施工 9章 法規【選択問題】 1 労働安全衛生法 2 労働基準法 3 建築基準法 4 建設業法 5 消防法 6 その他の法規 10章 実地試験-施工管理法- 1 実地試験の出題傾向 2 施工経験記述 1 施工経験記述・過年度の出題テーマ 2 施工経験記述の説明 3 記述文章の説明 4 記述文参考例(施工計画,工程管理,品質管理,安全管理) 3 記述式問題 1 問題No1 施工要領図の判読(空調・衛生問題) 2 問題No2 設備機器の施工,試運転時の留意事項(空調問題) 3 問題No3 設備機器の施工,試運転時の留意事項(衛生問題) 4 問題No4 工程管理(ネットワーク手法) 5 問題No5 法 規
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 電子回路の基本をしっかり理解! アナログ回路の基礎からCMOSによるデジタル回路の入り口までを一通り俯瞰できる電子回路の入門書です。電子回路の基本を多くの回路図と等価回路を使って解説します。等価回路については苦手意識を持っている方もいるかと思いますが、ていねいに変形、計算し、つまずかないようにまとめています。 [本書の特徴] ・回路動作をイメージしやすくなるよう、回路図と波形を多く掲載 ・感覚ではなく理詰めで理解できるように等価回路とていねいな式の展開で解説 ・等価回路による解析の導出をていねいにフォロー 第1章 電子回路とは 第2章 電子回路の解析手法 第3章 半導体 第4章 pn 接合とダイオード 第5章 トランジスタ 第6章 トランジスタの等価回路 第7章 トランジスタ増幅回路 第8章 MOSFET を使った増幅回路 第9章 増幅回路の周波数特性 第10章 差動増幅回路 第11章 オペアンプ(演算増幅器) 第12章 負帰還回路 第13章 発振回路 第14章 CMOS デジタル回路 第15章 集積回路と応用例
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 図表を多用、読んで見てわかる参考書! 2002年3月発行の「はじめて学ぶ 熱力学」の改訂版です。発行から20年弱経過する中で、時代にそぐわない記述内容の修正や最新の情報にアップデートする他、大学等での講義の中で、学生にさらに深く内容を学んでいただくためのAppendixを追加し、第2版として発行するものです。 第1章 熱機器と熱力学 第2章 熱エネルギー利用技術 第3章 熱エネルギーと仕事 第4章 エネルギーの状態と変化 第5章 理想気体の状態変化 第6章 エンジンのサイクル 第7章 熱エネルギーの運動エネルギーへの変換 第8章 蒸気の状態変化 第9章 蒸気サイクル 第10章 冷凍とヒートポンプサイクル 第11章 空気調和 第12章 エネルギーと環境
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 地域包括ケアシステムの構築へ、その要となる地域包括支援センターの役割を詳説する! 高齢者を含むすべての世代の人の尊厳保持と自立生活支援の目的のもと、住み慣れた地域で人生を全うできるよう、地域の包括的な支援・サービスの提供等、2025年を目処に地域包括ケアシステムの構築が進められています。 本書は、本格的な地域包括ケア時代の到来に向けて、その概念、しくみ、構築への道筋、そしてその中心となる地域包括支援センターの役割の進化等について、実例を交え体系的にまとめた書籍として発行するものです。 はしがきにかえて Ⅰ編 地域包括支援センターの位置づけとこれまでの実践 Ⅱ編 地域包括支援センターにおける他機関との連携 Ⅲ編 地域包括支援センターの機能評価とガバナンスの強化
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 大学、電力会社、研究所、工業会の4人の監修者と50人を超える著者陣による書き下ろし!電力・エネルギー産業における注目の技術がこれ1冊で分かります。 本書は、「変革」をキーワードに、2011年の東日本大震災以降、電力・エネルギー分野において今まさに注目されている技術を50個取り上げ、その道の第一人者、専門家が解説しています。ハンドブックや技術便覧、技術入門書のような基礎・基盤技術ではなく、技術の最新動向(実用化まで遠い技術は除外)を各テーマ4ページずつコンパクトに分かりやすくまとめているので、知っておくべき電力・エネルギー分野の技術動向・市場情報を広範囲に収集するのに最適です。 Ⅰ. 分散型エネルギーを統合する Ⅱ. エネルギー事業のデジタルトランスフォーメーション Ⅲ. 熱と交通を脱炭素化する Ⅳ. 脱炭素化された電気をつくる Ⅴ. 送る・届ける技術を変革する Ⅵ. 電気を支える基盤技術 Ⅶ. 電力市場の最先端
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 苦手意識はこれ1冊で解消!構造力学がスルスル理解できるようになる 本書は、2010年4月に発行し好評を博してきた『計算の基本から学ぶ 建築構造力学』から大きくパワーアップした「改訂2版」です。 建築構造力学は苦手意識をもつ人が多い分野ですが、そんな方にはこの本は強い味方になります。いままでわからなかった問題も、基本の基本から丁寧に解き進めていくことで、よく理解できるようになります。独学者の入門書には最適です。 演習問題には建築士試験の過去問題や類似問題が収録されているので、建築士試験対策としても役立ちます。 1章 徹底的に学ぶ(計算の基礎) 2章 計算なしでとらえよう(構造力学の基礎) 3章 はりから学ぶ(構造力学の基礎) 4章 はりの応力 5章 はりの断面算定 6章 ラーメン 7章 トラス 8章 いろいろな構造力学 9章 不静定構造
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 理工系の学生にとって基礎となる内容がしっかり身に付く良問を数多く掲載した微分方程式、ラプラス変換、フーリエ解析の演習書 本書は理工系の学生にとって基礎となる内容がしっかり身に付く良問を数多く掲載した微分方程式、ラプラス変換、フーリエ解析の演習書です。 高校数学で学んだ内容を起点に、丁寧にわかりやすく解説したうえ、読者が自ら手を動かして確かなスキルが身に付けられるよう、数多くの例題、問題を掲載しています。 第1章 理工系の数学の基礎 第2章 常微分方程式 第3章 ラプラス変換 第4章 フーリエ解析 第5章 偏微分方程式
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 傾向をしっかり把握して試験に合格しよう! 本書は,工事担任者試験 総合通信(AI・DD総合種)[技術及び理論]の過去問題集です.電気通信主任技術者規則改正により,現AI・DD総合種は2021年4月から総合通信に名称変更となります. 本書は,直近5年(10回)分の問題を出題分野に沿って整理・分類して並べているので,出題傾向・頻出問題の確認を行いながら効率よく学習できるようになっています.同時に,自身の得意・不得意な分野も把握できるようになっています. 一問一問詳しい解説に加え,POINT,参考情報などを其処此処に配することで,効率的に学ぶことができるようになっています. 1章 端末設備の技術 2章 総合デジタル通信網の技術 3章 ネットワークの技術 4章 トラヒック理論 5章 情報セキュリティの技術 6章 接続工事の技術 7章 工事の設計監理・施工管理・安全管理
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 光工学、電磁波工学を具体的にわかりやすく解説。 セメスタ制に対応し、光工学、電磁波工学を具体的にわかりやすく解説しているテキスト。 ともに波動としての性質をもつ光と電磁波について、その伝搬のしかたや干渉・回折といった波動の示す性質から、応用技術である光ファイバやアンテナに関するまで、基本的なポイントを的確に押さえて、工夫された図表で大学学部生向けに解説しています。 第1章 光と電磁波の関係 第2章 電磁波がもっている基本的な性質 第3章 空間や媒質を伝わる電磁波 第4章 電磁波による干渉と回折 第5章 電波の伝送路 第6章 光の伝送路 第7章 電波の放射とアンテナ
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 予防技術検定試験で出題される要点を図表を駆使し、コンパクトにまとめた試験対策書!令和2年の法改正に対応! 予防技術検定試験の受験対策書です。 同試験で出題されるポイントにしぼり、図表を駆使し、解説しています。 「防火査察」「消防用設備等」「危険物」の全区分をカバーしつつも全体をコンパクトにまとめました。 『テキスト+問題演習』の構成で、試験に出題されやすく、最低これだけはおさえておきたい重要事項が効率よく身につきます。 多忙な受験者の皆さんが、より短時間で、効率的に学ぶことができる1冊です。 1章 共通科目 2章 防火査察(専攻科目) 3章 消防用設備等(専攻科目) 4章 危険物(専攻科目)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 最新事例や周辺技術の解説を通じて、産業用ドローンのいまがわかる! 本書は、ドローンの各産業分野における応用事例やドローン開発の基礎的な内容を解説した「ドローン産業応用のすべて ―開発の基礎から活用の実際まで―」の続編となる書籍です。 ドローン関連技術の発展や活用分野の拡大は今なお進んでおり、2019年春の航空法改正などをはじめとする法規制や諸制度の整備など、産業用ドローンを取り巻く状況は変化しています。 本書では、各産業分野における最新事例について、その活用モデルや具体的手法などをより詳しく紹介するほか、産業用ドローンに関する世界の動向分析や、周辺技術の解説なども掲載しています。産業用ドローンの概況とその最新事例をつかむことができる1冊です。 1章 世界のドローン産業をめぐる最新動向 2章 ドローンの自律制御技術と周辺技術 3章 ドローン利活用最前線 4章 国プロ(NEDO)の研究開発の概要および国際標準化の動き 5章 大都市上空飛行をはじめとする目視外・第三者上空飛行の実現に向けて 結言 ドローン産業の新たな展開
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 現代土木の「わざ」が一目でわかる! 本シリーズは、日本の優れた土木技術、土木構造物に関して、小学校高学年~中学生にも面白く・わかりやすく解説したインフォグラフィッカルなピクチャーブックです。貴重な写真や図面を数多く散りばめています。 「暮らしを支えるわざ」では、私たちが暮らしていく上での何気ない行為が土木と深く関わってお り、水道や電気・ガス、通信設備などの敷設・整備も土木の役割であることを学び、また、今後私たちの暮らす街が、土木の技によりどのように発展していくかの未来像を概観します。 1 章 人間と都市 2 章 都市の機能を支える土木構造物 3 章 生活を便利にするために必要な設備 4 章 都市の維持管理 5 章 未来の都市
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 土質力学の基本が確実に学べる! 大学・専門学校の教科書として好評の『大学土木 土質力学』の改訂版です。 土の特性から応力分布、圧密や土圧理論等について、工学的側面および実用的側面から適切・簡潔に記述しています。 さらに、最新の知見も盛り込み、学びやすく、使いやすい標準的な教科書となっています。 第1章 土の特性 第2章 土の中の水 第3章 地盤内の応力分布 第4章 土の圧密 第5章 土の強さ 第6章 土圧理論 第7章 地盤の支持力 第8章 斜面の安定
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 現代土木の「わざ」が一目でわかる! 本シリーズは、日本の優れた土木技術、土木構造物に関して、小学校高学年~中学生にも面白く・わかりやすく解説したインフォグラフィッカルなピクチャーブックです。貴重な写真や図面を数多く散りばめています。 「災害に備えるわざ」では、日本の多様な自然環境を学び、代表的な災害である地震や火山、台風、豪雪がなぜ発生するのか、またそれらが引き起こす災害を知ると共に、先人たちがそれらの災害にどのように立ち向かってきたかの歴史を学びます。また、それらから身を守るための最新の土木の技、復旧工事に使われる土木の技、さらには環境と調和した社会を作るための土木の技をわかりやすく説明します。 1章 土木の役割と歴史 2章 なぜ災害が起きるのか ~地球は生きている 3章 日本の環境 4章 自然災害 5章 自然災害から命を守る 6章 食を支える 7章 エネルギーを作る 8章 環境を守る どぼくの仕事 9章 建設機械
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 “大規模停電”が発生したとき、人は何を考え、どう行動するのか 本書は、アメリカにおけるさまざまなブラックアウト(大規模停電)の事例を示しながら、人々と電気・電力網の関係を考察するものです。 1930年代から電気が日常生活の一部になると、大規模な停電が発生するようになりました。停電は、単に電力の供給停止だけではなく、社会的な混乱、軍事的戦略、ネットワーク都市の危機、工業技術システムの欠陥、経済的、社会的政策の不備といったさまざまな角度から理解すべき問題です。本書では、アメリカの停電の歴史を時系列で示しつつ、人文科学や社会科学の観点から、人々の動向や原因、背景などを考察し、アメリカ社会の歴史を読み解いていきます。 第1章 電力網 ─大停電の夜がわたしたちに与えたもの 第2章 戦争 ─軍事戦略に組み込まれる「ブラックアウト」 第3章 事故 ─電力の普及と社会的連帯感 第4章 危機 ─豊かな社会に潜む暴力 第5章 輪番停電 ─カリフォルニア電力危機と電力自由化 第6章 テロ ─9.11以後の世界をデザインする 第7章 自主節電 ─我々はどこから来て、どこへ行くのか
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 建築設備の基礎知識が、図解でわかりやすく学べる。 ベストセラー「図解 建築設備の知識」を、改訂3版として、10年ぶりに大幅改訂しました。 この間に、数多くの専門学校、大学、高専、職訓校等でテキストとしてもご採用いただく中で寄せられたご意見を反映させ、初学者にもわかりやすい図やイラストを大幅に増やしました。 最近の現場実務にもとづき、関連法規の改正等への対応はもちろん、収載内容および解説の方法も大幅にリニューアルしています。 また、2色刷としたうえで、よりビジュアルな図へと描きなおしを行いました。 初めて建築設備について学ぶ方から、実務者の方まで、ぜひおすすめしたい書籍です。 1章 建築と設備 2章 建築と空気(空気調和設備) 3章 換気・排煙設備 4章 給排水・衛生設備 5章 建築と光(電気設備) 6章 建築と輸送(輸送・搬送設備)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 読み込みたくなるオーソドックスな受験解説書 ●基本方針と特徴 ・機械科目をしっかり勉強できる解説書 ・受験者や「新電気」誌読者の要望を丸ごと凝縮した機械科目の最適な解説書 ・電験三種はもちろん二種にも通じる徹底的な基礎力養成 ・豊富な例題、演習問題、練習問題により、解法能力の確実な向上 第1章 直流機 第2章 同期機 第3章 変圧器・静止機器 第4章 誘導機 第5章 パワーエレクトロニクス 第6章 照明 第7章 電熱・各種応用 第8章 電動機応用 第9章 電気化学 第10章 自動制御 第11章 情報伝送・処理 練習問題と解答・解説
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 読み込みたくなるオーソドックスな受験解説書 ●基本方針と特徴 ・理論科目をしっかり勉強できる解説書 ・受験者や「新電気」誌読者の要望を丸ごと凝縮した理論科目の最適な解説書 ・電験三種はもちろん二種にも通じる徹底的な基礎力養成 ・豊富な例題、演習問題、練習問題により、解法能力の確実な向上 第1章 静電気 第2章 直流回路 第3章 磁気 第4章 単相交流 第5章 三相交流 第6章 電子理論 第7章 電気・電子計測 付録1.数学・物理の基礎 付録2.進んだ研究
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 NCプログラムの作成は、CAD/CAMや自動プログラミング装置を利用するのが一般的であるが、自動作成されたプログラムだけですべてに対応できるわけではない。プログラムの基本はマニュアルプログラミングであり、これを理解しておくことが機械加工技術者にとっては必須である。 本書は職業訓練用フリーソフト「CAM13」を利用して、マシニングセンタのNCプログラムに的を絞り、独学でマニュアルプログラミングを習得できるようにしたもの。 ※本書は、工業調査会から発行されていた『職業訓練用フリーソフトでマスターするNCプログラミング』(ISBN978-4-7693-2204-7、2009年9月発行)の内容に一部修正を加えて再発行するものとなる。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『計算の基本から学ぶ建築構造力学』の姉妹書として刊行する上田耕作著の第二弾である。 建築構造力学の基礎が学べる前著に対して、本書では、大学や専門学校で講義に登場する演習問題から、1・2級建築士試験に出題されるレベルの問題までを取り上げ、問題演習を通して、計算を解きながら重要な点や陥りやすいミスのポイントなどがズバリ、スッキリ学べるように工夫しているところが特長である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 二足歩行ロボットを作って、ロボコンに挑戦!基本から、製作ノウハウまで解説 本書は、二足歩行ロボット格闘技大会「ROBO-ONE」に参加できるロボットを製作する方法を解説したものです。 基本的なロボットの構成から、サーボなど使用する部品の概要、歩行などのプログラムの作成までを解説しています。サーボの制御はArduinoを使用し、最低限歩行がきちんとできるロボットを製作します。 後半では、「ROBO-ONE」の常連参加者による、ロボット製作のノウハウの紹介が中心となります。ロボット製作のコンセプトの考え方や、格闘技の技やダンスなどの動き(モーション)をプログラムする際のコツ、ハードウェア製作のコツなど、初心者がステップアップできるだけでなく、すでに製作の経験がある方でも役に立つ内容となっています。 はじめに 1章 これからはじめる二足歩行ロボット 2章 ROBO-ONEについて 3章 ロボットの駆動部分:サーボについて 4章 Arduinoによるサーボ制御 5章 ロボットアームを作ろう 6章 色々な姿勢センサ 7章 二足歩行ロボットを作ろう 8章 色々なハードウェアを作るコツ:クロムキッドの作り方 9章 連覇するロボットの作り方(コンセプト作りを主に) 10章 ロボットに多彩な動きをさせる:メタリックファイターでのモーション作り 11章 ロボットの高速化について:Frosty 付録 失敗しないための注意点
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 材料力学の基礎をわかりやすくまとめた教科書の決定版! 材料力学の基礎をわかりやすくまとめた新しい教科書シリーズの一冊。 わかりにくい概念や難解な数式には丁寧な解説を展開しています。また、図を効果的に用いることにより、学生がつまづきやすい箇所・重要なポイントをイメージしやすく、無理なく学べる内容構成となっています。解きながら、理解し学べるよう、本文中に例題、章末には「基本問題」と「応用問題」を2段階で豊富に配しています。 大学・高専・短大生に必携の一冊です! 目次 第1章 材料力学を学ぶまえに 1-1 材料力学を学ぶうえでの基本事項 1-2 力とは 1-3 物体に作用する外力(荷重)と内力(応力) 1-4 力および力のモーメントのつり合い 1-5 材料力学で使われる単位系(SI 単位系について) チャレンジ問題 第2章 垂直荷重およびせん断力が作用する棒の取扱い 2-1 材料力学で何を学ぶか 2-2 応 力 2-3 変形とひずみ 2-4 応力とひずみの関係(フックの法則と弾性係数) 2-5 引張り試験および各種機械的性質 チャレンジ問題 第3章 軸力が作用する棒の力と変形 3-1 直列に接合された棒の応力とひずみの算出 3-2 不静定問題における応力とひずみの算出 3-3 変断面棒 3-4 自重(物体力)による棒の応力と変形 3-5 熱応力 チャレンジ問題 第4章 軸のねじり 4-1 丸棒のねじりの基礎式 4-2 ねじりの応用問題 4-3 伝動軸に加わる動力とせん断応力 チャレンジ問題 第5章 曲げが作用するはり 5-1 はりの種類 5-2 はりのせん断力と曲げモーメント 5-3 せん断力図と曲げモーメント図 5-4 集中荷重が作用する各種はり 5-5 分布荷重が作用する各種はり 5-6 モーメントが作用する各種はり チャレンジ問題 第6章 曲げの応力とたわみ 6-1 はりの曲げ応力 6-2 図心と断面二次モーメント 6-3 曲げ応力と断面係数 6-4 はりのたわみ曲線 6-5 さまざまな曲げを受けるはりのたわみ チャレンジ問題 第7章 はりの応用 7-1 不静定はりのたわみ 7-2 連続はり 7-3 はりのせん断応力 チャレンジ問題 第8章 組合せ応力 8-1 応力状態の基本型 8-2 二次元応力とモールの応力円 8-3 二次元ひずみとモールのひずみ円 8-4 応力 - ひずみ関係 8-5 弾性係数間の関係 8-6 組合せ応力の実例 8-7 ひずみゲージによる計測 チャレンジ問題 第9章 ひずみエネルギー法 9-1 ひずみエネルギーと補ひずみエネルギー 9-2 各種内力とひずみエネルギー 9-3 衝撃荷重 9-4 相反定理 9-5 カスティリアノの定理 チャレンジ問題 第10章 柱の座屈 10-1 トラスの非線形問題 10-2 オイラーの座屈荷重 10-3 境界条件の影響 10-4 初期たわみが存在する実際の棒の圧縮 10-5 塑性座屈 10-6 エネルギー法によるつり合い状態の安定判別と近似解法 チャレンジ問題 第11章 材料の破壊 11-1 機械や構造物の信頼性と性能向上 11-2 実働荷重 11-3 材料の性質 11-4 応力の性質と応力集中 11-5 機械の強度設計と許容応力 チャレンジ問題 付表1 ギリシャ文字とその読み方および主な変数としての用途 チャレンジ問題の解答(抜粋) 索引
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 機構学の基礎を丁寧にまとめた教科書の決定版! 機構学の基礎をわかりやすくまとめた新しい教科書シリーズの一冊。 機構の一連の動きをイメージできるようイラストや図を効果的に用いて、ていねいに解説をしている。また、ある機構が実際に何に使われているのかを説明することで、知識と実例を結びつけて学習することができる。 目次 はしがき 第1章 機構の基礎 1-1 機構とは 1-2 対 偶 1-3 機構の自由度 チャレンジ問題 第2章 剛体の運動解析 2-1 ベクトル 2-2 剛体の速度解析 2-3 剛体の加速度解析 2-4 数式による速度・加速度解析 チャレンジ問題 第3章 リンク機構 3-1 4節リンク機構 3-2 4節回転リンク機構 3-3 スライダ・クランク機構 3-4 両スライダ機構とスライダ・てこ機構 3-6 球面リンク機構 チャレンジ問題 第4章 機構の静力学解析 4-1 静力学の基礎 4-2 平面機構の自由体図 4-3 仮想仕事の原理 4-5 シリアルメカニズムの運動と静力学解析 チャレンジ問題 第5章 摩擦伝動機構 5-1 滑り接触と転がり接触 5-2 摩擦伝動機構 5-3 摩擦車 5-4 無段変速機 チャレンジ問題 第6章 歯車機構 6-1 歯車の種類と各部の名称 6-2 歯車の歯形曲線 6-3 歯車の歯切り 6-4 中心軸固定の歯車列 6-5 遊星歯車装置の角速度比 チャレンジ問題 第7章 カム 7-1 カムの特徴と種類 7-2 カムの運動解析 7-3 カム曲線の設計 チャレンジ問題 第8章 巻き掛け伝動機構 8-1 巻き掛け伝動の種類 8-2 平ベルト伝動 8-3 Vベルト伝動 8-4 タイミングベルト伝動 8-5 チェーン伝動 チャレンジ問題 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Jw_cadとNCVCを用いて、CAD/CAMの入門から実際の製作までできる、実践書!! 本書は、フリーソフトで定評のあるJw_cadとNCVCを用いて、CAD/CAMの入門から実際の製作に至るまでを解説しています。 はじめに 第1章 ソフトのインストールと初期設定 第2章 NC 工作機械の準備とCAD/CAM 基礎知識 第3章 基本的な加工 第4章 その他NCVC の機能紹介とロボット製作事例 第5章 NC 旋盤とワイヤ放電加工機での切削 第6章 スクリプトとアドインによるNCVC の機能拡張 第7章 NCVC リファレンス 付録 A.1 対応G コード一覧表 A.2 交点計算 A.3 FAQ A.3.1 CAD データ関連 A.3.2 NC プログラム生成関連 A.3.3 NC プログラムシミュレーション関連 あとがき 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 全国の多くの大学のカリキュラムやシラバスに合った、「電気機器学」のテキスト 電気・電子・情報通信系の大学学部向け2単位用の教科書。 本書は、電気・電子系学科の専門課目である「電気機器(学)」の講義用教科書です。電動機、変圧器、同期機、誘導機、直流機を中心として構造・原理・特性、応用を解説するほか、パワーエレクトロニクス・制御との関連、よく使われるモータなどについてわかりやすく解説するものです。全体は1コマの講義の回数に合った15章構成をとっており、各章末には理解度をチェックする演習問題を配しています。 主要目次 1章 電気機器を学ぶにあたって 2章 電気機器と磁気回路 3章 変圧器の構造と等価回路 4章 変圧器の特性 5章 電気・エネルギー変換 6章 同期機の構造と等価回路 7章 同期機の特性 8章 誘導機の構造と等価回路 9章 誘導機の特性 10章 直流機の構造と原理 11章 直流機の特性 12章 パワーエレクトロニクス概説 13章 電気機器制御とパワーエレクトロニクス 14章 制御用モータ 15章 これからの電気機器 補遺 座標変換
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、紙版書籍のページデザインを再現した固定レイアウト型電子書籍です。 受変電設備のメカニズムから、試験・検査・保守・点検のノウハウを解説! 自家用電気施設で働く電気技術者のために、また自家用高圧受電設備の保安について初めて学習する初心者のために、受変電施設の管理ノウハウをまとめた実務書です。初心者からベテラン技術者までが必要とする実務知識を、平易に図解し詳細に解説しています。 ★このような方におすすめ 自家用電気工作設置者、電気主任技術者、ビル管理技術者 ★主要目次 第1章 自家用電気設備のメカニズム 第2章 自家用高圧受電設備の主回路と機器配置 第3章 電動機設備のメカニズム 第4章 自家用高圧受電設備の試験と検査 第5章 自家用高圧受電設備の保守・点検 付録1 電気設備の電気用図記号 付録2 保安規程の事例
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本電子書籍はA5サイズの書籍より固定レイアウトで作成しました。また、見開き頁が11箇所あります。 電気管理技術者が実務に必要なノウハウを徹底収録! 本書は、自家用電気設備で働く電気管理技術者のために、受電設備のメカニズムから、試験・検査・保守・点検などのノウハウについて、電気設備のイラストを交えてやさしく解説したマニュアル書です。 ★このような方におすすめ 自家用電気設備の電気管理技術者 ★主要目次 第1章 高圧受電設備のメカニズム 第2章 高圧受電設備に用いられる機器 第3章 高圧受電設備の主回路結線と機器配置 第4章 キュービクルのメカニズム 第5章 高圧受電設備の過電流保護 第6章 高圧受電設備の地絡保護 第7章 電動機設備のメカニズム 第8章 動力幹線と電動機制御回路 第9章 電気設備の試験・検査 第10章 電気設備の保守・点検 第11章 電気設備に関する電気用図記号 付録 自家用電気設備回路図対比表(JIS C 0617 vs 旧JIS C 0301)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本電子書籍はB5変サイズの書籍より固定レイアウトで作成しました。 ■豊富な図から、パワエレ回路の動作を徹底解説! 近年における半導体素子の技術進歩により、パワーエレクトロニクスを使った電力変換装置は広範囲の電気機器に適用され、今やパワーエレクトロニクスなくして電気機器の運転はありえません。本書では、パワエレ回路の動作を素子のオンオフとその時々の回路上の電圧・電流を図で示して解説しているため、入門者でも理解しやすい内容です。本書の改訂2版では、旧版から新たに「極性反転チョッパ回路」や「FD付きRL直列単相半波整流回路」の項目を追加するとともに、回路動作や計算方法などの説明を補足して全体的な内容の補強を図っており、電験・エネ管試験の学習にも活用できます。 ★このような方におすすめ パワエレ回路の動作を基礎から学びたい方、電気設備の現場実務や設計に携わる技術者、電気主任技術者試験・エネルギー管理士試験の受験者 ★主な内容 第1章 基礎知識 第2章 直流チョッパ回路の動作 第3章 ダイオード整流回路の動作 第4章 サイリスタ制御整流回路の動作 第5章 サイリスタ交流電力調整回路の動作 第6章 他励式サイリスタインバータ回路の動作 第7章 自励式IGBTインバータ回路の動作 第8章 PWM整流回路・STATCOMの動作 第9章 複合整流回路の動作 第10章 サイクロコンバータの動作 第11章 マトリクスコンバータの動作
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本電子書籍はA5サイズの書籍より固定レイアウトで作成しました。 ISO9001規格2015年版に基づく内部品質監査のノウハウを全公開! 本書は、ISO9001に基づく“内部品質監査”の考え方と具体例を詳しく絵とき解説した定番入門書の改訂5版です。基礎から計画、評価実務まで事例を多く取り入れており、内部品質監査を学習しようとするすべての人向けの基礎指導書であり、内部品質監査員のサブテキストとしても役立ちます。 ★このような方におすすめ ISO9001内部品質監査員、及び監査員を目指す人 内部品質管理に関係する企業の管理責任者、関係技術者 ★主要目次 絵でみる内部品質監査の監査サイクル 第1章 品質マネジメントシステムの基礎知識 第2章 まず、品質管理から学ぼう 第3章 内部品質監査の基本を習得しよう 第4章 内部品質監査の導入準備はこうする 第5章 内部品質監査の実施計画を立てる 第6章 内部品質監査は初回会議から始める 第7章 内部品質監査成功のカギは“監査証拠の収集”にある 第8章 監査所見を作成する 第9章 内部品質監査における不適合事例
-
3.0人工知能と人工生命をはじめて学ぶ方に最適の一冊 本書は、人工知能と人工生命の基礎的な考え方が学べる本です。 アルゴリズムや生物学の知識が十分でないビギナー向けに、AI(人工知能)の基礎から最近の確率的推論や複雑系などの話題をわかりやすく解説しています。またAL(人工生命)では基本的な考え方から生物指向型計算と最適化手法などの応用分野までの興味深いトピックを解説しています。最新の話題として「生命を創るプロジェクト:合成生物学」についても紹介しています。探索技法については本書では扱っていません。また数式やプログラムなどは必要最小限なものに絞っています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 機械製図の基礎が学べる。CAD操作の基本をマスター。 機械要素や機械部品を題材にした豊富な演習問題によって、AutoCADによる機械製図が実用レベルまで習得できます。 AutoCAD 2013/LT2013 対応。 メニューバーからコマンドを選択する方法に加え、リボンを使用した操作方法もくわしく解説。 主要目次 CHAPTER 1 機械製図の概要 製図と機械製図 図面の大きさ 図面に用いる線の種類と太さ 図面に用いる尺度 図面に用いる文字 図形の表し方 寸法の記入方法 寸法数値の表し方 おもな寸法補助記号の使い方 CHAPTER 2 AutoCAD LTの概要 AutoCAD LTの概要 コマンドの実行 キャンセル、「元に戻す」と「やり直し」 右クリックのメニュー ズームと画面移動 直交モード グリッド オブジェクト選択 画層 オブジェクトスナップ グリップ 線の太さ CHAPTER 3 CADの基本操作 演習を始める前に よく使うコマンドとCADらしい使い方 演習(線分の作成 絶対座標入力 相対座標入力 円、円弧、楕円の作成 一時オブジェクトスナップ 定常オブジェクトスナップ スナップモード スプライン曲線の作成 ポリゴンと長方形の作成 文字記入と編集 寸法記入 ハッチング) ◎参考 ハッチングのオプション機能 よく使う修正コマンド 演習(削除 複写とオフセット 配列複写 鏡像 面取りとフィレット 移動と回転 ストレッチ 尺度変更 トリムと延長 部分削除) AutoCAD特有の使い方 縮尺する図面、倍尺する図面、部分拡大図 演習(縮尺する図面 倍尺する図面) 部分拡大図(レイアウトを作成) 演習(部分拡大図) ブロック図形 演習(ブロック定義と挿入 DesignCenter ブロックと属性定義) ◎参考 ダイナミックブロック 新しいユーザインターフェース ◎本章で解説したコマンドに対応したリボンのアイコンボタン CHAPTER 4 CADの演習 演習(正三角形と内接円 正七角形と内接円 連続半円 平行四辺形 鍔 三角穴 トロコイドもどき プレス打ち抜き材 板製スパナ) CHAPTER 5 AutoCAD LTによる機械製図 一面図 演習(板厚の表示 φと□付き寸法 ボルト 公差の記入 ロッカーアーム) 二面図 演習(Fブロック Vブロック U継手 ダイアル 共口スパナ コンロッド 星形プレート フランジ継手 シリンダ クランクシャフト 平歯車 創成歯形 傘歯車) 三面図など 演習(スぺーサ コーナ部材 軸受 ボルト・ナット 補助投影図 回転投影図 部分投影図 組立図)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 企画の立案・企画書の作り方から調査やデータ分析までを盛り込んだ実践的な書籍! 本書は、企画の立案・企画書の作り方から調査やデータ分析までを盛り込んだ実践的な書籍です。既存の調査・アンケート関係書籍がデータ分析法の解説のみに終始している中、本書は企画の立案方法から、効果的な調査の仕方、Excelによる結果の解析までを網羅し、これ1冊で調査データ分析に関するすべてが学べる内容となっております。 第Ⅰ部 調査法 第1章 調査とは 第2章 調査の企画 第3章 調査票の作成 第4章 標本抽出 第5章 調査の実施 第Ⅱ部 データ解析法 第6章 データ入力と集計 第7章 データのグラフ化 第8章 分布の特徴を記述する統計指標 第9章 推測統計学(1)~確率分布と統計的推定~ 第10章 推測統計学(2) ~統計的仮説検定と効果量~
-
3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 パワエレについて、ゼロからわかりやすく解説。 本書は、パワエレ(パワーエレクトロニクス)について、ゼロからわかりやすく解説した書籍です。 パワエレは、高電圧、大電流(強電)を扱う電子工学であり、そのために電力の変換や制御を行います。現在の私たちの生活は、パワエレなくしては成り立ちません。スマホも自動車も電車も、身のまわりにあるありとあらゆるものが、電気を自在に操るパワエレによって支えられています。 本書を読むことで、パワエレの専門家でなくても、ひととおりのポイントを押さえることができ、身近な電気製品への電力供給のしくみと技術が語れるようになります。 第0章 そもそもパワエレとは 第1章 直流と交流、電圧と電流(電気の基礎) 第2章 コイルとコンデンサ(電気回路の基本) 第3章 パワエレの基本 第4章 パワーデバイスのしくみ 第5章 パワエレの主役「インバータ」 第6章 インバータの使い方 第7章 家庭の中でのパワエレ 第8章 乗り物とパワエレ 第9章 電力系統のパワエレ 第10章 ものづくりのパワエレ 第11章 社会生活でのパワエレ
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 省エネ、環境負荷軽減を背景に、注目を浴びている外燃機関、スターリングエンジンの技術入門書の第2版。 スターリングエンジンは外燃機関であるため、多種・多様な熱源を利用することが可能であり、環境汚染、地球温暖化が大きな問題となっている現在でも、その対策として各方面から引き続き注目を集めています。 本第2版においては、2009年発行以降、14年が経過していることから、スターリングエンジンの開発の歴史において、現状まで踏まえた動向を掲載、また、用途事例にも新たな内容を加え、現状にマッチした構成となっています。 第1章 古くて新しいスターリングエンジン 第2章 スターリングエンジンの動作原理とその特徴 第3章 スターリングエンジンの基礎理論 第4章 教育用エンジン 第5章 模型スターリングエンジンの設計製作と性能 第6章 スターリングエンジンの用途事例
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 国家資格「無人航空機操縦者技能証明」取得に完全対応した決定版テキスト! 2022年12月より国家資格(「無人航空機操縦者技能証明」)となったドローン操縦ライセンス取得の本邦初の対策書です。 学科試験に関しては、操縦士に求められる知識として国交省より公表されている教則の内容を各単元ごとに解説するとともに、それぞれの単元で実際の試験を意識したチェックテスト(三肢択一式)を設け、合格の参考となるような内容でまとめています。実地試験については、公表されている実地試験実施基準に沿い、実技試験、机上試験、口述試験のあらましを解説し、受験者の理解を助ける内容となっています。 §0 試験の概要・本書の使い方 1章 ドローンの国家資格制度成立の背景 1.1 ドローンの産業応用のはじまり 1.2 ドローンの操縦技能証明が国家資格制度化された理由 2章 試験概要、資格取得までの流れ 2.1 試験の概要 2.2 試験申込みから資格取得までの流れ 2.3 学科試験の内容と合格基準 2.4 実地試験の内容 2.5 身体検査 3章 本書の使い方 3.1 本書の構成 3.2 本書の使い方 §1 学科試験 1章 無人航空機に関する規則 1.1 航空法全般 1.2 航空法に関する各論 1.3 航空法以外の法令等 1.3.1 小型無人機等飛行禁止法 1.3.2 電波法 1.3.3 その他の法令等 1.3.4 飛行自粛要請空域 2章 無人航空機のシステム 2.1 無人航空機の機体の特徴(機体種類別) 2.1.1 無人航空機の種類と特徴 2.1.2 飛行機 2.1.3 回転翼航空機(ヘリコプター) 2.1.4 回転翼航空機(マルチローター) 2.2 無人航空機の機体の特徴(飛行方法別) 2.2.1 夜間飛行 2.2.2 目視外飛行 2.3 飛行原理と飛行性能 2.3.1 無人航空機の飛行原理 2.3.2 揚力発生の特徴 2.3.3 無人航空機の飛行性能 2.3.4 無人航空機へのペイロード搭載 2.3.5 飛行性能の基本的な計算 2.4 機体の構成 2.4.1 フライトコントロールシステム 2.4.2 無人航空機の主たる構成要素 2.4.3 送信機 2.4.4 機体の動力源 2.4.5 物件投下のために装備される機器 2.4.6 機体又はバッテリーの故障及び事故の分析 2.5 機体以外の要素技術 2.5.1 電 波 2.5.2 磁気方位 2.5.3 GNSS 2.6 機体の整備・点検・保管・交換・廃棄 2.6.1 電動機における整備・点検・保管・交換・廃棄 2.6.2 エンジン機における整備・点検 3章 無人航空機の操縦者及び運航体制 3.1 操縦者の行動規範及び遵守事項 3.2 運航時の点検及び確認事項 3.3 飛行申請 3.4 保険及びセキュリティ 3.5 操縦者に求められる操縦知識 3.6 操縦者のパフォーマンス 3.7 安全な運航のための意思決定体制(CRM 等の理解) 4章 運航上のリスク管理 4.1 運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案の基礎 4.2 気象の基礎知識及び気象情報をもとにしたリスク評価及び運航の計画の立案 4.3 機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案 4.4 飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案 §2 実地試験 1章 実地試験の概要 1.1 試験科目の構成 1.2 合格基準と減点適用基準 2章 机上試験 3章 口述試験 4章 実技試験
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 シーケンス制御を基礎から解説! 実体配線図とシーケンス図の対比で回路の流れが早わかり 大浜庄司著、待望の改訂版です。 初級者がシーケンス制御技術を体系だって習得できるよう、わかりやすくていねいに解説しました。 ①ボタンスイッチ、電磁リレー、電磁接触器、タイマなどは、その動作が明確にわかるように内部機構を色別に表記 ②配線用遮断器、熱動過電流リレー表示灯などの制御機器は、立体図で内部構造を表記 ③シーケンス図と実体配線図を併記 することで、初級者が学びやすい1冊となっています。 1章 シーケンス制御とはどういう制御か 2章 シーケンス制御に用いる電気用図記号の表し方 3章 ナイフスイッチ(手動操作開閉器接点)の動作と図記号 4章 ボタンスイッチ(手動操作自動復帰接点)の動作と図記号 5章 電磁リレー(電磁リレー接点)の動作と図記号 6章 電磁接触器(電磁接触器接点)の動作と図記号 7章 タイマ(限時接点)の動作と図記号 8章 シーケンス制御記号の表し方 9章 制御器具番号の表し方 10章 シーケンス図の表し方 11章 AND回路とOR回路の読み方 12章 NAND回路とNOR回路の読み方 13章 自己保持回路の読み方 14章 インタロック回路の読み方 15章 時間差のはいった回路の読み方 16章 電動機の始動制御回路の読み方 17章 電動機の正逆転制御回路の読み方 18章 ガレージシャッタ設備の制御回路の読み方 19章 給水設備の制御回路の読み方
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ディジタル回路を演習を通じて理解する教科書 初めてディジタル回路を学ぼうとする人に,その全般にわたり詳細な説明と多くの演習によりわかりやすく解説. ※本書籍は、日本理工出版会から発行されていた『図解 ディジタル回路入門』(1999年4月)をオーム社から発行するものです。 第1章 ディジタル信号 1-1 ディジタル回路で扱う信号 1-2 ディジタル回路の数体系 1-3 各種数体系間の基数変換法 1-4 2進数の四則演算 1-5 2進数の負数表現 1-6 情報のコード化 演習問題 第2章 基本論理素子 2-1 ANDゲート 2-2 ORゲート 2-3 NOTゲート 2-4 AND,OR,NOTの組合せ回路 2-5 NANDゲート 2-6 NORゲート 2-7 XORゲートとXNORゲート 2-8 正論理と負論理 2-9 NANDとNORゲートの機能変換 演習問題 第3章 論理代数と論理圧縮 3-1 論理式とブール代数 3-2 論理圧縮 演習問題 第4章 フリップフロップ 4-1 RS-FF 4-2 フリップフロップのトリガ方式 4-3 RST-FF 4-4 D-FF 4-5 JK-FF 4-6 T-FF 演習問題 第5章 符号変換回路 5-1 エンコーダ(符号器) 5-2 エンコーダ用IC 5-3 デコーダ(復号器) 5-4 デコーダ用IC 演習問題 第6章 選択回路 6-1 マルチプレクサの基本回路 6-2 マルチプレクサ用IC 6-3 デマルチプレクサの基本回路 6-4 デマルチプレクサ用IC 演習問題 第7章 比較回路 7-1 一致/不一致回路 7-2 大小比較回路 7-3 コンパレータ用IC 7-4 他機能ICのコンパレータとしての使用例 演習問題 第8章 算術演算回路 8-1 加算回路 8-2 減算回路 8-3 補数減算回路 8-4 加減算回路 演習問題 第9章 シフトレジスタ 9-1 シフトレジスタの基本回路 9-2 並列入力→直列出力 9-3 可逆シフトレジスタ 9-4 シフトレジスタ用IC 第10章 カウンタ 10-1 リングカウンタ 10-2 ジョンソンカウンタ 10-3 自己修正形リングカウンタとジョンソンカウンタ 10-4 バイナリカウンタ 10-5 バイナリカウンタ用IC 演習問題 参考文献 問題解答 付録 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 魚の身体検査?! 謎多き深海魚のCT画像集 近年、深海魚のユニークな見た目や生態に興味を持つ人が増えていますが、普段の食卓にあがらないものも多いので、体の中がどうなっているのか知る人はあまりいないのではないでしょうか。 本書は、深海魚のエックス線CT(断層写真)を見ながら体の仕組みやユニークな生態について知ることができる、これまでにない図鑑です。 ◎置き場所に困らないA4サイズ 目次 口絵:魚類標本写真 本書の見方 生息場所と種多様性 進化と適応 ■ Ⅰ 「特殊化」するという進化 1. 顎が大きくなる 2. 眼が大きくなる 3. 体の一部が変化する ■ Ⅱ 「退化」するという進化 1. 眼が小さくなる 2. 骨や鱗が発達しない
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 実務に必ず役立つ!空気調和施工図の作成マニュアル 2014年11月発行の「図解 空気調和施工図の見方・かき方(第3版)」の改訂版です。 空気調和施工図は、設備の納まり検討図(取合い図)を作成したあとに取り掛かる空調設備施工の大元となる図です。しかし、施工図に不備があると設備間で取付け後にぶつかりあったり、手直しが必要になったりすることがあるため、本書で基本の作成法を学びます。 1章 施工図のかき方 2章 施工図の見方 3章 基本の計画と寸法の決め方 4章 作図上の留意事項 5章 建築関連事項 6章 ダクト 7章 配管 8章 冷媒配管・パッケージドレン 9章 自動計装 10章 機器の配置とスペース 11章 スリーブ,インサート,設備複合図 12章 チェックリスト 付録 施工図教育・技術力確認シート(理解度テストI・II) 施工図サンプル
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 信号処理の基礎から最新の理論まで解説! 信号処理は、さまざまなセンサー(カメラ、マイクなど)から得られる信号(音響、画像、映像など)をディジタル化してコンピュータで処理し、瞬時に伝送するのに加え、インターネットで流通、共有させるために不可欠な技術分野です。信号処理によって、人間が聞きやすく、見やすく、分かりやすくし、さらには人間や機械がより高度な分析や判断を行うことを可能にします。 「IoT」や「ビッグデータ」においても、実世界に存在する無数のセンサーからの大規模データ(信号)が実時間で記録、保存、解析されることが前提となっており、「可視化」「見える化」「イメージング」などが実現されます。信号処理がなければ、現代のスマート社会は成り立たないといっても過言ではありません。 本書は、信号処理の大学学部レベルの教科書を想定して書かれていますが、大学院レベルの内容も含まれています。第13章「新しい信号処理」では、深層学習の基礎となるディープニューラルネットワークと、近年注目されているグラフ信号処理についてもふれています。また、本文中には多くの問いを設け、その解答も掲載しています。 第1章 信号処理とは 第2章 信号の表現と演算 第3章 信号処理システム 第4章 連続時間フーリエ解析 第5章 サンプリング 第6章 離散時間フーリエ解析 第7章 高速フーリエ変換 第8章 窓関数と短時間フーリエ変換 第9章 z変換 第10章 ディジタルフィルタ 第11章 離散コサイン変換とウェーブレット変換 第12章 画像・映像の圧縮:JPEG・MPEG 第13章 新しい信号処理
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 日常の鉄道システムの安全を支える舞台裏がわかる唯一の書 鉄道システムは、軌道・構造物、車両、信号・通信設備、電車線・電力設備、駅設備、踏切設備などのハードウェアに加え、運転計画・指令、信号システムなどのソフトウェアと連携する中で成り立っています。一方で、平時またはさまざまな事故の発生時にこのシステムの安全性、信頼性が担保されるよう、鉄道事業者は常に保安・管理に気を払っています。 本書は、この鉄道システムの保安・管理をテーマとして、日本鉄道技術協会の総合安全調査研究会で蓄積してきた技術や運用の実態、今後のあり方などの議論をベースとして、鉄道事業者はもとより、鉄道に興味をもつ一般の方にもリーチするようなわかりやすい書籍としてまとめたものです。 第1章 総論 ~鉄道の安全は総合力のたまもの~ 1.1 鉄道システム 1.2 列車走行の安定を支える(軌道・構造物) 1.3 快適さと安全を提供する鉄道の象徴(車両) 1.4 鉄道の安全を守る神経器官(信号・通信) 1.5 列車を動かす原動力(電車線・電力設備) 1.6 列車運行の管制塔(運転計画・指令) 1.7 利用客の安全の砦(駅) 1.8 道路交通と乗客を守る(踏切設備) 1.9 安全技術の習得と実戦力涵養(教育・訓練) 1.10 鉄道事業・活動のみなもと(法・規程) 第2章 軌道・構造物 ~列車の走行と安全を支える~ 2.1 車両を直接支える軌道 2.2 列車を支える構造物 2.3 自然災害への備え 第3章 車両 ~快適さと安全を提供する鉄道の象徴~ 3.1 鉄道車両の特徴 3.2 車両での安全確保方法 3.3 乗客の安全確保方法 3.4 地上設備検査用車両 3.5 車両基地の災害対策など 第4章 信号・通信 ~鉄道の安全を守る神経器官~ 4.1 信号・通信にかかわる設備の全体像 4.2 信号保安設備 4.3 駅や指令、列車、職場を網の目のようにつなぐ通信設備 第5章 電車線・電力設備 ~列車を動かす原動力~ 5.1 列車を動かす電気を作る変電設備 5.2 列車を動かす電気を運ぶ電路設備 5.3 駅を守る電気機器等設備 5.4 電気機器等設備の保守管理 第6章 運転計画・指令 ~列車運行の「管制塔」~ 6.1 運行管理における指令の役割 6.2 列車運行における安全確保の取組み 6.3 保守作業における安全確保の取組み 6.4 事故などが発生したときの対応 6.5 指令所施設 6.6 運行管理にかかわる情報収集・発信 6.7 利用者への情報発信 6.8 教育と他事業者との連携 第7章 駅 ~利用客の安全の砦~ 7.1 車両との接触防止 7.2 ホームからの転落防止 7.3 ホーム上での注意喚起 7.4 地下駅の火災対策 7.5 地下駅の浸水防止 第8章 踏切設備 ~道路交通と乗客を守る~ 8.1 踏切に列車の接近を知らせる踏切の制御方式 8.2 通行者に列車の接近を知らせる踏切警報機 8.3 踏切に列車の接近を知らせる踏切遮断機 8.4 踏切での異常を列車に伝える踏切支障報知装置 8.5 ATACSで実現した新しい踏切制御 第9章 教育・訓練 ~安全技術の習得と実践力涵養~ 9.1 教育目的の多様性と訓練シナリオの工夫 9.2 地域貢献も兼ねた安全啓発 9.3 教育効果を高める技術 付 録 法・規程、主な鉄道事故 付.A 法・規程 ~鉄道事業 活動のみなもと~ 付.B 主な鉄道事故など 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 RとPythonで統計学を実践的に学ぶ! 本書はRとPythonを使って,統計学の基礎を実践的に学ぶテキストです. 近年,IoTや人工知能ブームなどに代表されるように,人が日々扱うデータは増え続けています.データの量・種類が増えるにつれ,ただ闇雲にツールを使って分析するだけではなく,なぜその手法を使うのか,結果から何を読み取るのかなどといったことがポイントになってきます. このポイントを正しく理解し,適切にデータ分析を行うには十分な統計学の知識が必要になってきます.しかしながら統計学の土台は数学であり,数学に苦手意識をもつ方にとって純粋な統計学の教科書はハードルが高いと思われます.また,平易な参考書においても,結局のところ手元のデータをどうすればよいのかといったところで,また一つ壁があります. そこで本書は,データ分析に優れた環境であるRと,機械学習など大規模なデータ分析に定評のあるPythonによるプログラミングを通して統計学を解説します.統計学を学びたい,データを分析したいというエンジニアや学生に向けて,数学的な壁を取り払いつつ,実際にデータを分析するための統計学の知識を提供します. 第1章 データ分析と統計が注目される理由 第2章 基本統計量を知る 第3章 よく使われる分析手法を知る 第4章 確率の基本と推定を知る 第5章 検定の手法を知る 第6章 将来を予測する 付 録 数学知識の復習
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 配電ネットワークシステムを体系的に解説 電力システム改革や再生可能エネルギーの主力電源化等の環境変化の中で、一般送配電事業者は変革の時期にあります。再エネルギーを始めとした分散型電源の多くは配電系統へ連系されており、配電系統への関心はこれまでになく高まっています。本書では、配電系統の基礎を網羅しつつ、今後の電力システム改革で必要となるであろう技術動向を見据えて、重要と考えられる事項も丁寧に解説しています。配電を含むネットワークシステムを体系的に取り扱うこれまでにない1冊です。 序章 配電系統に求められる社会的要請と配電ネットワークシステム工学 第1章 電力ネットワークシステムの構成 第2章 配電ネットワークシステムに関する計算の基礎 第3章 配電ネットワークシステムの計画・保安・運用 第4章 配電ネットワークシステムにおける分散型電源との協調 第5章 配電ネットワークシステムにおける将来の技術動向
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ベッドサイドで役立つ! 超音波(エコー)初心者 必携の入門書 最新の第2版 非侵襲性検査として、医療現場において使用頻度が高い超音波(エコー)に関する実務入門書です。 初心者向けの入門書として、基礎の基礎から各部位における検査のポイントまでを一通り取り上げています。また、エコー画像とシェーマ(イラスト図)を併記し、さらにCT画像を掲載して、経験豊富な技師がどのように画像を見ているのかを、わかりやすく解説しています。 また、新書判なので、白衣のポケットに入れて携行でき、日常診療に役立つ「TNM分類」「カタカナ略語」「実践英会話」も掲載してあり、ベッドサイドにおいて利用できる内容を中心にまとめてあります。 改訂2版では,初版で説明の足りなかった箇所を見直し、新たに代表的な疾患画像を多く掲載しました。 第1章 検査に必要な基礎知識 第2章 走査法と表示法 第3章 基本走査と超音波画像解剖 第4章 肝臓・門脈 第5章 脾臓 第6章 胆嚢・胆管 第7章 膵臓 第8章 腎臓・副腎 第9章 膀胱・前立腺 第10章 消化管 第11章 腹部大動脈 第12章 子宮・卵巣 第13章 超音波診断基準・判定基準 第14章 病期分類・ガイドライン 第15章 会話略語・実践英会話 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 平成25年度~令和2年度までの全問題と解答解説を完全収録!! 本書は、高圧ガス保安協会が実施する「第3種冷凍機械責任者試験(第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験)」に関して、過去問題8年分とその解答・解説を掲載したものです。 過去問題は年度ごとに収録し、1問ごとに問題と解説、解答を掲載しています。問題の各記述について、正誤にかかわらず詳しく解説しており、周辺知識も身につけつつ学習することができます。 1問ごとに着実にマスターしたい方におすすめの一冊です。 令和2(2020)年度 試験問題と解答解説[法令・保安管理技術] 令和元(2019)年度 試験問題と解答解説[法令・保安管理技術] 平成30(2018)年度 試験問題と解答解説[法令・保安管理技術] 平成29(2017)年度 試験問題と解答解説[法令・保安管理技術] 平成28(2016)年度 試験問題と解答解説[法令・保安管理技術] 平成27(2015)年度 試験問題と解答解説[法令・保安管理技術] 平成26(2014)年度 試験問題と解答解説[法令・保安管理技術] 平成25(2013)年度 試験問題と解答解説[法令・保安管理技術] 平成24(2012)年度 試験問題と解答解説[法令・保安管理技術]
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 丁寧な図と解説で、初学者でもExcelを使ってデータ解析や統計処理ができる! 本書は、得られたデータの解析手順やその後の統計処理までをExcelを使って自学できるよう、分かりやすく丁寧に解説したものです。また、「ノンパラメトリック検定」もExcelで扱えるように解説してあります。統計学で必要な難しい数式は省略せずに掲載してありますが、エクセル操作部分を丁寧に解説しているので、数式が理解できていなくても、データ解析から目的の結果へと進めることができます。本書を片手に同じように操作を進めていくだけで、データ解析や統計処理で使える技術(目的に合わせて使いこなす技術)を習得でき、応用できるようになります。 <解析編> 第1章 ヒストグラム 第2章 基本統計量 第3章 正規分布 第4章 相関分析 第5章 回帰分析 第6章 周波数解析 第7章 グラフ 第8章 モデル関数のあてはめ <統計編> 第9章 関連2群の差の検定 第10章 独立2群の差の検定 第11章 独立3群以上の差の検定 第12章 関連3群以上の差の検定 第13章 分割表の検定 第14章 生存時間解析 <付録> 付録1 正規分布 付録2 t検定表 付録3 ウィルコクスンT検定表 付録4 F検定表 付録5 U検定表 付録6 クラスカル・ウォリス検定表 付録7 x2検定表(上側確率) 付録8 フリードマン検定表
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 実例に基づいた例題とわかりやすい図,丁寧な解説で効率よく学習! 医療でも統計は、研究、実験、学術誌投稿、臨床など様々なシーンで活用されていますが、多くの方は高価な統計ソフトを使いこなせていないのが現状です。本書では、最も普及している「MS-Excel」を利用して、初心者でもすぐに解析できるように、実例に基づいた実用的手法をやさしく丁寧に解説しています。 第1章 統計をはじめる前に 第2章 分析の準備 第3章 2つの代表値(平均値・中央値)の比較 第4章 3つ以上のデータの差を比較する 第5章 比率の差を比較する(クロス集計) 第6章 2つのデータの関連性をみる(相関と回帰) 第7章 多次元データを比較する(多変量解析) 第8章 イベント・ヒストリー分析:生存時間(率) 付録A 本書で使用した統計分析用Excel関数一覧 付録B フリーオンラインソフトの使用方法 付録C 本書で使用した主な統計用語
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 有機化学で整理不足の知識を「サプリメント(補充)できる」フルカラーの分かりやすい参考書! 本書は、体系的に学べる手軽でやさしい解説書が数多く出版されている中で、有機化学の「(他のことはともあれ)これだけは押さえて欲しい」という部分だけを精選し、「サプリメント(知識補充)式」としてまとめた参考書です。習得したい知識をダイレクトに得ることができるため、自分自身で知識の整理や反復復習など容易に行うことができ、卒業研究のためにポイントだけ知りたい学生以外や、突然、有機化学の知識が必要となった若い研究者の参考書として活用できるものです。 Supplement 1.化合物命名法 Supplement 2.化学反応 Supplement 3.立体化学 Supplement 4.脂肪族求核置換 Supplement 5.脂肪族求電子付加 Supplement 6.脂肪族求核付加 Supplement 7.芳香族求電子置換 Supplement 8.芳香族求核置換 Supplement 9.脱離 Supplement 10.転位 Supplement 11.酸・塩基 Supplement 12.酸化・還元
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 全ページ、図で解説、シーケンス制御のロングセラー実務書! 本書は、シーケンス制御の実務に関して全ページでイラストと図を使って説明した書籍です。 本書のオリジナル版は1973年に発行され、以来、数十万人の方々にシーケンス制御の独習書・現場教育におけるテキストとしてご愛読いただいています。 本書の特徴は、(1)イラストを使った用語解説、(2)シーケンス図の描き方を順序立てて解説、(3)シーケンス制御装置を配線図を使って解説、(4)シーケンス制御の動作順序をスライド式に図示、(5)動作回路を色つき矢印で図示、していることなどです。 なお、本書の電気用図記号は、JIS C 0617(IEC60617)に準拠しています。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 全ページ、図で解説、シーケンス制御のロングセラー入門書! 本書は、シーケンス制御の初歩を図を使って説明した入門書です。一部ではなく、全ページが図解となっています。 本書のオリジナル版は1971年に発行され、以来、数十万人の方々にシーケンス制御基礎の独習書・現場教育におけるテキストとしてご愛読いただいています。 本書の特徴は、(1)イラストを使った用語解説(2)シーケンス図の描き方を順序立てて解説(3)シーケンス制御装置を配線図を使って解説(4)シーケンス制御の動作順序をスライド式に図示(5)動作回路を色つき矢印で図示、していることなどです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 FPGAによるモータ制御回路の設計を解説 本書は、ソフトウェアのように回路構成を書き換えることができるFPGAを用いて、PLLモータ制御回路の設計と実現を解説するものです。 ディジタル回路の基本から、FPGAによるいくつかの応用回路の設計、PLLモーション制御までを解説します。著者の実際の経験を基にして、モータ制御回路を設計し、モーション制御を実装したい方向けに解説しています。 第1章 FPGAとは 第2章 ディジタル回路設計とツール 第3章 FPGAによる応用回路設計 第4章 PLLモーション制御 第5章 FPGAのIoTへの活用事例 おわりに 付録 A.1 Quartus Prime Lite Ed.のインストール A.2 VHDL言語かんたん解説 A.3 ディジタル砂時計のVHDLソースリスト A.4 PLL/PWMモータ制御系のVHDLソースリスト A.5 MAX7128S評価ボード
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 2016年4月の診療報酬改定に対応!一番わかりやすいテキストが内容を刷新し登場! 医師事務作業補助者とは、医師の文書作成業務を代わりに行う業務を主とする職業です。 現在、民間で医師事務作業補助者の資格試験が5団体で実施されており、約1万人程度の受験者数を集めています。これら民間試験の平均合格率は約50%と高く、試験自体はそれほど難しくはないのですが、いざ実務に携わるには知識不足となり、また、無資格でも診療情報管理士や医療事務から転属を命じられ、医師事務作業補助者として業務に携わっている方がいます。 本書はそのような方々向けに医師事務作業補助者のための知識の定着をはかる参考書として発行しましたが、2016年4月の診療報酬の改定を受け、内容を一部刷新し新たに改訂2版として発行するものです。 1章 医療関連法規 2章 医療保険制度 3章 医学一般 4章 薬学一般 5章 医療と診療録 6章 医師事務作業補助業務
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 SPSSシンタックスを用いたデータ処理の手順がよくわかる!! 本書は、統計ソフトウェアSPSSを用いてデータの計量分析を基礎から学ぶためのものです。初学者がデータ入力から分析、結果の見方、発表までを一冊で学べるものとし、初学者がつまずきやすい点についてもあらかじめ明示します。また、実際の分析の際にはクリックだけで行うよりも、シンタックスを利用した方が効率的、かつ容易であることがしばしばあるので、SPSSの基本操作と併せてSPSSシンタックスを用いたデータ処理の手順も解説します。 主要目次 はじめに 第1部 準備編 第1章 統計分析にあたって 第2章 SPSSの基本操作 第3章 変数の作成と加工 第4章 データの加工と応用 第2部 分析編 第5章 変数の特徴を知る:度数分布と記述統計 第6章 グループ間で平均値を比較する:平均値の差の検定 第7章 質的変数間の関連を調べる:クロス集計表 第8章 量的変数間の関連を調べる:相関係数と偏相関係数 第9章 複数の変数を重み付けして合成する:主成分分析 第10章 複数の変数の共通因子を探る:因子分析 第11章 量的変数に対する要因の影響力を調べる:重回帰分析 第12章 質的変数に対する要因の影響力を調べる:ロジスティック回帰分析 参考文献 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 <B5判カラーの書籍を固定レイアウトで制作したものです。カラー対応で大き目の端末でご覧ください> 分散型電源(太陽光発電・風力発電等)を電力系統に連系するための基本技術を図解で徹底解説!! 電力会社が再生可能エネルギーを固定価格で一定期間買い取る「再生可能エネルギー特別措置法」の施行によって、太陽光発電や風力発電の設備が飛躍的に普及しています。これらの発電設備は、電力会社の低圧・高圧の配電線につながれ、いわゆる系統連系されて運用されることになります。電力系統の周波数や電圧、さらには系統安定度を乱すことなく連系されることが条件であり、また事故時には発電設備としての保護対策をも万全にして連系することが前提の条件でもあります。 本書は、これら系統連系の基本の技術を、図解で徹底解説した発電設備側の解説書です。 ★このような方におすすめ 太陽光発電・風力発電設備等の設計・施工・管理に携わる電気技術者 電力会社・メーカーの電気技術者 ★主な内容 第1編 分散型電源を低圧・高圧配電線へ連系するための基礎知識 第2編 太陽光発電システムの原理と構成及び単独運転検出とFRT要件 第3編 低圧配電線への連系 第4編 高圧配電線への連系 第5編 分散型電源の設置・運転するための諸手続き ★目次 第1編 分散型電源を低圧・高圧配電線へ連系するための基礎知識 1.太陽光・風力発電の日本及び世界での普及状況 2.再生可能エネルギー固定価格買取制度 3.電気事業のいま・むかし 4.電力系統の構成と公称電圧及び低圧配電線の電気方式 5.系統連系技術要件ガイドラインの概要と変遷 6.用語の図解 第2編 太陽光発電システムの原理と構成及び単独運転検出とFRT要件 1.太陽電池の原理と種類及び特性 2.太陽光発電システムの構成 3.単独運転検出とFRT要件(系統連系規程JEAC9701-2012) 第3編 低圧配電線への連系 1.分散型電源の分類(低圧連系・高圧連系共通) 2.電気方式 3.系統連系保護リレー 4.高低圧混触事故対策 5.単独運転防止対策 6.FRT(事故時運転継続)要件 7.保護装置の設置 8.解列箇所 9.保護リレーの設置相数 10.変圧器 11.その他の事項 12.発電設備等設置者保護装置の構成例 第4編 高圧配電線への連系 1.系統連系保護リレーの設置 2.発電設備等故障対策と系統側事故対策 3.単独運転防止対策 4.FRT(事故時運転継続)要件 5.保護装置の設置場所 6.解列箇所 7.保護リレーの設置相数 8.自動負荷制限 9.線路無電圧確認装置 10.保護リレー:検出レベルと検出時限及び短絡事故に関する留意点 11.保護装置の構成例 12.逆潮流の制限 13.短絡容量 14.連絡体制 第5編 分散型電源の設置・運転するための諸手続き 1.電気事業法などの関連法 2.発電設備の認定 3.保安規程 4.電気主任技術者の選任 5.工事計画(事前届出) 6.使用前安全管理検査(使用前自主検査) 7.使用前安全管理審査 8.電力会社との手続き
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 12Vの低電圧で真空管アンプの情感ある音を生み出す。 本書では、12Vという電圧の制限を課して真空管アンプを製作します。通常使われる200Vから400Vという高い電圧を使用した真空管アンプと比べ、部品を安価に抑えられ、感電の危険をなくし、配線を間違えたときの部品の損傷もある程度防げます。しかも、高電圧のものと比べて遜色のない音の特性曲線を得られるように、LTspiceを用いてシミュレーションを行います。 LTspiceはインストール方法から便利な使い方、実際のシミュレーション例まで解説しています。そのため、経験がない方でも本書の通りにLTspiceを実行、真空管アンプを製作できます。 はじめに 第1章 ブレッドボードで製作する低電圧ハイブリッドアンプ 第2章 真空管と真空管アンプの原理 第3章 真空管を用いた増幅回路 第4章 LTspice XVIIの設定および使い方 第5章 低電圧における真空管のモデル作成 第6章 低電圧ハイブリッド真空管アンプの各パーツのシミュレーション 第7章 低電圧ハイブリッド真空管アンプのシミュレーション 付録A 真空管の低電圧特性実測データ 付録B 真空管の特性フィッティングプログラムとデータ形式
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 豊富な演習350問。徹底的に電気回路計算力を養う特訓書 長年、電気理論指導に定評ある著者が、電気系初学者に対する「回路の知識」「解析力の涵養」を目指して執筆した学習書です。改訂のポイントは、「①解説のブラッシュアップ」「②過渡現象、行列に対応です。解答に至る過程を丹念に解きほぐす手法も大きな特徴です。掲載の全問題は合計350問に達し、これを解くことで、電験三種合格レベルの実力に導きます。 〈このような方におすすめ〉 ・大学、高専、工高、専門学校生 ・電験資格取得を目指す受験者 ・電気回路の計算技術を磨くエンジニア 〈主要目次〉 第1章 直流回路計算(1) オームの法則 オームの法則 電流・電圧・抵抗 電力と電力量 湯沸かし器の電力と電力量 抵抗の直列接続 直列回路の電力 キルヒホッフの電圧則(第2法則) 電圧源の直列接続 抵抗と分圧(電圧の分割) 抵抗の並列接続 並列回路の合成抵抗 並列回路とコンダクタンス キルヒホッフの電流則(第1法則) 未知電流 分流式 直並列回路 抵抗と消費電力 ラダー回路 電圧源と内部抵抗 電位と電位差 電位差 3端子可変抵抗器と負荷抵抗 倍率器 2台の電圧計による電圧測定 電圧計の内部抵抗 分流器 2台の電流計で測定 電流を1:2に分割 文字式計算 電流を2倍にする 短絡した時の電流 電池1個の内部抵抗 ブリッジ回路と平衡条件 ホイートストンブリッジ 最大消費電力 自習問題 第2章 直流回路計算(2) キルヒホッフの法則とべんりな定理 キルヒホッフの法則と枝路電流法 ループ電流法 行列式を用いた連立方程式の解法(クラメルの公式) クラメルの公式による解法 クラメルの公式 3線式電線路 電圧源と電流源-1 電圧源と電流源-2 電圧源と電流源-3 重ね合わせの理-1 重ね合わせの理-2 負荷Δ−Y変換 負荷Y−Δ変換 ブリッジ回路の合成抵抗 節点電圧法-1 節点電圧法-2 ミルマンの定理-1 ミルマンの定理-2 テブナンの定理-1 テブナンの定理-2 ノートンの定理 ブリッジ回路の電流 可逆の定理 自習問題 第3章 交流回路計算(1) オームの法則と記号法 正弦波交流電圧と電流の瞬時値式 最大値・角速度・周波数 交流電圧と電流の波形 ラジアンと度数 平均値と実効値 電流の和 複素数の四則計算 S表示(スタインメッツ表示) 掛け算と割り算はS表示 四則計算とベクトル 瞬時値式とS表示 直交表示による電流の和 電流の和 インピーダンスZ・[Ω] R−L−C 回路 R−L 直列回路のインピーダンス 交流回路におけるオームの法則 直列回路のインピーダンスZ・[Ω] インピーダンスの端子間電圧V・[V] 未知インピーダンス R−C 直列回路 R−L−C 直列回路 電圧分割式 R−L 並列回路 並列回路のインピーダンスZ・[Ω] 分流式 R−L−C 並列回路とアドミタンスY・[S] 位相差 インピーダンスZ・[Ω]とアドミタンスY・[S]の関係 電圧測定と未知インピーダンス 未知リアクタンス 有効電力P[W],無効電力Q[var],皮相電力S[V・A] 電力三角形 力率改善 直交表示による有効・無効電力計算 並列回路の電力三角形 周波数変化と力率 直列共振回路 直列共振周波数 理想並列共振回路 並列共振回路 並列共振周波数-1 並列共振周波数-2 自習問題 第4章 交流回路計算(2) キルヒホッフの法則とべんりな定理 枝路電流法 枝路電流法とループ電流法 ループ電流と電力 重ね合わせの理 電圧源と電流源 節点電圧法-1 重ね合わせの理と節点電圧法-2 テブナンの定理とノートンの定理 ブリッジ回路の電流 節点電圧法-3 節点電圧法-4 負荷Δ−Y変換 Δ−Y負荷のインピーダンス 最大消費電力定理 最大消費電力-1 最大消費電力-2 可逆の定理-1 可逆の定理-2 ひずみ波回路 ひずみ波の波形 ひずみ波回路の電圧と電流 ひずみ波電圧・電流の実効値 ひずみ波電流の実効値計算 ひずみ波回路の皮相電力,消費電力,力率 ひずみ波回路の消費電力-1 ひずみ波回路の消費電力-2 ひずみ波回路の消費電力-3 ひずみ波回路の消費電力-4 自習問題 第5章 交流回路計算(3) 三相回路 三相交流電源 Y電源とΔ電源 相電圧と線間電圧 Y負荷とΔ負荷 Y−Y回路の電力 Δ−Δ回路の電力 線間電圧・線電流と電力 Y−Δ回路の電力 Δ−Y回路の電力 負荷のΔ−Y変換およびY−Δ変換 Y−Δ変換 Δ−Y変換 三相電力 三相電力の測定 不平衡Y負荷-1 不平衡Y負荷-2 不平衡Δ負荷 自習問題 第6章 過渡現象 過渡現象の計算 微分方程式解法1 微分方程式解法2 微分方程式解法3 微分方程式解法4 自習問題 自習問題の解答 1章自習問題の解答 2章自習問題の解答 3章自習問題の解答 4章自習問題の解答 5章自習問題の解答 6章自習問題の解答 付録:理解しておこう/覚えておこう 基本法則と公式 ●学習コラム 最小定理 覚えておこう三角形と三角比 電圧源と電流源の相互変換法 電圧V・[ V],電流I ・[A],インピーダンスZ・[Ω]の・(ドット)とは? 平均値とは 実効値とは 忘れないでピタゴラス(三平方)の定理 交流か直流か? 交直論争 抵抗R[Ω],インダクタンスL[H],静電容量C[F]の電流と電圧 覚えておこう「辺3,4,5の直角三角形」 ギリシャ文字を再確認しておこう 直列・並列回路のまとめ 二つの商用周波数 電気の研究小史 Y−Δ回路の相電圧と線間電圧および相電流と線電流の測定 Y負荷回路の線間電圧と相電圧および線電流と相電流の測定 平衡負荷Δ−Y,Y−Δ変換 時定数τの単位は[s] ●人物コラム オーム(Georg Simon Ohm) キルヒホッフ(Gustav Robert Kirchhoff) スタインメッツ(Charles Proteus Steinmetz) アンペール(André Marie Ampére) ドブロヴォリスキー(Dolivo Dobrowolski)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ヒヤリハット、波及事故例から学ぶことがある! 自家用の電気設備事故、感電事故の代表的な事例を取り上げて解説する書籍は数多く存在します。しかし、波及事故に至らない電気事故やヒヤリハットも多く、これらの情報については統計等も取られておらず、個別の講習会等で一部報告がされている程度です。 本書は、(公社)東京電気管理技術者協会が同協会に所属する電気管理技術者から、波及事故に至らない電気事故、ヒヤリハット情報および波及事故例を集めるとともに、その原因や防止対策を解説した、電気管理技術者に必須の書籍としてまとめたものです。同協会のみならず、全国の電気管理技術者にとって利用できる優位な情報であり、波及事故の撲滅の一助を為すものと考えます。 第1章 外的要因により発生したヒヤリハット、事故、波及事故 第2章 内的要因により発生したヒヤリハット、事故、波及事故 第3章 人的要因により発生したヒヤリハット、事故、波及事故 第4章 低圧回路のヒヤリハット、事故 第5章 知っ得知識
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ワンランク上の電気技術者となるための実務的な知識を詳細に解説 本書は高圧受変電設備の保守現場で生じる短絡や地絡をはじめとするさまざまな現象を理論的に分析し、計算することができるよう、事例や計算例を交えて詳細に解説した実務書です。 電気工学をはじめとするさまざまな知識をどのように考えれば、現場で遭遇するトラブルや事故などの解析に応用することができるのか。ベテラン技術者のノウハウが詰まった書籍になっています。 1.短絡電流 1.1短絡電流の計算 1.2配電線の三相短絡 1.3低圧回路の三相短絡 1.4三相回路の単相短絡 1.5単相3線式回路の短絡 1.6V結線変圧器の短絡 1.7遮断容量選定の考え方 2.過渡短絡電流 2.1過渡短絡電流の最大波高値 2.2対称値と非対称値 2.3遮断器の遮断電流 2.4高圧機器の短時間耐量 3.高圧受電設備の過電流保護協調 3.1小規模受電設備の過電流保護協調 3.2中規模受電設備の過電流保護協調 3.3大規模受電設備の過電流保護協調 3.4電力ヒューズによる機器の保護 4.変流器 4.1CTの過電流特性 4.2CT二次電流引外し方式 4.3V結線CTの負担計算 4.4CTの二次電圧 5.高圧線路の地絡 5.1健全時の電圧と電流 5.2完全地絡時の電圧と電流 5.3地絡電流の検出 5.4地絡電圧の検出 5.5地絡継電器 5.6完全地絡電流 5.7配電線の地絡特性 5.8間欠地絡 5.9もらい事故 5.10ケーブルの地絡保護 5.11高圧ケーブルの絶縁測定 6.高圧地絡の故障計算 6.1配電線の地絡電流 6.2配電線の残留電圧 7.配電線の地絡保護協調 7.1地絡保護協調 7.2地絡継電器の整定値変更 7.3DGRの動作協調 7.4配電線の再閉路 8.PAS・UGS 8.1SOG動作 8.2GRの二重設置 8.3PASによる受電操作 8.4PAS・UGSの特異現象 8.5PASの保守管理 9.低圧回路の漏れ電流 9.1回路方式と漏れ電流 9.2地絡時の対地電圧 9.3非接地回路の地絡検出 9.4漏れ電流I0と絶縁管理 9.5有効漏れ電流の測定 10.B種共用接地による対地電圧の上昇 10.1対地電圧上昇と地絡事故 10.2B種共用接地による対地電圧の上昇 10.3対地電圧とバリスタの選定 10.4対地電圧上昇と漏電遮断器の誤動作 11.インバータとクランプメータ 11.1インバータの漏れ電流 11.2クランプメータの特性 12.変圧器の励磁突入電流 12.1変圧器鉄心内の磁束 12.2鉄心の磁化特性 12.3磁束と励磁電流 12.4励磁突入電流の特性 12.5負荷の特性と残留磁束 12.6励磁突入電流の抑制 12.7励磁突入電流の求め方 13.変圧器励磁電流とΔ結線 13.1奇数高調波電流の特性 13.2変圧器の結線と第3高調波 14.高圧コンデンサの取扱い 14.1コンデンサの構造と保護方式 14.2コンデンサの放電装置 14.3コンデンサと再点弧現象 15.高圧コンデンサの突入電流 15.1単独コンデンサの突入電流 15.2並列コンデンサの突入電流 15.3突入電流の特性 15.4突入電流と瞬時電圧降下
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 楽しく学べる最高の入門書! ロングセラー『100万人の空気調和』の「給排水」編がリニューアル! 「100万人」シリーズ(累計10万部超え)は、技術本でありながら初心者でも理解できる本として、長年にわたって読者の皆さんから絶大な支持を集めています。給排水はなかなかイメージでとらえにくいために難しいと感じている方が多いようですが、本書では、豊富なイラストと身近な事例から徹底的にわかりやすく解説し、「読み物」感覚で、だれでも楽しく学べるように工夫しています。 ※本書は2005年発行の『100万人の給排水衛生設備』に加筆・修正を加え,書名を変えて発行するものです。 第1章 生活と水 第2章 水を配る給水設備 第3章 お湯を配る給湯設備 第4章 使った水の後始末・・排水と通気 第5章 衛生器具の話 第6章 衛生設備をつなぐ配管 第7章 多様な消火設備 第8章 給排水設備としてのガス設備 第9章 水を繰り返し使う 第10章 生活とごみ 第11章 水質を変えて使う
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 電気事故を未然に防ぐノウハウを凝縮! 電気技術者のための「最旬」マニュアル! 電気設備の事故事例について、その発生原因と対策は、最も肝要な情報であるにもかかわらず、さまざまな事情から詳細まで触れられないケースが多々あります。これは事故の特定による影響を最小限に抑えるための配慮ですが、結果、本末転倒を引き起こすことに……。しかし、本書は事故調査のスペシャリスト=中野弘伸氏が個人で動いているため情報の秘匿性が高く、なおかつ、通常はオープンになりにくい原因検証の手順も明確化。つまり、既存の類書では掘り下げられていない深層まで触れることができるのです。 電気事故の再現による原因の検証と分析、そして、事故を未然に防ぐための最良の一手。Dr.中野のノウハウが凝縮した、電気技術者のための事故防止マニュアルです。 第1章 電気事故のメカニズム 第2章 自家用電気工作物の事故事例
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 物理を知って、初めて自分の住む世界が理解できる 本書は、物理学を本当にわかりやすく解説した書籍です。最初の難関である力学から素粒子論まで、目からうろこが落ちるような解説をしています。初めて物理学を学ぶ学生から物理学が苦手な一般社会人、さらには物理学が得意なエンジニアまで、誰もが楽しんで読める内容になっています。 物理学は数学と似ているようですが、ポイントを押さえていないと、いくら問題を解いても会得することはできず、うまく応用することができないのが大きな違いです。しかし、いままで物理学をそのまま難しく解説した本や、高校物理をわかった気にさせる本はあっても、物理学のポイントをわかりやすく解説した本はあまりありませんでした。 本書は、難しい数式に頼らず、学生や一般社会人向けに物理学のポイントをわかりやすく解説した書籍です。ぜひ一度、手に取って読んでみてください。 物理学は難しい?‐原理から考えればさほど難しくはない 第1章 力学(ニュートン力学) 第2章 振動と波動 第3章 光 学 第4章 電磁気学 第5章 熱力学・統計力学 第6章 流体力学 第7章 特殊相対性理論 第8章 一般相対性理論 第9章 量子論と量子力学 第10章 素粒子論
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 凸解析と非線形最適化の数理をわかりやすく解説した参考書 本書は、n次元ユークリッド空間上の凸解析と非線形最適化(非線形計画)の数理について、基本事項からわかりやすく解説するものです。 凸解析や非線形最適化の数理は、回帰分析や機械学習(教師あり学習)で用いられる手法の背景となっています。本書では、幅広い応用が見られるエークランドの定理や不動点定理にも触れつつ、多くの命題や定理に詳しい証明を付しているため、理工学系、経済系の学生・研究者に読みやすい構成としています。また、巻末に、本文の理解に必要な微分積分と線形代数の内容をまとめた付録と各章末の演習問題の詳解を載せ、読者の利便性を高めました。 ※本書は、『数理情報科学シリーズ5 凸解析と最適化理論』(牧野書店)を、オーム社より発行するものです。 第1章 ユークリッド空間 1.1 ベクトル空間 1.2 ベクトル空間の次元 1.3 ベクトル空間の距離 演習問題1 第2章 位相の導入 2.1 近傍、開集合、閉集合 2.2 無限ベクトル列の収束 2.3 連続関数 演習問題2 第3章 射影定理とその応用 3.1 射影定理 3.2 直交補空間とその性質 3.3 グラム行列とグラム行列式 3.4 距離の最小化問題 演習問題3 第4章 凸集合とその性質 4.1 集合の凸包 4.2 凸集合の内部と閉包 演習問題4 第5章 超平面とその応用 5.1 超平面 5.2 ファルカスの定理 5.3 支持超平面と分離定理 5.4 凸錐と極錐 演習問題5 第6章 上半および下半連続関数とその応用 6.1 上半および下半連続関数 6.2 エークランドの定理 演習問題6 第7章 不動点定理とその周辺 7.1 縮小写像と不動点 7.2 ハウスドルフの距離 7.3 集合値縮小写像と不動点 7.4 複数写像と共通不動点 演習問題7 第8章 凸関数と方向微分 8.1 凸関数と準凸関数 8.2 方向微分とエピグラフ 8.3 凸関数と劣微分 演習問題8 第9章 微分可能な凸関数 9.1 勾配ベクトルと劣勾配ベクトル 9.2 凸関数の最適化問題 演習問題9 第10章 最適化問題 10.1 制約条件なしの最適化問題 10.2 不等式制約条件をもつ最適化問題 10.3 制約想定と最適化問題 10.4 双対最適化問題 10.5 接錐と法錐 演習問題10 付録 A.1 集合 A.2 上極限および下極限 A.3 微分とテイラー展開 A.4 偏微分および全微分 A.5 積分 A.6 行列および行列式 参考文献 演習問題解答 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 「対応分析」の多変数拡張版である「多重対応分析」のコンパクトな解説書! SAGE社発行の「多重対応分析」(Multiple Correspondence Analysis: MCA)の翻訳出版です。対応分析の知識を前提とせずに原理から解説し、分析手法としての幾何学的データ解析(GDA)の基本を習得できる構成となっています。 MCAの “入門的な”内容を学ぶ書ですが、同時に“実際の社会調査データの分析例”を通じて、MCAの要点を要領よく紹介するというスタイルで書かれています。分析の“どのような場面で、いかに利用可能か”,MCAの要点を要領よく紹介すること、とくに多数の質問項目を扱う実際場面の分析手順の理解を助ける実用向けの内容です。 翻訳にあたっては、多重対応分析特有の方言の理解を助ける「訳注」及び「グロサリ(語句注釈)」を加えることで内容をより充実させ、読者の理解が深まる構成となっています。 第1章 はじめに 第2章 雲の幾何学 第3章 多重対応分析の方法 第4章 構造化データ解析 第5章 帰納的データ解析 第6章 実際の研究調査での例 付録
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 「電技(省令)と電技解釈」の絵とき解説-2021年最新版!! 本書は、「電気設備技術基準」と「電気設備技術基準の解釈」の絵とき解説書です。長年電気設備の設計・施工・保守・管理に携わる技術者には欠かせない法令解説書として定評のある一冊です。 平成23年7月1日には「電気設備技術基準の解釈」が全文改正されて適用されていますが、その後も不定期に部分的な改正が行われています。本書では、この「電技解釈」とその元である省令の「電気設備技術基準」の絵とき解説に加え、関連の法令「発電用風力設備技術基準」及び「発電用風力設備技術基準の解釈」のほか、関連の技術資料(日本電気技術規格委員会規格JESCや参考技術資料)などを取り込んで理解しやすいようにしています。特に「電技解釈」については、条文を偶数頁に、その絵とき解説を奇数頁に配して、法令の条文に対応しながら理解しにくい箇所を解説頁で理解できるようにしていることが、本書の特長でもあります。 ■電気設備技術基準・解釈とその概要 1 新電気設備技術基準の背景と概要 2 電気設備技術基準の解釈の位置づけとその概要 3 技術基準と関係法規 4 条文の読み方 ■「電気設備技術基準」早わかり 電気設備に関する技術基準を定める省令 第1章 総則 第2章 電気の供給のための電気設備の施設 第3章 電気使用場所の施設 附則 ■「電気設備技術基準・解釈」早わかり 第1章 総則 第1節 通則 第2節 電線 第3節 電路の絶縁及び接地 第4節 電気機械器具の保安原則 第5節 過電流,地絡及び異常電圧に対する保護対策 第2章 発電所並びに変電所,開閉所及びこれらに準ずる場所の施設 第3章 電線路 第1節 電線路の通則 第2節 架空電線路の通則 第3節 低圧及び高圧の架空電線路 第4節 特別高圧架空電線路 第5節 屋側電線路,屋上電線路,架空引込線及び連接引込線 第6節 地中電線路 第7節 特殊場所の電線路 第4章 電力保安通信設備 第5章 電気使用場所の施設及び小出力発電設備 第1節 電気使用場所の施設及び小出力発電設備の通則 第2節 配線等の施設 第3節 特殊場所の施設 第4節 特殊機器等の施設 第5節 小出力発電設備 第6章 電気鉄道等 第7章 国際規格の取り入れ 第8章 分散型電源の系統連系設備 ■規格/計算方法/別表/JESC/参考 規格 計算方法 別表 JESC 参考 ■「発電用風力設備技術基準・解釈」早わかり 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 発電用風力設備の技術基準の解釈について 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐次解説 ●電気設備に関する技術基準を定める省令/電気設備の技術基準の解釈の改正の要点
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 建築計画の基礎知識が、図解でわかりやすく学べる! 専門学校、職業訓練校、大学などで建築士を目指す学生の方々を主な読者とした教科書シリーズ「図解建築シリーズ」の1冊です。 「建築計画」をテーマに、住宅や商業施設、図書館、公民館、劇場など16種類の施設について初学者にもわかりやすい図やイラストを多用して解説しています。また、各章末には建築士試験で出題された問題を中心にした演習問題を設けていますので、知識の定着を図ることができます。 初めて建築計画について学ぶ方から、実務者の方まで、おすすめの1冊です。 1編 建築計画概論 1章 建築計画の用語 2章 建築計画をするのにあたって 3章 建築計画技法 4章 建築史 2編 建築計画 1章 住宅(独立住宅) 2章 集合住宅 3章 事務所 4章 商店(店舗・レストラン) 5章 ホテル・旅館 6章 学校 7章 図書館 8章 公民館・コミュニティセンター 9章 博物館(美術館) 10章 病院・診療所 11章 高齢者福祉施設 12章 オーディトリアム(劇場) 13章 スポーツ施設 14章 工場・倉庫 15章 交通関係施設 16章 複合用途施設
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 「地中熱ヒートポンプ」の知識や設計手順を丁寧に解説し、最新動向を反映させた改訂2版。 本書は、2007年に発行され好評を博した『地中熱ヒートポンプシステム』の改訂2版です。 地中熱ヒートポンプシステムに関する基礎知識、設計手順、および導入事例などについて、建築設備技術者の実務に直接役立つように解説しています。改訂にあたり、地盤条件や事前調査について新章を追加し、種類に応じた採放熱量の比の記述追加や、交換器や熱源機の種類などについて最新動向を反映させています。 設備設計者はもちろん、積雪にお困りの自治体や実務者、省エネ化・二酸化炭素の排出量削減に関心のある建設関係者といった方々に読んでいただきたい1冊です。 1 地中熱ヒートポンプシステムの基礎知識 2 日本の地盤条件 3 地中熱交換器 4 熱源機(ヒートポンプ)と補機 5 冷暖房システム 6 地中熱利用のための事前調査 7 地中熱ヒートポンプシステムの設計 8 地中熱ヒートポンプシステムの評価と将来展望 付録 地中熱ヒートポンプシステムの実施例





















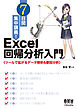




















![工事担任者試験 これなら受かる 総合通信[技術及び理論]](https://res.booklive.jp/869470/001/thumbnail/S.jpg)

























































