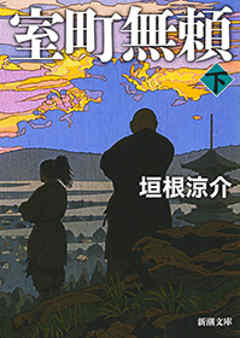あらすじ
唐崎の古老のもと、過酷な鍛錬を積んだ才蔵は、圧倒的な棒術で荒くれ者らを次々倒す兵法者になる。一方、民たちを束ね一揆を謀る兵衛は、敵対する立場となる幕府側の道賢に密約を持ちかける。かつて道賢を愛し、今は兵衛の情婦である遊女の芳王子は、二人の行く末を案じていた。そして、ついに蜂起の日はやってきた。時代を向こうに回した無頼たちの運命に胸が熱くなる、大胆不敵な歴史巨編。(解説・早島大祐)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
『室町無頼』、やはり面白い。
未曾有の飢饉の中、その後、頻発する土一揆の火付け役となる蓮田兵衛の損得抜きの命懸けの大規模な蜂起(寛正の土一揆)が、呼び水となり、時代を変えていく。人心荒廃した動乱期にも、我が道を悠々とゆく蓮田や骨皮、才蔵らの生き方はまさしく無頼。
Posted by ブクログ
室町時代が舞台の小説は、源平合戦、戦国時代、幕末・明治、戦中・戦後の時代に比べ少ない印象を受けるので読みました。
徳政一揆が題材の小説で巻末に描かれた歴史背景の解説的な描写は、良かったです。兵衛、道賢は史実にも記載がある人物みたいですが知らなかったので興味深く読めました。無頼達の生き様を通じ生きるということを改めて考えさせられました。
室町時代が舞台の小説をもっと読みたい。
Posted by ブクログ
兵衛、道賢、才蔵...カッコいいな笑
厳しい時代や状況にも負けずに自分の信じた道を進んでいく無頼なりの生き方
映画も先行公開で観に行きましたが、原作を読んでいく個人的にオススメかなw
何回リピートで観に行こうかな笑
Posted by ブクログ
魅力的な登場人物に引き込まれる。
物語の展開も痛快である。
話が進むに伴い、成長していく登場人物にも寄り添える。
「無頼」という生き方にも共感してしまう。
非常に面白く、読みごたえがあった。
Posted by ブクログ
室町時代の小説を探していたら、何冊か読んだことのある垣根涼介さんの本があったので読んでみた。とても面白かった。蓮田兵衛、骨皮道賢という人物について知れたし、魅力ある人物が多くて良かった。映画は必ず観ます。芳王子は松本若菜さん。
Posted by ブクログ
映画化が決まり、購入しました。
上下巻合わせてなかなかのボリュームでしたがとても面白く、すぐに読み終わりました。
才蔵の幸せを願わずにはいられません。
本作では才蔵の成長に重きが置かれていましたが、映画では兵衛が主役とのことで、どのような作品になるのか楽しみです。
Posted by ブクログ
過酷な修行を経て六尺棒の使い手となった才蔵は腕試しを通じて人を見る目、器量を上げる。
一方で蓮田は蜂起を計画し身内の武士だけが優遇される室町の体制に一石投じようとする。
道賢、兵衛、才蔵とその仲間達の行く末は、、、
Posted by ブクログ
面白かった!
グロい時代だけどカッコいい。
この時代はノーマークだったので余計に興味深かった。
歴史の授業や日本史マンガでも一揆や室町時代にはあまり興味が湧かなかったので、今回知ったことが新鮮。
骨皮道費と連田兵衛は実在の人物なので、他に登場する本があったら読んでみたい。
Posted by ブクログ
才蔵の強さが際立った下巻。読みやすくて歴史小説の入門にもってこい。才蔵が亀仙人前後の悟空ばりの成長を遂げ、男の子としてはワクワク。兵衛と道賢はトラとライオンのようにカッコ良いけど、下巻は才蔵を楽しむためのもの!
Posted by ブクログ
過酷な鍛錬を積み、圧倒的な棒術で荒くれ者らを次々倒す兵法者となった才蔵。一方、一揆を謀る兵衛は、道賢に密約を持ちかける。そしてついに蜂起の日がやってきて…。無頼たちの運命を描いた、大胆不敵な歴史巨編。
(再読)
文庫版のあとがきで、道賢の最後などは実際に記録に残っていることを知った。垣根涼介は執筆にあたって文献をかなり詳しく調べたようだ。
Posted by ブクログ
難しいことを考えずに楽しめる描写力に、室町から戦国へと移り変わる大きな時代の流れが加わり、骨太な時代活劇を堪能できた。道賢と兵衛そして芳王子の生き方には、どこか幕末の志士達に通ずるものが感じられたが、才蔵は、現代の若者を見ているようだった。
Posted by ブクログ
面白く読めた。室町時代というあまり知らない時代ながらも戦国時代でも江戸時代でもない戦国時代前夜みたいな感じかな。
飢饉なんか誰のせいにも出来ない中で支配的な仕組みは残っててそれの限界期。
立ち上がる無頼のお話。
ヤクザじゃなくて無頼。
いつの時代もこういう人がいたのかもなと思わせる作品だった。
Posted by ブクログ
垣根涼介らしい、漢の描写。
たぶんにもれず「光秀の定理」から、時代小説に入ったが、この人が書くそれはいつも面白い。
時代はどこに行っても、外道、バードボイルド、その中の美学や信念が心地いい。
Posted by ブクログ
一気読みでした
終わってしまいました…
才蔵が命懸けの鍛錬を終え、
来るべき日に向けて準備を進める。
才蔵、兵衛、道賢、芳王子、暁信
それぞれが、それぞれに苦しんで、戦っている。
この世は苦界。
どの道を進んでも苦しくて、
でも進まずにはいられない。
後半は続きが気になって、
戦に圧倒されて、
展開のスピード感にのまれ、
とても楽しんで読んでいるはずなのに、
同時に胸が苦しくなりました。
人が作るものはいつか寂れ、壊れ、朽ちていく。
それは作り手の人も同様に。
でも繋がっていくものもある。
過去を生き、今を生きる。
読書は楽しいだけでないけど、
自分にとって本作を読む時間は、
とても大切な読書時間で読書経験でした。
Posted by ブクログ
相国寺大塔が作中の重要な拠点、平安時代から京都には巨大なモニュメントが聳え立つ(古代から巨大建造物が大好きな国、トップ3の「雲太」「和二」「京三」の京=大極殿が相国寺大塔(110メートル)にとって代わられた)
正直、一揆の後の才蔵後日譚がくどかったのだが、あとがきで、逆に作者が拘り書き足した部分だとしる
主人公や周囲の生きざまが爽快だったが、作者の時代をすべて語りつくしたいという欲望を感じる・・・作家のサガ
Posted by ブクログ
室町時代、応仁の乱直前期くらいの京都を題材にしたピカレスク。主人公の才蔵が棒術使いとして厳しい修行の末に開花するまでの上巻が特に、修行好きとして超テンション上がった。下巻も一揆衆に参加しバトるのだがどちらかというと才蔵よりも、蓮田と道賢の一揆をめぐる攻防の方がメインとなり才蔵の強さも輝くけどメイントピックではなくなるため★一つ下げたが、しかし最後までとても面白かった。筆者の『ワイルドソウル』はいまだに忘れられない名作で、はまって一時期他の本もまとめて読んだのだが、超久しぶりに手に取ってみたらいまだに一級のエンターテインメントを書いてくれていて嬉しい限りでそれも良かった。
Posted by ブクログ
ついに下巻。
才蔵は過酷な鍛錬を積み圧倒的な強さを手にした兵法者となる。
後半は幕府軍と一揆軍との合戦の応酬がものの見事に描かれている。
兵衛、道賢、才蔵の無頼の生き方がかっこいい。
映画も観たくなりました。
Posted by ブクログ
前半は、才蔵の過酷極まりない修行とその成果、兵衛の根回しに道賢の憂いといったものを、後半は大規模な一揆とその後が描かれる下巻。
平和慣れした権力者と、武芸や先見の明に優れた兵衛たちの対比は、どこか現代社会にも通ずるものがあり、苦境の中、死を覚悟して闘った兵衛たちに熱くなりました。
映画の方も楽しみです。
Posted by ブクログ
室町時代の京を舞台にした小説です。
粋な男たちの物語でした。
混沌とした時代において、人の想いが歴史を動かします。
それにしても、才蔵の強さは半端ないです。
Posted by ブクログ
応仁の乱の直前という時代は、意外と描かれていないと思う。骨皮道賢という名前は、応仁の乱を描いた作品の中で「悪役」として登場することはあったけど、「志」を持った人物として描かれた作品は、初めてだった。来年の映画の封切りが楽しみだ。
Posted by ブクログ
(下)はもっと駆け抜けた!こんなに疾走感のある小説を読んだのは久しぶり…!
本題に入る前に訂正しておきたいのが、(上)のレビューで才蔵の修行について「ユニークだ」と書いたこと。(上)では彼の成長をワクワクしながら追っていたけど、冷静に考えれば半端なく命懸けである。
深手の傷を負えばまだ良い方で、身体が不自由になったり下手すれば落命することだって充分ありうる。自分ならまず生きて帰ってはこれないだろう。自分に置き換えるのもおかしな話だが…汗
そんな修羅のような特訓メニューを生き延びた彼の戦場での無双っぷりが、物語の疾走感を助長させていた!(それでいてあどけなさのギャップがまた凄まじい笑)
「だが、昔ながらの侍の世など、早晩に終わらせてやる。たとえその結果、一時この世が地獄になって構わない」
修行で棒術を会得して以降、才蔵は兵法者として洛中で名を馳せるようになる。
その間も百姓一揆の計画を進める兵衛と彼の動きを監視し続ける道賢。蜂起の時を前に張り詰めた洛中で、それぞれ進む道を見据えていく…。
「この男から戦国時代は始まった」
映画版の予告で流れた文言である。「この男」とは蓮田兵衛のことだが、実は兵衛や骨皮道賢、そして一部登場人物は実在しており、何と文献にも彼らの名前がちょくちょく登場するという。
つまり『室町無頼』は、史実に基づいたストーリーなのだ。
タイトルからは任侠もののような印象を受けるが、実際は兵衛が率いる百姓一揆が物語のバックボーンになっている。兵衛や才蔵をはじめ、日頃徴税や借金に苦しむ百姓や主家・俸禄を失った牢人・法外な関銭を徴収されている車借や馬借が一揆の構成メンバーである。
「室町幕府とは武家が在京して多くの職務をこなしていた政権で、そこから発生する負担は京都近郊の住人たちを家臣化して対処させていた」と解説には記されている。(これまた初耳!) そのようにして出自や階層の異なる人々の「つながり」が多用されていた時代に、兵衛もまたそれを重要視していた。
兵衛と人々の「つながり」が生んだ意思を守り通していった結果、戦国時代は始まったのだ。
「どのみちこの世は苦界だ。生きること自体が泥水を啜るような屈辱と、怒りと、苦しみの連続なのだ」
人々の生き方が縦横無尽に広がり始めていた時代に、才蔵もまた自分の居場所を見つける。それもまた感慨深かったが、法妙坊暁信(ほうみょうぼうぎょうしん)のケースが一番そうだったかもしれない。
(上)では才蔵の憎き雇い主であったが、彼もまた幕府や自らの運命に憤慨していた。一揆の混乱に乗じて手にしたものではあるが、あれは彼にとって真に輝ける居場所だったのではないかと自分は見ている。
時代がくだり応仁の乱を迎えても、暁信は命懸けでそこを守っているのだろうか。その時には、彼にも共に居場所を守ってくれるような「つながり」が出来ているといいな。
Posted by ブクログ
「『こころ』『ノルウェイの森』そして」
武術に関する垣根先生のネーミングセンスは個人的に絶品だと思う。
「吹き流し才蔵」といい、「光秀の定理」の「笹の葉新九郎」といい。道を究めた行く先は何か「さらさら」とか「ゆらゆら」みたいな物になるのかもしれない。
それはさておき、いよいよ兵衛の武装蜂起が始まる。
「世の中には、銭で買えぬものもある」と云う。兵衛の暮らしぶりを見るに上辺のきれい事ではなく、本心であるのだろう。そして、この乱れた世でのうのうと蓄財に励む既得権益をぶち壊すというのもまた真意であるには違いない。
しかし、兵衛には、何か損得の奥のその更に奥に「自らの器量を世に問う」みたいな衝動があるように感じられた。それが無謀な一揆を始めさせたのではないか。
そう考えると、兵衛、道賢さらには才蔵が芳王子と関係を持ったこと。また、幕府側の道賢、一揆側の兵衛、才蔵が敷いた陣を底辺とした三角形の頂点に東寺の五重塔、そして相国寺の大塔が聳えていること。どちらもとても「象徴的」に自分には思われた。
(読み方は自由かと思いますので悪しからず。)
Posted by ブクログ
男の友情と信頼を描いてるような気が。応仁の乱は知識もなく、テレビでならず者が暴れていたと言っていた気がしたが、この本では一揆の先駆けで自分が先導して後世の模範としたいという信念があり、幕府の衰弱と百姓の疲弊で暴れ回って世の中をどうにかしたいと奔走する。
かっこよく描かれているので飽きることなく読める。
Posted by ブクログ
無頼。その生き様を応仁の乱の前夜一揆を起こした男達のドラマを描いた作品。芳王子という絶世の美女を愛する3人の男たち。それぞれのプリンシプルに基づいて生きていくその生き様を描きたかったんだろうと思う。かっこいい無頼の男たち、人ったらしだが、生き方は変えられない、傭兵部隊を率いて街を守る道賢、縁もなく、地獄の修行で強くなった若い才蔵、そして一揆を謀り歴史に一石を投じることとなった蓮田。それぞれのバックグラウンドと熱い思いが、歴史を変えようとしている。そんな埃っぽい部分をすごくよく表していると思う。
Posted by ブクログ
才蔵の鬼のような強さに圧倒される。かっこいい。兵衛と道賢の最期は悲しかった。みんな生きていてほしかったと思うほど、それぞれ好きになってた。
Posted by ブクログ
舞台は応仁の乱より少し前の京都。主人公は貧困家庭に育つ少年。貧困に喘ぐ農民たちの大規模土一揆を率いた実在の人物に目をかけられ、彼は逞しく成長していく。
史実に創作を加え、当時の様子と出来事をドラマチックに描写している。主人公は創作。登場人物がかっこよすぎる気もするが、エンタメ感は十分。