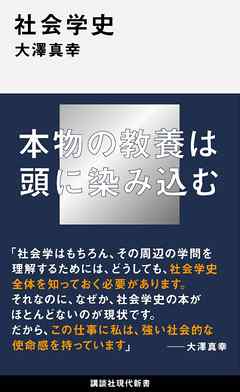あらすじ
本物の教養がこんなに頭に染み込んで、ものの見方がすっかり変わる経験をあなたに!マルクスもフロイトもフーコーも、実は社会学者なんです。「社会学はもちろん、その周辺の学問を理解するためには、どうしても、社会学史全体を知っておく必要があります。それなのに、なぜか、社会学史の本がほとんどないのが現状です。だから、この仕事に私は、強い社会的な使命感を持っています」――大澤真幸
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
社会学の古典に着手する前の準備段階として、社会学史を押さえておきたく本書を再読。「社会秩序はどのようにして形成されるのか」という社会学固有の問題意識が誕生した背景と各理論の繋がりを俯瞰できました。どの学問にも言えることだと思いますが、特に社会学は各時代の具体的な文脈と向き合うことが求められており、時代と向き合い、理解しようとする姿勢が欠如していると、独りよがりな営みになってしまうと感じました。その意味で、今起きていること・歴史に対して関心・問題意識を持つことが、社会学を学ぶ中で、最も重要な素養だと思います。歴史に疎く、きちんと学んでいなかったので、これを機に歴史を学びたいです。
Posted by ブクログ
著者の論理というか、問題意識がはっきりしているおかげで、歴史上のそれぞれの思想が驚くほど生き生きと頭に入ってきた。
以下、終盤のルーマンとフーコーの説明についての僕なりの理解。
ある要素は、システムを前提に他の要素との関係性によって相対的に構成される。システムの複雑化に伴い複雑性の縮減は進行し、アルシーヴの可能性の地平が拡張するとともに希少化し空間内での偏りが増す。偏ったアルシーヴ内で、可能性の地平が収縮して意味が選択されるとディスクールが立ち現れる。
一方、人間は社会を前提として他者との関係性によって相対的に構成される。社会進化に伴い生権力によるパノプティコン的支配が定着し、「告白」が常態化する。告白が蓄積され内面化され、他のあり得た可能性を否定して一つのアイデンティティが選択されると人間が立ち現れる。アイデンティティの構築には、告白だけではなく告白されなかった秘密も関与する。告白は選択されたディスクールに対応して、秘密はディスクールになり得たが否定された可能性に対応する。ディスクールが存在するためには、否定された可能性の地平が保存されている必要がある。
フーコーは権力を前提として人間が初めて立ち現れることを示したのち、人間が権力に抵抗する方法としてパレーシアに目を向けた。パレーシアは真実を語ることを表すギリシア語である。
パレーシアは、秘密のない告白、権力による監視を前提としない人間に対応するとみなせる。これはひいては、それでしかあり得ない必然的なディスクールを表すと考えられる。つまり、縮減していない空間内の全ての可能性がディスクールとして発現する場合にのみ、それらはパレーシアだとみなせる。しかしそれではカオス状態となりシステムとして機能しないためパレーシアは実現し得ず、人はレトリックを道具として利用し認識や表象を少なからず単純化せざるを得ない。
権力や社会システムがあることで初めて複雑性が縮減し、私たちは収縮したディスクールから成る制御可能な程度の複雑さをもつ秩序あるアルシーヴ(エピステーメー)を利用することができる。また、収縮した意味から構成される制御可能な程度の複雑さをもつ社会秩序がオートポイエーシス的に構築される。社会進化とは、社会システム内でその要素であるコミュニケーションの数の増加を指す。閾値を超えると本来カオス化するところ、その複雑性を縮減する方法が各段階に備わっており、たとえば近代社会ではそれが生権力である。複雑な社会に生きる人々は、物事をありのままに捉えたり発話したりすることはできない。
Posted by ブクログ
社会学に興味があり購入。
とても興味深く読めました。素人なので難解な言葉もあり、読むのに時間がかかりましたが時折「ふふふ」と笑える著者のセンスある表現に救われる完読できました。
オススメです。
Posted by ブクログ
非常に面白い。社会学の歴史を、それぞれの理論の生まれた背景を含めて、的確に提示してくれている。そして、各学問には、固有の問があることを教えてもらう。
社会学においての基本命題は、社会秩序は、如何にして成り立つのか?である。
社会学初学習者である私にとって、社会学の外観と、それぞれの位置付けを知ることができ、自分の興味のある事柄や、今現在生きている理論がなんなのかも合わせて知ることができた。これから勉強を進める上での地図が得られた。
ルーマンの社会システム論を掘り下げつつ、社会学のアプローチと、地理学、システム論、法律、マーケティング、数理最適化などを合わせてみていく中で、土地利用の最適化や、認証系の有効性を検証して、自然環境保全に資する論理を立てられないだろうかと、夢想する。社会実装に向けたことわりを、探究したい。
大澤先生の研究室を訪ねてみようか?
Posted by ブクログ
社会学の始まる前から、丁寧に解説している素晴らしい本。
今まで社会学の流れを知るには、最適な一冊。
紹介されている人物の、考えの本質を整理している。
Posted by ブクログ
社会学がどのような学問であり、どのような思想を辿って発展してきたのかを主要な人物と学説を用いて紹介していく内容である。600ページ以上と長いが、微妙な解釈の違いや世界の動向を簡潔にまとめられていると思う。大きなテーマとして、社会学の誕生、社会の発見、システムと意味に分けている。根底にあるのは、「社会秩序はいかにして可能か」という問いであり、これを基に読み解いていくと分かりやすいと思う。
社会学者は、一見何を考えるのか分かりにくい学問分野だと思う方にはぜひ読んでほしい。どの人物も社会が出来上がる方法、移り変わる法則、平和への方法を中心にあらゆる角度から物事を見ようとしていることが理解できるだろう。
本書を読んで、社会学に大きな貢献をもたらしたのは、マルクス、ヴェーバー、パーソンズだと思う。マルクスは価値形態論、ヴェーバーは予定説やプロテスタントについて、パーソンズは構造-機能主義を用いて功利主義で解決できないホッブズ問題を説明しようとした人物である。
本書以外にも様々な考えや現象について考察されていると考えると、人間同士の関わり方は数多の種類があり、それもフレームワークごとに異なるので、その複雑性に驚かされる。
Posted by ブクログ
おもしろかった。これを読んで、自分が社会学に興味が湧いた理由が感じられた。やはり世間の風潮は(小声で:ちがう)。なにかとこれが答えだ!善だ良心だ美だ!みたいな話が多すぎて、そんな気がしてしまうと同時に何か違う気がどんどん。だとしたらなにを誤解しているのだ?と。それで一定の学びジャンルに目が向き。それの一つとしてこの本に会った。社会学の社会を見つめる目。社会学全体の流れ、俯瞰。それで僕の社会観を調整してくれる。これからの僕にいいと思う。
Posted by ブクログ
最新版の社会学史。
社会学は近代のもの。たかだか200年の歴史。
近代の自己意識として社会学が誕生したことを古代の社会理論から始め、社会契約論という社会学前夜の話を経て、社会科学の誕生の中に、コントの名付けた「社会学」があるという位置づけ。
マルクスを間にいれたあと、社会の発見というテーマで、フロイト、デュルケーム、ジンメル、ヴェーバーを説明。
その後は、システムと意味というテーマで、パーソンズの機能主義の定式化、意味の社会学、さらにルーマンとフーコーの意味構成論的なシステムの理論が解説される。
社会学の主題は「社会秩序はいかにして可能か」というもの。前提として偶有性という概念がある。
読み終えての所感としては、ルーマンとフーコーがツインピークスであるという評価が自分が感じていることと一致したという満足感。
特に、現代社会においては、システムが多様に分化した社会であり、それぞれのメディアとコードが併存しているという点は、わが意を得たりというところ。
フーコーが唱えた「エピステーメー」=パラダイムが不連続であり、類似(ドン=キホーテ)→表象(地理と地図)→人間(博物学(生命)、経済学(交換)、言語学(動詞))と変化してきた話はぜひ読んでみたい。
対比として、ルーマンのシステム論も同様。
人間と社会の関係を、ユダヤ人とユダヤ教のたとえを引きながら、人間における弱さと神、社会における弱さと神、といった構図でとらえるという点も新鮮。
集団は「神」を必要とする。それは、人間が自らを不完全と信じるからであり、メディアとしての神とそこにおける二項対立は、自分たちの集団と他の集団を区別するために必要。線引きの話でもある。
Posted by ブクログ
社会学の誕生と生成の背景を明晰に語り、その問題意識と可能性をあぶり出した名著。
後書きにあるとおり、優れた聞き手がいたことも薄々感じられ、11年かかったのも頷ける。
今の自分と社会を照らし出す、いわゆるハッとする記述にたびたび出会いながら、一気に読み切った。
Posted by ブクログ
分厚いのにめちゃくちゃ面白くて読み進められました。
マルクス、フロイト、デュルケーム、ウェーバーまでは面白い。
構造と意味あたりの子細な議論のあたりに入ると疲れますが 笑
Posted by ブクログ
新書にして630ページの厚み。でも94册分(たぶん…巻末の索引で引用文献、数えてみました。)の社会学を巡る膨大な文献をエッセンスを詰め込みながら超コンパクトに社会学の歴史をツアーするガイドブックです。それは「社会学の歴史」こそが「社会学とは何か?」の答えになる、という学問だから。序文でも「社会学の歴史はそれ自体が社会学になる。そこに社会学という学問の特徴があるわけです。」と語っています。なるほど、ノーベル賞でも分野の確立している学問、例えば、物理学って何?とか経済学って何?とかは敢えて問わなくてもいいような気がしますが、社会学って何?についての答えは持っていないような気がして手にしました。出版社の編集者を生徒に講義形式でどんどん社会学の成立から今日までのタイムラインをたどっていくスタイルは気持ちよく「よくわかる!」感を作ってくれます。書き言葉だと反芻が必要な事例も、話し言葉と筆者の総括的視点をベースにした素材の整理によって、するする摂取できる気分になります。その総括性は、この学問の可能性として終章に向けて強調される〈偶有性〉というキーワードをゴールとして見据えているから、なのだと思います。少なくても、点としてでしか知らなかったホッブズとルソー、マルクスとフロイト、そして、社会学の歴史のビッグスリー、デュルケーム、ジンメル、ヴェーバー、さらにルーマンとフーコーという人々の仕事がフレームとして見えたことは楽しかったです。星じゃなくて、星座を説明してもらった感じ、かな…でも、いくら教えてもらっても実際に夜空で星座わかんなくなっちゃうように、たぶんいろいろわかんなくなっちゃうと思いますが、夏の終わりの読書として満喫しました。
Posted by ブクログ
どうやら社会学がブームのようだ。著者をはじめ古市憲寿氏や小熊英二氏等、若くてしかもテレビ映えのする学者が多く台頭してきている。書店の新書の棚を眺めても、「社会学」の文字は以外に目につく。政治学や 経済学に比べイデオロギー論にすり替わりにくく、哲学よりはとっつきやすい。手軽さ・気楽さと程よいアカデミックさが求められる新書のようなメディアにとってはうってつけの題材なのだろう。本書のボリュームは600ページ、価格は1,500円を超え、その意味では新書の枠を踏み越えてはいるが既に4版を重ねている。売れているのだ。なお本書は3年ほど前に出たちくま新書「社会学講義」中、著者が担当した第2章「理論社会学」の内容をほぼそのまま引き伸ばした内容となっているようだ。他社で出版したものとほぼ同じものを同一メディアで出すというのはこの世界ではノーマルなことなのだろうか、よくわからない。
おそらくレビューは多いと思われるため要約的な内容についてはそちらに譲るが、僕がこの本に興味を持った理由は「序」にあった次の一文に尽きる。
「社会学の歴史は、それ自体が一つの社会学になる」
これは何だろう?「ある対象に関するメタ的な論説がその対象と同一である」という物言いは、例の「全てのクレタ人は…」という古き良き自己言及パラドクスを否応なく想起させる。このようなパラドクスめいた命題を前提に持ってくるのは、論理学的には「私の議論は信用できない」と宣言するのと等価ではないか?私の素朴な脳細胞が素朴すぎるアラームを発する。しかし著者は「それこそが社会学という学問の特徴だ」とこともなげ。無論そんな素人レベルの議論が想定されているのではもちろんないだろうが、新書という形態を考えればこの議論の始め方はちょっと異様だ。何か危ない感じがする。しかし逆に考えれば、著者はそのようなリスキーなやり方を取らねばならぬほど、このことを強調したいはずなのだ。ではこの一文は何を意味するのだろう?社会学とはいったいどのようなものなのか?
と、大きな疑問を抱えながら読み進め、自分なりにこれが答えか?というものが得られたのは本当に最後の最後、ラスト数十ページというところ。ちなみにそこに至るまでにヴェーバーという大きなヤマがありそれなりのページが割かれているのだが、僕には正直ここの記述がダラダラと長すぎるように感じられた。確かに美しい。予定説と資本主義精神の論理的な繋がりについて、ここまで分かりやすく正面から突き詰めた議論は見たことがない。でも、僕には「序」のあのノリからして本書の最大の山場はここではないとしか感じられなかった。いやそれともやはり僕の読みがおかしかったのであり、社会学といえばなんとなくヴェーバーとか「プロ倫」だし、やっぱり彼の社会学的「神経症」が本書の議論の中心だったのだろうか?この本のラスト1/3は現代社会学の群雄割拠状態を俯瞰して終わるのだろうか?そんな不安が頭を離れなかった。そう、ルーマンが出てくるまでは。
ニクラス・ルーマン。20世紀後半に活躍したドイツ人社会学者であり、ユルゲン・ハーバーマスとの論争で名を上げた人物とのことだが、本当に恥ずかしながら全くの初見(ちなみにハーバーマスもタルコット・パーソンズも知っていたのは名前だけ)。しかし当該部分を一読して、なるほど著者の社会学は少なくとも現在はヴェーバーではなくルーマンにインスパイアされた部分が大きいと即座に感じられた。
ルーマンのシステム論は、システムが秩序のみならずその要素も自ら作り出すという「オートポイエーシス」という性質を前提とする理論。これによると「社会システム」内では、その要素である「コミュニケーション」がコミュニケーション間のネットワークより(主体である人間の意識の介在なしに)自律的に生産されている。つまり自分が自分自身で構成されているのであり、ここでは「xがxを用いて定義される」という自己言及の形式が取られている。ルーマンの章では他にも本書で頻出の「偶有性」というキーワードが出てくるが、より大きな存在感を占めるのはこの「自己言及」ではないかと思われる。「メタ社会学も社会学の要素である」という序文のあの文章と全く同型だ。
実はこれと似たタームがルーマンより前に出てくる。「論点先取」と「循環」だ。前者はパーソンズの「主意主義的行為理論」の批判の際に、後者は「状況の定義がその状況を現実化する」という「トマスの定理」を表現する際に用いられている。後者は「超越論的」という概念で乗り越えられることになっている(「原罪」とかいう、またぞろキリスト教上の概念が導入されておりやや辟易)が、僕には論理的な破綻を糊塗するレトリックに過ぎないように思える(だいたい定義からして思い切り循環論法だと思うのだが、著者はなぜかツッコまない)。だとすれば、序文のパラドクスめいた一文にも隠された否定的なニュアンスが込められているはずだとは考えられないだろうか。つまり、
「結局のところ、社会学という学問は今のところ自らのシステム上の不完全性を超越するための拠点を外部に発見できていない」
というのが、隠れた著者の主張なのではないか。
無論、そのようなシニシズムが本書の結論なのではない。ルーマンの「偶有性」を絶対的実在とみなし、これを梃子に相関主義を乗り越えようというのが最終的な提言だ。社会学というのは「まだやることが沢山ある学問である」と。
確かに「偶有性の保存」こそが社会学の本質であるとの宣言は力強く響く。しかし「偶有性」の手前にはもちろん「他者」という扱いづらい壁が立ちはだかっている。本書では割くべきスペースがなかったようだが、古き良き「他我問題」にも直結しかねないこの「他者」についての考察が著者の近著にあるようだ。機会があれば是非読んでみたい。
Posted by ブクログ
社会学史というテーマで社会学の学問領域の全てをわかりやすい語り口調で網羅した名著。
法は普遍化された犯罪。進化論はそういった社会だからこそダーウィンは辿り着いた。貨幣への信仰にも比せられる無意識の執着。社会学史の中のフロイト。神強制と神奉仕、西洋の合理性。ニューカムのパラドックス。個人の意図や意味付けとは違った水準で社会現象が生じるという説明→社会の発見。責任倫理。パーソンズ、動機指向⇄価値指向、構造ー機能主義。アローの不可能性定理。トマスの定理を理論的に精緻化すると意味の社会学になる。オートポイエーシスの理論。
Posted by ブクログ
新聞広告をみてビビっときて、書店で手に取ってまたビビっときた1冊。期待通りに面白かった。単に社会学の歴史と人物を羅列的に紹介するのではなく、その時代になぜそういう考え方が出てきたのかという点を大きな歴史の流れの中で整理して教えてくれるのと、それぞれの理論について、著者なりのかみ砕いた解釈により、身近な事象に置き換えて理解させてもらえるので、とても腹落ちしやすかった。特に、マックスウェーバーの理論の切れ味については、あらためて感じ入った。ただ、現代の社会学については、元の理論が少し細かい点に入りすぎているためなのか、自分の中で整理して考えることが難しかった。
学生時代、社会学専攻でしたが、当時、こういう本があれば、もっと包括的に社会学をとらえることができただろうに。これからも折に触れ、読み直したい1冊です。
Posted by ブクログ
長い講義録でも一瞬も飽きない。断片知っていた知識が繋げられ、そこに新たな知識が注ぎ込まれていく感覚は、快感だとすら思われ、その爽快さにその長さなど忘れてしまう。
Posted by ブクログ
(編集中)
社会学とは一体どのような学問で、どのように発展して来たか?と問われた時に、明確な答えを示せる者は決して多くないように思う。というのも、社会学という学問自体が学際的な学問であり、抽象的かつ広義の意味を含んでいるからである。そして本書では、そうした社会学の性質を認めた上で個別具体的な領域に留まらず、それを学際的なままとして評価している。
本書における重要な点は、社会学が誕生してからの歴史を問いとしているのではなく、そもそも社会学はどこから来たのか?といったことから問いを始めている点である。
社会学という語がコントによって用いられるようになったのは、19世紀のことである。人間を構成する最も重要な要素のひとつであるはずの社会というモチーフが学術的に取り扱われるようになるまでにそれほどまでの時間がかかったのは一体なぜか?
このような問いに対し、大澤は古代ギリシャから中世における神の存在をめぐる問題と啓蒙の時代、そしてフランス革命へと繋げることで返答している。私見を述べれば、社会学を評価する上でこの啓蒙の時代とフランス革命の存在への言及は避けられるものではない。しかし、一般に知られる社会学の入門書においてそれらが包括されているかと言われたら疑問が残るのが現状である。そのような点で、本書のような態度は貴重であるとともに賞賛できるものである。
Posted by ブクログ
「本書は、講談社の会議室で実際に行った講義を基にしている。」と「おわりに」であるように、いわゆる話し言葉に近い文章で、社会学の歴史について記述されている。
各研究者の理論や著作を紹介するという入門書であるが、大澤自身の見解も述べつつ、研究者間の関係性についても解説している(たとえば、ホッブズの社会学における意味など)。
新書であるということの意義としての読みやすさは高い。反面として、参考文献や注がないために、興味をもった著作については、本文を読みながらメモをしていくのがオススメ。
Posted by ブクログ
先週、今週とコロナウイルスのため自宅待機を余儀なくされていることから、積読の山の切り崩しにかかった。これほどまとまった時間がなければ、手を伸ばすのはもう少し先だったかもしれない。
タイトル通り、社会学の通史である。近代以降に始まった比較的新しい学問ではあるが、よくぞこの分量を新書にまとめたものだと思う。マルクス、フロイト、レヴィ=ストロースなど、社会学の枠ではあまり語られない人を入れたのは著者の独創的なところだろう。一人が書き切っているので、通史としてはまとまりがいいが、一人であるが故に厚みの凸凹さや恣意的な表記はあるように思う。何人かの評者からは事実誤認も指摘されているようだ。
とはいえ、社会学を学んでいない身としては読み応えは十分。難解で理解できない箇所も多々あったが、社会学の大きな流れは理解できた。
読みやすかった
著者の熱意を感じた。同領域の専門家から観たら首を傾げる箇所もあるだろう。素人の私は大変楽しめたし、興味もなかった社会学をもっと知りたいなと思えた。
Posted by ブクログ
ふつうに面白い。たしかに(大学での彼の講義を思い出すような)おいおいほんとか? みたいな大澤真幸らしさも残るけど、いつどういう学者がいてどういうことを言ったということを死ぬほど易しく教えてくれるのでいいと思う。
Posted by ブクログ
様々な学問の中でも、19世紀~20世紀になってそのディシプリンが確立された社会学は、比較的その歴史が浅い部類にあたる。しかし、歴史が浅いという点は、その学問自体の重要性とは何も関係がない。むしろ、近代において、社会学という学問がなぜ発達したのか、そして社会学とはどのようなイシューをその固有主題として成立したのか?、というごく自然な疑問に答えるのは実はなかなか難しい。
本書は、一つの学問史としてなかなか統一的なパースペクティブを描きにくい社会学の歴史にターゲットを当てた一冊である。本書では社会学固有の主題とは「社会秩序はいかにして可能か?」という1点にあることが提示された上で、社会学の始祖たるマックス・ウェーバーを中心に、社会学前史としての社会契約論やマルクス・エンゲルスらの存在と、20世紀社会学の代表格であるパーソンズやルーマンなどの学説が、大澤真幸の講義調のテキストで解説される。
近年は”歴史”に対する意識が極めて強い大澤さんの近年の本の中でも、比較的読みやすく、かつ社会学に留まらない人文社会科学の歴史を振り返る点で非常に面白く有益な一冊。
Posted by ブクログ
そもそも社会学の成り立ち、分類の部分を知れたのが大きな収穫
社会学の歴史を俯瞰できるだけで面白いことは面白いんだけど、最終的には、社会学は社会に関する感想文に過ぎず、その鋭さがそれっぽいかどうかでしか判定できない似非科学なんだろうなという印象に落ち着いた。
類書で社会学者自身が語るようにゆるふわ日本では生き残っているが、世界的には廃れつつ学問
Posted by ブクログ
まず社会学とは何??って知識レベルから読み始めたので、社会学がどういう学問か知れただけでも収穫アリ。
実はSNS上で見る社会学者さんたちの発言に首を傾げることが多くて、じゃあ彼らの研究している分野ってどういう学問なの?という疑問がすごく強くあったので。
宗教や王の立場が強かった時代が終わってから社会学という概念が生まれた、というのはなるほどなーという気づきでした。
確かに言われてみれば、自由意志のある個体が強い支配を受けてるわけでもないのに勝手気ままやりすぎずちゃんと「社会」をやってるのは不思議なことだし、どうしてそれが成り立ってるのかは研究の余地があるんだなぁ。
Posted by ブクログ
著者が、みずからの見解を織り込みつつ、社会学の歴史をいろどる主要な社会学者たちの業績を解説している本です。
600ページ頁を超える分量で、新書としてはかなりヴォリュームのある本ですが、語り下ろしということもあって、比較的やさしい語り口で説明がなされています。日本の社会学者による社会学史の著作としては、富永健一の大著『思想としての社会学―産業主義から社会システム理論まで』(2008年、新曜社)がひとつの到達点を示していると思いますが、富永が実証性を重視する立場をとっているのに対して、著者は社会学を「近代社会の自己意識の一つの表現」とみなす立場から、それぞれの社会学者たちの仕事の意味を解説しており、著者のオリジナリティが発揮された内容になっています。
ホッブズ、ロック、ルソーの社会契約説の解説では、ゲーム理論の発想を借りながら、「社会秩序はいかにして可能か」という問いがどのようなしかたで彼らの理論のうちに見られるのかということを解き明かす試みがなされています。また、フロイトやマルクスを社会学史上の重要な人物としてとりあげているのも、本書の特色をなしています。
20世紀の社会学についての解説では、パーソンズと、現象学的社会学やエスノメソドロジー、ラベリング理論などが、「機能」と「意味」というキーワードのもとで対照的にとりあげられるとともに、「第三の審級」論などの著者自身の理論にもとづくと思われる考えかたにもとづいて、両者の統一的に理解する可能性を切り開こうとしています。
さらに著者は、ブルデュー、ルーマン、フーコーなどの議論に説きおよんで、現代の社会学が取り組むべき課題を見定めようとしています。
Posted by ブクログ
「感情労働の社会学」とか「ケアの社会学」とか様々な社会学本があるけれど、メタ理論を理解していないと著者と問題意識を共有できなくて全く面白くないからね。だから社会学の主要なメタ理論をザクッと分かりやすく教えてくれる本は有り難いね。大澄先生は文章にリズムがあるし、テンションが高いから楽しく読めた。
だけどポストモダン系はさらっと押さえてるだけなのが唯一残念だったなぁ。