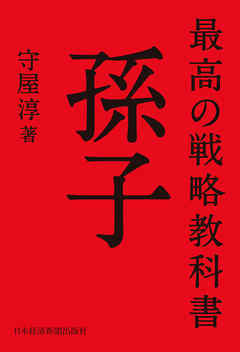あらすじ
読みやすさ、わかりやすさで、10万部を突破! ビジネスだけでなく、スポーツや人生のさまざまなシーンで活用できる 「負けないための戦略」が数多く紹介されています。複数の敵と戦わざるをえない今だからこそ読みたい、話題の兵法書です。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
いつぞや購入して中途半端に読んでそのままになっていましたが、キングダムを再読して気になったので、引っ張ってきました。
群雄割拠の時代に生きた孫武だけに現代のビジネスにも生かすことができるであろう、戦略的思考法はもちろん、組織マネジメントとしても参考になる内容が記載させれていました。
実際の職場に当てはめて、アナロジー思考でイメージしてみると、戦争が起きそうなので控えようと思います。
ー百戦百勝は善の善なるものに非ず。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなりー この精神で寛大な受容の姿勢で仕事をしていきたいです。
★与えられたモノ・コトで己の状況を知り、(五事)相手(ライバル)との比較を七つの切り口から行う(七計)⇒勝負の判断材料
五事:理念/時間的条件/環境/人的リソース/組織の状態
五事の観点をもって、相対的な分析・評価を行い判断を下す。
★勝ち負けだけで判断するのではなく、決着する時間軸も視野に入れる。(理想的な結果は何か)短期決戦は早々に利益を上げられるかがカギとなる。短期決戦が見込まれない場合は不敗を貫く。
*スピード勝負。自分には最小限のダメージに抑える。
・詭道=だましあい。臨機応変に動く。こちらを小さく見せる。意図を頓珍漢に解釈させる。自分を弱く見せることは1回限りにし、相手が隙を見せたら一気に突く。
・相手をこちらの意図した行動に誘導する。「急所」(相手が攻めれらると嫌がること)を見極め崩す。
★組織に勢いをもたらす際は、危機感を力の源泉とさせる。勢いは長続きしないため、それを活用して相手を早期に撃つことが重要。
*勝負所を見極めた行動を。
・勝敗を決する要素として…
> 情報や認識・判断ベースの力
> 環境・肉体ベースの力
> 組織化を測る物量・管理ベースの力
⇒ マネ・エスカレーションをすると地力・規模が大きい方が勝つ(同質化戦略)ただし、数が多いだけでも管理できないと意味がない。
・組織を率いる条件
> 先見の明(外的)
> 部下からの信頼(内的)
> 部下の思いやり(内的)
> 実行力(外的)
> 部下から恐れられること(内的)
⇒ いずれの資質をバランスよく持つことが重要。己を知り、自分の弱い部分を強みで補うことが重要。
★状況に流されない目。必ず利益と損失の両面から物事を捉える。心理的バイアスを取り除き冷静に一歩距離を取って最適な判断を下す。
★部下の力を最大限に発揮するためには、自分で考える機会を持たせることが重要。
そのためには自分が何を考えているのか(≒答え)を悟られないようにする。ムッツリして何を考えているのかわからない人に)
★100%利のあること、勝てると確信を得たときは、上の指示に反してもやり抜き、反対に損失を被るとわかった場合は止める。その結果、功績に対しては名誉を求めず、失敗の時は責任を回避しない。そのリスクは十分に勘案し、個人的な欲求を排して尽くすことが必要。
★相手を知るための情報について
> 組織力(まとまり)
> 戦力(人的・物的リソース「ヒト・モト・カネ・ジョウホウ」)
> 人間関係・士気(雰囲気)
> 管理者・マネージャーとその人物の能力
> 相手の意識・気づきはあるか?
*揺さぶることで、相手の状況は一定把握できる。
・他とは違ったものの見方・考え方をし、常に戦う姿勢を忘れないようにする。
*脆弱な環境に適応しないようにする。平和な時こそ生き残るため、強くなるための意識と行動を忘れない。
> 戦略=頂上へのコース選び・構築
> 戦術=途中の障壁(問題)の乗り越え方
★自分や組織にとって致命傷となる事象を考え尽くす。対策する。(不敗の策)勝ちパターンがあるならそのパターンを事前に知り尽くしておく(自分・組織の勝ちパターンのキャッチ)*不敗の策と勝ちパターンの定着
★失敗や負けは成果への貴重な元手。”我慢できるうちは負けてOK”負けを知り、戦略を修正する。自分の欠点を知る機会でいくらでも失敗する。勝負時で勝てばOK。
★不敗条件や勝利条件のラインは高すぎると心が折れやすいため、負けのラインは低い方がいい。しぶとさ・粘り強さ・胆力が生み出される
*死ななければ不敗。クビにならなければ不敗。
★「重心」を見極めた人や組織が成果を上げやすくもなる。他の人と同じような攻め方ではなく、相手を知り、相手が本質的に求めるものを見極める。
★約束は控えめに、実行はたっぷりと。顧客(相手)を満足させるだけではなく、相手に喜んでもらうことが重要。(瞬間的な喜び・驚きではなく、永続的なものに)サプライズは一回だけ行うから有効であるため、長続きした感動は得られない。王道を磨き恒久的な利益になるような戦略を考える。(逆を言えば、ハッタリも時に良手に)
★相手の矛盾を突く。相手が強みと思って絶対的な自信のあるサービスや商品・スキルを武器としている場合は、それらでは補完できないモノ・コトで対抗することが可能。(定量的かつ客観的に物事を判断する・結果を見る力)
⇒ 自分でいうとコミュニケーション能力・スピード・マネジメント力・気遣い
・勝ち癖=成功体験をつけることで勢いに乗る。「奇」を加えることでさらに勢いづく。「褒める+成功体験のサイクル」
・短期的な戦いで叱ることはしない。勢い重視のためにとことん褒める。
・長期的な戦いでは、その後の育成を踏まえて、叱ることも重要。
・勢いに乗っている相手は前のめりになりやすい。「流れ」を遮断する一手を差し込んで、主導権を渡さないようにすることも必要。
★何で勝つか?いつ・どこで勝つか?ビジネス上での戦いにルールはない。相手の弱点を突けば誰でも勝てる。そのために勉強と訓練は欠かさない。与えられたものが何か?足りないが補うことができるもの(代替できるもの)は何か?を熟考して自分に有利な状況を作り上げる。勝てる場所で勝ち、勝ちが見込まれない場合は、不敗(=相手の策に便乗して「期」を伺う)を守る。
★TPOに応じた対応を行うため、局面を適切に見極める視点を持つ。
Posted by ブクログ
多くの有名経営者たちが愛読している中国の兵法、「孫子」を現代の戦略へどう反映させていくか、という話。私自身は孫子について初めて触れた本なので、とても面白かった一方で、ビジネスへの汎用性という点はなかなかすぐには難しいと感じた本。
本の半分以上は孫子の兵法の考え方と時代背景を紹介しており、まずはどう戦争で勝つべきかということが中心。
6割すぎたくらいから実際どう使うかの考察に入っていくが、具体性はあまりなく、概念的な話も多いので応用しづらい。しかし欧米のクラウセヴィッツの戦争論との比較は結構面白かった。
まず兵法の特徴を抜粋。
戦わずして勝つのが最善
→そもそも国力を守るためには交渉などで戦わずに勝てるのが最高
勝算がなければ戦わない
→負ける戦はしない、疲弊し後に食われる
彼を知り、己を知れば百戦して殆うべからず
→敵を含む周辺情報を含み、五事七計のこと。7つの責任者、将軍、地の利、法令、軍隊、組織、賞罰の比較で勝てることが重要。
短期で勝てる相手とだけ戦う
→長い戦いで良い結果になることは少ない
兵は詭道なり
→情報戦であり、相手がやってこないと油断をしていることなどをやる事が重要(だから守っていない)
相手が最も重視する所を奪うと、相手を思いのままにできる
将とは、智謀、信義、仁慈、勇気、威厳によって決まる(これらは掛け算、どれか一つ欠けてもダメ)
戦略への活かし方
戦略の考え方の違いから、切り捨て、という点。立場により大事なことのレベルが異なる。下層を捨て駒にする事が発生する。
試行錯誤ではなく臨機応変に対応して、致命傷だけを避けるべき。それによって、勝たなくても不敗にできる。
クラウセヴィッツの戦争論はひたすら相手の急所(重心)を打倒することを重視。孫子の兵法ではじわじわ弱らせて料理することを重視。
→相手の急所はビジネスでは見えづらい、崩しと決めがある事が重要。
詭道はビジネスでは使えない、短期決戦ではないから王道を取るべき。
→孫子は同じ相手と一度の戦いしか想定していないが、クラウセヴィッツは複数を想定している。これが、観光地ビジネスとそれ以外の違い。(観光地はぼったくりが多い)
選択と集中。会社の規模以外で参入障壁を作るのは困難。過去の成功を捨てる決断が必要。
勝ち癖をつけて勢いに乗る。ニッチで大きく勝ち、「どう大企業に頭を下げさせるか」を考える。
などなど。
兵法の考え方自体が面白く、クラウヴィッツとの比較も興味深かったが、この本自体はビジネスの戦略の教科書には正直できない。入門書として孫子を知り、ここからもっと深めていきたいと思わせる内容として、とても良かった。