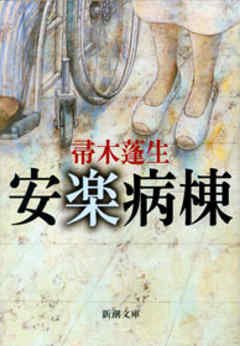あらすじ
深夜、引き出しに排尿する男性、お地蔵さんの帽子と前垂れを縫い続ける女性、気をつけの姿勢で寝る元近衛兵の男性、異食症で五百円硬貨がお腹に入ったままの女性、自分を23歳の独身だと思い込む女性……様々な症状の老人が暮らす痴呆病棟で起きた、相次ぐ患者の急死。理想の介護を実践する新任看護婦が気づいた衝撃の実験とは? 終末期医療の現状と問題点を鮮やかに描くミステリー!
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
帚木さんの『閉鎖病棟』が良かったので、今度はこちらを~。
て久しぶりの帚木さんの作品だよ。
老人性痴呆症、老後の生活、そして終末期医療を主筋にして書かれた小説です。
かなーり重い内容で460ページの長編。
考えさせられるね~。
パパが死ぬ前に入院してた頃、ちょっとだけ看病したのを思い出しながら読みました~。
今の時代、介護や看護は誰にでも切り離せない問題となったけど、
本当にみんなは理解してるのか?
そう思うわ~。
私は癌のパパの看病をそんなにしてたわけじゃないけど、最後は寝たきりになって少しは看護婦さんの手助けを少しはしたかな?
オムツの替え方、洗浄の仕方とかシーツの替え方、少しは知ってるからね~。
でも、果たして今の人たちの何人がそれを知ってるのか?
呆けても、一人の人間。
それぞれ自分の人生を生き抜いてきて、呆けも人それぞれ。。。
『呆け老人』を一つにひっくるめられるのではなく、一人一人の尊重がないと本当の介護はできないんじゃないか?と思う。
今は本当に物が豊かにありすぎて、それが当たり前のように生活してるけど、
おじいちゃんやおばあちゃんの若い頃は戦争から生き延び、物のない貧しい生活を生き抜いてきた人たち。本当に尊敬しないとダメだし、呆けても一人の人間として扱ってあげないと可哀想。
そして衝撃的だったのはオランダの医療事情。
もうダメだと思うと、医者や肉親は患者を死なせることに賛成してしまう。。。
生きても障害を持つだけ。金がかかるだけ。生きてることに意味がない。
そんなことを勝手に思って、患者を殺してしまう。
それが普通なんて信じられない。
それって殺人だよね~。
オランダ人じゃなくてよかった。。。
呆けて自分が誰かも他人が誰かも、何を食べたかも分からない人を殺す権利は誰にもないはず。
脳死の場合は別として、意志をもって何かを出来る生活を送ってるなら、誰でも生きる権利があるはず。
私はそう思う。
最後の章では、まんまとやられたな~。
これ、ミステリーだったとは思わなかったから、私としては大どんでん返しされた感じ。
でも、この一冊は絶対持ってて損はない本。
とても勉強になりました。
Posted by ブクログ
分類では医療サスペンス?だけど、小説の本質と良さとは全く違うところにある。なので本書がサスペンスの角度で紹介され、また呆け老人の行動の描写でまるで好奇心を煽るような紹介文には個人的に違和感を感じる。
小説の構成は、病院の中の老人個人個人のストーリを集めて構成される病院の日常、新人看護婦の視点、サスペンスのキーとなる医師の講演、その後老人のあいつぐ急死、手紙での告発。
小説後半のスピードが早く、たたみかけるような終結も箒木蓬生さんのパターンではあるが、今回も終盤で一気にギアチェンジし急にサスペンスに入った。だから医療サスペンスなんやけど、なんかちょっと奇妙。
本質は老人医療、安楽死等の倫理を問うもので小説中に答えもなく、私にもまとまった考えはないけれど、老人ひとりひとり生きてきた人生(特に戦争を体験した人の話は今の私のブーム)と、呆け方、呆けた後の人とのかかわり方、死に方については人間ドラマが凝縮されており興味深かった。この人の書く小説は淡々と書かれているのが余計、感情を深くさせる。(日本語が謎)
印象的で忘れられないのは、腰が痛くて曲がってしまったおばあさんが性格のキツイ実の娘に嫌味を言われ生活しにくい日常を過ごし、とうとう老人病棟への入院にあたり医者に対して語る言葉。
「本当にもう自分の体は焼いた方が楽かなと思ったりもします。何もかも焼いてしまって煙だけになり、まっすぐ空に昇っていくのもよさそうなきがします。・・・ほんに無様な格好になってしまいました。せめて煙になるときには背をピンと伸ばして空に昇っていきたいと思います。」っていうところ。
泣けた。