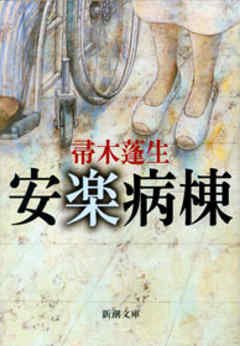あらすじ
深夜、引き出しに排尿する男性、お地蔵さんの帽子と前垂れを縫い続ける女性、気をつけの姿勢で寝る元近衛兵の男性、異食症で五百円硬貨がお腹に入ったままの女性、自分を23歳の独身だと思い込む女性……様々な症状の老人が暮らす痴呆病棟で起きた、相次ぐ患者の急死。理想の介護を実践する新任看護婦が気づいた衝撃の実験とは? 終末期医療の現状と問題点を鮮やかに描くミステリー!
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
刊行されてから20年近く時間を経ているが、
内容は色褪せないどころか、むしろ、切実になっている。
いずれもモノローグで記述されており、読み始めは戸惑ったが、
読み進むにつれ、全体像が掴めるようになり、
その結末たるや、読者に大きな問いを投げかけるものである。
高齢化してゆくのが自明である現代日本において、
誰しもが考えるべきテーマだと思った。
Posted by ブクログ
初めてこの人の本読んだけど、この人すごい!と思った。
痴呆老人、介護士の客観目、安楽死。
日本がこれから直面する問題であろう題材をミステリー仕立てに仕上げられている。
最初の語りあたりは、正直気怠くて、ずっと最後まてこんな調子かなあ。。だったらこの本海外小説並みに分厚いし、途中で挫折しようかなと思ってたんだけど、途中からドンドン面白くなっていって引き込まれていった。
直近未来に痴呆になる可能性がある親を持つ私には、小説の話だけとはいかず、かなり学びの感覚で読んでいった。
それにしても、登場人物の看護士の着眼点は見事としかいいようがない。
途中涙あり、笑いあり、驚きあり、で読み終わったらなんともいいようがない充実感に満たされた。
もしかしたら、中年の私だからこの本に感動したのかな(*^^*)
ま、でも年齢層関係なしにぜひいろんな方に読んでもらいたい一冊だと思ったよ。
この人の本はこれ以外にも評価が高かったので
今度読んでみよっと!
Posted by ブクログ
帚木さんの『閉鎖病棟』が良かったので、今度はこちらを~。
て久しぶりの帚木さんの作品だよ。
老人性痴呆症、老後の生活、そして終末期医療を主筋にして書かれた小説です。
かなーり重い内容で460ページの長編。
考えさせられるね~。
パパが死ぬ前に入院してた頃、ちょっとだけ看病したのを思い出しながら読みました~。
今の時代、介護や看護は誰にでも切り離せない問題となったけど、
本当にみんなは理解してるのか?
そう思うわ~。
私は癌のパパの看病をそんなにしてたわけじゃないけど、最後は寝たきりになって少しは看護婦さんの手助けを少しはしたかな?
オムツの替え方、洗浄の仕方とかシーツの替え方、少しは知ってるからね~。
でも、果たして今の人たちの何人がそれを知ってるのか?
呆けても、一人の人間。
それぞれ自分の人生を生き抜いてきて、呆けも人それぞれ。。。
『呆け老人』を一つにひっくるめられるのではなく、一人一人の尊重がないと本当の介護はできないんじゃないか?と思う。
今は本当に物が豊かにありすぎて、それが当たり前のように生活してるけど、
おじいちゃんやおばあちゃんの若い頃は戦争から生き延び、物のない貧しい生活を生き抜いてきた人たち。本当に尊敬しないとダメだし、呆けても一人の人間として扱ってあげないと可哀想。
そして衝撃的だったのはオランダの医療事情。
もうダメだと思うと、医者や肉親は患者を死なせることに賛成してしまう。。。
生きても障害を持つだけ。金がかかるだけ。生きてることに意味がない。
そんなことを勝手に思って、患者を殺してしまう。
それが普通なんて信じられない。
それって殺人だよね~。
オランダ人じゃなくてよかった。。。
呆けて自分が誰かも他人が誰かも、何を食べたかも分からない人を殺す権利は誰にもないはず。
脳死の場合は別として、意志をもって何かを出来る生活を送ってるなら、誰でも生きる権利があるはず。
私はそう思う。
最後の章では、まんまとやられたな~。
これ、ミステリーだったとは思わなかったから、私としては大どんでん返しされた感じ。
でも、この一冊は絶対持ってて損はない本。
とても勉強になりました。
Posted by ブクログ
痴呆になりつつある数人の老人の描写から始まる。この人のようになるのかあの人のようになるのか……。それぞれの理由で痴呆病棟に入院になる。
次は病院での様子を看護婦の目で教えてくれる。家族にとっての毎日は身内であるゆえの辛さや苦しさがあるのだと思える。仕事としてのほうが冷静に対応できるのかも知れない。痴呆になった人はもう人ではないのか?動く屍なのか?他人に迷惑をかけるなら早く死んだほうがいいのか?割り切れる回答は無いのかもしれないけれど、痴呆になっても生きていることを許していける社会だといいなと思う。
安楽死を、死なせることを医者が選ぶのではなく自然に、命の火が消えるのがいいな。ぽっくり逝きたいと言う気持ちもある。病院で沢山の管につながれて生かされるのはいやかもしれない。
見えてきた生の終わりを考える時期にきたと最近良く思う。
Posted by ブクログ
分類では医療サスペンス?だけど、小説の本質と良さとは全く違うところにある。なので本書がサスペンスの角度で紹介され、また呆け老人の行動の描写でまるで好奇心を煽るような紹介文には個人的に違和感を感じる。
小説の構成は、病院の中の老人個人個人のストーリを集めて構成される病院の日常、新人看護婦の視点、サスペンスのキーとなる医師の講演、その後老人のあいつぐ急死、手紙での告発。
小説後半のスピードが早く、たたみかけるような終結も箒木蓬生さんのパターンではあるが、今回も終盤で一気にギアチェンジし急にサスペンスに入った。だから医療サスペンスなんやけど、なんかちょっと奇妙。
本質は老人医療、安楽死等の倫理を問うもので小説中に答えもなく、私にもまとまった考えはないけれど、老人ひとりひとり生きてきた人生(特に戦争を体験した人の話は今の私のブーム)と、呆け方、呆けた後の人とのかかわり方、死に方については人間ドラマが凝縮されており興味深かった。この人の書く小説は淡々と書かれているのが余計、感情を深くさせる。(日本語が謎)
印象的で忘れられないのは、腰が痛くて曲がってしまったおばあさんが性格のキツイ実の娘に嫌味を言われ生活しにくい日常を過ごし、とうとう老人病棟への入院にあたり医者に対して語る言葉。
「本当にもう自分の体は焼いた方が楽かなと思ったりもします。何もかも焼いてしまって煙だけになり、まっすぐ空に昇っていくのもよさそうなきがします。・・・ほんに無様な格好になってしまいました。せめて煙になるときには背をピンと伸ばして空に昇っていきたいと思います。」っていうところ。
泣けた。
Posted by ブクログ
おばあちゃんっこだった私にとっては
患者さんたちのエピソードがとても和むし、癒される。
ますます高齢化が進む日本のことを考えずにはいられない1冊。
これからは良い"死の質"を求める人が増えるのだろうか
Posted by ブクログ
痴呆病棟を舞台にしたミステリーという括りだが、ミステリー要素はオマケ。新米看護師の目から見た痴呆病棟の叙述は密着ドキュメンタリーを観ているように細部まで描写されている。(身近に痴呆の人を見たことがない方は信じないだろうけど、かなりリアル)新米看護師の患者や家族との関わり方は慈愛に満ち、病棟で起きるハプニングもユーモラスにも思える。終末期の人間に関わるすべての人に対して粛々と問題提起する本。読んだ人は、家族なら、自分ならどうする?と考えずにいられなくなるはず。興味がある人は是非読むべき。
Posted by ブクログ
終末期医療の作品。
閉鎖病棟も読みましたが、痴呆病棟内の描写は秀逸だとかんじました。
ミステリーに仕上げてあるので、読み続ける愉しみも持ちつつ、また、主人公の看護師の公私ともの心の動きも興味深く読める帚木氏ならではの作品だと思います。
看護師さんが、ある種語り部みたいな役割を担っているので、
作品全体が優しいかんじになっているのかな。
ただ、ミステリーとして読むとラストは、ちょっと寂しかったなあ。
Posted by ブクログ
サスペンスとしては★★。終末医療の現場をリアルに描いた作品としては★★★★★。この作品にでてくる患者さんは純粋で生き生きしており、訴えかけられる部分が多い。なのでサスペンスにしてしまったのはとても残念。
Posted by ブクログ
痴呆老人たちの病院でのエピソードを、城野看護婦さんの目を通して描いています。城野看護婦さんは、その看護の状況を、担当の医師に報告しているという設定。
痴呆老人たちの、それぞれの生きてきた人生も語ってくれるので、一人ひとりの状況が身近に感じられ、その中で一人ずつ亡くなっていく時、ひどく悲しくなる。
痴呆老人は、人として生きていると言えるのか…自分の事が分からなくなってまで、オムツをしてまで生きる事に、意味はあるのか…
これから自分にも否応無く迫ってくる老いについて、考えさせられる。
Posted by ブクログ
痴呆老人の話。
人間の尊厳と安楽死について考えさせられる作品。
亡くなった祖父の最期は介護施設だったし、妹が銀行勤めを辞めて福祉の道へ進むことになったから特に身近に感じる題材だった。もっと早くにこの本を読んでいたら祖父母への接し方も変わったのではないかと悔やまれる。
人間は生きている限り人間なのだ。たとえボケてもたとえ体が動かなくても、やっぱり人間なのだ。そんな当たり前のことを再認識した。
この作品をたくさんの人に読んで欲しいと思った。
Posted by ブクログ
1年前に買ってようやく読み終えた。
『閉鎖病棟』に衝撃を受けた帚木さんの作品。
「脳死は人の死か」という脳死移植問題や、
「尊厳死」「意志表示」というターミナルケアの問題。
10年も前の作品だけど、今読んでもまったく古いと感じない。
IT環境はこの10年でものすごい進歩したけど、
終末期ケアの在り方は今だ議論が進んでいないんだと実感。
それだけ、「人の死」というのは結論を出すのが難しいテーマなんだと思う。
学生時代に読んでおきたかったなあ。
Posted by ブクログ
「目は窪んだところについてるから疑りぶかい器官、耳は外に開かれてるから楽観的でオープンな器官」というような一節がインパクト大でした。作者の方がお医者様てなことで院内の細かなところの描写がリアリティ溢れまくってて興味深いんですが、それを支えるのはこの方の深い洞察と研ぎ澄まされた美意識なんじゃないかなあと。しかもそれがすごくあったかい!「国銅」を読んでなおさらそう思いました
Posted by ブクログ
痴呆老人らをめぐる安楽死、尊厳死、終末医療が主題。
よく書かれている時事社会小説。
「全くぅ、まともに考えたらやってられないよなぁ、読むの辛いなぁ」と思わせつつ最後まで読ませる。
色々な痴呆老人現れ、自分は果たしてどの型なんだろ、なんて身につまされる。「私に限って大丈夫」なんて思えるのは30代までの若者。中年でそう思える奴は馬鹿か「おめでたい」か、もう「痴呆」が始まっているか、だ。
落ち込みかかっている人は絶対に読んではいけない。
Posted by ブクログ
痴呆病棟を舞台にした終末期医療について考えさせられる作品。
全てが日記・手紙調で書かれており、病棟での歳月を追っているため、文章はかなり長めになっている。文章自体は読みやすいのだが、登場人物も多いため「誰がどんな症状で、家族はどんな様子…」といったことを確認しながら読み進めるとかなりの時間を要する。
167ページまでは入院患者の紹介(患者本人や家族などから)のため、看護師の視点がなく本書を読み始めたときは「?」といった感じだったが、徐々に読み進めていくうちに内容が明らかになってきた。
ミステリーとされているが、謎解き要素は少ない。ただ、痴呆の現状と医療の問題点は浮き彫りにされているように思えるので、ミステリーとしてよりは医療ものとして読み進めていく作品に思える。
Posted by ブクログ
前半は年老いて、これから痴呆病棟へ入ろうと考える本人やその家族の側から描かれ、後半は痴呆病棟で働く看護師の側から描かれている。
両方からの目線で書かれているので、状況がリアル。
今から17年位前に書かれた作品だが、高齢化社会となった今も十分に読みごたえがある。
2018.11.6
Posted by ブクログ
最初に一人一人の入院までの過程が短編風に語られ、その後、病院での生活風景が続き、最後にサスペンス。「閉鎖病棟」によく似た構成でできています。
この人の文章はよほど私の波長と会うのでしょうか、導入部では一気に没入できました。しかし、祖父や母のことを思い起こさせる中盤はちょっと辛い。延々と痴呆の実態がつづられます。なんだか一種のルポルタージュみたいです。何がテーマなのか、どうエンディングにつながるのかと心配した頃、いきなりサスペンスに変わります。
サスペンスが書きたかったのか、痴呆と言う社会問題を提起したかったのか、どちらにしても中途半端な感じは否めません。
Posted by ブクログ
まず、痴呆老人の実情にびっくりします。この小説の主人公の看護婦の観察眼のするどさ、気配りの細やかさに感心します。
物語が進む中でじりじりと噴出してくる終末医療の問題点と疑念。
ミステリーとしてではなく、私たちが向かっていく老人としての生活を知る上でも必読の書です。
Posted by ブクログ
安楽病棟(痴呆病棟)で働く新人看護師・城野。ここには認知症が進んで家で生活できなくなった患者さんがたくさん入院している。一口に認知症といっても症状は十人十色。基本的に回復の見込みは無い患者さんばかりだが、城野は先輩看護師達と一緒に、どうすれば患者さんが快適に過ごせるか、楽しく人生を謳歌できるか。介護を工夫したりイベントを企画したりと毎日一生懸命働いていた。
裏表紙のあらすじを読んでこの本を購入したのは随分前である。そして、私はいざその本を読み始める時に改めてもう一度あらすじを読んでから読み始めることはしない。ということで、どんな話なのかわからないまま読み始めたのも同然だったので、これは痴呆病棟で奮闘する新人看護師と患者さんの日常が実録風に書かれている小説なんだと思いながら9割読んでいた。ところが最終章の「動屍」で雰囲気は一変。そうか、ミステリーだったのね(^^;残りの1割は食い入るように読んだが、いかんせんそれまでが冗長すぎたのが残念。主人公の城野看護師がとても熱血な優しい看護師だったおかげで、想像していたような重々しい痴呆病棟の話ではなかったのだが、もっとスマートに削れると思う。こうした病棟では切っても切れない糞尿騒動や家族と介護の問題なども、驚く程ポジティブに、そして何より患者さんのことを考えた看護がされていて、「こういう病棟や看護師さんばかりだったら幸せだなぁ」と思わされるものだったので余計にそう思った。タイトルからすると”安楽死”について書かれている部分が大半かと思われたが、そうでもなかったなぁ。それよりも、認知症介護について読みたい人に薦めたい。
Posted by ブクログ
戦争の話とか、医療の話とか、途中読んでてしんどくなってきたけど(内容理解できない的な意味で)読んでよかったと思う。
ミステリーな部分は本当にほんのちょっとで(最終章までミステリーだということを忘れていました)ドキュメントみたいに感じました。
安楽死の問題はいくら話し合っても答えの出ない重い問題だと思います。
この本ではミステリーなので殺人という形でしたが、実際自分の祖父母が、父母が、兄弟が、自分が、ああいう立場になったときにどういう決断をするのか、とても考えさせられました。
とりあえず自分には介護の仕事は死んでも勤まらないなと思いました。
世のヘルパーさんたちはすごい。
Posted by ブクログ
高校の頃ゴミ捨て場から拾って読書感想文に出した本。
『閉鎖病棟』もそうだけど、筆者の患者さんに対する目線のあたたかさにほっこり。
とはいえ一番印象に残っているのは医者とヒロインとのシャンパンデート(ドン引き)だったり。。。すいません。中身はとってもいい話です。
Posted by ブクログ
深夜、引き出しに排尿する男性、
お地蔵さんの帽子と前垂れを縫い続ける女性、
気をつけの姿勢で寝る元近衛兵の男性、
異食症で五百円硬貨がお腹に入ったままの女性、
自分を23歳の独身だと思い込む女性…
様々な症状の老人が暮らす痴呆病棟で起きた、
相次ぐ患者の急死。
理想の介護を実践する新任看護婦が気づいた衝撃の実験とは?
終末期医療の現状と問題点を鮮やかに描くミステリー。
Posted by ブクログ
絶対年取りたくないと思わせる、一品。
ミステリーではなく、ドキュメンタリーかと思うほどの描写。
結末よりも老人たちの描写に鳥肌が立ってしまいそうだ。
しかし、連れ合いがこうなってしまったら、私は…。
う〜ん悩む。。。。
Posted by ブクログ
痴呆病棟で起きた相次ぐ患者の急死。
理想の介護を実践する新任看護婦が気づいた衝撃の事実とは。
終末期医療の現状と問題点を正面から描いている。
序盤は患者や患者の家族の独白が並び,痴呆の悲惨さを訴え,
中盤から新任看護婦の視点で病棟の日常が詳細に描かれる。
結末に意外性はなく,ミステリーとしては物足りないが,
過剰医療に対する積極的安楽死の問題を巧みに扱っており,
医療現場リポートとして,興味深く読むことができる作品