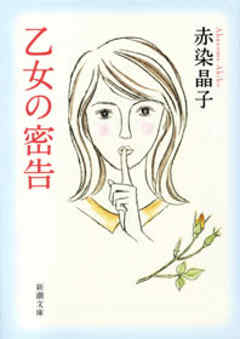あらすじ
ある外国語大学で流れた教授と女学生にまつわる黒い噂。乙女達が騒然とするなか、みか子はスピーチコンテストの課題『アンネの日記』のドイツ語のテキストの暗記に懸命になる。そこには、少女時代に読んだときは気づかなかったアンネの心の叫びが記されていた。やがて噂の真相も明らかとなり……。悲劇の少女アンネ・フランクと現代女性の奇跡の邂逅を描く、感動の芥川賞受賞作。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
外語大学でのスピーチコンテストに向けてのスパルタ教育。熱心に取組む乙女達の間で起きる噂と真実…そして密告。スピーチの題材『アンネの日記』のユダヤ人と乙女達が重なり、さらに『密告』が主人公みか子と麗子様を苦しめる。15歳の若さでこの世を去ったアンネ・フランク…彼女の書いた日記がこれだけの影響力をもって後世に受け継がれているとは。彼女に教えてあげたいですね。
Posted by ブクログ
タイトルの乙女という言葉から、つい少女小説や恋愛小説なのかと推測してしまうが、さにあらず。
学生たちに“メンチ”を切り、怒って教室を立ち去るときは「あたくし、実家に帰らせて頂きます!」と言い放つドイツ人教授や、指にストップウォッチだこができている麗子様などなど、強烈なキャラとその言動にゲラゲラ笑ってしまうのだが、読み進めていくと作者の《さあ、ここからが本番やで》という声が聞こえてくるかのように、作者の冷徹な目をもって《真実をみつめよ》と言葉が紡がれていく。
素晴らしい音楽を聴き終えた瞬間、人は深い溜息が出るものであるが、この本を読み終えたとき、同じように深い溜息が出た。
この作者は鬼才である。早世が本当に悔やまれてならない。
Posted by ブクログ
⚫︎受け取ったメッセージ
「真実とは乙女にとって禁断の果実だった。」
⚫︎あらすじ(本概要より転載)
ある外国語大学で流れた教授と女学生にまつわる黒い噂。乙女達が騒然とするなか、みか子はスピーチコンテストの課題『アンネの日記』のドイツ語のテキストの暗記に懸命になる。そこには、少女時代に読んだときは気づかなかったアンネの心の叫びが記されていた。やがて噂の真相も明らかとなり……。悲劇の少女アンネ・フランクと現代女性の奇跡の邂逅を描く、感動の芥川賞受賞作。
⚫︎感想
すごい短編小説だった。ユーモアとシリアスをこのように巧みにブレンドし、密告する側とされる側という葛藤と統合を描く。深刻なホロコーストというテーマを自分たちの生活に引きつけて考えることは、普段の生活ではなかなかできない。それを「乙女」な女子大生という「清純」を密告者側とと置きかえ描かれた作品。いつ誰が「乙女」と見なされなくなるか、わからない。
真実は多くの人が夢見ていたい中で隠されなくてはならないものである。
人は同じ美しいと思える幻想をみんなで信じて安心したがる生き物だということを改めて思った。
面白く読ませてくれる漫画風なところがありながら、実はメタファーを盛り込み深いテーマを描いている。ぜひ再読したい。
Posted by ブクログ
短めの文章のリズムと登場人物たち(特に教授)の強い言葉が強く印象に残った。
主題となっている『アンネの日記』とともに、読み継がれて欲しい本。
『アンネの日記』は未読の状態だと「悲劇的な少女」のイメージを持ち、実際に読むとあまりに等身大な小女性に驚くもの(と勝手に思っているけれど)。
本書はその後もう一度、余計なイメージを捨ててアンネを読み、アンネと向き合う時に最適ではないかと思う。
Posted by ブクログ
ナチス政権下で異分子として個の名前を奪われた人々。毎日の日記の最後に記したアンネ・フランクという名前は、悲劇に抹消された人々にも名前があったんだと語ってくれる。
乙女は日々に翻弄されながら、自分の名前を探し続ける。
真面目な文体にユーモラスが顔を出してくる雰囲気が大好きだった。乙女とは乙女らしからぬものを好む生き物なんだなぁ。
Posted by ブクログ
ナチスの政権下で奪われてしまった名前たち、そんな中でアンネ・フランクは決して彼女の名前を失わなかった。
異なるものとして排除されてしまうという歴史は繰り返されていると思う。そんな世界でどのように生きていくのかを再度考えるような作品だった。
Posted by ブクログ
とても読みやすい。私小説風であり、歴史小説風であり、哲学書風であり、人情噺風でもあり、ライトノベルロマンス風でありながら軽快な語り口にあっという間に飲み込まれてしまう。そして最後に残る重いテーマの余韻。なるほど芥川賞に相応しい傑作小説だと思う。
Posted by ブクログ
私が初めて、受賞時から読みたいと思った芥川賞作品です。
外大の女子学生達が繰り広げるお話、
とのことで、気持ちの上で、
近年の受賞作より何となく敷居が低いというか。
そうして「読みたい」「読みたい」とは常々言っていたものの、
結局、本屋さんで遭遇したのは、文庫本になってから。
買う予定だった本を戻してしまって(ごめんなさい~!)
即刻購入ののち、帰宅後一気読みしました。
まず、執拗に繰り返される、
「乙女」という言葉が印象的で癖になる。
そういえば、最近では最早死語のような気もする程、
歪に聞こえる言葉だけど、私達は乙女なのだー。
少し前に、アンネの日記を読んだところだったので、
彼女のユダヤ人としての誇りや葛藤、
「オランダ人になりたい」という本音、
アツい叫び声を読む中で圧倒される、
その気持ちはよく分かりました。
そして、彼女の周りで起きる「事件」や「密告」と、
アンネの周りで起きたことやミープの存在等を、
熱に浮かされたように重ねて、
突き動かされていく様子は、あまりにリアル。
読書家って、こういうところがあると思うのです。
実際起きていることは大した話じゃない。
だけど脳内では勝手に壮大なドラマになっている。
誰か、強烈な人物と重ね合わせてみたりして。
個人的に衝撃を受けた部分として、
主人公のお友達(貴子さんだっけ、、、)で、
ドイツからの帰国子女の方のエピソードがあります。
彼女は、ほぼ母国語と同じようにして、
ドイツ語を学んだ経緯がありながら、
長い間触れる機会がなかったために、
発音なんかは完璧だけど半端に忘れてしまっている。
その「忘れている」という事実を強烈に恐れている。
「○○ってドイツ語でなんていうんだっけ」
に答えられないとき、
「答えられなかった」「単語を忘れてしまった」
という事実に驚愕し、おびえる。
みんなとは異なる結び付き方をしているからこそ、
日本人目線でのドイツ語の授業には違和感がある。
これをフランス語に置き換えたら、
完全に私になりそうなんですもの。
最も、まだ、私は大学生ではないけれど、
フランス語を完全に取り戻すために、
専攻語にするつもりでいます。
だけど、これを読まなかったら、
彼女と同じになっていたかもしれない。
変に、やさぐれていたかもしれません。
どれだけ意気込んでいても、
自分の記憶と正面から向き合ったときに、
失ってしまったものに愕然として、
背を向けてしまっていたかもしれません。
今だってふと冷静に、
自分がどれだけフランス語を覚えているか考えてみて、
単語が抜け落ちすぎていることを思うと、
胸が苦しくて、自分の一部がどこかに行ってしまったような、
喪失感に襲われるものです。
だけど、今はその事実と、
わざわざ向き合う必要は無いからいいのです。
もしも、大学で勉強するとなれば、逃げられなくなるのです。
その「来る日」を前にこれを読めて良かった。
勿論、失ったものと対峙するのは、
どれだけの覚悟があっても足りない位、怖いことです。
だけど、一度、やさぐれてしまった人を見て、
それを反面教師にして、自分なりに戦ってみるのと、
何も無くしてぶつかるのとでは大きな違いです。
赤染さんがこの作品の中に、そんな人物を生んでくれたこと、
本当に感謝しています。
「なり得たなりたくない自分」を見せてくれたこと、
本当に感謝しています。
(赤染さん自身外大出身とのことで、ひょっとしたら、
赤染さんの周りにそんな方がいらしたのでしょうか。)
ありったけの★を差し上げたいです。
Posted by ブクログ
まずは本が薄くてびっくり。それはどうでもいいか。
芥川賞受賞のときはけっこう話題になっていておもしろそうと思った記憶があったので即買い。
うーん、さすが芥川賞っぽい純文っぽい不思議な感じ。わかるようなわからないような。おもしろいようなおもしろくないような。エンタメじゃあないからな。
たぶん、ささっと読んでおしまいにするのではなく、じっくり何度も読むとよく意味がわかって発見もあるような気がするけれど。
京都弁が印象的。ユーモアがあって文章は好きかも。
Posted by ブクログ
芥川賞を受賞したのは2010年。その時から気になっていた本。難しかった。
乙女とアンネ・フランク。密告。アイデンティティ。キーワードはあるけど、あの人形にどんな意味があるのか、麗子様の存在や言動はなんなのか、よく分からずに読み進めた。麗子様は始め、エースを狙えのお蝶夫人のようだと思いながら読む。教授は宗像コーチかな。そう思って読むと、乙女のことも分かってくるような気がする。
アンネの日記、しばらく読んでいない。完訳、というかアンネの日記の最初のものしか読んでいない。アンネが戦争が終わったらオランダ人になりたいと書いていたことは初めて知った。ユダヤ人であることをどう自分の中で取り扱うか。アンネのアイデンティティ。
そのあたりからとても難しいと感じた。人形の誘拐に至っては、謎でしかなかったが、読んでいて苦痛になる難しさではなかった。難しくて、理解はできていないのだが、読んでいて楽しいと感じる不思議な本だった。
赤染さんは2017年に亡くなられているので、今出版されているものが全てだ。いつか、読んでいきたい。
分からない、難しい、理解できない。そんなことも含めて楽しんだ稀有な読書体験だった。
Posted by ブクログ
短い文章の羅列は正直言って自分には読みづらく、リズムに乗れなかった。物語の世界観も自分の趣味ではなかった。ただし、アンネの世界と女子大生の世界を乙女、密告というキーワードでうまく重ね合わせた構成の芸術的完成度は極めて高いと思う。
Posted by ブクログ
赤染晶子さん初読です。文庫筋書きの「悲劇の少女アンネ・フランクと現代女性の奇跡の邂逅」に惹かれました。本作は100ページに満たない中篇小説で、2010年の芥川賞受賞作です。赤染さんは2017年、42歳で早世されました。
ナチ体制下で究極の迫害を受けたユダヤ人と、大学のスピーチ・ゼミで孤立させられる主人公の対比が斬新で興味深かったです。その物語の切り口は、異質な存在を排除しようとする根源的な人間の性(さが)に通じ、普遍的問題なのかと思いました。ただ、隠れ家のアンネ・フランク一家の密告と、現代の閉鎖社会での告げ口では隔たりが大きく、そもそも比較にならない恐怖レベルでしょうが…。
こんなレビューを書くと、重く暗い堅苦しい物語に思えますが、京言葉の会話にユーモアがあり、一文が短かくリズムもあるので読みやすかったです。
そして『アンネの日記』が、強制収容所に送られた悲劇の少女の話だけではない優れた文学であることに、今一度目を向ける必要性を感じます。
アンネ・フランクに造詣が深く、様々な著書もある小川洋子さんの「100分de名著」ブックスの名解説を思い出しました。奇しくも、本作が候補となった芥川賞の選考会で、選考委員であった小川さんが本作を強く推したことも頷けました。
『アンネの日記』の奥深い世界の中に、主人公はアンネの真実の言葉、人を救う言葉を見つけたのでしょう。社会に蔓延る差別や偏見に惑わされず、困難な時代を生き延びていくヒントがあるんですね。
80年前のアンネの言葉に再び光を当てる、とても奥深い作品でした。
Posted by ブクログ
芥川賞受賞作のこの本は非常に薄い。
読みづらいかなと思ったが、書き出しが台本のト書きのようですんなり入り込むことができた。軽やかな文章の合間に笑いも上手く散りばめてある。
ここは京都の外国語大学。授業中に乱入してきたのはドイツ語学科のバッハマン教授。スピーチコンテスト(暗唱の部)の課題『アンネの日記』の一節を明日までに暗記するよう告げ教室を出て行く。
主人公のみか子は暗記しながらアンネの心の叫びに触れる。学園に流れる黒い噂に翻弄される自身をリンクさせながら…
自分の言葉を獲得していく終盤が良かった。
乙女という生き物は「信じられな〜い」と驚いて見せ、誰よりもそれを深く信じる。
自分とは違う異質な存在をきっちりと認識する。
文中で繰り返し目にする「乙女」は噂が真実であるかどうかより「信じる」ことに同調を求める。「乙女たち」から排除されたものは密告される運命にあると怖さも感じさせる一冊。
著者が2017年、42歳の若さで亡くなられたと知りとても残念に思う。他の本も読んでみたい。
Posted by ブクログ
微妙に張り巡らせられた緊迫感と、平の文でたまに登場するおふざけのギャップがとても良かった。読みながら笑ってしまった。
物事を自分の見みたい一側面だけで判断するのは良くないな
Posted by ブクログ
赤染晶子が、観光地であるアンネの家を訪れて「アンネは本当はこんなこと望んでいなかった」と思った。それを忘れないでいようと思って書いた……という挿話を読んで手に取ってみました。
要するに『私』を発見する物語なのですが、自分が自分であることを他人に委ねてはいけないし、委ねることも出来ない。
他人が奪ってはならない。
他人が勝手に物語を与えてもいけない。
そういった尊厳についての物語だと思います。
まあアンネの尊厳についてドイツ人と日本人が語るなと言われればそれまでなんですが。
逆にアンネがみずから密告したアイデンティティを尊重せねばならぬと、ドイツ人が日本人に教えるというのは……まあやっぱつまらんギャグかもしれんがしかし、アンネを語るバッハマン教授の言葉は胸に迫りました。
再読だったのですが1回目と違って面白く読みました。
Posted by ブクログ
文体がミュージカルみたいで何か面白かった。
舞台は現代の外語大ですが、女子大生達は古き良き大正時代のハイカラな女学生を思わせます。
しかし、お人形を持ち歩くドイツ語学教授(中年男性)ってどうなんだろう(笑
Posted by ブクログ
文体がリズミカルで
登場人物も面白いので
さくさく読めてしまったが…
ラストに近づくにつれ
?????
読み返したけど、
???
だけど
疑問とは違う何かが残る。
乙女たちの習性がやっぱり嫌になる。
乙女をやめて良かったと思う。
Posted by ブクログ
自己、他者、密告者、言葉、記憶、乙女、噂。。。。。
観念の風が、断続的に折り重なって吹いてくる。
そんな印象と、アンネフランクの生きた情景が
オーバーラップして、重ね書きされていく。
関西弁がいい、オアシスのようになっていて、
独特の感じを醸し出していて。
良い出来なんじゃないかと思いました。
面白い作品です。
Posted by ブクログ
無駄のない構成で、完成された方程式のような作品。淡々とした文章は乙女が集う大学という閉鎖的な空間をうまく表現するのに適しているように思える。
後で、書くお
Posted by ブクログ
本の紹介にもある通り、「アンネ・フランクとの邂逅」ということばがぴったりの物語でした。しかも、生の切実感を伴った「邂逅」です。
意識的なのか、描かれている世界が少女チックな世界で少々とっつきにくかったのですが(笑)、解説の方も書いておられるようにスポ根物に近い背景と、ところどころに繰り出されるユーモア(特に、バッハマン教授の常軌の逸脱ぶりが面白い!)で、何とか物語に馴染むことができました。(笑)中盤の衝撃的告白には、自分もみか子同様、「ええっ!」と思ってしまいました。(笑)
社会の中で認められ働きたい。しかし、その「社会」は人を「他者」として疎外する側の集団でもある。そして、いったん「他者」と指定されてしまったら・・・。それでも、やはり「社会」の一員でいたい。しかし、名前のない「他者」ではなく、「私」と認めてくれたのは、皮肉にも密告者だった!「ユダヤ人 アンネ・M・フランク」であると!主人公・みか子の現実の世界と、「アンネの日記」のスピーチを通して絡み合う2人の切実な想いを、綺麗に融合した作品だったと思います。
Posted by ブクログ
女というのはつくづく面倒くさい生き物だなあ、と実感できる作品。それはもう怖ろしささえ感じるくらい。そのことをとても深い洞察で描かれた小説です。
Posted by ブクログ
学生たちから「麗子様」と呼ばれている女子学生が「ほな!」とか関西弁使うところや、
バッハーマン教授が、誘拐された人形にモーツァルトを聞かせてほしいと懇願するところなど、
ユーモラスな場面がある一方、
バッハーマン教授のアンネの日記考は考えさせられた。
確かに、日本での「アンネの日記」の扱い方は、かわいそうな乙女の物語、というもの。
この本で、アンネ自身のアイデンティティに関する記述もあったと知り、2年間もの潜伏生活を送る中で、よほど自分の心と向き合ったんだろうなぁ・・・と想像しました。
Posted by ブクログ
2017.11.08
「アンネの日記」が大好きだった女子学生が、大学のスピーチの授業と先生の指導を通じて、「アンネの日記」を再発見する物語。
いつ読んだか忘れてしまった「アンネの日記」。学生の頃だったと思う。
今思えば、歴史上の出来事というより、1つの物語として読み流してしまったように思う。
ユダヤ人であること。アイデンティティ。
そういうものを自分自身の問題として考えたことがない。
日本人であること。
自分は日本人なんだなって、改めて感じた経験がない。
いつかまた、アンネの日記を読んでみようと思った。
Posted by ブクログ
解釈の余地の多いお話という印象。高校などでこの本を題材に議論をしたら、きっと色々な意見が出て、面白いのではないかと思った。
自己が確立されてきているけれど、まだ揺らいでいる、20歳前後の少女 …作中では「乙女」という呼称になっている…達が主人公。作者の出身校でもあるらしい京都外語大学のドイツ語学科に通う彼女達は「アンネの日記」を題材に、スピーチコンテストの練習に余念が無い。スピーチコンテストを主導する個性的なドイツ人教授や、スピーチコンテストに人生を掛けているかの如き女学生を巡る噂。
色々なテーマが読み取れるが、やはり一番強く考えさせられたのは、自己…アイデンティティ…ということについて。アンネと同世代の女の子達の純粋や潔癖、真実よりも美しいフィクションを愛してしまう心、本当の自分を探し求める心などが、アンネと共振したり対象の位置に置かれたりしながら、たくさんの問いをあたりにキラキラ撒き散らしていく。
Posted by ブクログ
外国語大学に通う「乙女」たちは『アンネの日記』の一部をスピーチコンテストで暗唱することとなっていた。
『アンネの日記』の決まった一節を必ず忘れてしまうみか子、スピーチを生きがいとしているような麗子、帰国子女の貴代、そして風変りなバッハマン教授。「乙女」たちが見つけるアンネ・フランクとは、そして「自己」とは。
うーむ…なんというか…とても勿体ない!!という感じの作品だった。
試みていることもわかる、伝えんとしていることもわかる、でも何もハッキリとは見えてこない。
思うに、『アンネの日記』の中でもとりわけ彼女のエスニック・アイデンティティが揺らいでいる部分を取り上げて、それを自分は日本人であるというアイデンティティに欠片ほども迷いを抱いていない「乙女」の自意識形成とラップさせようとしたのは失敗だ。
その溝を、帰国子女である貴代や、日本で教鞭を握るバッハマン教授が埋めてくれるのかと思いきや、彼ら(特に貴代)はこの問題に何ら関与しない。
他にも母娘の関係など、何かあると匂わせておいて結局なにも起こらない伏線もどきが多かった。
蛇足ながら、女子校育ちで大学は外国語学部という、この作品で言うところの「乙女」度合は筋金入り(笑)の私から言わせてもらうと、この作品に描かれるような「乙女」らの争いやアイデンティティ・クライシスは大体中学校か高校までには収束し、大学生になる頃にはもう少し地に足がついた?生活を送っている。どうせなら「第二外国語としてドイツ語を習うお嬢様高校の一幕」くらいにしておいた方が、まだ設定にリアリズムがあったのに。
…と思っていたら、作者自身が京都外国語大のご出身とのことで、もしかしたら世の中にはこういう純粋な外語大生もいるのかもしれない。
Posted by ブクログ
スピーチコンテストに向けて「アンネの日記」の暗唱に取り組む外国語大学の女子学生たち(「乙女」と呼ばれる)の話。「乙女」の一人、みか子の視点で描かれる一人称小説。バッハマン教授や麗子様など、名前を与えられた他の登場人物の描かれ方はマンガ的で、ユーモア小説と呼んでよいと思う一方で、「乙女」たちのアイデンティティの話が「アンネの日記」そのものとのリンクしていく感じは、割に重たい社会批評小説にも見える。薄くて、文体も読みやすいが、思いの外、難しい小説だったなあ。
難しさは、「乙女」という語が多義的であるところや、大学内の人間関係が「アンネの日記」に登場する人物に喩えられたりするところ、あたりにあると思う。