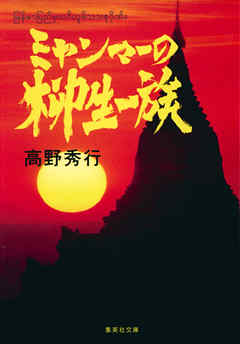あらすじ
【電子版特別カラー写真収録】探検部の先輩・船戸与一と取材旅行に出かけたミャンマーは武家社会だった! 二人の南蛮人に疑いを抱いたミャンマー幕府は監視役にあの柳生一族を送り込んだ。しかし意外にも彼らは人懐こくて、へなちょこ。作家二人と怪しの一族が繰り広げる過激で牧歌的な戦いはどこへ…。手に汗握り、笑い炸裂。辺境面白珍道中記。電子版には特典写真10点を追加収録。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
高野さんが先輩作家・船戸与一さんの取材旅行に同行した2週間のミャンマー旅。
20年くらい前のことですが、ミャンマーの社会が日本の武家社会みたいなことに気づいた高野さん。
旅の監視役となるミャンマー国軍の情報部がまるで柳生一族じゃないか!から始まります。
ミャンマー国軍を徳川家にたとえて、柳生一族、老中、大目付まで出てきて、おもしろく、ミャンマーの国家の対立の様子などがわかりました。
柳生一族とも打ち解けてしまう高野さんの人間力が大好き。
辺境と言われる場所の、普通は知ることのできない人々の素の姿や魅力を引き出す力もさすが高野さん。
Posted by ブクログ
舩戸与一の付き添いという緩い立場の高野秀行がのびのびと笑いの才覚を発揮されており、面白くて仕方ない。
他のミャンマー2作もとても面白いが、これは病気になったりヒルに襲われたりしないので軽く読めて良い。
ミャンマーにおける秘密警察のような役割を担う柳生が、次第にアホな高野・船戸ペアに懐柔されていくのが笑える。トイレの前で待つ三十兵衛、本当に勘弁して。
外国の小難しい政争を日本史になぞらえて説明するという意味不明な技法を開発しており、これは後にソマリランドなどでも活かされることになる。
とにかく笑えて楽しい馬鹿な小説だ。
Posted by ブクログ
椎名誠氏のミャンマー本を読んだので続いてこちらを。
「柳生一族」の意味を知らないまま読み始めたので、日本から逃げた誰かの話だと思い込んでいた。反省。
ミャンマーで江戸時代の柳生一族のようにスパイ活動をする集団と、船戸さんの取材に通訳として同行する高野さんの現地取材小説。ミャンマーにはほとんど正規入国していないという高野さんが、おもしろおかしく、しかし真面目にミャンマーの現状を紹介している。そして、最後の最後にまたミャンマーに変化が起きてびっくりである。
ミャンマーの周縁部の統治状況、パンロンでのアウンサン遺構の紹介の雑さ、ミャンマーの識字率の高さ、椎名本で出てきたタナカ(こちらではタナッカー)の様子など、色々と興味深い話が続く。個人的には、それまで監視/護衛を怠らなかった三十兵衛がパゴダの中では全てを忘れて祈りを捧げているシーンが印象的であった。
その後みなさんどうなったのでしょうかね……
Posted by ブクログ
高野氏離れが続いていたけど、先日の『語学の天才まで1億光年』によって長い眠りから覚めた。
自分への快気祝いにと今回手に取ったのは、世にもおどろおどろしいタイトルと表紙が特徴の本書。(相変わらず、刊行年順関係なしに読んでいくスタイルをキープ)
いつものことながら、彼の文筆にかかれば恐怖は軽減され、寧ろ愉快な気分にさえなっていた。
早大探検部の先輩で作家の船戸与一氏とミャンマーへ取材に出かけた著者。今回は珍しく観光に近い合法的な旅行なのかと思いきや、そんなはずはなく。題して「柳生一族と過ごすミャンマー辺境14日間」の旅だ。
ここで早速、謎のワード「柳生一族」が登場。これは現地の軍情報部を徳川家の大目付であった柳生一族に準えた、高野氏による例えである。彼らの監視下で著者と船戸氏は取材をすることになったのだ。
彼は事あるごとに人や事物の呼称を独自開発しており、例えば政治の実権を握るミャンマー国軍を「徳川家」。他にも「江戸ヤンゴン」「大坂マンダレー」と双方の第一・第二都市をくっ付けたり等しているが、それらが妙にイメージしやすい上にしっくりくるもんだから侮れない。
内容よりも先に彼の秀逸なネーミングセンスに度肝を抜かれていたが、船戸氏の「(下調べや細かいことは気にしない)行けば何とかなる」マインドにも実は感心していた。
特にツアーに同行した柳生一派とお酒を酌み交わすシーンは痛快だった。ある程度考えていらっしゃるとは思うが、後は成り行き任せで現地に溶け込むというのが本当にお上手。時には現地の人まで(意図せず)翻弄する。そのスキルの高さに何度も衝(笑)撃を覚えた。
性格がほぼ真逆の高野氏とは抜群のバディだったんじゃないかな。この2人にかかれば柳生一派の監視役も大したことなく見える笑
自分も抗議デモの勃発する数年前にミャンマーを訪れたことがある。
しかし、料理は日本人の口に合うまろやかテイストのものが多く、国民性はどことなくおっとり穏やかというしょぼい感想しか持ち合わせていない…。
そのせいか、昨今のデモや「柳生一族」・更に主君の「徳川家」に見られる不穏な影と実際目にしたミャンマーがなかなか結び付かずにいる。(本書の旅は色々と腑抜けて見えたが、後日談の「政変」にて一気に意識を持って行かれた。道中では味わうことのなかった胸のざわつきも感知したし)
ミャンマーの国民性について自分にはおっとり穏やかだと映ったが、高野氏は対等な立場同士だと非常に社交性・国際性が高い人々だと書かれている。(事実、一派への緊張感も次第にではなく、急激に薄れていた)
民族と宗教の多様性がそれらを養っているというのが何もかもを見てきた著者の推測であるが、それらもまた彼らの寛容さ・穏やかさに直結しているのかな。
彼が実際目にしたミャンマーを自分も恋しがっている。
Posted by ブクログ
早大探検部の先輩・船戸氏に随行する形でミャンマー(ビルマ)入りした著者。入国前の審査から船戸氏との扱いに笑えたが、題名のとおり軍事政権の情報部を隠密・柳生一族になぞらえての記述は、まさにエンタメ系ノンフィクションと呼ぶに相応しい。奇しくも2015/11/11現在、ミャンマーでは千姫ことアウン・サン・スー・チー氏率いるNLDが勝利を収める報道が世界を駆け巡った日だったことは偶然にしても出来すぎ(笑)
Posted by ブクログ
掛け値無しに面白すぎる!
クレイジージャーニーで見かけたヤバイ人だぁと思って読み始めたけど、ヤバさはそのままにミャンマーの体制や人びとの濃い部分を描き出している。
人を観察する視線はフラットで、そのフラットさが激ヤバな状況でもそのままだからこそのおもしろさ。
ユーモアたっぷりミャンマー紀行
過去に許可などなしにミャンマーに侵入し、ゲリラとも交友のある著者であり、本件は軍事政権側の監視の下でのミャンマー行であったから、本来ヤバイはずの紀行であったのに、同行の船戸与一氏と著者の人柄からか、監視の人達も著者らと一緒になって笑う場面が多い。探検家でノンフィクションの作家であるが、面白おかしくがモットーの著者だけに読後感も明るい。本格的な探検紀行を望まれる方には、『西南シルクロードは密林に消える』をお勧めします。
Posted by ブクログ
まず一言…とても面白かった!!
初めはこじつけのようにミャンマー政府を江戸幕府に例えていて柳生やら高杉やら著者の想像力に圧倒された。ただ読み進めていくうちに確かにその通りだ…と納得していく自分がいた。
小ネタや自虐、他虐が色んなところに散りばめられていてクスクス、時には大笑いしながら楽しく読めた。ミャンマーの当時の状況も大まかだが垣間見ることができた。ぜひ著者の他のハチャメチャな旅行記も読んでみたいと思った。
Posted by ブクログ
著者は早稲田大学探検部当時に書いた『幻獣ムベンベを追え』でデビュー。本書は同部先輩の船戸与一が小説の題材旅行でミャンマーを訪れることになり、案内役として高野氏に同行を依頼し、その道中を面白可笑しく書き綴っている。
たいに隣接する反軍事政権のゲリラちくを何度も訪れ、ヘロイン栽培にも手を染めた著者、その内容を書籍にもして一部は英訳されていることから、ミャンマー入国許可は降りないと心配していたが、すんなりビザが発行された。逆に船戸氏にはなかなかビザが発行されない。理由は氏の書籍が反政府軍事団体に好意的な内容が多いこと。高野氏に、ちょっぴり不貞腐れる。
トヨタランドクルーザーで各地を巡るが、必ず謎のミャンマー人が同乗する(ドライバー、ライフル携行の兵士ではない)。彼らは謎の人物達を軍事政権(幕府)の隠密柳生一族と呼び警戒するが、一緒に旅を続けていくうちに、彼らが愛すべきお間抜け軍情報部と目に映るようになってくる。流石に中国国境付近の山中では、反政府民族ゲリラ「シャン州軍」が出没する危険がある。シャン人はシャン州からマンダレーに来るとき「ビルマ(ミャンマー)へ行く」と言う。シャン州軍は仙台伊達藩の反乱軍、カチン独立軍は加賀前田藩、ワ州連合軍は蝦夷松前藩と高野氏は例える。
実は家元もほぼ同じ時期の年末年始にミャンマーを訪れ、ヤンゴン、ニャウンシュエ(インレー湖)、マンダレーなどに立ち寄った、エーヤワディー川沿いのゲストハウスでは、現地の筒スカートロンジーを着用してタナカーを顔に施しデジカメで写真を撮ってもらった(家元、まず自身の姿を写真には撮らない、テロリストなので、笑)。
Posted by ブクログ
探検部の先輩・船戸与一と取材旅行に出かけたミャンマーは武家社会だった!二人の南蛮人に疑いを抱いたミャンマー幕府は監視役にあの柳生一族を送り込んだ。しかし意外にも彼らは人懐こくて、へなちょこ。作家二人と怪しの一族が繰り広げる過激で牧歌的な戦いはどこへ…。手に汗握り、笑い炸裂。椎名誠氏が「快怪作」(解説)と唸り仰天した、辺境面白珍道中記。
Posted by ブクログ
旅へ出ようよ、愉快な旅へ。何度も不法に入った国へ。民主化したと思ったら、また軍事政権に舞い戻る。うんざりするニュースしか聞かない国へ。…その昔、独立を目指して立ち上がった三十人の志士たち。筆頭アウン・サンは紋次郎ならぬ紋次。次席ネ・ウィンは高杉晋。時が下り暗殺されたアウン・サンは家康になる。二代目ネ・ウィン秀忠の世では大目付柳生キン・ニュン宗矩が実権を握る。軍直営の旅行会社。ツアーガイドは十兵衛ならぬ三十兵衛。何を監視しているのやら…クーデターから3年。続く混乱。憂いてばかりではなく、知ることが大事。
Posted by ブクログ
南西シルクロードは密林に消える、アヘン王国潜入記の後日譚もしくは副読本的に読むと、この2作品が立体的に捉えられる。ミャンマーという国の政府側の視点がメインなので。
単体でももちろんいつも通り面白い読み物
Posted by ブクログ
高野さんの冒険はいつだってワクワクさせてもらえる。そして面白い視点と解釈、というか噛み砕き方と味わい方。
どんな場所にいる人だって、どんな立場にいる人だって、袖触り合うも他生の縁。旅は道連れで、別れたあの人は今どうしているんだろうと遠くの空を思う。
Posted by ブクログ
船戸与一さんの取材旅行についていく中で、当時のミャンマーの政治状況を日本の江戸時代に例えて面白く説明してくれる正にエンタメノンフィクションになっている。
ミャンマーが識字率の高い読書大国とは驚いた。
この旅で関わった政府の人たちが属する派閥も高野さんの帰国後少ししてボスが失脚し大勢が逮捕されており、高野さんの旅はその瞬間のチャンスをつかんで行うことができているのだなと思う。
Posted by ブクログ
「高野秀行」の面白おかしいノンフィクション作品『ミャンマーの柳生一族』を読みました。
紀行は、昨年11月に読んだ「村上春樹」の『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』以来ですね。
-----story-------------
旅行ガイドは軍情報部!?
爆笑必至の珍道中記。
探検部の先輩「船戸与一」と取材旅行に出かけたミャンマーは武家社会だった!
二人の南蛮人に疑いを抱いたミャンマー幕府は監視役にあの「柳生一族」を送り込んだ。
しかし意外にも彼らは人懐こくて、へなちょこ。
作家二人と怪しの一族が繰り広げる過激で牧歌的な戦いはどこへ…。
手に汗握り、笑い炸裂。
「椎名誠」氏が「快怪作」(解説)と唸り仰天した、辺境面白珍道中記。
-----------------------
軽めの本が読みたくて本書を選択… ふざけたタイトルに目を奪われてフィクション作品だと思って買ったのですが、、、
実はノンフィクション作品… こんなエンタテイメント性のある旅行記は初めて読みましたね。
■前口上
■序章 ミャンマーは江戸時代
・ミャンマー柳生、おそるべし
■第一章 アウン・サン家康の嫡子たち
・柳生、仕事すべし
・幕府にたてつく人々
・幕府の豆鉄砲狩り
・ミャンマー幕府成立とスー・チー千姫
■第二章 柳生三十兵衛、参上!
・柳生三十兵衛、参上
・謎の男は「裏柳生」
・柳生一族、懐柔作戦
・かけがえのない「元麻薬王」を大切に
・スーパー外様「ワ藩」別件
■第三章 たそがれのミャンマー幕府
・中国がアメリカに見えた日
・武家社会はつらいよ
・鎖国の中の国際人
■第四章 柳生十兵衛、敗れたり!
・アウン・サン家康の風呂場
・柳生と老中の死闘
・ミャンマーのシャーロック・ホームズ
・柳生十兵衛、敗れたり
■終章 柳生一族、最後の戦い
・キン・ニュン宗矩はタカノを知っていた!?
・柳生一族の没落
■あとがき
■解説 椎名誠
2004年(平成16年)に著者の「高野秀行」が、冒険小説作家「船戸与一」の取材旅行に同行する形で、ミャンマーを旅行した際の様子を描いたノンフィクション… 解説の「椎名誠」が「快怪作」と表現したほどのユニークな辺境面白珍道中記です、、、
本書では、当時、軍事政権だったミャンマー政権を、武家社会で鎖国政策を取っていた江戸(徳川)幕府に例え、軍情報部のミャンマー人たちを、「徳川家」の隠密になぞらえて「柳生一族」と称しています… そして、「アウン・サン」は「徳川家康」、「スー・チー」は「千姫」となるという奇抜な発想により、一見すると、バカバカしい旅行記のように思えてしまいますが、時折、吹き出しそうになる場面を盛り込みながらも、ミャンマーの国政や国民性について、丹念に書き込まれており、ミャンマー入門とも呼べるべき作品に仕上がっていましたね。
識字率が高く読書大国であることや、都市部に住んでいても鎖国により外国人との交流機会はないし、他地域との交流がない辺境の少数民族が多いにも関わらず社交性に富んでいること等が、面白おかしい文書の中で、その理由等も含め鋭く考察されているのが印象的でした… こんな面白い紀行は初めてですね、、、
これまで遠く感じていたミャンマーが、少し近くに感じられるようになりました… 行ってみたいな。
Posted by ブクログ
いつものような、純粋に自分の探検道中記ではなく、探検部の先輩・船戸与一との取材旅行での記録。……というか、旅行中に出逢った現地の人たちとのやりとりをからめつつ、ミャンマーの政治や現状(2004年当時)を江戸時代に例えておもしろおかしく、かつ分かりやすく説明する内容でした。最近ではさらにクーデターが起こり、未だ激動の国であるミャンマー。その国の成り立ちを楽しく知る入門編として最適。
Posted by ブクログ
『世界の辺境とハードボイルド室町時代』の中で紹介されていたので読んでみた。テンポよくスルスルとあっという間に楽しく読め、ミャンマーの地理と民主化以前の国情をザックリ掴むのに役立つ。民主化が後退しつつある今、ミャンマーの今後について考えるために読んで損はない。
Posted by ブクログ
ーーアウン・サン・スー・チーをどう思う?オレは、彼女が政権をとっても国を運営することはできないと思うんだけど。(p.140)
ーー民衆がスー・チー千姫を熱狂的に支持している理由は……彼女がアウン・サン家康の娘だからだ。……このように幕府対倒幕派は……「お家騒動」の側面もあるのだ。そして、そのいちばんの証拠は、スー・チー千姫が少数民族問題について、何一つ具体的な提案をしておらず、少数民族のリーダーたちとそのテーマで議論をすることすら拒んでいる現状だ。(p.66)
なるほどねー、と思った。
何の知識も先入観もなく(映画『ビルマの竪琴』を小学生の時に見たくらい)「なんかまたミャンマーがよくニュースに出てくるなぁ。よし、読んでみるか」くらいの感覚で読んでみた。結果、大変に面白く、勉強になった。
かつて、スー・チー氏は自由の女神みたいに報道されていた。のに、国のトップに立つや否やロヒンギャ問題で叩かれるは、カレン族の動きは不穏だわで「わけわからん。何でそうなる?」と思っていた。そういう理由だったか。
つまり、彼女にはアウン・サンの孫娘という血筋と西側の思想はあるけれど、ミャンマーの多民族国家を多様性を保ったままに舵取りするプランは最初からなかったわけね。本書は15年前に初版が出てるけれど、今の混乱ぶりを見ると、現在も冒頭の指摘とさほど変わらない感じなんだろう。
大手新聞や国営放送は「民主主義の危機でござる‼︎」と喧伝するのに忙しそうだけれど、内幕のところは語ってくれない。セイギノミカタを演じることでお金もらってるのだから仕方ないけど。
Posted by ブクログ
以前同著者の「アヘン王国潜入記」を読み。
この本も読みたいと思ってました!
今回は作家船戸与一氏と取材旅行で入国。
高野氏自身に危ない事も特になく、旅行は進んでいきます。
ミャンマーの軍事政権を日本の江戸幕府のようだと、独自の視点を用いて、ユーモアたっぷりの文章で書かれています。ミャンマーの人は鎖国のような国でありながら意外と国際的だったり、民族や宗教が多様であったり、読書家が多いとか、現地の人の暮らしが垣間見れるのも良いです。
高野さんの冒険記は、謎の国が気になる私の好奇心を大いに満たしてくれます!
Posted by ブクログ
ミャンマーに興味を持った人が最初に読む本としてお薦め。
世界の秘境ハンターとしてすっかり有名になった著書が、船戸与一の取材旅行の案内にとしてミャンマーに向かう。
タイトルがいかにも怪しげなのはいつもの癖。軍事政権下で鎖国政策を取る、ってことは開国前の日本とそっくりじゃないかということで、ミャンマーを江戸期日本に見立てて説明していくのがこの本の趣向。
取材は10数年前のこと、ジャーナリストビザはなんとか貰えた、ただし条件として軍情報部の旅行会社のお膳立てに従うこと。情報部の元締めキン・ニュンは首相でもある。彼のような人物を日本で探すと、江戸初期の柳生但馬守が一番しっくりくる、小説やドラマの中では裏柳生はおなじみだし、、ってなことで、すべてが江戸時代に例えられていく。
正直、最初の方はちょっと苦しい例えが多いというか、ちょっと滑りがちのような気がするものの、だんだんこれ以上の方法は無かったように思えだす。
というのは、やたら複雑な民族問題、領土紛争の話を、固有名詞を次々に出されて説明されても日本人にはまずついていけない。それがカレン島津藩、シャン伊達藩、タン・シュエ家光みたいな書き方してあると、すんなりイメージできてしまう。そして最後にはどんでん返し。
Posted by ブクログ
面白かった、為になった点 3点。
p137
日本で働くミャンマー人がストレスを感じるのは上司に意見を聞かれること、つまり発言の自由。
p151
ミャンマー人の社交性はどこで身につくのか。
p158
答えは国内。ミャンマー国内で様々な宗教・民族の人="異国"の人と接するため。
p171
パンロン条約締結後アウン=サン亡くなる。その後地方を押さえるために軍事独裁体制を築いたのがネ・ウィン。
Posted by ブクログ
内容(「BOOK」データベースより)
探検部の先輩・船戸与一と取材旅行に出かけたミャンマーは武家社会だった!二人の南蛮人に疑いを抱いたミャンマー幕府は監視役にあの柳生一族を送り込んだ。しかし意外にも彼らは人懐こくて、へなちょこ。作家二人と怪しの一族が繰り広げる過激で牧歌的な戦いはどこへ…。手に汗握り、笑い炸裂。椎名誠氏が「快怪作」(解説)と唸り仰天した、辺境面白珍道中記。
今僕が一番偏愛している高野さんは、とにかく色々な冒険をしているのですが、場所がとか世界情勢がという以前に、現地の人達に対する愛情がほとばしり出ていて、笑いながらもとってもジンとくる文章を書くお方です。今回も行動を共にした政府の監視役と思われる人々とも仲良くなって、最終的には読んでいる方が名残惜しくなる感じでした。
ミャンマーの情勢を徳川幕府になぞらえ軍部を柳生一族に置き換えて日本人に分かりやすく説明をしてくれていますが、残念ながら僕は日本史にあまり興味がなくて残念でした。これそこに精通している人ならもっともっと楽しめます。
Posted by ブクログ
辺境作家の高野秀行氏と、早大探検部の先輩で小説家の船戸与一氏によるミャンマー珍道中。船戸氏がミャンマーを舞台にした冒険巨編『河畔に標なく』を執筆するにあたり、取材旅行の通訳兼ガイド兼雑用係として、ミャンマーに詳しい高野氏を指名したのが旅のはじまり。
なんとなくミャンマーに住む柳生一族の末裔の話かと、勝手に想像しながら読み始めたが、全く違ってて最初から戸惑ってしまった。高野氏がミャンマーの軍事政権を徳川幕府に、そして取材旅行の監視役であるミャンマー国軍の情報部の人たちを柳生一族に、勝手に例えただけだったのだ。でもこの例えが絶妙で軍事政権と反政府ゲリラ、そしてアウンサン親子との関係を理解するのに、新聞なんかより格段にわかりやすい。
しかし旅程的にはフツーの取材旅行なのだが、高野氏が参加した時点でなぜか面白くなってしまうのは、いつも通りさすが。しかも今回は、同行した柳生一族のポンコツぶりとの相乗効果で、想像以上の面白珍道中だった。それにしてもこの作品と船戸氏の小説、どちらの方が売れたのかね?
Posted by ブクログ
2004年にジャーナリストの高野氏と作家の船戸与一がミャンマーに取材に行き、経験したいろいろ。ミャンマーの政治について、わかりやい例えに沿って話が展開されていく。
Posted by ブクログ
作者の高野秀行が船戸与一のお供でミャンマーを旅したときのエピソードや出来事をおもしろおかしく描いた本である。
当時のミャンマーの政情を徳川幕府と外様大名に見立てて説明し、この旅についてくる情報機関を柳生一族になぞらえたもので、それが題名になっている。
周辺国から非合法にミャンマーに入国した経験が豊富な作者が、真正面から入国し旅している。本書は、作者が周囲の人々の動向をおもしろく描くだけではない。ミャンマーは最貧国ながら識字率が高いという実態を貸し本屋や読書する少女を観察することで示すなど、現地の人々を見る視線に確かなものもある。
故人となった船戸与一の人となりが垣間見れるのも興味深い。高野秀行さが十分楽しめる本である。
Posted by ブクログ
誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをやる。そんな辺境作家の
著者が、早稲田大学探検部の先輩でもある作家・船戸与一の取材にガイド
役として同行したミャンマーでの珍道中エッセイである。
軍事政権下のミャンマーを日本の江戸時代に模して政治背景を解説している
ので、少々複雑なミャンマーの勢力構図も分かりやすい。
そして、非常に怪しい日本人ふたりの監視役が軍情報部。これが本書の
タイトルになっている柳生一族なのである。
でも、全然怖くないし、これが軍政国家の情報部なのかと思うほどの
へたれぶりを発揮するのだ。
ミャンマーに非合法入国すること8回、時にはアヘン栽培の地に半年も住み
着き、その栽培・収穫に携わった著者だけあってミャンマー情勢の分析には
鋭いものがある。
でも、お堅い話ではなく、かなり砕けた書き方をしているのですんなりと
頭に入って来る。
著者も著者だが、その上を行くのが船戸与一だ。あのミャンマーで、誰彼
構わず「スー・チー女史は好きか?」と聞くわ、いきなり麻薬王に会いに
行くとか言い出すわ。傍若無人にもほどがある。
本書では何が怖いって船戸与一が一番怖かったよ。
Posted by ブクログ
ミャンマーの辺境•ワ州に世界で初めて長期滞在した経験を持つ辺境ノンフィクション作家の高野秀行さん。その経験を買われたのか、今回は冒険小説作家の船戸与一さんの付き添いとして“合法的に”ミャンマーを訪問。二人は早大探検部の先輩後輩という関係だったのは驚き。
高野さんらしくユーモラスなエンタメ系ノンフィクションに仕上がっている。ミャンマーを江戸時代の日本に見立て、国軍と情報部を徳川幕府と柳生一族と対比して描いているところは、わかりやすくて面白い。アウンサンスーチーは千姫かよ(笑)
こういった例えは後に『謎の独立国家ソマリランド』や『イラク水滸伝』でも用いられ、いまや高野さん流の表現手法として定着している。
また、奔放で豪快な先輩•船戸与一を若干ディスりながらイジっているのも笑える。取材メモなど一切とらずに、「タイトルさえ閃いたら小説書ける」と宣う船戸さんもやはり大作家なんだなぁと。ホームズが好きという高野さんの意外な趣向も知れてよかった。多様な民族と宗教、そして読書好きな人が多いという意外な一面もあるミャンマー。歴史や国民性など勉強になった。
本書と合わせて読みたい作品達↓
『ビルマ•アヘン王国潜入記』高野秀行
『西南シルクロードは密林に消える』高野秀行
『河畔に標なく』船戸与一
『マヌサーリー』ミンテインカ
Posted by ブクログ
ミャンマーの政治事情を、徳川幕府にみたてて
面白おかしく綴った旅行記。
いつもの高野節で安定の面白さ。
現在の軍事政権になっているの
はこういうことだったのかと納得してしまった。
Posted by ブクログ
基本強引に徳川幕府に繋げていくのでちょっと違和感。親しみを持って例えているのは分かるがかえって混乱した。
コンデンスミルクをたっぷり入れたチャイ、飲んでみたい。その茶店の風景と共に味わったら楽しいだろうな。電気が部分的にしか通っておらず、夕陽が沈むと街が赤く染まり闇に包まれていく、終末を迎えたかのような感覚というの、ちょっと興味がある。人々の温かみや、少ない娯楽を堪能しながらゆっくりと時間が流れているミャンマーに想いを馳せた。
お酒の席での話なんかは、人種や言葉や育ち方や住むところが違っても、おじさんはおじさんでみんな一緒なんだと思えて面白かった。
Posted by ブクログ
普通の人は行かないようなところばかりをわざわざ選んで旅をする、辺境作家の高野秀行。コンゴへ怪獣を探しに行ったり、ミャンマーへアヘンを栽培しに行ったりしていた彼が、早稲田の探検部の先輩後輩のよしみで、大作家の船戸与一からミャンマーへ一緒に行こうと誘われます。ミャンマーに合法的に入ったことがなかった高野さん。絶対にブラックリストに載っていると自負していたのに、意外にも入国は簡単に認められ、駄目だと言われたのは船戸さんのほう。作家としての知名度の差らしく、高野さんガッカリ。なんとかふたりとも入国できることになったものの、ミャンマーの某旅行会社を必ず使うようにと指定されます。これがなんと旅行会社に姿を借りた軍情報部、高野さん曰く、まるで柳生一族。ワケのわからん日本人に勝手をさせてたまるかということで、ガイドのふりをした柳生一族が監視役として同行するのでした。高野さんが行けば何でも珍道中に。船戸さんの酔っぱらいぶりも楽しい旅行記。