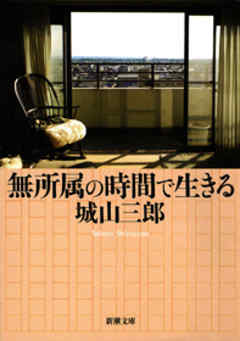あらすじ
どこにも関係のない、どこにも属さない一人の人間としての時間──それは、人間を人間としてよみがえらせ、より大きく育て上げる時間となるだろう。「無所属の時間」を過ごすことで、どう生き直すかを問い続ける著者。その厳しい批評眼と暖かい人生観は、さりげない日常の一つ一つの出来事にまで注がれている。人と社会を見つめてきた作家の思いと言葉が凝縮された心に迫る随筆集。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
数々の重厚な小説を残した城山三郎の大変楽しいエッセイ。「無所属の時間」とは必ずしも定年後の時間ではなく、組織に属さない作家という立場を意味しているようだが、還暦を控えて読むのは丁度良い。20 年以上も前の文章なのに古さは感じない。
Posted by ブクログ
久しぶりの城山さんのエッセイです。ここに書かれているエピソードが正に当てはまるステージに立ちつつあるので、そこここで気になるくだりがありましたね。とはいえ、よほど気持ちを本気で入れ替えないと「無所属の時間」は過ごせないでしょう、私の場合は。しばらくぶりに「毎日が日曜日」を読み返しますかねぇ。
Posted by ブクログ
■時間
A.4 つの時間
・真珠の時間:仕事のアイディアを練る、深夜の時間
・黄金の時間:仕事上のゴールデン・アワーとなる、9 時頃から1 時過ぎまでの時間
・銀の時間:資料調べや下書きなどをする午後の時間
・珊瑚の時間:新聞や郵便物に目を通したり、仕事とは関係のない本を読んだりする、夕方以降の時間退職後の自由時間の大きさにおびえる人もいるが、こうして分割すると、1 日という単位も相手にしやすい。
B.戦後最大の財界人、石坂泰三は、出張の際、「空白の1 日」を日程に組み込んでいた。そしてその1 日を、どこにも属さない1 人の人間として、ただ風景の中に浸っていたり、散歩したりして過ごした。こうした無所属の時間は、人間を人間としてよみがえらせ、より大きく育て上げる時間といえる。
Posted by ブクログ
城山三郎。品格ある日本人。読んだ後、とても上質なコーヒを飲んだ後の感覚。とても自然体に、求めない生き方、自然体の生き方。もっと城山三郎の本をまた読みたくなった。「この日、この空、この私」といった気持ちで行きたくなったという、その一節、同感できた。自然体に生きる重要性が日増しに強くなってきた。相手に「求めない」も同じであろう。
Posted by ブクログ
随筆とエッセイの違いは解らないが城山三郎と一緒に居ると肩凝るだろうって事ははっきりしてる。作中「毎日が日曜日」が何度となく登場。再読してみようかな
Posted by ブクログ
このところ城山三郎のエッセイを、手に取る機会が続く。
「無所属の時間」とは、まさに読書子の現状にピッタリと、15年ぶりに再読。
「無所属の時間」とは、どこにも属さず、肩書きのない状態を指すと思うが、著者は「人間を人間としてよみがえらせ、より大きく育て上げる時間ということではないだろうか」と、積極的に捉えている。
著者は、「この日、この空、この私」と所々に綴っている。
人生は考え出せば、悩みだせば、きりがないから上記のような気持ちで生きるしかないのではないか、と。
諦念という意味ではなく、「その一日こそかけがえのない人生の一日であり、その一日以外に人生は無い」「明日のことなど考えずに、今日一日生きている私を大切にしよう」という積極的な意味だとも。
戦争を体験した著者だからこその、言葉だろう。
Posted by ブクログ
久し振りにエッセイなるものを読んでみた。
著者の日々の生き方、考え方に触れることができて面白かった。
自分も社会人になってから、一度だけ無所属の時間を1ヶ月ほど過ごしたことがあり、そのとき感じた解放感、本来の自分に戻れた安心感とちょっぴりの不安感、そんなことを思い出した。
「この日、この空、この自分」…。自分に立ち返る時間も必要ということ。
Posted by ブクログ
身辺雑記のような城山三郎のエッセイ。妻に対して「〇〇させる」って表現してたり、巷のかしましいご婦人たち、女子高生たちへのミソジニーっぷりとか、旧人類男性だなと思うんだけど、そうした強気ないっぽうで彼の日常や心象のなかにやさしさや弱気やシャイっぽい部分が存在する。こんな男っていいかもね、とも思った。
本書は「無所属の時間で生きる」という。「無所属の時間に」とか「無所属の時間を」じゃないんだよなあ。そうすると恒常的に無所属という感じがするかなあ。確かに彼は、フリーの文筆家だからこういう表現になるということか。いずれにせよ、無所属の自分だけの時間でこそ、生きる、生かされるということだろう。
そもそも手に取ったのが、「組織の歯車たちよ、そこから離れた時間(余暇とか退職後)のことも考えよ」といったことをきわめて常識でうるさ型のジジイが教訓的に語ってくださるのかと思ったからだった気がするんだけど、そういう本じゃなかった。彼自身も、経済小説の先駆者という認識から商社や銀行など企業上がりの人かと思っていたけど、そうじゃなくて大学教員から文筆家に転身したという人だった。びっくり。
そういえばこの人、『そうか、君はもういないのか』とか、確かに彼なりの優しい気持ちをもった人みたいだもんな。
改題前の書名には「この日、この空、この私」とついていて、この言葉が書中にも何度か出てくるんだけど、この言葉もやさしくさわやかでいい言葉だ。実は「この日」も「この私」も結局はいまそのままいるしかない、連続性の範疇のことだと思う。でもこれに、「この空」という言葉が加わって三拍子そろうと素敵なフレーズになるんだよね。そらを見上げる心の余裕とか、そこから目に入る空の広さや高さ、青さを感じさせる。
Posted by ブクログ
来年からは無所属。
フリーランス、プータロー、フリーター。
1つ目以外の言葉の弱さはなぜなのか。
どれにせよ、どう生きるか、どう在るかが
充実につながる。
絶望と希望は常に心の中に。
Posted by ブクログ
戦後の財界人、石坂泰三は、幾日か出張するとき、どこにも属さない一人の人間として空白の一日を日程に組み込んだ。著者は「もう、きみには頼まない」の中で、その時間の大切さを書いた。
著者が文学界新人賞をもらって間もないころ、ベテラン編集者から言われたことは「自分の世界ができるまでは、テレビにはなるべく出ないことです。雑文なども書かないことです。」
友人が「四十代の終わりからは、もう死に体も同然さ」の言葉を聞いて、さまざまなケースを取材し、死に体になった後の人生を探ったものが「毎日が日曜日」。
Posted by ブクログ
無所属の時間の中に成すこともなく置いておかれるのか、無所属の時間でどう生き直すか生を充実させるか、を探ってみたい。
一日の時間帯に名前をつけ、何をして過ごすかを決める。急にでかけることが癖になっている。
作家として、もともと多く持っていた自由時間の過ごし方、参考にさせていただきます。
Posted by ブクログ
一日一日を私はどのように過ごしたいのか考えるいいきっかけをもらった。変わりない毎日を送っていると思い込んでるけど、実は一日一日違うんだよなあ。いろんなことを私は見過ごしているような気がする。
一日に一つでも愉快だと思えることがあれば、この日私は生きたと思える。もしどうしても愉快なことがひとつもなければ、奥の手がある。寝る前に好きな本を読んで眠りにつくのだ。この『一日一快』の考え方に気持ちが楽になった。人生もっと楽しまないと♪
Posted by ブクログ
毎朝、所属する時間に向かう通勤時間で読む「無所属の時間」。。
結構しんみりするときも、
スイッチ入ってみるときも、
所属する時間には裏切られたりもするけれど、
自分自身である時間を作ってみようと思う、一冊でした。
Posted by ブクログ
故城山三郎氏は私の好きな作家の一人である。氏が描く男はどれも漢であり格好いいのだ。
本書は、城山氏自身が「無所属」というキーワードを軸に書き溜めたエッセイである。城山氏は約10年間の大学教員時代以外はフリーの経済作家として、いわば社会的に無所属の立場で過ごされてきた方である。
本書にて城山氏の造語が二つ、紹介されていた。
ひとつは「一日一快」。一日にひとつでも、爽快だ、愉快だと思えることがあれば、「この日、この私は、生きた」と自ら慰めることが出来るということである。私も仕事などで凹み、ぐったりして帰宅することがあるが、そんなときに道端に咲く花が素敵だったり夕焼けが綺麗だったりすると、爽快に感じて疲れを忘れることがある。
もうひとつは「珊瑚の時間」。一日を振り返って、どう見ても快いことがない場合の奥の手という位置付けである。晩餐後に短時間でもよいから寝そべって好きな本を読み、眠りに落ちていくというものであり、私も実践している。「今日は何ひとつ良いことがなかった、何をやっても上手くいかなかった」という日でも好きな本を読んだり、DVDを観賞したりしながら酒を飲むという至福の時を過ごすことがある。今後、私も「珊瑚の時間」と呼ぼう。
本書で手に取ることの出来る城山氏の人柄の温かさは、生き馬の目を抜くような経済小説を書いてきたとは思えないほどである。読んでいてホッと心温まる内容だった。今度、久しぶりに城山氏の経済小説を読んでみよう。
Posted by ブクログ
昨年他界された城山爺さんによる、生き方にまつわるエッセイ集。流れるように読みやすくも刺さる文体は、読んでいて心地よい。けれど、まるで自分の父親の話を聞いているよう、というのも2~3歳程しか違わないから、かもしれない。
渋沢栄一をモデルにした小説や石田禮助についてのノンフィクション等、氏のいわゆる経済小説なるものは、学生の頃には結構読んでいた。でも年を経ていわゆる「偉人伝」よりも「市井の名もなき人々の物語」の方に興味が移ってきたからか、氏の本からは遠ざかっていた。追悼の意味で読んだけれど、心地よすぎて実は何も残らないことが分かった(笑)。まー私のまわりには、自分も含めて結構「無所属な人」が多かったりするので(笑)、参考まで。(←何の?)
Posted by ブクログ
無所属であるということは、自分を直に見つめる機会にあるということである。
いかに生き、いかに精神的な満足(あるいは不満足じゃない)を得られるのか…
作家となり数十年来、無所属であることを節目節目で振り返る。
三十代、四十代、五十代、六十代…
一日の中でも自分の時間をいかに生きるかで、それは大きく変わるのだから。
“ほぼ完全な無所属の時間の中に、同じように居てどう生きたか、自分をどう生かしたか。
その差がはっきり顔つきに出てくる”
のだから、それはとても怖いものだ、とも著者は言う。
“この日、この空、この私”
一日一快、その日生きたと思えるような、そんな生き方ができればよいのだろう。
自己を客観的に見つめ、真っ当な組織社会との接点に己の生き様を映し出そうとする、
そんな珠玉のエッセイだ。