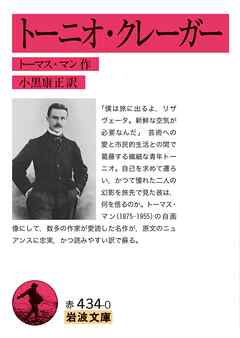あらすじ
「僕は旅に出るよ,リザヴェータ.新鮮な空気が必要なんだ」 芸術への愛と市民的生活との間で葛藤する繊細な青年トーニオ.自己を求めて遷ろい,かつて憧れた二人の幻影を見た彼は,何を悟るのか.トーマス・マン(1875-1955)の自画像にして数多の作家が愛読した名作が,原文のニュアンスに忠実,かつ読みやすい訳で蘇る.
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「人生の過ごし方」を深く考えさせてくれる本だと感じました。
主人公は芸術家として人と違う存在でありながらも、そのことで人から一目置かれると自らが思う姿が描かれています。
また、嫉妬の場面や、人に冷たくしてしまう場面などを読みながら、「自分にも似たような動きがある」と感じました。結局、人は同じような感情や行動を繰り返しているのだと気づかされます。その描写に共感。
この本を通じて、自分を少し上から見つめるような視点を持てるのではないかと思います。
Posted by ブクログ
久々の岩波文庫。最近引っ越した家の近くに小さな小さな個人経営の書店があり、岩波文庫も揃えていたので、せっかくだからと薄くて読みやすそうなコイツを読んだ。浅はかな理由だけどしょうがない。
解説で三島由紀夫らが影響を受けたと書かれているあたり、ひと昔前はかなり広く読まれていたのだろうか。芸術家とその対極としての一般市民、そのどちらにもなり切れない自分という、存在の置き場がない不安みたいなものを、芸術を愛する男の青春という切り口で描く物語。
市民社会に疎外感を覚えてしまう少年時代、芸術家になりきれないもどかしさを覚える青年時代、そしてその悩みが昇華されてゆく終盤。そんな物語展開。とりわけ、終盤は気高さある孤独を受け入れる主人公が描かれるのだが、この明るくも哀しくもある終わり方が、「世界のどこかで自分のように孤独と戦っている人がいる」として、たくさんの人の心を励ましたのかもしれない。「物語に救われた」って現象は、得てしてそういうものなのかもしれない。私も、この本ではないが、物語に救われたことがあった。
私は、大学時代、大学院に進んで学問の道を……などと考えていたが、結局挫折してしまい、就職もせずフラフラしていた時期があった。主人公の葛藤とは種類も程度も異なるものではあるが、何ものにもなりきれない自分、という不安や悲しさのようなものは、その一端が少しは理解できる気がする。
他方、トーニオ・クレーガーのような生き方はしておらず、普通に手堅い仕事に就職して、結婚して、子どもを授かった。悪い意味で、これからも小市民として普通に暮らしてゆくのだと思う(不幸なイベントが起きないと楽観しているわけではないが)。そんな人生は世界に溢れていて、それを肯定する声はいくらでもある。でも、そうした声に救われたと感じたことも、自分の人生は正しいと感じたこともない。学問の道など進んだところで、私にはそぐわなかったと思うけれど。
この物語は二つの世界のどちらにも属せない孤独を一心に受け止める主人公の物語だ(と思う)が、結局世界は二つじゃないし、類別したって境界線は実際にはないのだから、程度の差はあれどんな生き方をしてもそれをしっかりと受け入れるしかないのだろう。自身の生き方を、自身で選んだ道としてにがっつりと抱き留めた主人公。対する自分は、成り行き任せの安直な道として人生を送っていないか。人生を送り流していないか。そんなことを思わなくもないけど、まぁ特定の生き方を批判しているような物語でもないし、この本の感想としては測わないかもしれない。
Posted by ブクログ
主人公トーニオの、自己矛盾に起因する愛と孤独を理解するのが難しく、いま一歩踏み込んで読めなかった。
・トーニオはリザヴェータから「迷子になっている市民」と言われたように、市民的なものへの憧れ・愛を捨てきれず、一方では、「愛されるなんて、吐き気を催しながら虚栄心を満足させることだ」などと考え、自分を理解し、愛してくれるマクダレーナ(黒い瞳の少女)には見向きもしなかった。さらには、インゲボルグ(青い瞳の少女)には、好きと言ってほしいなどと思っていて、彼の孤独の複雑さがうかがえる。
・望むような愛情が返ってくることはないと知りつつ、彼は結局、市民への愛情を捨て切れなかった。それでも満足していた?「この愛情をけなさないでください、リザヴェータ。それなりにまともで、実り豊かなものがあります。そこには、憧れがあり、気がふさぐような妬みがあり、少しばかりの蔑みがあり、純潔この上ない歓喜があるのです。」ここはこの小説の核心的な部分だと思うが、いまいち理解・共感できず、この小説に踏み込めないでいる。これは希望なのか諦観なのか?純潔この上ない歓喜とは何か?なぜ苦しみつつも、黒い瞳の少女を選ばなかったのか?