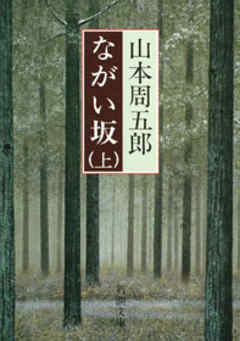あらすじ
徒士組という下級武士の子に生まれた小三郎は、八歳の時に偶然経験した屈辱的な事件に深く憤り、人間として目ざめる。学問と武芸にはげむことでその屈辱をはねかえそうとした小三郎は、成長して名を三浦主水正と改め、藩中でも異例の抜擢をうける。若き主君、飛騨守昌治が計画した大堰堤工事の責任者として、主水正は、さまざまな妨害にもめげず、工事の完成をめざす。
...続きを読む
幼いころ、下級武士だった父の卑屈な態度を見て、「出世してやる!」と誓った小三郎は、文武に努力を重ねて階段を上がっていきます。しかし、成長を重ねるにつれ、ライバルや師と出会い、社会への視野を広げることによって伸びる力を養い、才能を認めてくれる見えない力によって「人生の長い坂道」を一歩一歩上がってきたのだと気付くことになります。
若い藩主から絶大な信頼を受け、藩政改革の主役に躍り出た時、自分が何に支えられてきたのか、誰が自分をこの地位に押し上げたのかを振り返り、出会ったすべての人が自分の血となり骨となったことに気付くのでした。
私はこの小説と出会って、男は行動しなくちゃいけない!と思い、しかし、時には回り道も必要だと胸に刻んだのでした。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
人はときに、いつも自分の好むようには生きられない、ときには自分の望ましくないことにも全力を尽くさなくてはならないこともある。生き方に共感出来る。
Posted by ブクログ
評価は5。
内容(BOOKデーターベース)
徒士組という下級武士の子に生まれた小三郎は、八歳の時に偶然経験した屈辱的な事件に深く憤り、人間として目ざめる。学問と武芸にはげむことでその屈辱をはねかえそうとした小三郎は、成長して名を三浦主水正と改め、藩中でも異例の抜擢をうける。若き主君、飛騨守昌治が計画した大堰堤工事の責任者として、主水正は、さまざまな妨害にもめげず、工事の完成をめざす。
常に謙虚で常に自分を見つめ直しゆっくりだが確実に人生を歩んでいく主人公。辛いことがあると人を責めるよりもまずは自分の中で消化し、そして自分への反省とする。
そんな主人公の考え方は昔の作家で昔の話だから・・・と簡単にかたづけられない。
現代のストレス社会に生きる自分にも必要な心の持ち方や心の逃がし方が描かれている。
久しぶりに読み応えのある本に出逢った。と感じた。
Posted by ブクログ
「“人生”というながい坂を人間らしさを求めて、苦しみながらも一歩一歩踏みしめていく一人の男の孤独で厳しい半生を描いた本書は、山本周五郎の最後の長編小説であり、周五郎文学の到達点を示す作品である。」(裏表紙より)
一人の人間の行く道の重さ、苦悩が描かれていますが、それを完遂する要因とは何なのか?を学んだ気がします。
「『――なにごとにも人にぬきんでようとすることはいい、けれどもな阿部、人の一生はながいものだ、一足跳びに山の頂点へあがるのも、一歩、一歩としっかり登ってゆくのも、結局は同じことになるんだ、一足跳びにあがるより、一歩ずつ登るほうが途中の草木や泉や、いろいろな風物を見ることができるし、それよりも一歩、一歩をたしかめてきた、という自身をつかむことのほうが、強い力になるものだ、わかるかな』
小三郎はじっとしていて、やがて『よく考えてみます』と答えた。人の一生はながい、という言葉は、小三郎に強い印象を与えた。」
「『人間というものは』と宗岳も茶碗を取りながら云った、『自分がこれで正しい、と思うことを固執するときには、その眼が狂い耳も聞こえなくなるものだ、なぜなら、或る信念にとらわれると、その心にも偏向が生じるからだ』
小三郎は訝しげな眼つきをした。
『そうさな』と宗岳は茶を啜ってからゆっくりと云った、『俗な譬えだが、人間には食物にも好き嫌いがある、或る者には焼魚がもっともうまいし、他の者には魚は煮るのが本筋だと思う、また料理人は魚によって区別をし、これは焼くものこれは煮るものと、流儀によっておよそきめてかかるようだ、それが固執であり、その固執は人にかたよった考えをいだかせる、魚に限らずどんな食物でも、自分でうまいと思う料理法で食べるのが正しいので、料理人の主張だからこうして食べよう、と思うのはすでに心が偏向しているからだ』」
「見た眼に怠け者のようだからといって、しんじつ怠け者であるかどうか、誤りのない判断が誰にできるだろう。あらわれたかたちに眼をくらまされてはいけない、人の評にひきずられてはならない」
「主水正は『世間』というもの、そこに生きている『人間』たちを知るようになった。彼は江戸屋敷にいるあいだに、多くの人と接し、その生活をみてきた。人世は単純ではないし、人の生きかたも単純ではない。善悪の評価でさえも正当であるよりも、そうでない場合のほうが多いし、それを是正することが殆ど不可能で或る事も知った。」
「――人間の一生とはどういうことだろう。主水正はあたたかい夜具の中で、熱いほどのななえの体温に包まれながら思った。死ぬまで生きる、というだけなのか、それともなにか意義のあることとをしなければならないのだろうか。
――もしも後者だとして、意義のあるというのはどんなことだ、と彼は続けて思った。殿は五人衆の握っている利権を奪回しようとなすっている、堰を設けて三万坪の新田を拓くのは一着手だ、けれども堰は永遠に殿の御意志を支えるものではない、殿はいまでもお首をねらわれているし、長寿を保たれても百年のちはもうこの世には在られない、多額な資金と人間の労力を注ぎ込んだあの堰も、いつかは崩壊し、べつの堰堤が造られ、もっと合理的に灌漑ができるようになるだろう、それは三歳の童児にも想像のできることだし、いまおれたちが、泥まみれになってやっている仕事もばかげた徒労ではないだろうか。」
Posted by ブクログ
下級武士に生まれた主人公が、少年の時に人間として目覚めて、成長していく。読売新聞ゴローさん紹介の本。ドンドンと引き込まれます。サラリーマン必読書。
Posted by ブクログ
会社の上司に勧められて20代の頃読んだが、周五郎作品は若い世代には少し難しい(3回読み返した)
主人公、主水正に自分を重ねて読むうち引き込まれていった。
上を目指すサラリーマンにはバイブルとなる山本周五郎、最後の長編作品
Posted by ブクログ
ある一つの出来事をきっかけに自分の人生、世の中の不条理を変えようと一心腐乱に進む主水正があるとき、周りからの羨望・嫉妬、期待や仕事に対する重圧に耐えかね、恩師の谷宗岳に相談した時、谷から「お前が自分で進むと決めた道ではないか、その道へ進んだときからもう逃れることはできない」と言われた言葉が印象に残った。自分も普通の会社に終身雇用を期待して就職したのではなく、自分の力で仕事を得て、食べて行こうと決意し、その道を歩み始めた。今は日本の会社はいるが、あくまで契約社員としてのプロの自覚を持って行動するべきであると思う。辛いがそういう道を選んでしまったわけで自分も主水正と同じように後戻りはできないのだから。
自分の進路や目標に悩んだときには、試行錯誤しながら前へ進む彼の姿をまた読むべきだと思う。
Posted by ブクログ
主人公が子供の頃に、彼にとって山や川と同じように不動の存在であった橋が土地の所有者である城代家老の都合で取り払われてしまった。そして、その際、川を迂回するよう告げた小使いへぺこぺこしていた父親を見て小三郎は二度とこんなことのないよう決心し、学業に剣術に明け暮れ平侍の子にはない出世を果たしていく。
彼は同じ藩に暮らす人たちには心底親切でいい街づくりに明け暮れていく。自分の進む道を信じて突き進む。納得のいかないことも人から言われると客観的に考えてみる。しかし、実家の家族からの頼みごとはじっくり考えることなく甘い戯言と切り捨ててるように見える。
彼にとっては父親は進歩することを諦めた惨めな存在で、それに対する反発が怒涛の勢いで出世を果たす原動力となっている。
僕は父親のように釣りなど小さなよろこびを大切にする暮らし方もいいと思うが、出世していく息子を当てにする態度はみっともないと思う。
小三郎の生き方も自分の信じる道を突き進むことで、彼の価値観とは相容れない父親の価値観をないがしろにする側面が気に入らない。
どの観点から評価しても完璧な生きかたなんて存在しないのはわかっているし、自分のものさしを信じて人の評価は消化しときたま反芻しながら突き進むしかないと今の僕は考えている。
だけど、なんだか寂しく感じた。
Posted by ブクログ
最高。主人公には正直ついていけない部分が多すぎるのだけれど、それはそれで、男としてそういうこともあるよね。山本周五郎、イイとは聞いていましたが、これほどイイとは!瀬尾まいこは女の本でしたが、この本は男なら読まねばならないでしょう。
Posted by ブクログ
(01)
普通には時代小説として読まれるだろう。また、文庫版の奥野健男の解説にあるようにビルドゥングスとして、また現代的にはサクセスのコツを含むビジネス小説として読まれるのかもしれない。
しかし、本書は文体論としても問題的なあり方をしており、驚きをもって読まれる。例えば、時系列あるいは空間系列に従うシークエンシャルな文脈の流れにあって、文脈から離れた回想や記憶の手がかりが、けっこう生々しい(*02)タイミングで突然に、普通のコンテクストからゆうとありえない角度からぶっこまれてる。こうした違和感のある文体、いってみればアバンギャルドな文体について、現代文学史の中では、川端康成の意想と比較しても面白いと思われる。
(02)
生々しさという形容から類推すれば、藩政時代の武家のエロスを会員制クラブあるいは秘密結社さながらの、魔窟な方面から描いてしまう件についても寡聞にしてちょっと知らない。戦国時代の女忍者や、中世の貴族、近世の町民や庶民(*03)といった典型ならあるあるなパターンであるが、そうではない時代と階級のエロスを描いている。主人公の夫婦関係や性愛のあり方についても異数(*04)といえるだろう。
(03)
匿名と顕名のありかたにも独特の徹底ぶりが発揮されている。つまり、名のない者が出てこないことの煩雑さのうちに物語が紡がれている。植物学の牧野富太郎が著者に範を垂れた雑木(*05)の有名性については有名なエピソードなのだろうか、本書での人名に対する偏執ぶりもかなり異様な部類に入るだろう。
この煩雑な顕名性は著者のポリフォニカルな語り口との関連で読まれてよいだろう。数章の並びの中に挟まれる断章あるいは幕間劇についても、脚本の柱のように立てられたシーンの下に繰り広げられる対話という構成は、神話的な情景すら帯びさせるにいたっている。
(04)
地の文にも面白味があって、普通の文体であれば、主人公が、云々と思った、何々と考えた、という構文なるところを、本書の場合、鉤括弧を付けない地の文で、科白のように言いかけて、やっぱり止めた、みたいな寸止め口調として現れている。科白にもなっていない、地の文にした主人公の思いでもない、宙吊りともいえるような、言いかけでやっぱり思いとどまってしまうこの寸止めな言葉については、近代私小説を解く鍵のひとつとなるだろう。
ちなみにこの寸止め感が主人公夫婦の寸止めな営みに通じることは言うまでもない。
(05)
植生を含む地勢という歴史地理の問題も含まれている。坂を呈示する標題からして地形地勢的であるが、橋、水路、山林、くぬぎの雑木を植栽した屋敷の趣味なども興味深い。エピローグとみなされる章で主人公はこれまで認識の外にあった緩い勾配に衝撃される。この一点をもってしても衝撃的な小説である。
Posted by ブクログ
山本周五郎の長篇時代小説『ながい坂〈上〉〈下〉』を読みました。
『寝ぼけ署長』、『五瓣の椿』、『赤ひげ診療譚』、『おさん』に続き、山本周五郎の作品です。
-----story-------------
〈上〉
人生は、長い坂。
重い荷を背負って、一歩一歩、しっかりと確かめながら上るのだ。
徒士組の子に生まれた阿部小三郎は、幼少期に身分の差ゆえに受けた屈辱に深い憤りを覚え、人間として目覚める。その口惜しさをバネに文武に励み成長した小三郎は、名を三浦主水正と改め、藩中でも異例の抜擢を受ける。
藩主・飛騨守昌治が計画した大堰堤工事の責任者として、主水正は様々な妨害にも屈せず完成を目指し邁進する。
〈下〉
人間は善悪を同時に持っている。
一人の男の孤独で厳しい半生を描く周五郎文学の到達点。
突然の堰堤工事の中止。
城代家老の交代。
三浦主水正の命を狙う刺客。
その背後には藩主継承をめぐる陰謀が蠢いていた。
だが主水正は艱難に耐え藩政改革を進める。
身分で人が差別される不条理を二度と起こさぬために――。
重い荷を背負い長い坂を上り続ける、それが人生。
一人の男の孤独で厳しい半生を描く周五郎文学の到達点。
-----------------------
新潮社から発行されている週刊誌『週刊新潮』に1964年(昭和39年)6月から1966年(昭和41年)1月に連載された作品… 山本周五郎の作品の中で『樅ノ木は残った』に次いで2番目に長い作品です。
憎む者は憎め、俺は俺の道を歩いてやる… 徒士組という下級武士の子に生まれた阿部小三郎は、8歳の時に偶然経験した屈辱的な事件に深く憤り、人間として目ざめる、、、
学問と武芸にはげむことでその屈辱をはねかえそうとした小三郎は、成長して名を三浦主水正(もんどのしょう)と改め、藩中でも異例の抜擢をうける… 若き主君、飛騨守昌治が計画した大堰堤工事の責任者として、主水正は、さまざまな妨害にもめげず、工事の完成をめざす。
身分の違いがなんだ、俺もお前も、同じ人間だ… 異例の出世をした主水正に対する藩内の風当たりは強く、心血をそそいだ堰堤工事は中止されてしまうが、それが実は、藩主継承をめぐる争いに根ざしたものであることを知る、、、
“人生"というながい坂を人間らしさを求めて、苦しみながらも一歩一歩踏みしめていく一人の男の孤独で厳しい半生を描いた山本周五郎の最後の長編小説。
下級武士の子に生まれた小三郎が、学問や武道等の実力や努力、そして強靭な克己心により困難を乗り越えて立身出世する展開… 上下巻で1,100ページ余りのボリュームですが、意外とサクサク読めました、、、
自ら求め選んだ道が現在の自分の立場を招く… 善意と悪意、潔癖と汚濁、勇気と臆病、貞節と不貞、その他もろもろ相反するものの総合が人間の実体、世の中はそういう人間の離合相剋によって動いてゆくもので、眼の前の状態だけで善悪の判断はできない… 江戸自体が舞台の物語ですが、現代の自分たちの生き方にも示唆を与えてくれる物語でした。
生き方や働き方について考えさせられましたね… 山本周五郎の人生観・哲学などが感じられる作品でした。
Posted by ブクログ
身分の低い家に生まれた阿部小三郎はある日今まで通行に使用していた橋が上士により破壊されてしまった姿を目にする。それでも何も言わず何も無かったかのようにそこを迂回する父の姿に成り上がりに心を燃やすのであった。。。
時代小説でありながら現代にも通ずるものを感じる作品でした。
一度読み始めたらなかなか読むことを止めることができず、一気に読み通してしまいました。
Posted by ブクログ
平侍の子として生まれた主人公が立身出世し、荒れ野を潤すための大堰堤を造ることを志す、という筋の時代小説。タイトルが示すとおり困難が続くけれど、主人公の誠実な性格と、時折、年月を飛ばして描くことから来るテンポの良さで、読みすすめやすい。
Posted by ブクログ
江戸時代の小藩の下級武士に生まれた主人公が、子供の時に遭遇した事件に憤慨し、長くつらい道を生きる決断をして成長していく様を描いている。お家騒動の権力争いの中で繰り広げらる人間模様などは、現代でも不変の営みのように思われる。自分に厳しい主人公の成長がこまやかに描かれており、著者の小説の重さが心地よくもある。
Posted by ブクログ
徒士組頭の父を持つ小三郎(後の三浦主水正)は、
自分たち親子の普段使う橋が取毀された様子、
そしてそれに対する父の対応を目の当たりにし、
その時から年相応の子供ではいられなくなった。
所謂成り上がりものの話だけれども、
主人公の成り上がりのための動機が
なんとも直感的で衝撃的。
大人になってからは
妻との確執や藩内の権力者達の陰謀、
過去の事件の謎が複雑に絡み合い、
更には得体の知れぬ刺客との戦いもあって
様々なエンターテイメント性を持っている。
仲間も増えていくのだが、
一方で裏切り者の存在も発覚する。
そんな中で主人公の三浦主水正は
果たして人格者であり続けることができるのか。
対比して描写される滝沢兵部の行末も
気になるところ。
Posted by ブクログ
実直な男の人生。
こういう書き方が受けると思って書いてた山本周五郎はすごいわ。。。
今こんな風に書ける人はいないとおもう。
あの壊れた橋をみた時から
彼は八歳ではなかった。
続きが気になる。
Posted by ブクログ
8歳にして人生の意味を見つけた三浦主水正の物語。
ストイックに信念を貫く、こんな生き方をしてみたい。
さまざまな状況が渦を巻いているが、さて下巻ではどのように決着するのだろうか?
Posted by ブクログ
読むのに随分と時間がかかってしまった。
幼いときから達観した主人公が今後どうなっていくか気になる。
つるがいいキャラクターだと思った。鼻持ちならない部分も多いけれど今後変わっていく気がする。
強い信念で下の身分から這い上がる主人公とサラブレッドで英才教育を受けたにも拘わらず落ちぶれていく兵部の対比が面白い。
Posted by ブクログ
もんどのしょうの努力の連続とその知性と能力を見出した国主の藩の改革物語。史実ではないが、多くの脇役がそれぞれ良い味が出ていて飽きない。利己を捨て自己犠牲を厭わない勇気と純粋な使命感が無ければ大きな改革を成し遂げる事はできないだろう。ものどのしょうの苦悩がまた非常に良く描かれている。思春期と若手が読むべき人生の1冊。
Posted by ブクログ
三浦主水正が、家格の低い家に生まれながら国家老になるまでを描いた出世物語。時より押し寄せてくる不安が,時折感じる感覚が自分と似ていてドキッとした。数々の困難を潜り抜けるのだが,その度ごとにかんがえさせられる。さすが。
Posted by ブクログ
読み始めは、とにかく「うわー、長そう。読みずらいし、人物掴めねぇーよ」と毎回、山本周五郎の長編に手を出すたびに思うんだが、これも同様。序盤、流れに乗るまでは正直きつかった。
でもね、一度、主水正に感情移入(しにくいけど)した時点から、展開にスイスイ付いていけた。どっちかとゆーと、冗長な流れなんだが、話の中心に、一本の骨太な筋が通ってるあたりが凄い。
たんなる立身出世物語じゃなくて、一国を動かすマツリゴトとは斯く在るべし、といった忍耐と信念を感じさせる。
読後は一時的に信念の人と自己変革をもたらす。三日で元に戻ったがな。
心に残る作品だけど、まとまった時間がないと読みにくいので、どちらかとゆーと、周五郎のほかの人情系短編のほうが好みかも。
でも最後の登城のシーンはね、コイツはくるぜ?ジーンとね。
若い頃は大好きな作品だった
しかし最近読み返してみたら、主人公の余りの人間味のなさにちょっと辟易してしまった
両親や兄弟、同僚、恩師、愛人、妻
それぞれの切り捨て方が酷い
お人好しでは務まらぬ厳しい道を歩んでいたのは理解出来るが、だからといって人としてどうなのかというレベル
主水正は長い間立派に留守宅を守っていた妻のつるの意思などおかまいなしに、未練がでるからと子供を作らない事に決めている
愛人との間には二人も子供を作っていたのに可哀想すぎるだろ
主君以外には自分の生き方を絶対人に左右させないのを若い頃はかっこいいと思っていたのだが、やはり年を取るとそんな人間と関わってしまった周囲に目が向いてしまう
この作品は周五郎の晩年にかかれたはずで、作者の疲れが主水正の疲れと重なっているというような解説を読んだ気がするのだが、周五郎自身は主水正の生き方をどう思っていたのだろう
樅の木の原田甲斐も似たようなタイプだから、そういう男に憧れていたのかもしれない
Posted by ブクログ
時代小説はふだん読まないので,新鮮。
「人間というものは……自分でこれが正しい、と思うことを固執するときには、その眼が狂い耳も聞こえなくなるものだ、なぜなら、或る信念にとらわれると、その心にも偏向が生じるからだ」(91頁)
Posted by ブクログ
時代小説を嫌煙してはいけないね。ここには現代社会にも通じる事が沢山ある。
三浦や滝沢の経験すること、思うことは時代に関わらない。谷の言も真理をついている。
下巻、すぐに読むぞ〜。