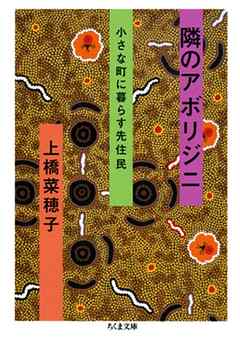あらすじ
独自の生活様式と思想を持ち、過酷な自然の中で生きる「大自然の民アボリジニ」。そんなイメージとは裏腹に、マイノリティとして町に暮らすアボリジニもまた多くいる。伝統文化を失い、白人と同じような暮らしをしながら、翻弄されて生きる人々……その過去と現在を描く。多文化主義オーストラリアのもうひとつの素顔。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
文化人類学の本は、どの土地のものであれ、読んでいて辛い気持ちになることが多い。大体「文化人類学」という学問分野で「調べる側」に立つのは西欧をはじめとした先進国側が圧倒的に多いわけで、「調べられる側」に立つのはアフリカや中南米、アジア、太平洋島嶼国といった、調べる側にとって「遅れた国」。結果、白人から見て相手の文化がどれほど劣っているか、異なっているかという視点が絶対に入り得る。それは、調べる側が「後から入ってきた先進国」、つまりアメリカや日本、オーストラリアなどになっても、大して変わるものではない。
そんな中、この本は著者が9年近くをアボリジニとともに暮らして感じたり調べたりしたことを元に書かれているためか、文化人類学の本のようでもあり、アボリジニの生活に関するエッセイのようでもあり、非常に読みやすく、公平な立場で書かれ、かつ読み応えのあるものになっている。
著者は序章で言う。
「この本で描くことが過度に一般化されて理解されてしまうことを防ぐために、私-日本人の未熟な娘-が、どんな風に彼らと出会い、どんな事件を経て、どう彼らを理解していったのか、それがきちんと見える形で語ることを心がけようと思っています。これからお話しすることは、あくまで私の体験という狭い窓から覗いた世界でしかないのですから。」
まさにこの視点を欠いた「過度な一般化」が、「貧しくて文明化されていない、可哀そうな途上国の少数民族」という固定観念をもたらしてしまうのだと思う。
逆に、この視点を持つことができれば、どんな土地にも「可哀相な人々」なんていない、ということがストンと理解できる。この考え方は、どの国のどの民族や文化に対しても適用できる普遍的で重要な視点。自分が妙な偏見に囚われないようにするためにも、今後も持ち続けていきたい。