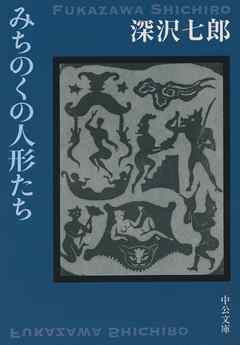あらすじ
お産が近づくと屏風を借りにくる村人たち、両腕のない仏さまと人形――奇習と宿業の中に生の暗闇を描いて世評高い表題作をはじめ名作七篇を収録する。谷崎潤一郎賞受賞作。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
どこか小島信夫の作品に近いエネルギーを感じた。
悪文とも言えるバラバラな文章に独特の引力があり魅力的。
土着の気味悪さや暗さで統一感ある作品集、とても好み。
表題作と『秘儀』は名作。
Posted by ブクログ
不思議な文体に、うねうねと続くトンネルを這っていくような気持ちがした。
ほの暗い、それでいて湿り気のある、長くて細いトンネル。そこを進んでいくのは、まるで胎内めぐりをしているかのようだ。
収録されている短編はどれも土着的な色合いが濃く、直接的にはそれらに関係のなさそうな短編でも、不思議と土の匂いがする。
私は特に、「秘戯」にもっとも打たれた。どぎつくて、生々しくて、それでいて悲しい、とても好みの短編だったと思う。
しかし、どうしてこう、土俗的な話というのは恐ろしいものが多いんでしょうねぇ。
Posted by ブクログ
深沢七郎の名作『楢山節考』を読んだのはたぶん高校生の頃で、よく覚えていない。その後見た映画版のほうが印象に残っているくらいだ。
しかし深沢七郎はどうやら「奇妙な作家」ということで他にも面白い小説をたくさん書いているらしいことは知っていた。
ようやく43歳を目前にして読んだこの短編集、実に面白い。
表題作の冒頭から、とにかく特異な文体にめまいを覚える。文法的にもなんか妙なところがあるし、「・・・なのだ」という文末が変なタイミングで執拗に出てくる。一体、こんなふうにしゃべる日本人がいるのか? これは異邦人の言語、ねじこまれ変容した日本語である。
そんな独特な語り口に乗せられながら、『楢山節考』同様に、奇怪な虚構の民俗誌をえがきだすのが「みちのくの人形たち」。それは世俗的、民衆的で、残酷かつ、人間社会なるものの形態の根源を窺わせるような、異質なフォークロア世界を現前させる。実に見事だ。
つづく「秘戯」「アラビア狂想曲」「をんな曼荼羅」も特異な文体でぐんぐんと異様な世界に入っていく。印象深い作品群だ。
著者のえがきだす土俗的世界は虚構なのだが、不思議なリアリティーを獲得している。一切「論じる」ことも「歌う」こともせず、余計な情緒性も排し、異様な文体でうねうねと穴の底へと突き進んでゆく。深沢七郎は異貌の語り部とでも呼べる存在である。
しかし「『破れ草紙』に拠るレポート」では文体が一変、とても「普通」のものになる。この本に収められた短編は全部昭和54年から55年の作品で、作風の変化とかいうことではない。では、「みちのく」「秘戯」等に見られたあの変な文体は、完全に意識的なものだということだ。
芸術作品という観点から言うと、深沢七郎のこれら短編はかなり逸脱しており、そういう基準からははみ出してしまうモンスター的な実存である。おもしろい。また深沢七郎を読んでみよう。
Posted by ブクログ
エディプスコンプレックスの物語ってやつは
ひっくり返せばライオスコンプレックスとべったり背中合わせだ
つまり、子殺しの欲望がはじめにあって
それへの反発から親殺しの欲望も生まれてくるわけだ
「楢山節考」で親殺しを書いた深沢七郎も
キャリア末期には、子殺しばかり書いていた
間引き、去勢、近親強姦などといったものである
しかしその語り口は軽く
因果と言ってよいものか、ちょっとよくわからない
最後は、まつろわぬ民の自死を経て
自らも子供に戻っていく