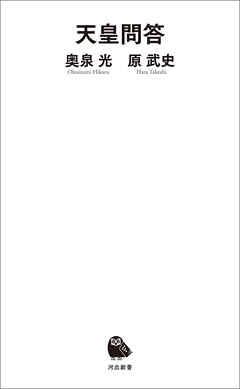あらすじ
明治・大正・昭和・平成・令和……今こそ問う、この国にとって天皇とは、皇室とは何なのか? しばしば天皇制を扱ってきた小説家と、天皇研究の第一人者が、対話を通じてその本質に迫る。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
譲れない反戦平和の意志を持つ自分が「天皇制」というものにずっと感じ続けている疑問を相当に解き明かしてくれた書であると思う。
奥泉光さんの分厚くて重たい「虚史のリズム」を読み終えたとき感じたモヤモヤもかなり晴れた。
奥泉、原の両氏のようにこれからも考え続けていこうと思う。
Posted by ブクログ
書名にある通り、対談がまとめられたものなので、まとまった論考が展開されているわけではない。でも、明治以降令和にいたるまでの天皇や皇室の変遷を二人で振り返ってくれているので、頭の中を整理できる。昭和天皇の崩御で、それまで存在感が薄れていた天皇の身体が急に表面に登場し、天皇のタブー性を再認識させられたこと(p156)、平成天皇は雲仙普賢岳の大火の時被災地を訪れひざまずいて国民と対話する姿が印象的だったが、一方で戦地訪問先は敗れたところのみ訪れ、旧満州や真珠湾などは意図的に回避しており、平成天皇の訪問した戦地のみであの戦争を振り返るのは実態を歪めてしまうこと(pp166-177)、眞子さんのニューヨーク行きは、国民の平安を祈るよりも「私」を優先させますという宣言であり、皇室のイメージを変えると同時にパッシングにつながったこと(pp190-193)。本書の最後では、天皇制は、多様性やLGBTQを認めていこうという時代の流れと乖離しており、被災地の視察や祈りは政治家や宗教者に任せ、天皇の仕事を減らし、いずれくる、天皇の存在しない社会の姿を考えておくことが大切、という結論で締められる。
Posted by ブクログ
20世紀の総力戦に取材した小説を多く発表してきた小説家と、近代天皇制とメディアとのかかわりを粘り強く追いかけて来た政治学者との対談本。新書という媒体的な制約もあって、基本的な知識の確認に多くのページが費やされているが、大正天皇の振る舞いを「大正流」として取り出したり、徳川時代の身分差をめぐる人々の身ぶりと近代天皇制のそれとの連続性を問題化したりと、興味深い論点も提示されている。原武史が、近代天皇制を研究していて最も分からないのは、「なぜ民衆が天皇制を支持し続けたか」「いったい誰が宮中の儀礼を設計したのか」が分からないことだ、とコメントしていたことも印象に残った。原が構造的な女性差別性を提起することで、近年では絶滅危惧種(?)となった天皇制廃絶論に言及していることにも注目したい。
本書の中では、原が日経新聞記者時代、昭和天皇の癌の手術の際に遊軍的に宮内省詰めとなった際の経験についての記述が印象に残った。何一つ新しいニュースはないのに、「万が一」を考えて毎日深夜まで宮内庁記者クラブに詰めていなければならない。社の上層部もほんとうはどうでもいいと思っているのに、自社だけが「特ダネ」を逃すのは失態に当たると惰性で報道の準備を続けていることこそが、「王の身体が日本という国の時空間を支配している現実」を再生産している――。では、そのような天皇の権威は誰が・どんな理由で求めているのか?
Posted by ブクログ
一家言ある者同士の対談は読みにくい、と感じる。小説家と政治学者、立場を異にするとはいえ、両名ともに近現代日本史に関する著作を書いている。また「天皇制」に対する考え方も、一致はしないが、遠いとも言い難い。
本書で目についたのは“皇后の強さ”。本書によれば、貞明皇后(大正天皇の皇后)、美智子上皇后、紀子皇嗣妃は、宮中祭祀に熱心であった/であるらしい(紀子皇嗣妃も“皇嗣妃”となったことから宮中三殿に上がることとなった)。「家父長制的イエのトップ」(p.184)として天皇家を捉えたとき、外から皇室に嫁いできた女性というのは、そのイエの中でのアイデンティティ確立のために、熱心になってしまうのではないか、と思った。目一杯「俗」に引き寄せてイメージするなら、テレビのホームドラマ(橋田壽賀子ドラマ的な家庭劇)において奮闘する「嫁」の立ち位置。なお、雅子皇后と香淳皇后(昭和天皇の皇后)は「宮中祭祀に熱心」というふうには語られないのだが、雅子皇后は「体調が万全ではない」(p.189)からということだろう。また、香淳皇后は本書にまったく登場しないのだが、生まれながらの皇族(誕生のときから「女王」の身位)というところが前後代の皇后と異なるものと思う。
Posted by ブクログ
加藤陽子との対談「この国の戦争 太平洋戦争をどう読むか」の、相手は代われど続編的な本。
実は高校の頃は中上健次や大江健三郎、三島由紀夫、吉本隆明にカブレたクチなので、いろいろ考えたものだが、その後はとんと。
実際天皇と聞けば必ず、もう何百回も思い出すのが、女子高生のツイート「「天皇誕生日おめでと あんま絡みないけど、素敵な82歳にしてね」の、唐突なブッコミ作法と、無知ゆえのフランクさと。
で、その想起にこちらの頭も浸されてグズグズになったくらいに自分も落ちていたわけだが、その地点に片足置いて、またいろいろ考えるようになったのが、やっぱり文芸経由で、しかし四半世紀後に背中を押してくれているのは石牟礼道子や森崎和江だったり。
しかしこの停滞の時期ずっと読み続けていたのが、奥泉光だったので、その当人がまるで自作解題のように出してくれた対談、面白くないわけがないし、四半世紀のあいだ自分にマスキングしてきた考えが、ぶわっと沸騰した思いがする。
が、結論としてはグズグズ考え続けなければというものでしかないが。
このおふたりが本書の最後のほうで天皇制反対の理由を簡潔に述べているが、その落ち着いた、現実的な口調に、同意するものである。
ファナティックになってはいけない。
@
明治・大正・昭和・平成・令和……今こそ問う、この国にとって天皇とは、皇室とは何なのか? しばしば天皇制を扱ってきた小説家と、天皇研究の第一人者が、対話を通じてその本質に迫る。
この国には天皇がいる、皇室がある。
それはいったいどういうことなのか――――?
神格化のはじまり、「大正流」の可能性、昭和の戦争と熱狂、行幸啓の変遷、宮中祭祀の内実、「平成流」の功罪、「象徴」の意味、令和の空気、皇室のこれから……
【目次】
まえがき(奥泉光)
Ⅰ 天皇制の見方・考え方
天皇制の何が難しいか/フィクショナルな出発点/徳川時代と変わらない/生き神がやってくる/三つの層で考える/「新しい伝統」は誰がつくったのか/「祈る天皇」というイメージ/貞明皇后が立ちはだかる/昭和・平成・令和の宮中祭祀/文明開化は天皇とともに/明治天皇の神格化と一般大衆への浸透/現れる天皇、見えなくなる天皇/神出鬼没の大正天皇/昭和天皇を神格化する演出/主導する中間層/秩父宮と二・二六事件/一般大衆の想像力と空虚な支配構造
Ⅱ 昭和の戦争と天皇制
江戸時代との断絶と連続/「国家神道」への道/天皇が東京に移るということ/男性化する「玉」/「国民」をどうつくるか/明治憲法が孕んでいた矛盾/日清・日露戦争に勝ったことの意味/世代による感覚の違い/大正天皇という人/封じ込められる「大正流」/君主制の危機と新しいイメージ戦略/天皇崇拝が止まらない/「政治」が消えてしまう/とにかく神器を失ってはならぬ/大衆の熱狂はどこへ行ったのか/最大の疑問/新憲法下での昭和天皇/変わらない国民/なぜ熱狂に火がついたのか/反省しても反省しきれないポイント
Ⅲ 昭和から平成へ、平成から令和へ
代替わり体験/天皇崇拝の構造/昭和の聖性、平成の聖性/ひざまずく皇太子妃──「平成流」の萌芽/宮中祭祀という使命/天皇が私たちの代わりに死者を悼む/一人一人と相対してきた厚み/国民は「象徴」の意味を考えてこなかった/自衛隊との結びつき/反天皇制の理由/平成と令和の皇室の違い/秋篠宮家の存在感/令和の空気/天皇制は続くのか
あとがき(原武史)