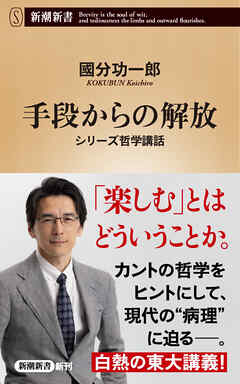あらすじ
「楽しむ」とはどういうことか? 『暇と退屈の倫理学』にはじまる哲学的な問いは、『目的への抵抗』を経て、本書に至る。カントによる「快」の議論をヒントに、「嗜好=享受」の概念を検証。やがて明らかになる、人間の行為を目的と手段に従属させようとする現代社会の病理。剥奪された「享受の快」を取り戻せ。「何かのため」ばかりでは、人生を楽しめない――。見過ごされがちな問いに果敢に挑む、國分哲学の真骨頂!
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
國府先生、これはかなり難しかった。何回も行きつ戻りつしてやっと一周読みましたが理解が追いつかない。。。
私なりに理解したところによると、目的を持たない快(酒やタバコをを嗜むような)が、現代では目的に蝕まれつつある=純粋に行為自体を快楽として受け取る余裕がなくなってるよ、っていう警鐘なのかなと思いました。実際私も酒びたりのときが一時期あり、現実から一瞬でも思考を切り離す道具として酒を飲んでいたなぁと今は思います、当時は美味しいから沢山飲んでると思い込んでましたが(病)。
前作の新書より具体性が上がってるのについていけない自分の理解力のなさに悲しみを覚えつつ、一方で凡人がついていけないレベルの内容でも平易な言葉で何回も何回も丁寧に説明して書いてくださる國府先生の姿勢に、そこに痺れる憧れる〜!となってしまう一冊です。おすすめです、帯の先生の写真もかっこいいし!
Posted by ブクログ
人生に目的手段の連関がある程度必要なのも事実だが、享楽の快という単なるそれ自体を楽しむことを意識して過ごしていきたいと感じる、とても良い著書だった
ただ、消費社会の原因が資本主義にあるかのように述べられてることには違和感を持った
確かに消費社会は資本主義から生まれたことには同意するが、それを消費してしまう個々人の内面的事情に大きな問題があると自分は見ており、資本主義というより、資本主義であるこの社会に対しての思考があまりに脆弱な人間が問題なのでは、と思ってしまうのは自分だけなのだろうか
Posted by ブクログ
「楽しむ」とは何か。
楽しむとは、何かの目的のためにするのではなく、ただすること。ただその行為が心地よいということ。と読み取った(間違っているかもしれないが)。
私にとって、楽しむとは、読書することかな。読むこと自体が楽しい。
…とはいえ、読書をして「賢くなりたい」「世間を色鮮やかに見たい」といった、手段としての側面もある。そういった動機は「楽しむ」とは少し違うかもしれない。
でも、ただ読むこと、それを楽しむ感覚。
それこそが「楽しむ」と思う。
また、著者は「楽しむことは、誰からも奪われてはならない」と書いており、共感した。
Posted by ブクログ
カントの「判断力批判」を元に、快の対象を四つに分け、そのうち「ただ快適なもの:享受の快」を重視する議論を展開する内容。(p85の図がわかりやすい)
これと混同されがちな快として、「設定された目的にとって手段として有用なもの:目的達成の快」がある。
たとえば健康はそれ自体が快適だが、健康であろうとする目的で運動をするとか野菜を多く食べるとかは純粋な享受の快ではないとされる。(p82)
お酒の例で言えば、お酒を味わって楽しんでいることは享受の快だが、アルコールに酔いたいという目的のための手段として使われればもはや享受の快は失われている(p92)
その最たる例がドラッグであり、これは正に目的(ハイになる、リラックスするなど)のための純粋な手段として用いられ、享受の快は全く無い(p101)。
この本の帯にも引用された下記の表現が最も印象的だ。
「享受の快を剥奪することは、人間に病としての依存症への道を開く。社会がこのまま進み、すべてを手段化した時、我々はおそらく、『これまで見たこともないような依存症』に出会うことだろう」(p109)
過去作『目的への抵抗』『暇と退屈の倫理学』よりも難解で、具体的な解決策の無い本書だが、人間の快い生き方について注意深く論を進めたことで、資本主義が全てを手段化して人間の享受の快を剥奪することへの強い警鐘を鳴らしている。
今後の手がかりとしては、下記の2つが挙げられている。
「アディクションと資本主義についての考察を深める」(p203)
「主体が再来するためのヒントの一つはおそらく『習慣(habit)』にある。我々主体は無数の大小の習慣の集積であるが、現代の経済体制では常に新しい需要、目的を追い求めさせられる。我々は習慣を作る暇もなく、主体を失っている」(p207)
現代をめぐる著者の哲学について、引き続きフォローしていきたい。
Posted by ブクログ
現代社会の風潮が、手段に支配されつつあるという感覚は、確かに感じる。楽しいてなんだろう。なぜ趣味が思い浮かばないのか?趣味も手段化しているのではないのか?例えば、子供の頃は泳ぐのが楽しかったのに、大人になると健康維持の為の手段となっているように感じる。睡眠も、仕事のパフォーマンスを上げる手段になっている。資本主義というOSが知らず知らずに自らをそのように仕向けているのかなと、読みながら思い当たった。
Posted by ブクログ
嗜好品とは何なのか。そうした疑問へのヒントを得るために、今回はカントの哲学の深淵に迫る。
カントはその認識論で有名であるが、今回は、カントの著作をもとに、享受の解を探る。
途中の理屈付けはやや納得できない、理解が難しいところもあったが、カントは何かの目的のために行うことを低次の欲求能力を満たすものと位置付けた。定言命法によって理屈付けられる、つまりそれ自体が目的となるような(目的なき合目的性)事象は崇高や美とされるが、なんらかの目的があるからそれを行う、接種するというような事象はレベルの低い欲求とされる。
本書を読んで、個人的に腹落ちした部分としては、『健康経営』というコンセプトへの生理的な忌避感が言語化できたところであった。本書でも、健康はそれ自体が快適なものであるが、何らかの目的のために健康であるという、健康の手段化が行われてしまうと、それは低いレベルの欲求を満たすことになってしまう。
健康経営は経産省発信のコンセプトで、健康な労働力が生産性を向上させ、結果として健康に取り組む会社は業績が良くなるので、株価が高くなるという情報発信である。
個人的には、過酷な職場やメンタルヘルスに悩む友人等を見るに、企業が健康経営に取り組むことは9割は納得しているが、1割だけもやもやとした感情があった。それは、私たちは生産性を上げるために健康であるのではなく、ただ単に健康そのものが快適であるから健康を目指すという視点が抜け落ちており、まさに我々の健康というものが資本を増やすための手段に置き換わってしまうことの違和感である。これはある種の疎外であり、その違和感があった。
会社は健康な社員を臨むが、その単純な目的と手段の関係性ではなく、本来どの人間にもあるはずの、健康そのものへの快適さやを、個人の裁量で追求する、享受するという観点が必要なのではないかと感じた。
Posted by ブクログ
Youtubeの企画で朝井リョウがおすすめしていたため、手に取ってみましたが、、、
あまりにも哲学的すぎて、私にはなかなか理解が追い付かない点が多かった。
Posted by ブクログ
掲載された元の論文も読んでいたが、改めて面白かった。どうしてかはわからないけど善いとか心地よいとか美しいと感じる感性を呼び覚ましたい。
あと、あとがきにあった目的に縛られた主体は経験を失う、という視点がすごい。窮屈さや寂しさを感じるのは経験によって何も蓄積されないからかもしれない。目的と手段に多様性は求められない。
Posted by ブクログ
「日常生活が目的の為の手段と化した皆に告ぐ。救いはあまりないが、ヒントはある。」
拒食症はご存知だろうか。
端的に言えば「食べたくても食べられない」病であり、現在私が罹患している病でもある。正確にはトレーニングを積んで飲み食いをゆっくりなら出来るが嚥下が苦手である。だがそこには「食事の楽しみを剥奪された人間」が確かに居る。
本書はカントの快の分類を援用しつつ、「目的や手段を持たない、純粋に快適を享受する」ことが「目的達成の為の手段としての‘‘病的‘’行為」に貶されないように、「目的ー手段」に人生を従属させないことを説いている。本書の例をアレンジするならばこう言えるだろう。「喫煙は快適を享受するが、健康目的の禁煙パッチを利用する人間は病的である」と。
では「目的ー手段」から逃れるためには何が出来るのか。自己の道徳法則に従わせる他に、享受の快適を受け取る術を知ることだと著者はカントを読み解き言う。なお、後者のみに生きることにはカントは批判的であるが、後者自体は否定していない。
この結論は『暇と退屈の倫理学』と同じ話である。焼き増しではないか。ただ本書は「嗜好品」についての考察が続く。嗜好品を味わうことは、目的達成の満足の為の手段ではなく、その行為から快適を得られる、だと言う。つまり「目的ー手段」から外れた存在だというわけだ。
本書では、嗜好品たるアルコールやタバコと依存物質であるドラッグを大きく区別している。ただ、これは何とも納得感がない。依存物質の多い少ないで決められるものなのか。快適の享受に普遍性はなく、個別的なものである。単に私は楽しみ方を知らないだけなのか。(とすれば、著者はドラッグの楽しみ方を知らないということになる。)
ここで白状しよう。このレビューはタリーズで書いている。飲み込むのが苦手なのを克服する目的でコーヒーを飲んだのだ。飲み始めはリハビリとして飲んでいるので、快適ではない。「目的ー手段」関係だから当然である。だがどうだろう。レビューを一生懸命書いているうちに、確かに昔のようにコーヒーを楽しんでいる人間がそこにはいた。
「自然と快適を享受していた」現象は、「目的ー手段」関係からの解放とは言えないだろうか、國分先生。
Posted by ブクログ
現代社会では、あらゆる行動が何らかの目的に向かうことが当然視されている。
その結果、「第四象限の純粋な享受を守る」ことは、ほとんど不可能に思える。
目的を伴わない行動は奇異と受け取られやすく、自分自身もつい「何のためにやるのか?」と目的を探してしまうからだ。
そんな社会で、私ができるささやかな抵抗は、第三象限と第四象限のはざまを意識的に往復することだと考えている。
具体的には、
• 何かを成し遂げるための手段として行動しながらも
• その手段自体にも純粋な快を見いだし続ける
つまり「目的に向かいつつも目的に縛られない」問いかけを日常に散りばめる。
この生き方こそが、手段化された快の連鎖から自分を解放し、ほんの一瞬でも第四象限の自由な享受を取り戻す鍵になるはずだ。
Posted by ブクログ
記号化されたもの。
その最も象徴的な概念は「数字」だが、それを存分に纏った存在が「お金」や「偏差値(学歴ステイタス)」、「年収(これもお金だが、それに繋がる就職先や社会的ステイタス)」だ。本著の指摘で重要なポイントは〝記号は際限なく消費される“というもの。
大学に入るのがゴールではない、部長になるのがゴールではない、お金自体は目的ではないはず。しかし、記号化された、その二次的な価値自体を追い求めてしまう。著者はこれを「本来は手段であるはずのもの」と捉え、それに縛られて生きる社会に警鐘を鳴らしている。
本質を見失った人たち。
お金が欲しい。良い大学。出世がしたい。
それで、何がしたいの。ただ、欲望を満たすための人生の消費。追い求め、大切な事を忘れ、命を消費して終わり。ワンセット80年で上がり。今回の人生の報酬は、関心も本心でもない誰かからの刹那的な賞賛。それと、自己満足。
我慢して快楽を求める。これは手段。単に快楽を享受する。これも手段。理想がまだ手段である場合は低次。道徳的理想ならば高次。
信仰こそ、道徳を規定する。日本人の道徳や信仰におけるモデルは今は実存が心許ないので、日本人は幸福度が低いのだろう。何を求めるにも、低次しか目指せない。
ー 流行の店が変化すれば同じことを続けなければならない。「その店に行った」という観念のためにその店に行くわけです。「流行の店」はここで完全に記号になっている。そして記号はどれだけ受け取っても、決しておなかいっぱいにはならない。満足が訪れない。だから記号の消費はいつまでも終わらない。演出した自らの生活を、たとえば写真投稿の形でSNSにおいて切り売りして「承認」(「いいね」)という対価を得ることが当たり前になった現在、ボードリヤールの言う消費は、彼がそれを主張した六〇~七〇年代よりもよっぽど理解しやすくなっているかもしれません。
勿論、手段から得る快楽を否定はしていない。それが自己目的化した虚無に陥らなければ、必要なことでもある。しかし、そればかりでもいられない。
その救いは信仰にある。だが、言葉で語り得る宗教は全て偽物である。だから、自ら真理を探さねばならない。
Posted by ブクログ
國分先生の講和シリーズで「目的への抵抗」に続く一冊。「楽しむ」とはどういうことかを考えるもの。「〇〇のために楽しむ」のは一見当たり前なのだが、単純に、自然に、楽しむことから離れているのでは。「浪費」ではなく「消費」させられていることも主客逆転。時々こういうことを考えるのは大事だなあと思う。
Posted by ブクログ
「目的への抵抗」の続きのような哲学講話だったので、読んでみたくなりました。
楽しむとはどういうことだろう。楽しいって何なのだろう。と十数年考えてこの本を書いたと言う。
カントのタバコ論からはじまり
嗜好品、享受の概念についての解説。
スポーツや旅行を楽しむことも含まれるかと思っていましたが、タバコやお酒、お茶、珈琲などを楽しむことについてなので、あくまでも嗜好についてでした。
前半は専門的な語彙が多いので分かりづらいところもありましたが、後半は東大での講話はとてもわかりやすく、腑に落ちました。
カントの嗜好や享受の説明で、五感によるレベルがあるようで、触覚と視覚と聴覚はレベルが高くて、味覚と嗅覚はレベルが低いという。
その中に「快」と「快適なもの」の違いなど、楽しむための「目的」が、いつのまにか「手段」としてすり替わってしまう恐ろしさとか。
最後の手段化する現代社会として、お酒は楽しむためだったのに、依存症になってしまったことを「手段からの解放」とし、依存症の方たちのバックグラウンドが重要で、楽しむものが手段化してしまう社会を考えないといけないのではないか、と提唱していました。
こうなってくると、まだまだ続きがありそうですね。
いつも、ただの哲学ではないところが國分功一郎のドキドキするところです。
Posted by ブクログ
シリーズ前作に比べると、前半部は論考の形を取り後半部がそれを受けた講話という構成もあるが、内容自体もカント哲学の辺縁から嗜好や享受についての考察ということでなかなか骨の折れる内容。(JT関連との共同研究)
言われてみると、嗜好品やアディクションへの考察が社会学や生理学的に説かれるものは目にしたが、それを哲学上の議論で目にかかることも少なく、込み入った話になりがちなのかもしれない。
朱喜哲氏の連載に、似たような話があったような。
Posted by ブクログ
カントの「快」に対する分析(快を①端的に善いもの、②美しいもの、③崇高なもの、④快適なものに分類)をベースとして、目的のために手段化する傾向の強い現代社会の問題を指摘し、④快適なもの(目的のための手段としての快ではなく、それ自体を楽しむ享受の快)の重要性を説くもの。
カントについては名前を知っている程度で全く知識がなかったので、カントの議論を分かりやすく噛み砕いて説明されていて勉強になった。
前半:論文をベースとしたもの、後半:講演をベースに文章化したものという構成であったため、前半パートでは難解であまり理解できなかったところもあったが、後半パートを読むことで理解が深まった。
Posted by ブクログ
何かに駆り立てられるように生きている、何かに駆り立てられるように何かをしている、それでいて人間自体は虚しさを感じながらカラッポな状態で行きている。そのような現代社会の病理のようなものに言葉を与え、その解決として提案されるもので我々の生や思考に一つの道筋を提案する。
目的とも手段とも切り離された快を享受することで、所謂精神的な満腹状態に達し、消費社会、資本社会の構造に抵抗する、そして主体を取り戻す、ということがシリーズを通じて繰り返し述べられる。
「楽しむ」という卑近なテーマからスタートする思索であるが、巻末でも述べられているように、このまま行くと人間が、依存症に陥ることに留まらず、取り返しのつかない悲劇を繰り返しかねない、そのような社会の構造になってきていると筆者は懸念する(と僕は読んだ)。人間全体の生に関わる、大きなテーマ、大事なテーマのための思考のスタート地点として、本書、本シリーズは非常におもしろいし、刺激が得られる。
Posted by ブクログ
カントの三大「批判」書のエッセンスを、美、崇高、善、快適という視点で整理。
現代は、快適なものが直感的なものとして楽しめず、目的を手段化してはいないか、と指摘する。
健康であることさえ、手段化する。そこには、人間の作った資本主義、消費社会のシステムが見え隠れする。デジタル社会だから逃れようも無いとも言えようが、デジタルデトックスした状態で、暇と退屈を直感的に楽しむ余地は持っていたいと、つくづく思った。
Posted by ブクログ
『暇と退屈の倫理学』:國分功一郎
・消費は、終わりがない。浪費、すなわち物を受け取って、物を楽しむことを楽しめるようになれば良い。そうなれば、この消費社会から抜け出すことができる。
→「楽しむ」ということの定義がしっかりしていない。
・本書では「楽しむ」を定義する。
『判断力批判』:カント
・快の対象:快適なもの、美しいもの、崇高なもの、善いもの
①善いもの
・実践理性批判で提唱される、高次の欲求能力の実現
・自分自身を決定する根拠が純粋に自分自身の道徳法則にのっとってのみであることが、快を生み出すもととなるカントは、人間は自らのうちに目的を持ち、その目的から逃れることはできず、その目的の実現のために意志し、行為することを運命づけられているとする。
・享受=嗜好のためだけに生きていてはいけない。
②美しいもの
・判断力批判で提唱される、高次の快
・「美しい」と判断する働きを趣味判断と呼ぶ。
・趣味判断は個別的(⇔論理的判断)であると同時に、普遍的(感官判断:快適である、などの個別判断)であるという特徴をもつ。
・本来、構想力は対象が現前していなくてもその対象を直観し多様なものを一つの表象にまとめあげる(図式化作用)能力であり、感性で感じたものを悟性で整理する際に、語性をサポートする。すなわち、構想力は悟性に従う。
・趣味判断においては、「構想力と悟性が自由な戯れ」をするという。「美しい」ものを見た際に、構想力がひとりでに何らかの形象を生み出し、悟性がその中に合法則性をみいだし、構想力も悟性に自らの産物が受け入れられたことを喜ぶ。
・「目的」とは、もののあるべき姿を意味している。
・「構想力と悟性が自由な戯れ」の状況下では、美しさの根拠となる概念(悟性によって作られる)は決して先に与えられないのに、すなわちそうあるべきだといいうる根拠がないのに、そうあるべきだと感じてしまう状態を「目的なき合目的性」と呼ぶ。
③崇高なもの
・判断力批判で提唱される、高次の快。下記のように、内面に抗争がうまれるという点で、高次の不快ともよべる
・我々を圧倒するような「ものすごい」ものに対して発生する感情
・対象が圧倒的であるがゆえに構想力は全体を図式化することができない。認識されることはできないものを扱う概念である「理性」が独立して働く。構想力は理性に対し無力感をかんじるとともに反発を感じる。
・この構想力の挫折・抗争によって、人間性という目的が再認識される。すなわち崇高も合目的性とされる。ただし、崇高は、外部の対象そのものが合目的性であるわけでなく、判断者の心のうちに合目的性があるとする
④快適なもの
・享受の快。
・美しいもの、との差異:美しいものの趣味判断は普遍的であるのに対し、快適なものの感官判断は個別的である。しかし、感官判断が普遍的である状態(快適なものについての日普遍的で個別的な判断を、万人が同じ対象に下す事態)
・善いもの、との差異:カントは2つの善いものを区別している。それ自体として善いもの(高次の欲求能力)、すなわち直接的によいもの、と「何かのために善いもの」(低次の欲求能力)である。後者は、快を直接あたえるものでないということで、、カントは快の対象としていない。
・低次の欲求能力によって行為しているとき、pathologischであるという。欲求能力の低次の実現とは、あらかじめ設定した何らかの目的を達成するのに役立つからよい、という考えである。
・行為が目的意識に満たされているとき、快適なものを享受するはずの行為は、手段として有用なものに変容してしまう。
・快適なものだけが目的と無関係である。また、快の対象の4つは、欲求能力の低次の実現と異なり、手段と無関係である。一方で、快適なものは、そこに手段-目的連関がもちこまれるとすぐに欲求能力の低次の表現となる。
・嗜好品は、目的手段連関から独立した、享受の快をもたらす。しかし、酔うためのアルコールなどのように容易に目的と化すとともに、依存症におちいることもある。依存症では行為のすべてが目的手段連関に奉仕する形で進行する。
・現在の消費社会は、享受の快について、万人が同一の快適なものについて、同一の非普遍的で個別的な判断を下すという、これまでとは違う状態が訪れている。これは、固有の趣味を獲得する機会を奪う第一歩であるとともに、嗜好品の排除という問題もある。目的を持ち込まれたとたんに存在することをやめる享受の快をはく奪することは、依存症への道を開く。
・人間から享受の快をはく奪してはならない。それは人間の生すべてを目的手段連関に従属させることだから。
Posted by ブクログ
読みにくいけど、読みたい内容。
その行為が、それ自体を楽しむものでなく、何らかの目的のための行為、手段としての行為になってしまうことの警鐘と受け止めました。目的だろうがなんだろうが何かに支配されていくのは嫌だな思いますが、依存行動と付き合っていくにも、そこから卒業するにも、基本の理解として役立つ考えだったと感じています。
Posted by ブクログ
2025.04.29 かなり考えさせられる良い本だと感じた。全てが手段化する現代社会。コスパなんでいう概念はその最たる証では。余白が無くなっている。well-beingと言われるけど、どんどん逆の方向にいっているのではないか。
Posted by ブクログ
第三象限(手段の概念を含む)と第四象限(享受の快)の違い説明は非常に興味深い。
この議論は哲学的なものでなくとも、一般的に議論されていたりする内容だと思い至る。
趣味や嗜好品を手段としてはならない。
誰もが無意識に陥る罠ではないだろうか。
気を付けたい。
Posted by ブクログ
本書は、カントの提唱する快の四分類(快適なもの、美しいもの、崇高なもの、善いもの)を丁寧に解説することから始まる。
- 快適なもの:感官的な快であり、個人的な好みに依存する。目的や合目的性を持たない、純粋な享受の対象。
- 美しいもの:反省の快であり、主観的ながら普遍性を要求する。目的はないが、合目的的に感じられるもの。
- 崇高なもの:理性的観照の快であり、人間の想像力を超える強大なものに対する畏敬の念から生じる。
- (端的に)善いもの:道徳法則に従うことによって得られる快であり、理性の実践的な働きによる。目的そのものであり、自律的な意志によって実現される。
美しいものや崇高なものが、それ自体として価値を持ち、我々に直接的な喜びや感動を与えるように、快適なものもまた、手段性を超越した純粋な享受として捉えられるべきだと著者は主張する。直接的な満足を与える三つの領域と、目的達成という手段に依存する「間接的に善いもの」との明確な区別は、我々が普段何気なく享受している快の中に潜む構造を明らかにする。
また、『暇と退屈の倫理学』でも論じられていた「浪費」と「消費」の対比、嗜好品が排除される傾向、そして依存症の問題についても、具体的な例を挙げながら議論が展開される。特に、あらゆるものが目的のための手段とされる全体主義社会における享受の否定(「チェスのためのチェス」は許されない)というアーレントの指摘は、現代社会が陥りつつあるかもしれない危険な兆候を示唆し、読者に強い警鐘を鳴らす。「アーレントは全体主義社会を目的の概念から分析する過程で、ナチの政治家ハインリッヒ・ヒムラーが全体主義社会の理想とする人間を定義して述べた言葉、「それ自体のために或る事柄を行うことの絶対にない人間」を引いています」という箇所にはドキッとさせられる。会社勤めの人間であれば、誰しも際限のない業績向上と株式市場の期待への応答を求められる毎日に疑問を禁じ得ないが、アーレントの指摘は過度な効率化や目的至上主義がもたらす心の貧しさを浮き彫りにする。
いま、私たちが何か一つでも自分にとって快適だと感じられるものがあり、それを享受しているのであれば、決してそれに目的を持たせてはいけない。それが目的への抵抗、すなわち合目的性からの逃走線であり、まさに幸福なのだから。
Posted by ブクログ
暇と退屈の倫理学の結びに登場した楽しむとはどういう事かというテーマについてとてもわかりやすく考察されていた。人間性は生活習慣によって積み上がっていくものではないかと少し前に思った事があったが、筆者の予感として同じ様な事が書かれていて大きく頷いた。
カントのタバコに関する考察の邦訳文に惚れ惚れした。素敵な文章でした。
Posted by ブクログ
1章は難しく感じるというか、あれ何を指してるんだっけとなり、少し理解半ばだったが気にせず進めた。
2章は1章を苦しみながら読んだおかげもあって、理解が進んだので、ちょうどよい読み方だったかも。
結論はまあそうですねえという感じではあったかな。
Posted by ブクログ
前半が論文。後半はそれをもとにした講義録。前半は難しい。後半はちょっと難しい。総じてやっぱり難しい。目的と手段の整理だけでなく、目的自体もダイジョブか!?って内容でしょうか。流されずに自ら考えるって大変、って内容でしょうか。うん、難しい。
Posted by ブクログ
●本書は、人間の行為を目的と手段に従属させようとする消費社会に対して警鐘を鳴らしたものである。カントの批判哲学を紐解き、人生を楽しむための「享受の快」について考察する。
●哲学の本は難解なイメージがつきまとうが、この著者の本はわかりやすく読める。
Posted by ブクログ
『目的への抵抗』の続編。哲学講和シリーズ。本著ではカントに焦点を当てつつ、享楽や嗜好について哲学的に深堀りしていく。資本主義により飽くなき欲望が喚起されるーーそんなフェーズすらもZ世代以降は飽きて、悟りつつある。では人間生活の根幹となる仕事はどうなるのかといえば、生成AIの台頭で、ホワイトカラーを中心に人間の仕事の本義が問われている。一面的にみれば、エッセンシャルワークをはじめとして、ブルーカラー領域での仕事が需要面だけをみれば重要性を相対的に相対的に増しているように見えるが、話はそう単純でもないのだろう。そうした経済合理性から距離を置いた上で、もう少し違った位相から人間の本源的な欲求や感覚の拠り所を思索したいときに、カントの批判哲学は強力な立脚点を指し示してくれるのだと思う。
「ある人間がたんに享受するためだけに生きており、そのひとの現存が(そしてたとえ、そのひとがこの点ではどれほど熱心であろうとも)、それ自身である価値をもつことを、理性はけっして納得させられることはできないであろう。」(『判断力批判』上巻、六二頁)
Posted by ブクログ
論文の部分が難しかった…
「楽しむ」ということをカントの哲学や嗜好品から読み解く話。
「チェスをチェスのまま楽しむ」ような、手段でも目的でもない楽しさを享受するのが大事だよとかそういう話だった。
暇と退屈は読みやすかったな…