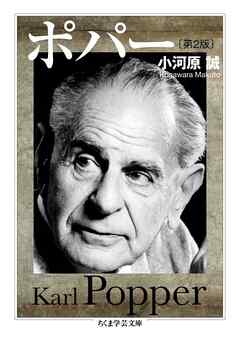あらすじ
ウィーン出身の哲学者カール・ポパー(1902‐1994)。その思想は「批判的合理主義」として知られ、主として科学哲学や政治哲学の領域でこれまでに大きな影響を与えてきた。だが、この「知の巨人」の反証主義などの思想はたびたび誤解され、批判にもさらされてきた。本書は、ポパーを最も深く、かつ正確に理解する著者がそうした誤解を正し、ポパーの明晰さそのままに知の体系を解説するものである。『開かれた社会とその敵』の新訳も担当した著者による、いちばん信頼できる伝記として、また専門的見地に基づいたポパー哲学全体を俯瞰できる最良の入門書としても広く読まれてきた定番書、待望の改訂版。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
どういうわけか、ポパーが好きだ。
彼の思想をすべて理解しているわけではないけれど、なぜかとても惹かれる。
世界を推測し、その推測を反駁できること、そして、反論や批判に対して開かれた社会の重要性――それらに深く共感している。
その思想がもたらす恩恵を信じたい気持ちがある一方で、それが時に辺境を生み出しているのではないかという不安も、ふとよぎる。
もっと生きて、意識についての研究を続けてほしかった、その思索に触れてみたかった。
Posted by ブクログ
注意、長文
ポパー哲学の解説書にして入門書。
ポパーは、全てが批判に開かれている、それゆえに安全が確保されている開かれた社会という理念を擁護し、逆の自身に何らかの権威を付与したり、力づくで批判を不可能にするそれゆえに安全が確保されない閉じた社会やその担い手達を批判した。
また昨今はやたらとエビデンスというものが強調されるが、それについての小河原氏の意見も聞くべきものがある。ポパーはまさにそのようなものを批判した。
■第一章 若きポパー
科学と非科学の境界線、反証可能性、ヒストリシズムの倫理、本質主義の弊害といったポパーが生涯にわたり思考し続けた哲学的議題は、若い頃から存在していた。
ポパー哲学の中の目玉といえば自分は反証可能性を挙げる。どのような言明であれ偽である可能性があり、どのような言明であれ批判にさらされる必要がある。なぜならいくら肯定的証拠を積み重ねても、当該の理論を立証することにはならないから(全てのカラスは黒い、という言明は黒いカラスをあらゆる場所で見つけても、白いカラスが一匹見つかっただけで偽となる)
また反証可能性は倫理とも繋がっていく。常に偽とされる可能性があるということは、自分に対して自分は絶対に間違えないと慢心したり驕りたかぶったりしなくなるだろう。
そしてこの帰納の問題と、科学と非科学の境界線の問題は、若い頃に染まったマルクス主義についての疑問から発生した。
例えばマルクスの理論は当時の人々にとって、世界のあらゆるものを説明できる万能理論だった。真である証拠もたくさん見つかる。全てが「階級闘争理論」で説明がついた。皆大得意で自信満々だったが、この態度にも彼は違和感を覚えた。というのも科学者アインシュタインはもし自分の理論が一定のテストに落第するなら支持しがたいものだと認める、と非常に謙虚だった。アインシュタインは一般相対性理論をかげろうのごときものと呼んでいた。
また、全てが批判に開かれているということは、形而上学に対しても批判ができるということ。ウィトゲンシュタインのように、語りえないものについては沈黙するしかない、と言うとき死後魂は存続するのかしないのか、天国や地獄はあるのかないのかと言った宗教的言明に口を閉ざすということを意味する。つまり、批判すべきいかがわしい宗教団体、カルトや集金目的の集団だったりについて、その居場所を確保してしまっている。
■第二章 反証主義
ポパー以前の科学的態度を批判し、ポパーの反証可能性をじっくり解説する章。
ポパーは、科学的理論は反証にさらされうるものであり、そして科学的態度とはなによりもまず理論をそうした反証にさらそうとする批判的態度であると考えた。
帰納法は成り立たない。過去の経験によってすでに知られていることから、未来についての妥当な知識を引き出すことはできない。
そして私達が自然に押し付けた法則は永遠に仮説に留まり、自然界から反証されてしまう可能性を常に残している。
人間が好む「法則」というものにもメスを入れる。
反復というものが見る者の観点に依存しているなら、反復がそれ自体として事象そのものに与えられているというのは誤っている。出来事の反復が観点に依存しその観点が経験に先立っているなら、私達の経験的世界が拡張されるにつれ、そのような観点が挫折する可能性は否定できない。つまり期待された反復が起きない可能性。法則も理論も永遠に仮説であり、原理的に反証されうるものであり、それらに対して絶対的信頼を寄せることはできない。
これらのことから、科学的態度とは批判的態度であり、肯定的証拠をかき集めることではないとの結論に至った。
反証可能性という言葉通り、言明は反証できる余地がなければならない。しかし反論されたくないばかりに、自身に封印を施し反証不可能にしてしまう人達がいる。
例えば、何か批判されたとき「君が私を批判するのは劣等感がそうさせてるのだ」と言うとする。
これ何を反論されようとも「それは劣等感だ」でいなすことが出来る。
また何でも説明できる言明。小河原氏の例が分かりやすい。
ある人が「明日の天気は雨であるか雨でないかである」と言ったとする。
これは明日が雨だろうが晴れだろうが、雪だろうがみぞれだろうがどんな天気だろうとこの言明は真ということになる。
じゃあこの言明はすごいのか?と問われると、全然すごくないのはすぐに分かる。
明日の天気が知りたい人にとっては無に等しい。つまり現実と関わっていない。
こういうのはやってる本人は愉快だろうが、その代償として「何も語っていないに等しい」
またポパーは、法則とは己と矛盾する出来事の生起を禁止していると表現する。だからこそこの禁止が破られた時に反証が生じる。
ここからポパーは、科学には、古来哲学者や科学者の多くが追い求めてきた確固とした不動の基礎はないという洞察に至る。このような科学のイメージは革命的実践、絶対的に真である階級闘争理論などには致命的となる(エンゲルスは『共産党宣言』で階級闘争理論は歴史科学の基礎となる使命を持つと語った)
この辺りの話はのちのマルクス主義批判に繋がっていく
■第三章 社会科学の方法
この章は主にポパーのヒストリシズム批判の解説。
ヒストリシズムというのは、社会科学の課題は長期的な歴史の予言の提供にあり、それは歴史上の出来事の成り行きを予見させる「歴史の法則」を発見すべきと信じる立場。私達は歴史を動かす巨大な力・リズムに動かされており、これに抗う術はない。よって法則を暴き未来を予知した少数のエリートに権力を集中させ、そのエリートに従い、巨大計画により一刻も早くその予知された社会を実現すべきという考え。
これが全体主義と独裁を導き、倫理を崩壊させるとしてポパーが弾劾したもの。
第二章まで読んだ読者なら、法則というのは永遠に仮説で、人間というのは必ず間違う。対等の立場で皆で話あって間違いを除去していくのが穏当だろう。小さな計画でも予期せぬエラーが起こるのに、巨大計画ではいくつエラーが見つかるか見当もつかない。権力を集中した人物が批判もされず野放しになるのは、法則をはき違えた時の被害も甚大にならないか、というポパーの説を理解してると思うので、このヒストリシズムの無謀さが良く分かると思う。
第二章とは違った視点から法則というものにメスが入る。
ヒストリシストは法則と傾向・トレンドを混同している。ヒストリシストのいう法則というのは実は傾向のことで、全く別物。傾向や流行は初期条件に依存する。初期条件が消滅したり変更が加えられればその傾向も消滅する。世界史には人間は戦い続けなければいけない法則があるのだろうか。いや、確かに古代世界は戦争ばかりしていたが、平和の理念、自由の尊重が人類に広まったとき戦いは激減した(第二次世界大戦後の欧州大陸)
貧困も国家が介入し弱者を救済したことで緩和され、革命を起こす機運は消滅した(予言成就のためにプロレタリアの貧困化を望まなければならなくなった逆説)
これはヒストリシズムの非科学性のほんの一部。
また巨大計画、ユートピア社会工学も批判する。
継起の法則や発展段階の法則は存在しない、真理を見つけてしまったと確信することは決してないというポパーからすると、これは無謀以外の何物でもない。
予期せぬエラーは必ず起こる、人間の無知は膨大であり驕ったり自己満足に浸ってはいけない特に権力者はと釘を刺すポパーにとっては、社会をすべて破壊し一から作り上げるなど正気の沙汰ではない。
エラーが起こると言ったが、まず計画が膨大すぎてエラーがどこにあるのかも分からない。そして膨大すぎてコントロールできないし、第一世代ではユートピア作りが終わらない。今の私達はこれらのことを試した国が50年以上経っても終わらなかったのを知っている。政策と言うものは現実的な期限で完成するものにしなければならない。このように不便をかけるから当然下から計画が終わらないことへの怨嗟の声が上がってくる。これは抑圧せざるをえなくなるし、そうすることのできる権力も都合よく持ち合わせている。しかし合理的な批判も抑圧せざるを得なくなるから、もう誰も彼らの間違いを正せなくなる。全てを良くご存じのエリートのみが権力をふるえるという考えから権力者の神格化が進み、この理由によっても批判が不可能になる。
ポパーは別の個所『開かれた社会とその敵』で、批判こそが間違いや誤謬を発見し、そこから体系的に学ぶことに至る唯一の道だと言っている(事実、基準そして真理、相対主義へのさらなる批判)
絶対的な正しさの基準を持っているとうぬぼれ、それゆえ他人の意見に耳を貸さずに次の社会を作り出さんとする人々は、学んでないし、進歩もしないということになる(独裁者がなぜ討論をしないのか、その理由も分かる。最も自分は、言い負かされるのが怖いからではないかと思っているが)
「未来の楽園のために現在の君達は犠牲になってくれたまえ!」
ここから私見
よりよい世界のために現在の人々が苦しんだり、反対したり協力しなかった人々が殺害されるのはおかしくないか。
酷い矛盾だと思う。
よりよい世界というのは、そういう犠牲が出ないような世界だと思う。
これについては『よりよき世界を求めて』
■第四章 開かれた社会とその敵
この本は政治と歴史についての新しい哲学であり、そして民主主義再建の原理の探求です。
それはまた文明に対する全体主義的な反乱を理解することに貢献し、そしてこうした反乱が民主主義的文明そのものと同じくらい古いものであることを示そうとするものです。
『開かれた社会とその敵』小河原誠訳・岩波文庫版第二分冊463ページ
『開かれた社会とその敵』はポパーの主著の一つで出版されたのは1945年だが、ポパー最晩年の1992年まで改定が行われた。これはポパーにとっても特別な著書だったと思われる。
執筆の動機は、独ソ不可侵条約に立ち向かうこと。二大閉じた社会が手をつないで、開かれた社会に大反乱を起こした時。
『ヒストリシズムの貧困』で全体主義と独裁に繋がる、そして知識を破壊するとして批判されたヒストリシズム、『開かれた社会とその敵』ではその具体的な担い手、プラトンとヘーゲルとマルクスが批判される。
ちょっと待って、あのプラトンが知識の破壊手?何かの間違いでは?と思うかもしれない。しかしプラトン賛美の伝統はヴィクトリア朝期に形成されたものに過ぎず、ポパー以前にもプラトンを批判した人がいなかったわけでもない。
閉じた社会とは、魔術的な、部族に縛られた、あるいは集団主義的な社会
開かれた社会とは、個人が個人的な決定と向き合う社会
・プラトン
人道主義者や自由の擁護者と一般的に思われてるプラトンが、実は全体主義と独裁の擁護者として弾劾される。
哲学者の王はプラトンでは有名かもしれない、具体的にどんな人物かというと、最高の英知である(変化・腐敗を停止させる)善のイデアを所有し、それを誇る者。ほとんど全知全能であり、神のごとき者。
これはソクラテスの知の観念の対極にある。ソクラテスは「自分がいかに無知か、いかに知らないことが多いかを知った」
ここまで読んだ読者なら、ソクラテス的謙虚さとプラトン的傲慢の目もくらむような対比、というポパーと小河原氏の評価に納得いくだろうか。
変化を停止させたいプラトンが提唱するのは、階級区分の完全な固定。プラトンは社会の腐敗は支配層が腐敗するから起こるのだと考えた。つまり支配層の血統を純粋に保つことが肝要。労働者や戦士の階級の者が支配層に混じってはいけない。
またプラトンの手腕で上手いなと思ったのは、個人主義だけを利己主義・エゴイズムと同一視させ、個人が自分の知力を使うことを覚え閉じた部族社会から離脱していくことを妨げたこと。
ポパーの表
個人主義 と対立するのは 集団主義
エゴイズム と対立するのは 博愛主義
これを見ると、集団主義がエゴイズムと対立するわけでもない。実際集団がエゴイズムに染まり、従わなければいけないルールなんかないのに、ただ自分達が助かりたいだけの利己主義により従わない人に圧力をかけたり強要したりする事例はある。
プラトンは集団主義を擁護するときは、自分を犠牲にする人道主義的感情に訴え、個人主義を攻撃するときだけ忌まわしいエゴイズムというレッテルをはった。
彼は、のちにカントが提唱しポパーに受け継がれた「知による自己解放」の理念の破壊力と恐ろしさを見抜いていた。これで全体主義が解体する。
結局プラトンの、個人主義と利己主義の同一視、人道主義を集団主義に吸収した手法は功を奏した。
ここらの原典は『国家』に詳しい。
ヒストリシズムの手法の一つ、現在ある社会をいったん全て破壊せよ、という要請もプラトンのもの。芸術家はまず画布をまっさらにしてから仕事に取り掛かる。
また支配者は国民に嘘をついていい、プロパガンダを使用していいと述べたり、『法律』では「矯正所」なるものまで提案している。神のごとき哲学王に従わない者は矯正施設に入れられる。それで「魂が救済された」者は監視下で生きていけるが、それでも従わない者は死刑。これがプラトンの理想国家(一番恐ろしいのは、現在でもこれを実践してる国があるという事実か)
『政治家』では、プラトン的理想国家では支配者は真なる知識を所有していることが支配者たる唯一の条件となり、その人物が金持ちだからとか評判がいいからとか全く関係ない。恐るべきは、この支配者が法律に従って統治していようといまいと関係ないとされること。大事なのはただ真の知識を所有してるかどうかだ。そして、そのような支配者は邪魔だと思ったなら人を死刑にしていいと言っている。法に関係なく気に入らないなら殺していい。
これは、様々な意見の人間がお互いを尊重しあい、自分が間違ってるかもしれないから批判して欲しいと謙虚になるべき、これでこそ知識が成長するというポパーが見過ごせる問題ではなかった。
プラトンに限らないが、このようなやり方では新しい社会の成否を検証することができない。初めから全ての計画が決まってる全体論的な取り組みでは、検証(批判)の余地が残らない。人々が暮らしやすい社会を形成するという要請が、新しい社会に適合する人間を形成するという要請に置き換わってしまう(『ヒストリシズムの貧困』)
そして、このような全ての社会的発展を停止させるような試みは「知による自己解放」、自分の知力を使う勇気を示した人には通用しないということ。無理矢理実現しようとすると異端審問と秘密警察のギャングの世界になるだろう。
またプラトンは、民主主義下の自由を放埓や無秩序と同一視して攻撃した。自由の恐ろしさを見抜いていたと思われる。なぜなら自由とは神のごとき哲学者(最高権力者)を批判できる言論の自由のことだから(現在の独裁者が同じようなレトリックで自由を攻撃している)
私はこういうところに開かれた社会の敵の狡猾さを見て、彼らは民主主義誕生と同じぐらい古くからいる、というポパーの主張を思い浮かべる。
彼らははっきりと、偉い自分を批判してくる自由が憎いとは言わない。さも私達に利益をもたらすかのように伝え、自由を排除しようとする。
・ヘーゲル
ポパーの本ではマルクスの前にヘーゲルが批判されている。が、本書ではヘーゲルの解説は割愛されている。
ヘーゲルとは
歴史的発展の法則を信じたヒストリシスト、にせ予言者の一人。哲学は森羅万象あらゆることについて知っている、どんなものでも答えて見せる、と見せかけた。ヘーゲル弁証法により科学的な研究をせずとも科学者として膨れ上がることに成功した。実は当時のプロイセンを歴史の達成物の頂点に祭り上げることが目的だった、絶対主義のために奉仕した。プラトンと現代の全体主義とを結合したヒストリシズムの環(左右の全体主義に自由を潰すための古代から存在していた永続的な武器を手渡した)。ヘーゲルの同時代人であったショーペンハウアーが手厳しく批判した。不誠実の時代と呼ばれた。矛盾を許容することで、あなた矛盾してますよと言われても「矛盾は世界を動かす力だからいいんスよ」と批判を回避することに成功した。
自分は何でも知ってるとか、この理論で何でも答えられるとか、反証回避戦略とか、ヘーゲルはポパーが何度も批判した要素を身に着けており、逆ポパーとしか言いようがない存在だった。ポパーの批判もプラトンやマルクスとはトーンが違う。そもそもヘーゲル哲学が不誠実でまともに受け取るものじゃないという。
・マルクス
マルクスは、プロレタリアの窮乏を救う道は、民主主義的議論で労働者と資本家の折り合いをつける・国家が介入し弱者救済の法律を作るという穏健的な可能性もあると想像できなかった、それは自身のお気に入りの理論(予言)を守護することに拘泥した結果だったが、そのおかげで労働者は武器を取って戦うしかないという破れかぶれの暴動戦略一本になってしまい、それ以上に武力と資金と権力を持つ資本家側に武力行使と弾圧の口実を与えてしまった。これをポパーは「ヒストリシズムの貧困」と名付けたが、貧困とは予言に目をくらまされた想像力の乏しさをいう。
①プロレタリアの絶対的窮乏
②階級の二極化、不可避の社会革命
③プロレタリアが勝利し社会主義の実現
ポパーはこれを必然的な法則ではなく、傾向を法則と混同し偽の予言となったもので、人々を暴力の方向に誤導したとして批判する。
批判は③からされていく。つまり①と②は前提として正しいものとされる。これは、論敵と同じ前提から違う結論を引き出すという意味で、批判としては強力だと小河原氏は述べる(岩波文庫版『開かれた社会』4分冊目450ページ)
法則とは己と矛盾する出来事の生起を禁止しているもの、だった。だから①②③それぞれと矛盾する出来事が起きたとき、マルクス理論に対して反証が生じた。それを「いや資本主義が崩壊しないのは、植民地から搾取して延命してるだけだ」と言い繕っても何の反論にもなっていない。
1992年に追加されたドイツ語第7版への序でポパーは
要約
「開かれた社会をマルクスが資本主義社会と名付け、今でもマルクス主義者が相変わらず資本主義と呼んできたが、これは今ではマルクスが知っていた社会とはほとんど同じものを持っていない。今や私はこう言いたい、マルクスが資本主義と名付けた社会は最初から存在しなかった、と。なぜならマルクスは社会革命なくしては改良できないと考えていたから。そのような社会は存在しなかった。私達の開かれた社会は、かつて存在した中でも最良にして変革を喜ぶ社会だ、各段によいわけではないが」
と語っている。
・民主主義とは多数派の支配にあらず
ポパーの民主主義論。
今でも開かれた社会の敵から絶えず自由と民主主義が攻撃されている。
最近の流行りはこうだ
「今の世の中の流れが速い。もう民主主義のように何か一つ決めるのにいちいち大勢で議論してたらこの速さについていけない。民主主義は捨てられ、独裁者が即決する世界になるだろう」
このように言われると、上手い反論が思いつかないかもしれない。
しかしこの言明は民主主義の本当の役割を覆い隠している。
民主主義とは多数派の支配にあらず、解職のメカニズムだ。
私達が普段選挙で何気なく行っているあれが、実は被支配者が支配者をコントロールし、支配者を暴力によらず取り換えている。私達は民衆の支配がしたいから民主主義を採用してるのではなく、たとえどんな悪辣な為政者だろうと暴力によらず解職することのできる機構の保証された唯一の体制だから採用しているのだった。
専制国家ではこのようなことは不可能だ。トップを取り換えるには暴力によるしかない、それは事実上交換が不可能であるに等しい。しかも優秀な指導者ならまだしも、ろくでもない明らかに悪と分かる指導者が誕生したらどうなる。餓死者が数百万人出ても、文化が破壊されても、自由を求めるデモも潰す、それでもトップが責任も取らずのうのうとのさばっていられる。民主主義を採用する人達はこのような社会を拒否している。知恵の木の実を食べた者が楽園に還帰することはない。
■第五章 思想の冒険――論争の哲学
批判的討論が知識を成長させると言ったポパーはウィトゲンシュタイン、アドルノ、クーンといった哲学者と論争した。
ウィトゲンシュタインは、哲学というのは言明されうるもの、つまり自然科学以外語らない。明晰化できない形而上学については語らない、とした。これは形而上学に無関心を装っても無駄だと言ったカントを継ぐポパーには聞き捨てならなかった。形而上学だって語る必要がある。形而上学を悪用するエセ宗教団体は批判する必要があるだろう。
アドルノは、ヘーゲルに影響を受け、つまらないことを大仰に、言葉を堆積させて人々を煙に巻く手法を使用していたが、ポパーはそれを批判した。また道徳的な価値を実証的事実(支配的な人倫や法)と混同していることを批判した。この混同が生じると現在の権力=正義という構図になり(ヘーゲル)、アドルノの場合は未来の権力=正義となる。これが独裁者に都合の良い論理であるのは言うまでもない。
クーンとは、フレームワークの神話についての論争。相対主義批判の一種。フレームワークが異なると相互批判は不可能なのか?いやそんなことはないというのがポパー。
■第六章 オープンユニヴァース
宇宙は開かれている
・非決定論
物理的な出来事も、心理的な出来事も全て前もって起こることが決定している、このような決定論が古代から唱えられていた。ポパーは非決定論の立場で、世界が非決定であるからこそ新しいものが生まれてくるという。宇宙が決定論だとしたらとんでもない矛盾が生じる。ある作曲家が1年後に作曲する曲を現時点で予測できるということになる。これは1年後の曲を現時点で入手しているということになってしまう。決定論だとしたら、未来において始めて知ることのできる知識が、現在の私達の歴史に影響を与えてもいいはず。これはヒストリシズムとの関連で述べれば、歴史を歴史の内部から予測することはできないということになる。
・三世界論
①物理的世界
②意識の世界
③客観的内容の世界
これらが相互に作用しているという考え。
世界3に属する客観的知識は、世界2とは別の独立した世界とされる。自律し客観的に存在している。円周率を全て把握してる人はいるだろか、また1、2、3、…といった無限の自然数列を全て把握してる人は。世界3は世界2・個人の頭脳の中に全て収まるものではない。芸術作品やその他の創作品も全てこの世界に属すものなので、全て収まるどころか、私達は世界3のほんの一部を知っているに過ぎず、大部分が無知である。
これは、その分野の全てを知っていることを要求する古い職業倫理、プラトンの神のごとき哲学者、全てを説明してやると大言壮語するにせ予言者、現在の独裁者への反論となる。
■第七章 倫理
個人的に一番面白かった章。ポパーが各地で語った倫理についての話がよくまとまっている。
ポパーの倫理、その首尾一貫性は不正との闘いであり「悪の排除」
人は何が善かは意見が分かれるが、何が悪かは意見の一致を見やすい。地獄への道は人々の善意によって舗装されるという歴史の現実を忘れない。高邁な理想を掲げた熱狂的な善への運動ではなく、悪の排除に眼目を置く。
またヒストリシズムによって倫理が崩壊することも指摘する。
・道徳的未来主義
確実に当たる未来予知が本当にあったとしたら、社会はどうなるだろうか。
未来予知が本当にあったら、倫理が成立する余地がなくなる。私はどのように生きるべきかとか考える必要もなくなる。どうしようとその社会は実現するのだから。何としてもその予測された社会を実現することが最優先になり、一刻も早く実現しなければならない、という一種独特の倫理が成立する。君達はどう生きるかとかもう頭を悩ます必要はない。歴史を動かす諸力に服従せよ、こうなる。
そしてマルクスとの関連で述べるなら、未来はよりよくなるのだから、未来の権力や道徳が正義ということになり、未来の道徳を現時点で代表してる人達の倫理を採用せよ、とこうなる。
未来が確実に分かる、なんて突飛な前提なのでこのような変な倫理になる。
未来予知に対する反論はなされたので、未来の道徳を現時点で代表してる人達の倫理を採用せよ、これを批判する必要がある。
仮に未来予知が本当に出来たとして、それでその人達の言うところの未来の倫理を私達が絶対採用しなければいけない決まりはあるのだろか。
小河原氏の分かりやすい例
タバコを吸うことが倫理とされる世界が確実に到来するとして、このとき私達は喫煙の道徳を採用しなければいけないのだろうか。そんなことはない、拒否し戦うことができる。どのような権威が下した命令だろうと、それを受け入れていいかどうか判断するのは私達だ。いかなる情報源にも権威はない、全てが批判にさらされる、これが開かれた社会の鉄則。その喫煙の道徳も批判にさらされる必要がある。
ここには現在あるものが事実として善という道徳的実証主義の未来版が働いている。現行の道徳以外に道徳的判断基準がないなら道徳への批判は不可能になるが、マルクス主義的形態はこの未来版。
道徳を採用するかどうかは私達の判断と責任になるが、道徳的未来主義はこの責任を免除する。なぜなら未来が確定してるならその方向に進めばいいだけで、道徳的決定に頭を悩ます必要はないから。
・報酬を求める倫理の拒否
ヒストリシストのもとでは倫理すらも歴史を動かす諸力の道具にすぎない。つまり歴史的成功という報酬のために倫理が存在する。ポパーは、このような倫理観は閉じた部族社会の名残、戦場で武勲をあげ英雄になれ、支配者になれさもなくば奴隷でいろといったロマンチックな道徳が基礎にあるという。このような倫理観は大事なのは少数の支配者で後の大多数は無視されていた時代の道徳。このような道徳は自由や平等を少しづつ実現していこうとする人々の道徳とはならない。
ポパーの対抗倫理は、どのような価値があってもいいが、誰もがその価値から自由でなければならない、というもの。
例えば、教師が生徒に人格の完全な発展などと称して高次の価値を押し付けてはいけない。
「全ての政治的理想のなかで、人々を幸せにしたいという願望くらい、危険極まりないものはない」『開かれた社会』
・古い職業倫理への批判
前述の通り、私達の客観的知は一人の人間が習得できることをはるかに超えている。これは人間というのは誰でも常に無知の状態であり差がないということ。むしろ知識を知れば知るほど己の無知が露になる。そして自分の知が明日には批判を浴びて古びてしまうことを思えば、自己満足になったりうぬぼれたりすることもなくなる。そして他人を尊重するようになる。つまり誤りを許容できる。
古い職業倫理は、その分野の一切の知識を習得せよ、知識を持つものは権威者たれ、誤りは許さない(誤りは多くの場合権威を守るため隠蔽される)
本書では省略されてるが、ポパーの文では具体的にどういう職種がこの古い職業倫理に陥りやすいか指摘している。
それは医学(『よりよき世界を求めて』)
Posted by ブクログ
●感想要約:
哲学者「カール・ポパー」の思想を専門外にもわかりやすく整理した入門書.「反証可能性」という科学の発展過程や誤りの排除の仕組みが主題です.700ページの大著を通して,「反証可能性」が科学だけでなく,進化論・歴史観・社会哲学・政治哲学にも広く適用され,「開かれた社会」や正義の基盤となるといった主張に深く感銘を受けました.一方で,この概念自体も反証可能であるべきではないかという問いもあり得ると感じつつ,長大ゆえ深い理解のためには再読の必要性を感じながら,現状では「自己批判的な態度と誠実さ」が重要だと理解するのでした.
●科学博士の書評指数:
楽しみ度:★★★☆☆
共感度 :★★★★☆
学び度 :★★★★★
話題度 :★☆☆☆☆
お薦め度:★★★★☆
●概要:
20世紀哲学を代表するカール・ポパーの思想を,専門外の読者にも理解できるように整理した入門書です.ポパーが打ち立てた「反証可能性」を中心に,科学理論がどのように発展し,誤りを排除しながら真理へ近づこうとするのかを解説しています.また,進化論・歴史観・社会哲学・政治的立場などへと思想を広げ,「開かれた社会」の意義を紹介.ポパーの思考の一貫性を,論じる概説書です.
●感想:
・科学の定義としての「反証可能性」というキーワードを生み出した哲学者「カール・ポパー」に興味を持ち,700ページ近くの長大なこの本を読み始めました.2週間近くかかってしまいましたが,大変読み応えのある本だと感じました.
・ポパーの主張する「反証可能性」という観点が,純粋な「科学」という分野だけでなく,進化論・歴史観・社会哲学・政治哲学と幅広い分野に適用されている事が非常に印象に残ります.さらに,各分野での「反証可能性」に基づく開かれた社会と言う考え方に代表される意義について検討されており,思想・学問・政治における正義というか,正しさという事へ導く基本的な考え方が提案されていると感じました.
・多分、「反証可能性」は間違っていないと思うのですが,「反証可能性」という考え方にも「反証」される可能性があることを認めないといけないので,そこはどう考えれば良いのだろうか?と思うのでした.
・幅広い分野に適用可能な汎用性を持つ考え方「反証可能性」は,まさに哲学という学問の重要性を実感させてくれると思います.実用性という観点からは,ちょっと遠い世界かもしれませんが,人類が共通に持つべき倫理観といった考え方につながるなと感じるのでした.この本の中でも倫理観と関連する「正義とは?」について論じられています.
・正直,長い本なので,自分の中で体系化して理解することは出来ていないです.気になったチェック点を見返すと,断片的にしか理解できず,より良く理解するためにはもう一度読み直さないといけないと思うのであります.その中で,あえて一文をあげるとすると,最後の部分に記載されている「自己批判的な態度と誠実さが義務となる」を挙げたいと思います.この考え方は「反証可能性」の考え方につながる重要な一文であると自分は理解しました.