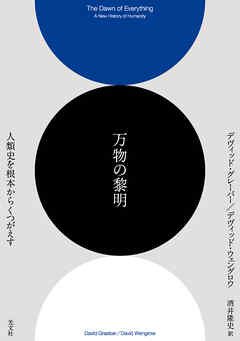あらすじ
『負債論』『ブルシット・ジョブ』のグレーバーの遺作、ついに邦訳。「ニューヨーク・タイムズ」ベストセラー。考古学、人類学の画期的な研究成果に基づく新・真・世界史! 人類の歴史は、これまで語られてきたものと異なり、遊び心と希望に満ちた可能性に溢れていた。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
やっと読み終わった、という感じ。だが、それに見合う本だった。世界の見方を変えてくれる本というのはそうそうあるものではないが、本書は自分にとってまさにそういった本の一つとなった。多分、何度か読み返してそのたびに考察のヒントを与えてくれそうな予感がする。
一般に流布している人類史の見方として、1 人間集団はその規模を拡大するにつれて複雑化するため、やがて集団を制御するための非生産階層が必要となり、その階層が集団を支配するようになる。2 規模の拡大につれて支配層が分厚くなり、ヒエラルキーの度合いが増大する。3 農業などのテクノロジーにより、規模拡大が加速し、ヒエラルキー形成が加速する、といったところがあると思うが、それらを裏付ける証拠は何もない、人類の発展はもっと多方向で自由なものであった、ということが趣旨と思われる。
人類はどうしても自分が一番可愛いものと見え、近年のビッグヒストリーに関する論説では、現在ある社会を前提としてそれをバックキャストして過去の社会を考える傾向にある。そうすると、社会は基本的に複雑化の階層を進む一直線な発展の仕方しかなく、過去のより小規模な社会は現在の社会に至る途中段階の一つという見方をされてしまい、現在を「プラスの到達点」と考えれば、過去の社会は「未開」ということになってしまう。あるいは現在を「マイナスの到達点(資本で堕落しているなど)」とすれば過去は「本来の人間性を持つ理想郷」になる。
だが現在の社会はあり得た到達点の一つにしかすぎず、過去の社会は人口の規模、農業の有無などに関係なく、自分たちにとって望ましい社会を試行錯誤しながら、時には複数の体制を行き来しながら社会を作り、壊し、移りゆきながら生きてきた、というのが本書の要点の一つと思われる。他のビッグヒストリーを扱う論評と異なり、多くの古代遺跡という物証をもってそれらが推察されている。そうだとすれば、現代社会のなんと画一的で非人間的なことか。「民主主義は最悪の政治形態である。これまでに存在したすべての政体を除いたとすれば」などと得々としていながら、実際には多くの可能性を自ら捨て去って「閉塞」していたわけだ。
思うに、これまでのような現代社会を「到達点」とみなす考え方は、自分可愛さということもあるが、キリスト教の影響(すなわち、西洋的な思考)も大きいのではないか。本書でもそのような感触の記載はあるが、一神教で神から選ばれた人類が世界の最高到達点である、という考えに立つと、それ以外の生物、および神に祝福されていない人類は、どうしても一直線のゴールに向かう途中段階とみなされるようになる。最高到達点の神に認められた人類からすれば、まさに「下等」というわけだ。予定説に従えばさらにその傾向は強まるはずで、意識しようとそうでなかろうと、神を頂点にする神聖さのヒエラルキー、という見方が強く影響した西洋文明が支配的になると、そうした歴史の見方に偏るのも無理はないと思う。
過去の人類が、規模や技術発展に関係なく、ヒエラルキーによらない相互扶助的で男女同権的な社会を築けていたとしたら、なぜ人類はそれを捨ててしまったのか。本書の範囲内ではまだ明確な結論は得られていない(これからの研究に待たなければならない)が、行き過ぎたケアリングが権力と結びつくなどのいくつかの可能性が示唆されており、考察しがいがある。
個人的には、人間が思考のリソースを節約する傾向を持つことも関連しないか、と思っている。社会の規模が大きくなりつつも自分で社会と積極的にかかわって社会を運営していくことが必要だと、どうしても考えるべきところが多くなり、思考が大変になる。そうしたときに、何かの理由で大規模な計画に大勢を動員するようなことが起こると、「誰かの指示に従うことによる思考リソースの節約」に味を占めるものも出てくるのではないか。いったんそれが定着すると、支配者と被支配者が共依存の関係になり固定化が進む、ということもあるように思う。
ちなみに個人的にはハラリ氏やダイアモンド氏の著作が大好きなので、彼らの論説がポップ人類史扱いされているのは少し悲しいが、それもやむなしと思うほどの圧倒的な説得力であった。