無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
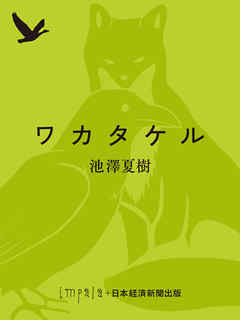
『古事記』現代語訳から6年、待望の小説が紡がれた!
神話から歴史へのあわいの時代に
森羅万象を纏った、若く猛る大王が出現した
暴君であると同時に、偉大な国家建設者。
実在した天皇とされる21代雄略の御代は、形のないものが、形あるものに変わった時代。
私たち日本人の心性は、このころ始まった。
時代の転換点の今こそ、読まれるべき傑作長編! !
時は5世紀、言葉は鳥や獣、草木たちにも通じていた。歯向かう豪族たちや魑魅魍魎を力でねじふせ、國を束ねるワカタケル大王(雄略天皇)。樹々の合間から神が囁き、女たちは夢の予言で荒ぶる王を制御する。書き言葉の用意のない時代、思いを伝える歌と不思議な伝説、そして残された古墳の遺物や中国の史書……。作家は言葉の魂に揺さぶりをかけ、古代から現在に繋がる、「日本語」という文体の根幹に接近する――
令和改元をまたいで日経新聞朝刊に連載された小説がさらにパワーアップして単行本化。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。