無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
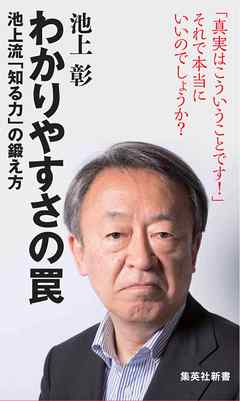
コピペやフェイク紛いの「エセ情報」が、インターネットやSNS、さらには新聞や日常会話にまで溢れている。安易な「わかりやすさ」を売りにするバラエティ番組は、事態をさらに悪化させている。私たちは、どうすればホンモノの「情報」や「知識」を得られるのか? ニュースの世界における「わかりやすさ」の開拓者が、行き過ぎた“要約”や、出所不明の“まとめ”に警鐘を鳴らし、真の情報探索術を伝授する。日本で最も「わかりやすい」解説者がその罠について論じた、池上流・情報処理術の決定版! 【目次】序章 「わかりやすさ」への疑問/第一章 その「わかりやすさ」、大丈夫ですか?/第二章 ネットの「真実」の向こう側/第三章 「知る力」を鍛える/第四章 「わかりやすさ」のその先へ
...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。