無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
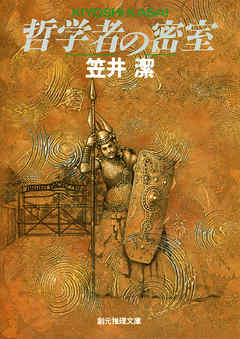
三つの事件を経て、矢吹駆に対する自分の感情を持て余していたナディア。そこに起こった新たな事件は、頭部を殴打され、背中に刺傷を負った死体が、誰も入ることのできぬはずの三重密室の中で発見される、という衝撃的なものであった。さらに、その謎を追う彼女の前に、第二次大戦中、コフカ収容所で起こった密室殺人事件が浮かび上がってくる。二つの事件の思想的背景には、二十世紀最大の哲学者のある謎が存在した。ナディアに請われ、得意の本質直観による推理で事件に立ち向かう矢吹駆の前には宿敵イリイチの影が……!? 現代本格探偵小説を生み出した大量死の謎をも解き明かす、シリーズ最高傑作の呼び声高い第4作。/解説=田中博
...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。