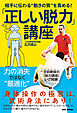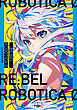感覚神経作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 力の消失ではなく“最適化” 「力まない」ことは「力の消失」ではない。 動かす部分と動かさない部分を分け、適切にコントロールすることだ。 それによってラクに動け、最大の力が伝わる。 意外と気づけない「コロンブスの卵」的発想! 武術、スポーツ、芸事はもちろん、日常動作でも使える。 空前絶後の「脱力講座」、いざ開講! 「月刊秘伝」の好評連載が遂に書籍化!! 身体操作の極意は、武術身法にあり! 一瞬で読者を「脱力」に導く(!?)イラストが盛り沢山! 写真解説で誰でもすぐにコツを掴める! CONTENTS ●第1回 重心移動と腰の分離 脱力とは力のバランスをコントロールする技術 人間の重心移動 重心移動の実験 重心を分離して動かすためのエクササイズ 重心移動と体重移動の違い 重心移動による〝従身移動〟 ●第2回 距骨で立つ 安定して立つためには三点の支えが必要 距骨に体重を乗せる かかと側とつま先側との重さを受け止める配分 つま先立ちでも同じことができる 鳥のように軽やかに ●第3回 肩甲骨をしめる 肩甲骨を使いこなすために必要なこと 腕と肩甲骨を分離させて動かす 「肩甲骨をしめる」とは? 「肩甲骨をしめる」感覚を掴む 「しめる」と「固める」の違い ●第4回 重力でしゃがむ まっすぐしゃがむ まっすぐのラインを身体の外に設定する 重さを感じ取る いかに筋力を使わないかが大事 ●第5回 重力をつなげる お腹で重さを感じ取る 左右の腕の重さを一つにする 全ての人や空間は重力でつながっている 重力の可能性 ●第6回 手の内を感じる 手指は身体全体につながっている 「手の内・手の外」「内手首・外手首」への意識 手の内で車線を増やす 手の力の使い方からはじめることは合理的 ●第7回 足の内ゾーン 「足の内」の感覚を掴む 「足の内ゾーン」を意識する 何もない空間をイメージするコツ まずは足の内側にしっかりと意識を向ける 手のように足を使いこなす!? ●第8回 股関節をゆるめる 股関節の脱力 自分と相手は鏡合わせのように影響し合う 坐骨に重さを乗せる 股関節や内転筋の感覚を掴む 股関節を意のままに動かせるように ●第9回 仙骨のしめ 帯をしめることの効果 ターンアウトで仙骨をしめる感覚を掴む 実際の重さと主観的に感じる重さの違い 「役に立つ脱力」をつくり出す 脱力の稽古は足し算ではなく引き算 ●第10回 丹田と輪郭 丹田の位置 丹田の輪郭を感じ取る 肛門括約筋を使う 丹田とそれ以外の境界線をつくる 肛門と肚(丹田) ●第11回 丹田と手 手の感覚を使って丹田の意識を強化する 両手を意識することと姿勢の安定 丹田を貫く棒 ひもを使う 丹田から手足が伸びているイメージ ●第12回 見えない力 相手に気づかれないほどの小さな力=見えない力 意識した段階で身体は反応する 弱い力を感じ取るには無駄な力を抜いておくこと 丹田に意識を向ける 技術を高めていくことで見えてくるものがある ●特別編 感覚神経と手の内 神経の働きを理解する 感覚神経を使った手の内にする 大事なのは手の内を「感じる」こと 「考えるな、感じろ」
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量20,000文字以上 24,000文字未満(20分で読めるシリーズ)=紙の書籍の40ページ程度) 【書籍説明】 内容の一部紹介。 「第3章 幼児前期(1歳~2歳)のはたらきかけ」より …ものが数えられるようになったら、つぎはものの量の理解です。みかんを「…3、4、5」とかぞえたら、すぐにみかん全体を指して「5こ」と言ってあげます。これで子どもは、最後に言った数がそのものの量であることを理解していきます。子どもの両手の指を順にタッチして、「…9、10。10ぽんだね」などと遊んでもいいでしょう。… 「第6章 はたらきかけがうまくいかないときは」より …現代の日本はなぜか、道徳心と、安全と、効率がとても求められる社会です。これは好奇心の持続にとってはマイナスです。とりわけ子どもの好奇心にとって、必要以上の道徳や安全や効率は、じゃま以外のなにものでもありません。 子どものいたずらは、ちいさな範囲にとどまるかぎり、大目にみましょう。命にかかわる危険でないかぎり、危ないことは身をもって体験させましょう。そしていろんなムダを経験させましょう。… ほかにも目からウロコの情報がいっぱいです。乳幼児を子育て中のママ必見! 【目次】 第1章 「ことば」「数感覚」「神経」がポイントなわけ ○ことばの能力は親子関係と学力の基礎 ○勉強でいちばんつまずきやすいのが算数・数学 ○神経を行きわたらせて、心身のバランスのとれた子どもに 第2章 胎児期・乳児期(~1歳)のはたらきかけ ○はたらきかけをするときの3つの注意点 ○胎児期・乳児期における「ことば」のはたらきかけ ○乳児期における「数感覚」のはたらきかけ ○乳児期における「神経」へのはたらきかけ 第3章 幼児前期(1歳~2歳)のはたらきかけ ○「ことば」のはたらきかけ:絵本 ○「ことば」のはたらきかけ:文字遊び ○「数感覚」へのはたらきかけ ○「神経」へのはたらきかけ 第4章 幼児中期(3歳~4歳)のはたらきかけ ○「ことば」のはたらきかけ ○「数感覚」へのはたらきかけ ○「神経」へのはたらきかけ 第5章 幼児後期(5歳~6歳)のはたらきかけ ○「ことば」のはたらきかけ ○「数感覚」へのはたらきかけ ○「神経」へのはたらきかけ 第6章 はたらきかけがうまくいかないときは ○子どもがいやがる ○子どもが興味を示さない ○何事にも好奇心がうすい ○はたらきかけをするのが苦痛だ
-
3.5
-
-耳鳴りが聞こえ、耳鳴りはだんだん高周波かつ大きな音になる。 手足の筋肉が硬直し、電気刺激のようなビリビリした振動を感じるだろう。 このビリビリする振動は肉体の感覚神経が幽体と遮断され幽体の感覚が優位になるときの兆候で、麻酔にかかったように肉体の感覚が麻痺する。 そして今度は幽体の感覚が残っていることに気づく…… 幽体離脱のやり方からトレーニング法までを紹介。28日間でマスターする訓練コース付! さあ、未知の世界に飛翔しよう!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 オールカラー・イラストと簡潔な解説で生命システムの不思議をやさしく学べるビジュアル図鑑。 〈本書の特徴〉 (1)器官別だけでなく「しくみ」で学ぶ 脳・心臓・血管などの「器官別」だけではなく、細胞分裂・免疫・消化などの「しくみ別」に学べるから、全体のはたらきが理解できます。 (2)イラストだから直観的にわかる 適度にディフォルメされたオールカラー・イラストで、複雑なしくみも直観的に理解できます。生々しい人体写真は苦手……という方も安心。 (3)情報がコンパクトで読みやすい それぞれのテーマは見開き(2ページ)単位で簡潔にまとまっているので、興味に合わせてどこからでも、短い時間で読むことができます。 (4)コラム形式でさらに気軽に 「応用コラム」、「Q&Aコラム」、「雑学コラム」など、各テーマは多彩なコラム形式でまとまっているので、長々とした文章を読む必要がありません。 (5)体から心まで幅広いテーマを網羅 体の物理的な構造だけでなく、ホルモンなどの化学的な反応、脳や神経に関わる精神的な事柄まで、人間の不思議をさまざまな切り口で解説しています。 〈各章の主なテーマ〉 第1章 顕微鏡で見ると(細胞分裂のしくみ) 第2章 支え合う(体の構造) 第3章 活動中(筋肉や運動神経のしくみ) 第4章 感覚(感覚神経のしくみ) 第5章 物事の本質(血液の循環) 第6章 入口と出口(消化器官のしくみ) 第7章 体調と健康(免疫のしくみ) 第8章 化学物質のバランス(ホルモンのしくみ) 第9章 命のサイクル(生殖のしくみ) 第10章 心のはたらき(脳や精神のしくみ)
-
3.0
-
-2050年、東京――現実(リアル)と仮想(バーチャル)が融合した超越現実(MR)社会。人々は脳内のMR感覚神経(チップ)によって、かつてなく便利で快適な生活を享受していた。原因不明のMRバグを抱えた高校生・タイキを除いて――。はじまりは“空飛ぶ幽霊”の噂だった。MRアバターの連続投身自殺……犯人を追うタイキは、屋上でひとりの“少女”と運命的に出会う。バグ少年とAI少女が、心の闇と対峙する近未来青春小説!