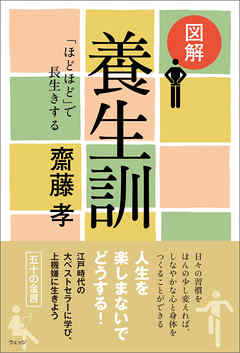あらすじ
■大好評、齋藤先生の図解シリーズ第2弾!
江戸時代に大ベストセラーとなった、貝原益軒の『養生訓』。いまでも、健康ガイドの先駆けとしての『養生訓』に学ぶことは多々あります。とはいえ、実際に読み通したことのある人は意外にも少ないのではないでしょうか。
本書は、昨年出版した『図解論語』に続く、シリーズ第2弾です。50の金言として取り上げた益軒の言葉は、言葉そのものが心の支えになります。今回も、わかりやすく図解にし、先生自身のエピソードをふんだんに盛り込みました。また、各項目には、誰もがすぐに実践できる健康法として「齋藤孝の今日からできる養生法」も加えました。『養生訓』を既に読んだことがある人にも、まだ読んだことがない人にも、養生を実践していくためのきっかけとなる、読んで良し、実践して良し、の1冊です。
第一章 生きる力──養生の基本
第二章 飲食の心得──何をどう食べるか
第三章 日々是好日──心をととのえる
第四章 健康配慮社会の到来──身体をととのえる
第五章 年を重ねるほど「ほぐれる」生き方──人生の楽しみ
[著者プロフィール]
齋藤孝(さいとう・たかし)
明治大学文学部教授。1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学院教育学研究科博士課程を経て現職。専門は、教育学、身体論、コミュニケーション論。『まねる力』(朝日新書)、『語彙力こそが教養である』(角川新書)、『新しい学力』(岩波新書)等、著書多数。
※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『図解 養生訓─「ほどほど」で長生きする』(2017年3月20日 第3刷)に基づいて制作されました。
※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
貝原益軒の『養生訓』を齋藤孝さんが抄訳し、解説をつけた本。
昔おじいちゃんおばあちゃんがよく言っていたような事だけれど、今はすっかり忘れられているような生活の知恵的な話が多く、はっとさせられる。
どこかのテレビ番組で、ドイツ出身の人が「日本では毎日が修行なのだ」とポツリと話していたのを今でもよく覚えているが、この本を読むと、その意味が身に染みる。
Posted by ブクログ
養生訓の基本は欲望をほしいままにしない(恣にしない)
内なる欲望(飲食、好色、眠り、言葉をほしいままにする欲、七情の欲)
外からやってくる邪気(風、寒さ、暑さ、湿り)
七情の欲とは感情のこと(喜び、怒り、憂い、思い、悲しみ、恐れ、驚き)
これらが身をそこなう
心配事は振り落とすように軽くジャンプする
手足をブラブラさせて巡りをよくする
アロマオイル
ヨーグルトで腸内の世話をする
「たのむ」自信過剰を慎む
ほしいまま=恣を忍=節制に変える
身体の内なる声に耳を傾ける
何を食べたいのか、何をしたいのか、身体の声を聞く
バランスのとれた食べ方、同じものを食べ続けない、幕の内弁当
腹八分目、酒は微酔のみ
食細くして命ながかれ=114歳の長寿者の健康の秘訣
食べ過ぎると不幸になる、楽しみの絶頂は悲劇の元になる
福沢諭吉は大酒飲みだったが禁酒した
食事のときは怒り、憂いを忘れる
いただきます、は忘れるための合図
体を冷やす冷水は飲まない
日本に生きているだけで幸せ、という基準をもつ
なにをしても幸せに感じられる。
これがあれば幸せ、というもののリストをもつ(ビール、新聞、本、山)など
これを少し嗜んで幸福感を得る。やりすぎてはいけない
できないことがあることを知る
餃子であれば全部うまい
反省しても後悔するな
失敗したら失敗は天からのミッションと思うこと
養生の道は怒りと欲をこらえること、
過ぎたる欲をもたないこと
怒った時は、間違いを箇条書きにする、その間に怒りも収まる。
アロマオイル
目に生気のある人は長命である
3・2・15呼吸法
羽生名人でも将棋には尽きないほどに学ぶことがある、といっている
何事も深く掘り下げて学ぶことは長生きにつながる
学ぶと長生き、をセットで考える
三楽=善を楽しむ、健康、長く楽しむ
今日一日を楽しんで過ごす
笑う 落語や映画のDVD、エッセイ、土屋賢二、リリー・フランキー、辛酸なめ子、ウッドハウスのそれゆけジーヴス、など
Posted by ブクログ
江戸時代の儒学者、貝原益軒の書いた「養生訓」の要約書。
著書が養生訓の内容を一部抜粋し、その教えを現代に合わせてアレンジしたもの。
健康関係の本を読むとたびたび出てくる「養生訓」。
原本に当たるのはちょっとしんどそうだったのでこちらを読んでみました。
〇変わらない体と変わっていく生活習慣
日本人は腸の長さが他の国の人よりも長い。
それは、穀物を中心とした食文化が長年根付いたことに体が適応したため。
日本の食文化は戦後急激に欧米化したが、数千年にわたる穀物中心の生活で作られた体は変わらない。
そのため、肉や牛乳、アルコールに適応できない人がいる。
〇万の事、皆わがちからをはかるべし
→何事も、自分の力の及ばないところで無理をするな。自分の力量を知って行いなさい。
〇凡の事十分によからんことを求むれば、わが心のわづらひとなりて楽なし。
いゝさかよければ事たりぬ。
十分によからん事を好むべからず。
→すべて完全にやろうとすると、負担になって楽しめなくなる。
多少でもきにいればよい。完全無欠なものを好んではいけない。
→何事もほどほどに、6,7割良ければそれでよしと考える。