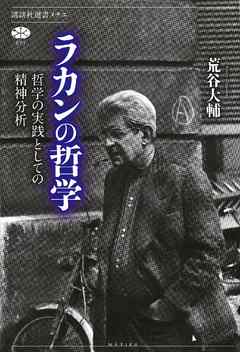あらすじ
フロイトが創始した精神分析を刷新し続けた不世出の存在、ジャック・ラカン(1901-81年)。1953年から最晩年の1980年まで続けられたセミネールでは何が起きていたのか? 主著『エクリ』をも読み解きつつ、セミネールの全展開を時系列順に通観していく本書は、ラカンを「哲学」として読むことによって前人未到の眺望を獲得していく。気鋭の哲学者が渾身の力をそそいで完成した、平易にして画期的な本格的概説書!※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ラカンのテクストを年代順にとりあげ、その哲学的な意義を解明する試みです。精神分析の実践の場面からラカンのテクストを読み解くのではなく、あくまでテクストに内在的な解釈をおこなっているところに、本書のもっとも大きな特徴があります。
ラッセルのパラドクスやうそつきのパラドクスに対するラカンの考えを整理している箇所や、晩年のボロメオの環をめぐる議論につきしたがってていねいな検討をおこなっている箇所は、個人的には興味深く読めましたが、不毛な試みに感じる読者もいるかもしれません。ただし、本書がめざしているのは、あくまでラカンのテクストの整合的な解釈を示すことであり、そのかぎりにおいて本書の議論はじゅうぶんな成功をおさめているといってよいと思います。
もし、本書の議論に不毛さを感じるとすれば、それは本書によって解き明かされている「ラカン」よりも、本書の解読の下敷きになっている「哲学」のほうにあるのではないかという気がします。著者は、カントが認識主体の成立をただ超越論的に要請していたのに対して、ヘーゲルは『精神現象学』の「主人と奴隷の弁証法」にかんする議論のなかで、奴隷たちが「われわれ」としておなじ自己意識を獲得するにいたるプロセスを明らかにしていることをとりあげ、ラカンの「哲学」にもこれとおなじ企図が認められると考えています。ただ、こうした粗い図式だけではラカンの哲学の意義がいまだ明確になっていないように感じてしまいます。たとえば本書でもくわしく解説がなされている「四つのディスクール」について、マルクスやアルチュセールの思想の哲学的な意義とのつながりに言及があれば、読者にもラカンの思想の「哲学」としての意義が明瞭に理解されるようになっていたのではないでしょうか。