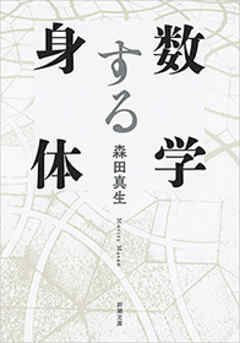あらすじ
数学はもっと人間のためにあることはできないのか。最先端の数学に、身体の、心の居場所はあるのか――。身体能力を拡張するものとして出発し、記号と計算の発達とともに抽象化の極北へ向かってきたその歴史を清新な目で見直す著者は、アラン・チューリングと岡潔という二人の巨人へと辿り着く。数学の営みの新たな風景を切りひらく俊英、その煌めくような思考の軌跡。小林秀雄賞受賞作。(解説・鈴木健)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
アラン・チューニングと岡潔の数学、心、身体、自然とのつながりなど。
いずれも、映画化やドラマ化された人物だ。
アラン・チューニングについては、映画「イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密」(2014年)
岡潔については、ドラマ「天才を育てた女房~世界が認めた数学者と妻の愛~」(2018年)
映画やドラマは、脚本家や監督によって見せ方のアプローチが違うだろうから、映画やドラマがすべてではないだろう。
この本は、特に岡潔さんの魅力が伝わってくる。
小川の流れについては、ドラマでも描かれていて、私はそのシーンに衝撃を受けたけど、この本を読むと、そのシーンは実際何を伝えたかったのか、今ようやくわかった。
この本は、自分の心が動かされる。
詳しくここでは書かないけど、感動が伝わる。
Posted by ブクログ
遺伝的アルゴリズムのような人工進化では、磁束などのノイズをリソースとして活用した効率的な回路ができる話は面白い。科学的な思考をもとにしたエンジニアリングではノイズとリソースを明確に分けるが、自然的で即興的なブリコラージュではノイズもリソースもありものの材料として組み合わせて世界を創る。
人類にはまだ理で理解できないこの世界の全体感を、全身とこころで分かろうとする岡潔のアプローチの素晴らしさを改めて感じられる一冊。これが本来の日本のこころなのかも。
Posted by ブクログ
数の歴史から数学史の話を通して、「数学する」とは何か、「数学する身体」とは何かについて語り、ヒルベルトやチューリングにたどり着く。そして数学を数学する者としての岡潔の解説を行うと同時に文学的な物語を語っている。
数学に関する本ではあるものの数学の本ではない。何の本かと聞かれるとこれという表現が見つからない。
改めて数学というものを考えるきっかけになる本
Posted by ブクログ
#ヨンデルホン
#数学する身体 / #森田真生
#新潮社 #ドクリョウ #ヨミオワリ
もっと集中して読むべきであったか。まぁ、本は逃げない。次は、じっくり。俄然、岡潔を読んでみたくなった。
Posted by ブクログ
著者の数学に〈情緒〉動かされてる体験がひしひしと伝わってくる。学問の探究へと道を進む稀有な人たちって何かしらこういう信念と、出会いがあるんだろうなと胸踊る内容です(本書の本筋ではないので、悪しからず)。
チューリングと岡潔を軸に、数学と身体というテーマを深ぼっていく構成。恥ずかしながら岡潔の存在を知らず、こんなに観念的な数学との付き合い方があるんだと目から鱗状態になりました。
チューリングの数学を道具として利用して人間と心と数学の境界を暴きにいくアプローチ対して、岡潔は心の奥深くは分け入る行為そのものこそが数学であるという立場をとる。どちらも魅力的で勝つ痺れる対比で捉える筆者の洞察力に傑物感が窺い知れます。同世代ということで、すごい人っているんだなーと単純に感動しちゃう。
丁寧に論を進める筆致と、そのテーマの深淵さかつ引き込まれるその面白さを十二分に堪能できます。数学に興味があってもなくても、必読となっておりますよ。
Posted by ブクログ
これを10代で読んでいたら数学に対して興味や愛情を持てた可能性すらあるな…と、数学が大の苦手だった私でさえ思うほど、数学の新しい捉え方を教えて貰った。面白かった。
Posted by ブクログ
センスオブワンダー、岡潔のエッセイの編纂?でぼんやりと存在を知り、数学ってホントはなんなのだろう、と思って手に取りました。
いや、なるほど、数学の歴史を知るとこんなにも世の中のことや、学術界の変遷を感じることができるのか、と脳がわくわくどきどきしています。
読み終わる前に『計算する生命』を入手。読み始めたところ。
これもまた、脳と感情が喜ぶ本です。こういう理解ができていれば、高校数学ももっと楽に理解できていたよな、と思います。
そして、数学は生活につながっている、といことをびりびりと感じます。
Posted by ブクログ
本書は数学書ではなく、「数学する」ことについて思索した哲学書だ。
著者の森田真生氏は「独立研究者」というちょっと変わった肩書きで、スマートニュース会長の鈴木健氏からの影響で文系から東大数学科に転向したという経歴の持ち主。
読み進めるごとにセンスオブワンダーが溢れてくるのだが、本書を30歳の若さで書き上げたというのだから驚き。
前半では数学史を辿りながら、数学と身体との結びつきについてその起源から洞察がなされる。
数式はほとんど出てこないので、数学が苦手な読者でもスイスイ読み進められる。
後半では著者が影響を受けたアラン・チューリングと岡潔の魅力が語られ、心の問題にまで踏み込んだ少し抽象度の高い論説が展開される。
アラン・チューリングといえば「コンピュータの父」「人工知能の基礎を作った天才」であり、昨今のAIブームにつながる話にも触れられているので、興味のある方はぜひ。
うむうむむ。難しい。のにおもしろい。
ーーーーーーー一以下、抜書きーーーーーーーー
.
起源にまで遡ってみれば、数学は端から身体を超えていこうとする行為であった。数えることも測ることも、計算することも論証することも、すべては生身の身体にはない正確で、確実な知を求める欲求の産物である。曖昧で頼りない身体を乗り越える意志のないところに、数学はない。一方で、数学はただ単に身体と対立するのでもない。数学は身体の能力を補完し、延長する営みであり、それゆえ、身体のないところに数学はない。古代においてはもちろん、現代に至ってもなお、数学はいつでも「数学する身体」とともにある。
.
〝数〟は、人間の認知能力を補完し、延長するために生み出された道具である。「自然数(naturalnumber)」という言葉があるが、それは決してあらかじめどこかに「自然に」存在しているわけではない。「自然」と呼ばれるのは、もはや道具であることを意識させないほどに、それが高度に身体化されているからである。
.
例えばオーストラリアのヨーク岬とパプアニューギニアの間にあるトレス海峡諸島の原住民は、両手だけでなく、肘や肩、胸や足首、膝、腰など、全身を使って33まで数える方法を持っている。中世ヨーロッパにおいては、両手の指を使って9999まで数える方法があった。しかし、身体の部位には限りがあるから、いずれにしても限界がある。
.
ところが紀元前五世紀頃のギリシアを舞台に、それまでとは異質な数学文化が花開く。計算によって問題を解決することよりも、「証明」によって結果の正当性を保証するプロセスに重きを置く姿勢が生まれたのだ。ギリシアの数学者たちは、「いかに」答えを導き出すかという技術以上に、「なぜ」その答えが正しいかという理論に拘った。とりわけ象徴的なのが、ユークリッドの『原論』である。
.
私たちが学校で教わる数学の大部分は、古代の数学でもなければ現代の数学でもなく、近代の西欧数学なのである。数学は初めからいまの形であったわけではなく、時代や場所ごとにその姿を変えながら、徐々にいまの形に変容してきたのだ。
.
チューリングは数学の歴史に、大きな革命をもたらした。〝数〟は、それを人間が生み出して以来、人間の認知能力を延長し、補完する道具として、使用される一方であった。算盤の時代も、アルジャブルの時代も、微積分学の時代においても、数は人間に従属している。数はどんなときにも、数学をする人間の身体とともにあった。チューリングはその数を人間の身体から解放したのだ。少なくとも理論的には数は計算されるばかりではなく、計算することができるようになった。「計算するもの(プログラム)」と「計算されるもの(データ)」の区別は解消されて、現代的なコンピュータの理論的礎石が打ち立てられた。
.
岡潔によれば、数学の中心にあるのは「情緒」だという。計算や論理は数学の本体ではなくて、肝心なことは、五感で触れることのできない数学的対象に、関心を集め続けてやめないことだという。自他の別も、時空の枠すらをも超えて、大きな心で数学に没頭しているうちに、「内外二重の窓がともに開け放たれることになって、『清冷の外気』が室内にはいる」のだと、彼は独特の表現で、数学の喜びを描写する。
.
チューリングが、心を作ることによって心を理解しようとしたとすれば、岡の方は心になることによって心をわかろうとした。チューリングが数学を道具として心の探究に向かったとすれば、岡にとって数学は、心の世界の奥深くへと分け入る行為そのものであった。道元にとって禅がそうであったように、また芭蕉にとって俳諧がそうであったように、彼にとって数学は、それ自体が一つの道だったのだ。
Posted by ブクログ
同じ著者の『数学の贈り物』を読み、すっかりファンになってしまい読んだ一冊。数学というものを、数字や記号を使った「純粋に」論理的な思考と考えるイメージに対して、そうした思考に「身体」の役割を取り戻そうとする本。
数学史についての説明は、ユークリッドに始まる古代のギリシア数学から、チューリング機械まで。数学史に関する本を一度でも読んだことがあれば大体知っているような有名どころが押さえられている。
ただ、面白いのは、古代の数学には、「身体性」があった、というところだ。
ユークリッドの書いた『原論』には、多くの命題がある。しかし、現代数学の命題と明らかに異なっているのが、命題を読んだだけでは、状況がよく分からず、横に付けられた図とセットになっている点だと言う。
著者は、このことについて、古代の数学は、ただ、数式や記号を使って、論理的な思考を書くだけでなく、数学というものが、まさに、自分の「身体」を使って図を書くという行為と、不可分だったのだという。つまり、数学をすることは、頭で考えるのと同時に、体で考えていた。
頭の中で考えることと、実際に体を動かして頭の外で考えること。こうした「考える」ということの捉え方が面白かった。
後半、著者は、自分が最も影響を受けたという岡潔の言った「情緒」の言葉を鍵に、数学を体で、直感で理解することを取り戻すべきだという主張を説明していく。
高校時代に学んだ数学も、難しくなればなるほど、そこに数式として書かれたものは、現実的な感覚から遠ざかっていってしまう。著者の主張の通り、そんな数学に、体でなることができたとき、どんな風な景色が見えるようになるのか、とても心惹かれる。
本の数学に関する本筋からは脱線になるが、この本の中で紹介されている、アルタイの写真の話が一番印象に残った。木に立てかけられた板の前に一人の男が立ち、その周り数十人の子どもたちが座っている。
学校という場所があって、そこで勉強をするのではない。たとえ、そこに学校という建物がなくとも、誰かが誰かに教えるという行為が先にあって、そこに「学校」という空間が生まれる。
自分が今まで身につけてきたことを以て、日々生きること。そのためのヒントに満ちた本だった。
Posted by ブクログ
参考文献が挙げられている本を読んだとき、それらの参考文献のいくつかを読んでみようかなと思うことも、その本自身の面白さを物語る尺度ではないだろうか?数学の魅力を、チューリングと岡潔を取り上げて語る。入りに身体を意識させ、そのごチューリングに至っては、コンピューティングに、最後に身体とつながる心の重要性に向かう。数学読み物としては、なかなか楽しめると思います。間違いなく、(一部は有名な著作も散見されるが)参考文献の何作かは読んでみたいと思いました。
Posted by ブクログ
【感想】
面白かった。数学の歴史と発展、記号化と身体化、アランチューリングと数学、岡潔と数学の話のどれもが興味深い。文書が美しく、優しい。この人生において数学を勉強し直すことがあれば、読み返す気がする本。
【本書を読みながら気になったコト】
・小学校で当たり前にならう筆算が定着するまでは、二桁の掛け算は非常に高度なものされていた
→数学も使用目的によって発展していった。ギリシア数字は計算そのものには使いにくかった。計算に使える数学が生まれたのは、インドに依るところが大きい
>>数学の目的はかつて、数学的道具を用いながら、税金の計算や土地の測量など、生活上の具体的で実践的な問題を解決することが中心であった。このとき、数学者の関心は、あくまで数学の外の、実世界の方を向いている。
>>数学の道具としての著しい性質は、それが容易に内面化されてしまう点である。はじめは紙と鉛筆を使っていた計算も、繰り返しているうちに神経系が訓練され、頭の中では想像上の数字を操作するだけで済んでしまようになる。それは、道具としての数字が次第に五分の一部分になっていく、すなわち「身体化」されていく過程である。
ひとたび「身体化」されると、紙と鉛筆を使って計算をしていたときには明らかに「行為」とみなされたおも、今度は「思考」とみなされるようになる。行為と思考の境界は案外に微妙なのである。
行為はしばしば内面化されて思考となるし、逆に、思考が外在化して行為となることもある。私は時々、人の所作を見ているときに、あるいは自分で身体を動かしているときに、ふと「動くことは考えることに似ている」と思うことがある。身体的な行為が、まるで外にあふれ出した思考のように思えてくるのだ。
・私たちが学校で教わる数学の大部分は、古代の数学でもなければ現代の数学でもないく、近代の西欧数学である
・数学の計算困難性が増すなかで、コンピュータが誕生した
>>チューリングは数学の歴史に、大きな革命をもたらした。
”数”は、それを人が生み出して以来、人間の認知能力を延長し、補完する道具として、使用される一方であった。算盤の時代も、アルジャブルの時代も、微積分額の時代においても、数は人間に従属している。数はどんなときにも、数学をする人間の身体とともにあった。
チューリングはその数を人間の身体から解放したのだ。少なくとも理論的には数は計算されるばかりではなく、計算することができるようになった。「計算するもの(プログラム)」と「計算されるもの(データ)」の区別は解消されて、現代的なコンピューターの理論的礎石が打ち立てられた。
>>身体から切り離された「形式」や「物」も、それと人が親しく交わり、心通わせ合っているうりに、次第にそれ自体の「意味」や「心」を持ち始めてしまう。
物と心、形式と意味は、そう簡単には切り離せないのだ。
・岡潔によれば、数学の中心にあるのは情緒。肝心なのは、五感で触れることのできない数学的対象に、関心を続けてやめないことだという。
>>なぜそんなことができるのか。それは自他を超えて、通い合う情があるからだ。人は理で分かるばかりでなく、情を通い合わせあってわかることができる。他の喜びも、季節の移り変わりも、どれも通い合う情によって「わかる」のだ。
ところが現代社会はことさらに「自我」を前面に押し出して、「理解(理で解る)」ということばかり教える。自他通い合う情を分断し、「私(ego)」に閉じたmindが、さも心のすべてであるかのように信じている。情の融通が断ち切られ、わかるはずのことも分からなくなった。
>>かぼちゃの種子の生成力が、種子や土、太陽や水の所産であって、人間の手によっては作れないものであるのと同じように、「生きる喜び」も本当は、周囲や自然や環境から与えられるものであって、自力で作り出せるものではない。ところがいまは、何でも「個人」ということが強調されて、その「個」が「全の上の個」であることを忘れている。大自然には通い合う情があり、一つ一つの情緒はその情の一片である、ということが忘れられている。それで日々の生き甲斐までわからなくなった。自他を分断し、周囲から切り離された「私」の中から、生きる喜びが湧き出すはずもない。
・アランチューリングと岡潔の共通点、それは両社とも数学を通じて心の解明を目指したこと
>>『数学する身体』と名付けられた本書は、生命が矛盾を包容するとはどういうことが、そのことがテーマとして貫かれている。数学と身体の間には一見すると矛盾がある。数学は三人称性を纏って形式化と記号化に邁進し、身体はその成り立ちからして一人称的である。これは論理学的な矛盾ではなく、直感的なものである。したがってこの矛盾は、数学そのものによって乗り越えられるものではない。
Posted by ブクログ
「数学する身体」魅惑的なタイトルです。
著者は、京都に拠点を構え、独立研究者として活動する数学者だそうです。「数学の演奏会」なるライブ活動で、数学に関する彼の想いを表現しています。そして、本作で最年少で小林秀雄賞受賞されています。(小林秀雄先生の著作を理解できたことが無いのですが)
「はじめに」において、この作品を 数学にとって身体とは何か、ゼロから考え直す旅とします。まず、著者の文章力に驚きます。どなたかが、悟りを開いているようなと形容されていました。明確で簡潔。脳と文章が一致しているような印象です。(あくまで個人の感想です。)
第一章では、数学する身体として、数学は身体を使ってきたことを説明します。視覚で少数の数を認知する。体の部位を使って物を数える。(手の指10本で10進法⁉︎)そして、それらの限界から 数字や計算など道具の発見に繋がります。
第二章では、計算する機械として、数学の道具の進化の歴史が語られます。古代ギリシャの言語による証明から、算用数字の発明、記号•代用数字の利用と長い時間をかけて、世界の各地でそれぞれの数学の道具が発展していきます。そして、計算が追いつかなくなり、概念•理論への進化となります。
第三、四章では、著者が啓蒙する、岡潔氏という日本を代表する数学者への想いと、その実績について解説されます。まず、身体の中の脳へ科学的アプローチしていきます。そして、岡潔氏の情緒に対する考え方を丁重に扱っていきます。身体の心「彩り輝き動き」を喚起する言葉として「情緒」を表現に使います。情緒は個々の身体に宿る、とも。
著者は、この岡潔氏の日本的情緒を身体に備えることを望んでいるのかと思う。
終章で 岡潔氏の言葉を取り上げる。心になり心をわかる 心の世界の奥深くへ分入る。という、西欧的な心作る心を理解するとは違うアプローチに自身も惹き込まれているようです。
ライブ映像がネットにありましたので視聴させていただきました。若くきらめく知性でした。小中学生にも是非ライブしてもらいたい。数学だけでなく、あらゆる学びに共通すると思いますので。
Posted by ブクログ
わかるは自身が変わる、数字という言葉が脳にある記憶を介して自己の世界に認識される。すると、五感により自然を分けようと数字が無意識に機能する。そこに生活が繋がり合理を求めようとする。居心地の良さは数の整列でもある。時流の一方で "0" と "1" に配列されたデジタルが存在するが、果たしてデジタルで人々は幸せになるのか。所詮デジタルでできることはSNSや情報という言葉である。それよりも自然の中にある数字に興味を抱く。例えば植物で "葉の配列や花びらの形成" を言葉に頼らずに "わかる"。自然は言葉以前の根源にある。だからわかると言葉にするときに人は変わっている。人もまた自然であることの証でもある。
Posted by ブクログ
学生の時に読んだらこの世界にのめり込んだかもしれない、と思うほど、何も知らない人が読んでも引き込まれる一冊。難しい部分は頭が固くなった今では噛み砕くのに時間がかかり過ぎるので流してしまったが、それでも興味深い話が散りばめられていて面白かった。
Posted by ブクログ
常に身体と共にあった数学が、証明や記号(+,=)を含んで、どんどん抽象的で普遍的な物へと変わっていく。
そして遂に「コンピューター」「AI」という産物を生むに至る。
そのプロセスは「身体」「心」と「物」とを分離していく事であった。
そしてそれを進めたのは、数学者たちの普遍の追求に対する情熱だった。
だから、今日の数学は一見身体から数字が離れて一人歩きしている、空虚な物に見える。
しかし、「コンピューター」「AI」は再び人と人の心を通わせる。
「物」と「心」はそう簡単には分離できない。
アラン・チューリング / 岡潔の2人の巨人は、「数学=物」を追求する事で、「心」とは何かを追求した。
Posted by ブクログ
数学から一番縁遠いと思っている自分が、この本に魅了された。岡潔という巨人に導かれながら、著者はこころに迫ろうとしている。文庫174p
聞くままにまた心なき身にしあらば己なりけり軒の玉水という道元禅師の和歌を岡潔は次のように読み解く。外で雨が降っている。前肢は自分を忘れて、その雨の音に聞き入っている。このとき自分というものがないから、雨は少しも意識に上らない。ところがあるとき、ふと我に返る。その刹那、「さっきまで自分は雨だった」と気づく。これが本当の「わかる」という経験である。
森田は、それを次のようにとらえる。自分がそのものになる。なりきっているときは「無心」である。ところがふと「有心」に還る。その瞬間、さっきまで自分がなりきっていいたそのものが、よくわかる。「有心」のままではわからないが、「無心」のままでもわからない。「無心」から「有心」に還る。その刹那に「わかる」。これが岡が道元や芭蕉から継承し、数学において実践した方法である。
なぜそんなことができるのか。それは自他を超えて、通い合う情があるからだ。人は理によってわかるばかりではなく、情を通わせ合ってわかることができる。他(ひと)の喜びも、季節の移り変わりも、どれも通い合う情によって「わかる」のだ。
ここで展開される「わかる」とは、日々自分が行っている訪れる人の話をひたすらに聞く、そのことで話す人と私との間で、言葉を超えて動かされる情が共有されたときにお互いに「わかる」「わかられた」と感じられる営みにつながっていると思った。
Posted by ブクログ
森田真生さんの『数学する身体』を読みました。
その不思議なタイトルから、未知の世界を開いてくれそうな期待を感じます。
“数学”という言葉に、私はどこか身構えてしまいます。
“数学”とは難しい公式を覚えて、正解を求めるもの。
その自由のなさを、ひたすら暗記した私の身体は覚えています。
数の概念の進化から、哲学の変遷を辿ってみよう。
数字の美学を、俳句の五七五調とともに考えてみよう。
そんな授業があったら、私たちの身体に宿る“数学”が躍り出しそうな予感がします。
「きっと森田さんの授業を受けてたら、もっと数学を好きになってただろうな。」
20まで数えられるようになった娘の顔を見ながら、
私はそんなことをしみじみ考えてしまいました。
Posted by ブクログ
タイトルに惹かれて手にして、小説かと思ったら違った。難しかったけど、数学で言えることが、他のことでも言えるような結びつきや普遍性を感じたりして、面白かった。情緒は心の糸口、って知れてよかった
Posted by ブクログ
数学者の岡潔とアラン・チューリングを通し、数学と身体と一見すると全く別のものについて様々なアプローチから迫っていく。
著者が岡潔の著書を読み感じたことを抜粋すると、『バスケに捧げた日々を思い出した。この人にとって数学は、全心身を挙げた行為なのだと思った。生命を集注して数学的思考の「流れ」になりきることに、この人は無上の喜びを感じていることが伝わってきた。この人の言葉は信用できると直観した。』
本書を読みながら、著者に対しても言葉に信用が持てると感じた。
Posted by ブクログ
数学に関しての知識はないが、数学者が探究する姿勢、数学の奥にあるものを見ていきたいという心にグッときた。森田さんの言葉選びが美しい。まさに確信をもって書かれた本。もう一度読み返したいところ
Posted by ブクログ
内容が扱うものが数学で難解なものなので、本当に理解できているかはわからないが、数学の歴史の中でたどり着いた、客観的な計算ではない、人間的なもの、閃き、心、情緒にたどり着いたチューリングと岡潔。心でないものをタマネギの皮を剥くように特定していって、残る心を探究するチューリングと、数学という道の中で、数学になりきり、情緒とはを体得しようとした岡潔の、最後行き着くところは近しいがアプローチが全然違うところが、絶対的な真理というものはないのでは、と思わせて面白い
Posted by ブクログ
数学の生い立ち、数学に人生を捧げる人達と数学との向き合い方・考え方など、『数学と人間』をテーマに書かれているような感じです。数学をよく理解していない私にとって、聞いたことのない数学理論の話しが登場しますが、逆に興味が湧いてくるのは、著者の描き方たる所以だと思う。
Posted by ブクログ
前半は数学の刺激的な歴史のはなし。
subitizationスービタイゼーション:
人間は少数のものは一瞬で判断できるが、およそ3個を超えるとこの能力は消える。それで、指折り数えるような方法は世界には様々発展した。漢字やローマ数字のみならず、マヤ文明でも古代インドでも、数を表す文字は1から3までは棒の本数、しかし4から異なる。
紀元前5世紀ギリシャ:
古代文明の時代から、数は測量や暦など、日常の具体的な問題の解決のために発展してきた。ところがこの頃「いかに」正しい答えを導くかよりも「なぜ」正しいかを重く見る動きが現れる。→ユークリッドの『原論』:素数が無限にある証明で有名。
定理theoremの語源は、「よく見る」というギリシャ語theorein、
数学mathematicsの語源は「学ばれるべきもの」というギリシャ語μάθημαマテーマタ
(ハイデッガー「学びとは、はじめから自分の手元にあるものを掴み取ることである」)
アルジャブル:
古代ギリシャ文明衰退後、数学的遺産の後継者は、アッバース朝(750-1258)のイスラム社会。理論先行のギリシャと、計算重視のインドの数学が合流。初期アラビア数学者アル=フワーリズミー著『ジャブルとムカバラの書』『イルム・アル・ジャブル・ワル・ムカバラ("Ilm al-jabr wa'l-muqabalah")(約分と消約との学=The science of reduction and cancellation)』 →代数を表すラテン語algebraアルゲブラの語源→アルジャブルの目指す、未知数を含む式を解きやすい形に持ち込むための機械的手続き(即ちアルゴリズム)を考案し、その正当性を幾何学的手段で証明すること。
記号化する代数
この時代の計算には記号がなく、自然言語だけで表現されていた。16世紀に活版印刷の普及も手伝って記号法の統一が進み、+-×÷や√が出揃ってくる。
フランスのヴィエトは記号操作による「一般式」を確立。未知数に母音、既知数に子音を使っていたが、デカルトは未知数にxyz、既知数にabcなど、記号代数の表記をほぼ現代の形に整理した。
図形の問題も、古代ギリシャ以来の「作図された問題を解く」のではなく、記号化によって(図形を一般式に置き換えて解く)代数の問題に書き換わった。
その後、ニュートンとライプニッツがそれぞれ、微分と積分を発明。個々の図形に接線を引くのではなく、一般的な方程式に対してその接線や面積を求めるアルゴリズムを確立。
この流れにより、数学は物理的制約から自由になり、「無限」や「虚数」などの概念を獲得していく。つまり、図形に描けないような「あり得ない」ことでも、数式上「あり得る」ならば、数学で扱えるようになった。
作品の後半は、2人の天才の人生にフォーカス。
数学は、天才の頭脳の中で発展したのではなく、むしろ身体性に裏打ちされた行動の中で発展したのだというような話。詩や俳句からのインスピレーションが数学の進展に寄与したりもする、そんな話を読んで、理系とか文系とかいう区分には何の意味もなく、技術者でありながら読書趣味の自分を肯定してみたりする。