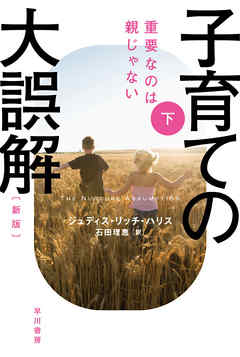あらすじ
「子育て神話」を葬り去る、革命の書! 〈本書に登場する事例〉 ・子どもは家と学校とで性格ががらりと変わる ・英才教育を受けた「神童」の多くは悲惨な末路を辿っている ・移民の子どもたちは家では母国語、外では第二言語を話す ・スラム街を去った不良少年の学業成績は劇的に向上した
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
上に書かれていた内容と同様に、ここでも引き続き社会集団仮説が唱えられている。子供は親の影響よりも、共有している仲間集団の影響を強く受ける。ということだ。文化の継承においても同様のことが言える。例えば、家では正直者なのに、外では不誠実になる(仲間の影響)ということもある。親が家庭内でどれだけ丁寧に子育てをしても、家庭の外においてもその影響が続くとは限らないのだ。
ジェンダー論においても興味深い主張がされていた。(私は性差別者ではないです笑)筆者の主張では、やはり男女は異なる。実際に偏見と言われていることは正しいことが多い。女の子はおままごとをし、男の子は電車の模型で遊ぶ。ただ、勘違いしてはいけないのは、おままごとが好きな男の子もいる。ということだ。確率の問題なのである。私は、女性が不当に差別される社会は望んではいない。が、変に男女平等にするのもおかしいと思う。
ここでは、学校に関する興味深い話もされている。クラスの集団は基本的に分裂する。例えば、頭の良い・頭の悪い、の二つに分かれたとする。すると、その差は時間を経るにつれ顕著になる。運動ができる・できないでも同様だ。ここで、教員は、分裂させないことが肝になる。全員を、運動ができて、勉強もできる集団に参画させるのだ。つまり、均質化は有効な手段になる。女子校や男子校が良い成績を収められるのは、性別的な部分で均質化が行われているからかも知れない。
問題児。これを見ると、親のせい。と考えたくなる人もいるかも知れない。しかし、遺伝的な要素も排除しきれないし、上記同様に仲間集団からの影響も受けているので、どこまで親が悪いのかがわからないのだ。実際に、体罰をする親に介入をしたとして、体罰をなくしたとしても、その子供の社会での振る舞いが大きく変化することはない。
この本を読んで、自分が教育者(そして、将来持つであろう子供の親)としてできることは限られていると、改めて感じた。だからって、全て投げ出すわけではない。自分にできる範囲を定めて、自分に矢印を向けて、生きていきます!
Posted by ブクログ
・スキナーの行動主義が強かった時代には、泣いている赤ちゃんを抱き上げるという行為は抱き上げることで泣くという行為を強化する、として戒められていた。今は全く逆のことが言われている。
・そもそもこうした社会科学の研究ではコントロールを置くこともできないので因果関係を立証することは甚だ困難だ。親が叩くから難しい子になるのか、難しい子だから叩かれるのか、はっきり立証されないまま一般的に正しい意見とされていることが非常に多い。
・人の心理的特徴はその50%が遺伝の、50%が環境の作用による。環境には家庭などの共有環境と、友人関係などの非共有環境がある。しかし1970年代にはアメリカの心理学は行動主義の影響下にあり、遺伝の影響を認めない傾向が強あった。政治的にも生まれながらの相違点の存在を認めず、遺伝の影響を否定する傾向があった。
・Dunn & Plomin(1990)によると、出生順位と性格傾向についても関係はない。長男はこういう性格、、、などというステレオタイプな見方は間違っている。家の中では出生順位と性格の関係はあるかもしれない。第一子は支配的で責任感が強い。しかし、こうした出生順位との関係は家庭内にほぼ限られている。仲間との付き合いにおける社会的生活能力は子供の中に存在するのではなく、それぞれの人間関係の中に一つずつ存在する。
・親よりも環境が重要な証拠として、非行少年たちも(家族同伴で)転居するだけで問題行動が減るという。孟母三遷の教えはやはり正しいのだろう
・IQも労働者層の親に育てられるよりも中流階級の養父母に育てられた方が12ポイントほど上昇するという。ただし、養父母に育てられた養子二人のIQの相関は幼少期には強い。これはおそらく各家庭の環境によるものだろう。しかしこの相関は大学入学ぐらいの年令になると消えてしまう。血のつながりのあるきょうだいに近いIQになり、12ポイントほどの優位は7ポイントほどに小さくなる。