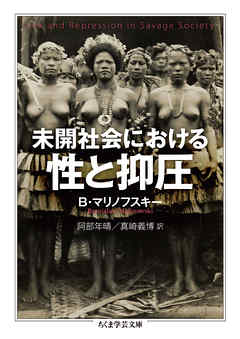あらすじ
「エディプス・コンプレックスはあらゆる社会に存在する」とフロイトは説いたが、マリノフスキーはこの仮説に対し民族誌的資料を駆使し、それが近代西欧の家父長制的社会特有の現象であると根底から相対化してみせた。近代的社会人類学の確立者として学説史に不朽の名を刻んだマリノフスキーが、性において人類の内なる自然と文化的力との相互作用のドラマを考察した古典的名著で、家族の起源、近親相姦の禁忌、父系制と母系制との関係等いまだ多くの示唆を与えてくれる。また、文化の概念をはじめ、彼の主要な理論、概念が展望でき、マリノフスキー理解の恰好な入門ともなっている。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
当時フロイトらを中心とした精神分析が学術界を覆っていた中で、人類学的な長期間の参与観察に基づいた共時的な研究において、真っ向からエディプス・コンプレックスに挑もうとしたマリノフスキの名著である。
フロイトらの精神分析論は、西洋社会を基礎に置いて展開された理論であるために、非西洋社会にそのまま理論を当てはめることはできないことを論証した。尚且つ、西洋社会においても上流階級と中流、下流階級の生活や社会的な様相は異なることが想定され、フロイトらの理論は西洋上流階級を基盤に置いたものであるため、そもそも同地域においても若干の齟齬が見られるのではないかと、鋭い指摘をしているのは印象的である。
マリノフスキが後世に名を残すことになる数々の名著を生み出すうえで、そのフィールドの中心となったトロブリアンド諸島では、西洋社会とは異なる母系制社会によって生活が営まれている。そこでは父親は、エディプス・コンプレックスに見られるような殺害の対象ではなく、生涯に渡って仲のいい遊人的ポジションに位置している。その代わり、母系制社会において権力を発揮するのは母親の兄弟であり、子どもからするとオジに当たる人が西洋社会の父親と似たポジションだということになる。しかし、夫方居住婚であるためにオジとの物理的距離は遠いなど、母系制社会における中核コンプレックスは一概にエディプス・コンプレックスとの対比によって導き出せるようなものでもないことは、注意しなければならない。
そのような社会では、母親に対するタブーではなく、(男性中心的な研究であったために一視点に偏っている点は批判に値するが)同じ家族の姉妹へのタブー意識が強いことが確認されている。それは、神話やからかい、冗談、夢といった、様々な要素における現地民たちの語りから明らかとなっている。
マリノフスキの試みとしては、エディプス・コンプレックス批判にあることは確かだが、そのなかで「エディプス・コンプレックス」という言葉を軸にトロブリアンドの社会を論じてしまうことへの抵抗感を感じている。そこで、マリノフスキは「情操」という言葉を使用して、当該社会の性質について論じようとする。これは、エディプス・コンプレックスという言葉を使用することを避ける試みであるほか、マリノフスキが機能主義人類学にて心理的側面に注視したという、教科書などで度々目にする説明の該当部分に当たるものだ。
マリノフスキは、心理学における「情操」という用語を使用し、レヴィ=ストロースが論証したことで有名な「近親相姦」の問題についても、見解を述べている。彼によると、近親相姦をするということは教育という側面において育まれてきた家族の絆としての情操を破壊してしまうことに繋がるため、避けられていると主張する。レヴィ=ストロースのインセストタブーは誰しもが知っているかもしれないが、数十年前に既にマリノフスキが論じていたという事実はさほど知られていないのではないだろうか。
また、フロイトらがトーテミズムから文化を論じようとしていたことも恥ずかしながら初めて知ることになった。文化や精神、情操といった問題は当時の学問領域における中心的な問いであり、その中でも実証的な研究によってそれを導き出そうとしたマリノフスキの姿勢は、(現代に生きる我々からすると数々の問題点は指摘されうることは承知の上で)人類学を学ぶ者からすると尊敬に値する。
Posted by ブクログ
現代人類学初期の立役者であるマリノフスキーが、フロイトの精神分析理論に真っ向から取り組み、これに人類学的視点からの批判を加えるという、テーマを聞いただけで血湧き肉躍るような興味深い本である。
初版は1927年だが、それ以前に書かれた前半部と後半部で内容が分かれている。
マリノフスキーはフロイトの学説に衝撃を受け、大いに敬意を払ったのだが、「エディプス・コンプレックスは、人類のあらゆる文明において普遍的根源的である」とするフロイトの説を修正せざるを得ず、彼への敬意からなかなか歯切れが悪く最後は中途半端な譲歩も示すものの、「性」に関する人類学的考察に関しては一徹に自らの方法を貫いている。
私見によれば、「トーテムとタブー」(1913)等でフロイトは自らのエディプス・コンプレックス論を普遍的な文化論にまで高めようとするあまり、これを再-神話化し、途方もないようで粗雑な、夢想的な文明論を開陳するに至ってしまう。私もフロイトが現代の知における巨大な偉人であることに異論はないものの、彼の理論はエディプス・コンプレックスにしろ去勢不安にしろ、どうも彼自身のコンプレックスを理論化したもののような気がし、当時のオーストリアの、ユダヤ系の非-貧民層という限定的な状況(社会)においては定式化し得ても、他の時代他の社会においてはそのままに適用できないのではないかという気がしてならない。再-神話化されたエディプス表象も、あまりにもキリスト教的である。
私のそのような懐疑は、本書のマリノフスキーの「健全な」学術的議論に同調した。マリノフスキー得意のトロブリアンド諸島の女系制社会の描写は冴え渡り興味深く、ヨーロッパ的社会とはまったく異なった「性」の自由なあり方の記述は面白い。
トロブリアンドでは子ども時代後期からすでに、子どもたちは「自然なままに」互いに性的遊戯を楽しみ、大人や社会がこれを禁圧することはない。この社会で性的抑圧があるとすれば、徹底的に禁忌されている「異性のきょうだいとの性的ニュアンスを伴いかねない親密さ」だけである。
また、母系制であるトロブリアンド諸島では、父親は子どもたちのよき友人ではあっても権威的存在ではなく、母方の叔父のみが、子に対する強大な権力を持つ。
こうしたメラネシアの民俗誌はたいへん興味をそそるし、途中で引用される彼らの神話を読むと、レヴィ=ストロースを想起させる部分もあった。
マリノフスキーは最終的にフロイトよりもシャンドの「情操」論により多く共感したようで、例の「近親相姦の禁忌の絶対的普遍性」という人類学の大問題については、近親相姦というあまりにも例外的な行為が、社会制度およびそれを支える人々の「情操」を破壊してしまうからだ、という、説得力のある仮説を呈示している。
「本能」は「可塑的」なものであり、社会形成のプロセスによって生物学的欲求は修正されるのであって、人間の「本能」はその結果、決して純-生物学的なものではあり得ない、とする著者の説も正しいような気がする。
フロイトがどうこうということは置いといて、本書はレヴィ=ストロース以前の人類学として実に充実した名著であり、かけがえのないものだと思う。