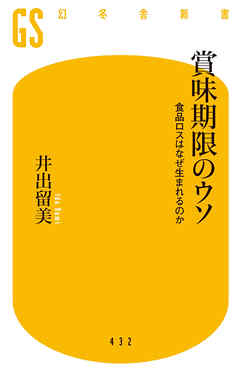あらすじ
卵の賞味期限は通常、産卵日から3週間だが、実は冬場なら57日間は生食可。
卵に限らず、ほとんどの食品の賞味期限は実際より2割以上短く設定されている。だが消費者の多くは期限を1日でも過ぎた食品は捨て、店では棚の奥の日付が先の商品を選ぶ。小売店も期限よりかなり前に商品を撤去。
その結果、日本は、まだ食べられる食品を大量に廃棄する「食品ロス」大国となっている。しかも消費者は知らずに廃棄のコストを負担させられている。食品をめぐる、この「もったいない」構造に初めてメスを入れた衝撃の書!
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
『サステナブル・フード革命』(アマンダ・リトル)がキッカケで読む事になった『賞味期限のウソ』(井出留美)。
まだ食べれる食品が廃棄されるアメリカのスーパー事例を読んだ時に「日本ではどうなってるんだろう」と気になりました。
2016年に書かれた本なので、2023年である今では変化があるかもしれませんが、
とりあえず2013年における日本の食品ロス量は632万トン。
そのうち約半数は消費者由来、残りが飲食店や食品メーカー、販売店など事業者由来のものだったそうです。
世界の食糧援助量が比較として出され、約320万トンと見た時には口が開いてた。
このデータが弾き出された背景には、スーパー・百貨店・コンビニの食におけるルール(3分の1ルール、日付後退品、廃棄前提の品出し計画など)や
各家庭における無駄な買い物があり、
私自身「うっ!」と思うようなご指摘がポツポツ。
「安いから…」「いつかこのレシピやるから」で買った食品の慣れ果てが冷蔵庫や冷凍庫から発見された経験が頭をよぎる。(白くブニュブニュになったキュウリとかね…)
この光景を見てからというものの、「冷蔵庫の中の物で何か作る」「野菜を買う時は作るレシピを決めておく」「賞味期限が長めのモノはストックOK」という自分ルールは出来上がりました……笑
こういった各問題に対して行われてきた解決策の紹介もあり、
《各企業における賞味期限延長》や【フードバンク】【フードドライブ】などの《食べ物のシェア》の話は面白かったです。
正直こんな取り組みがあったなんて全然知らなかったし、無知って恐ろしいと思った次第。
《興味関心のアンテナ》を広く張る事の重要さを知って、
好きな分野だけ掘り下げてる場合じゃないなって思えてきた。
いろいろ読んだ上でいろいろ決めてこう。
Posted by ブクログ
賞味期限のウソ 食品ロスはなぜ生まれるのか。井出留美先生の著書。賞味期限についての常識は実は間違っている、虚偽であることがわかりました。世界にはいまだに十分な食べ物を得られずに苦しんでいる人がたくさんいるのだから、社会全体として賞味期限についての正しい知識を身につけて食品ロスをできる限り減らすような努力をするべきです。
Posted by ブクログ
【深刻な「食品ロス」を知ろう】
食品に関わる、恐ろしく深刻な問題の数々を知ることができます。決して他人事ではない、食品ロス。最新の傾向と対策を学びましょう!
Posted by ブクログ
食ロスの課題が多い中で、オリンピック組織委員会が「8月27日の会見で、オリンピック期間を含む7月3日から8月3日までの1か月間に、およそ13万食の弁当などが廃棄されたことを明らかにしました。」と報道がありました。なんとも悲しい。ボランティア分の弁当廃棄など、まったく無駄を減らそうという努力が感じられない大会だったのが残念だった。
賞味期限と消費期限については改めてしっかり考え勉強して無駄を無くさなければと感じました。
Posted by ブクログ
本書に書いてある事で驚いたのはほとんどの商品に記入してある賞味期限の長さは、実際の賞味期限のだいたい八割だという事だ。さらに店で商品を売るときには「3分の1ルール」が適応され賞味期限の3分の2を過ぎたら廃棄するということになっているらしい。だからスーパーやコンビニなどでは単純計算で本来の賞味期限の約半分しか経っていないものを廃棄しているということになる。またコンビニで売られている物の値段が高い理由の一つとして廃棄のための費用が値段に組み込まれている事が挙げられる。コンビニの商品は廃棄されることが前提で売られているのだ。
筆者は日本の消費者が食品はゼロリスクではなくてはならないと信じている事を批判している。多くの消費者が臭いや色など五感を使えば安全かどうか分かることを、脳死状態で賞味期限だけを見てまだ食べられる物を捨てている。それと農家がキャベツや白菜などを地産廃棄することに関して消費者がクレームを言うことはお門違いだと主張している。僕もニュースなどで耳にしたことがあり勿体ないとは思ったことがある。しかし筆者曰く「捨てざるえなくなってしまったのは元はと言えば消費者のせいである。需要と供給の関係で消費者がそれらを買わないせい値段がそれらが安くなり、出荷すると手間と輸送費のほうが高く付くので農家は渋々廃棄したのだ。たくさん買って農家に貢献したわけでも無いのに文句を言うな。」ということらしい。そう言われると反論できない。
この本を読んで自分も他人ごととしてではなく自分ごととして食品ロスのことを考えなくてはいけないと思ったら。
Posted by ブクログ
配達のついでに余った食べ物を回収する取組を自分が利用しているパルシステムがやってくれているのにはびっくりすると共にちょっぴり誇らしかった。
買いすぎには気をつけてはいるが、すぐ使うことが分かっているときは賞味期限の近いものを買うこと、フードドライブに参加するなど、自分にもやれることがあるなと思った。
それにしてもフードロス撲滅にいろんな取組があるのに驚いた。
ラスト10ページくらいは、くどすぎで読み飛ばしたが、少しはフードロス撲滅に貢献できる知恵はついたかな。
Posted by ブクログ
本屋で衝動買い。内容は表題からちょっとだけずれている。この本のテーマは「食品ロス問題」。食品ロス問題は消費者にも責任があるという、著者の主張には共感できる部分が多い。たとえばこの問題に関連して最近注目されている「3分の1ルール」も、消費者による馬鹿げたクレームが遠因となっていることは、意外に知られていない。これからも乳製品を買うのに、棚の奥に手を突っ込むようなさもしい行為をしないでおこうと思う。
Posted by ブクログ
「生卵なんて1カ月はじゅうぶんもつよ」と言ったら、ダンナと弟にドン引きされたことがあります。賞味期限が1日過ぎただけで、食べたらお腹をこわすのではなどと心配をするのは、女性よりも男性に多いように思います。そんな心配は無用だよとまでは言いませんが、本書を読めば、少しは男性陣の心配が減るかも。
日本において卵の賞味期限として表示されているのは、「夏場に生で食べること」が前提。冬場であれば57日間、2カ月近くも生で食べられるのだそうです。もちろん管理の状態にもよりますから、日数だけで判断してはいけないでしょう。でも、日本でどのように賞味期限が設定されているのかを知るためには非常にいい本。
法律で定められているわけではないのに、食品業界で商慣習として守られている「3分の1ルール」。賞味期限が6カ月ある食品の場合、最初の2カ月で納品、次の2カ月で販売。それを過ぎると商品棚からただちに撤去されてしまうという。海外のどの国と比較しても、販売できる期間がもっとも短いのが日本。日本はそれだけ安心してものを食べられる国でもあるわけですが、それゆえに日々廃棄される食品の多いこと。年間何百万トンという食品が廃棄される一方、餓死する人もいるという現実。
ドギーパック(食べ残したものを袋等に詰めて持ち帰る)を推奨しているホテルやレストラン、常に商品棚をいっぱいにしておかなくてもいいじゃないかという姿勢のスーパー、食べることに困っている家庭にお供えをおすそわけするお寺などが少しずつ増えているとのこと。フードドライブ(家庭で余っている食糧を寄付する活動)にも興味を持ちました。食品ロスについて考えるきっかけになる本だと思います。
Posted by ブクログ
2022.08.27
若干タイトルと内容に齟齬があるような気がするけれど、読んで良かった。
具体的に読者が行動できることを明記していることから、著者の「この問題をどうにかしたい」という必死な思いが伝わってくる。
家庭でできることはもちろんたくさんある。
買うことは投票すること。信頼できる企業から買うことで消費者も社会を変える一員になれる。
大きく変えるには大企業や政府の力が必要だけれども、だからと言って個人が何もしなくていいわけではない。できることから少しずつ。エシカルな消費を目指していこう。
フードバンクという取り組みがある。
まだ食べられるのに外装の破損などで出荷できなくなった食品を企業から引き取り、福祉施設などへ配給する組織のことだ。
それと似たような活動でフードドライブというものがある。
家庭で余っている食材を集め、困窮している人たちへ配る活動のことで、フィットネスクラブのカーブスや一部地方自治体などで実施されている。
ただフードドライブには難点もいくつかある。
まずは賞味期限の問題。外国では賞味期限が切れていても回収OKなところもあるが、日本では2ヶ月以上賞味期限までゆとりがあること、等厳しい。
「賞味期限が切れてもまだ食べられる」ことが広く知られるべきなのである。
そもそも厳しすぎる賞味期限設定が悪いのか、「ルールをきっちり守り、守らなかった場合は個人の責任」という国民性が良くないのか・・・
あとは「余った食品を与えられる困窮者への差別や栄養の問題」もある。
余ったものを何でもかんでも与えてもまた廃棄されることだってある。
まだまだ問題が山積みだと感じた。
国民性なのか、杓子定規に判断したがるところが日本では多い。それが高度な衛生管理にもつながっているし、食の安心安全のためには必要なのかもしれないが、そのせいで多くの食品廃棄を産んでいるように思う。
例えば賞味期限が3ヶ月以上ある食品は日付表示を省略しても良いとされているにも関わらず、日付表示をしているものがまだまだ多い。
日付表示をしない方が期限にゆとりを持たせられるのにしないのは、ロット管理の観点からだという。
また、日本人は「何をどれだけ食べると体に悪い(良い)」と考えるとき、「何を食べるか」に重点を置きすぎ、どれくらいの量を食べるか、が抜け落ちている場合が多いように感じる。
どんな良い食べ物も、また悪い食べ物や添加物なども、どれくらいの量を食べると体に影響があるのかを考えて摂取する必要がある。
Posted by ブクログ
賞味期限と 消費期限があるのは 知っているし
多少切れていても 大丈夫と思っていましたが
卵が 冬場なら57日間は 生で食べれるとは
びっくりしました~~
テレビとかで やったそうなので知っている人も多いと思いますが
私には 驚きです~~~
まぁ 卵とか 割ってみて においとか大丈夫そうなら 火を入れちゃえば 問題ないですよね~~
体調が悪い時は やばそうなのは リスキーですけどね。。。
日本では なかなか テイクアウトが出来ないのは
いつも 困ります。
だから ライスに関しては うっかり言い忘れない限りは 半分とかにお願いしています。
お店の人は値引きできないから と 言うような言い方をされますが 持って帰れないし 捨てちゃうなら 問題ないと思っています。
ファミレスでも ライスの大きさによって 価格が異なるところもありましたけど
そういうお店はいいですよね~
一般家庭でも まとめ買いは お買い得というので 買いすぎて 食べきれず 処分するのも多いそうですが フードバンクなどが もっと周知されるといいですね~~
(残念ながら 我が家は 期限切れとか 食べちゃうので 寄附できませんが)
あと、ずっと 気になっていた お寺さんとかにお供えしたものってちゃんと 頂いてるのかと疑問でしたが 「おてらおやつクラブ」という 活動があるそうです。
お供え物を おさがりとして 頂いて それらを 支援施設などから 個人へという流れが作られているそうです。
少しづつですが 食べられる物を 食べたい人に 上手く行き渡るような仕組みができているようですね。
もったいないと 思うなら 消費期限の近いものから 購入しましょうと 書かれていました。
はい。。。勿論 その方が 価格も安くなってるので 優先的に頂いています。
学校とか 家庭でも
食品ロスについて 話をしてみて 意識が変わると良いですね。
Posted by ブクログ
食品ロス対策として、フードバンク、フードドライブ(フードスタンプ)という素敵な取り組みを初めて知る機会でなった。
フードバンクは、まだ食べれるが外装等の欠陥で市場に出まらわないものを、買取、生活困窮者に提供する取り組み
フードドライブは、店や指定場所に家庭で余った食品を集め、上記同様生活困窮者に分け与える取り組み。
まだ食べれるにも関わらず捨てるのは環境にも経済的にもよろしくはないと考えていた矢先、上記取り組みはとても素晴らしい。
日本での食品ロスは年646万トンで、その内330万トンが家庭からの破棄となると、一部富を得られる人がいる反面、得られない人に分け与えることは、まさに共存社会となりえるだろう。
Posted by ブクログ
食品メーカー、小売店、消費者。
三者三様の思惑が複雑に絡み合い、
“食品ロス”をめぐる問題が生じている。
賞味期限はわざと短めに設定され、
まだ食べられるものも売らず、
廃棄前提に大量に仕入れ、
家庭でも食べられるものが捨てられている。
誰も悪くないが、誰もが悪い。
食品廃棄物を効果的・効率的に再利用する手段を考えることも大事だけど、
食品業界のシステムや考え方を一新することが、根本的な解決方法ではないだろうか。
Posted by ブクログ
タイトル通り、食品のパッケージに書かれている「賞味期限」についての数々のギモンに迫った一冊。例えば卵に関しては、賞味期限は(日本では)「夏場で生で食べる」ことを前提に設定されており、賞味期限後も加熱調理すれば食べることができる(1か月半の賞味期限に設定している国もあるようだ)。また、コンビニで常に賞味期限近い商品が並ぶカラクリだったり、毎日大量にパンを棄てているデパ地下のパン屋だったりと「食品ロス」大国日本の現状が語られる。この大量消費の時代、一度立ち止まってじっくり考えてみたい問題だと思った。
Posted by ブクログ
賞味期限を過ぎたら捨てなければ! と思っている人は
けっこういると思いますが、たかが2日3日過ぎた程度
普通に食べられます。
何故ならば、本来の賞味期限よりも2割短く
設定されているから。
目安ですから、そこまできっちり食べるほどでも
ないと思います。
そもそも変な匂いがしなければ
いけると思ってますし。
と考えていた事を、肯定してくれたような内容。
そして言われてみれば…な現実にも気が付きました。
なぜあれだけ店頭に商品が置かれているのか。
言われてみれば、爆発的に売れた、というもの以外
欠品になっているのを見たことがありません。
あれもこれも、自分達の生、と言えばそうなるのか、と
驚いて読んでました。
さらには、余ったものを今食べたい人のために。
寺でそういう事をしているのは知っていましたが
国外では普通にされていて、日本は遅いのだな、と。
そもそも安全性重視なので、蓋が開いているような
食品はお断りされるでしょうし。
食べきれる量を、食べられるように買う。
もったいない、はどういう意味なのか、を
多少なりとも学べた気がします。
Posted by ブクログ
食品ロスは、SDGsの目標にも掲げられている。
食材が大量廃棄され、一方で食に困っている人がいることはよく分かっているのだが、、、あまりに当たり前になっている。
社会の持続性に目を向けていきたい。
Posted by ブクログ
リスク志向の強い日本では賞味期限が実際より短く設定されているうえ、店頭からも更に早く撤去される。生ものの消費期限は重要だが、長期保存可能な食品についてはもう少し緩やかでもよいのではないか。食品廃棄を支援に変える活動が生まれ、大きな社会的な流れとなってきている。
リスク回避のもとをたどれば、責任回避・クレーム回避、自分のアタマで考えず横並びな日本人。
Posted by ブクログ
食糧不足は誰もが知っている問題だが、食料を廃棄する食品ロスもまた問題になっている。
日本ではどれくらいかの食品ロスかというと年間632万トン、一人あたりあたり毎日136グラムの食料を捨てている計算。
なぜ起きるのかと、新しいものから選んだり、割安だから大量の買い物をする人間の習性、コンビニに代表されるような商品大量陳列など理由は様々。
面白いのは草の根活動で問題解決ができること。京都市では自治体が音頭をとり15年でゴミの量を半分近く減らした。具体的な施策の一礼が生ゴミ3キリ運動。「使いキリ」「食べキリ」「水キリ(ゴミを出す前に水を切ること)」。削減効果は焼却施設の縮小など年間106億円もの大きなコスト削減につながった。
小さな行動の積み重ねが大きなロスにも繋がる、逆に大きな改善にも繫がる。
Posted by ブクログ
タイトルからして、規制の問題が中心かと思ったが、実際、食品ロスの問題だった。
フードバンクとかフードドライブとか、日本人特有というか完了特有というか、無謬性というか、そういうところが問題なんだろう。リスクを確率で捉えることができない。ある意味、善悪二元論みたいなもんか。
賞味期限が近いものから買うとか、できることはやっていこう。
Posted by ブクログ
日本の食品ロス量は、632万トン。これは東京都民が一年間に食べる量とほぼ同じ。
世界の食料援助量は約320万トンなので、日本は世界全体で支援されている2倍の量を、国内で捨てているという異常な状況。
食品ロスの約半分は企業から、残り半分は家庭からとのこと。
企業は安全係数を持って賞味期限を設定しており、
食品業界には3分の1ルールがあり、
小売店が絶対的に力をもっており、
そもそも食品には、廃棄する分のコストが乗って、価格設定されているということ。
家庭でも、無駄なもの、必要以上に買わない、賞味期限は目安ということ、他できることを意識して、買い物をしていかないと、いつまでたっても、食品ロスは減らない。
最近フードバンクの活動が知られるようになってきたが、まさに、そういった活動を通して、無駄のないように、(そもそも食べ物を捨てるということ自体、違和感を感じるが・・・)
食品業界も食品ロスに対して、もっと取り組まないと、
一向に減らないように思う。
意識、行動、習慣を変えて、よりよい方向に。