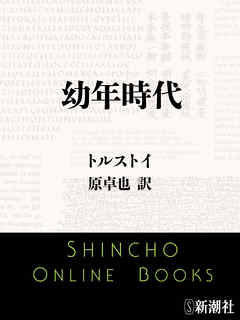あらすじ
10歳になったわたしは、父の領地で何不自由のない生活をしていたが、勉強のために、兄と一緒にモスクワで暮すことになった。最後の狩、母との別れ、都会での貴族的な生活、そして母の死――。みずみずしさ、屈託のなさ、愛への渇望、純粋な信仰心に満ちた、人生における最も美しい時代を描きながら、のちのトルストイ文学の特質をあますところなく備えもつ、自伝的処女中編である。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
特に印象的なのは当然物語のクライマックス、母親が死ぬシーンになるが、トルストイが書きたかったのは、その後の主人公の心理、思考描写だろう。おれも最近ばぁちゃんが死んだが、そこには悲しい人の役をどれだけうまく演じられるか競っているような面があって、本当に自分が考えていることを見つめるのが怖かった。トルストイはそれをあっさり書いていて、彼の鋭い眼差しは自分にも容赦がない。ただ宗教的な面で彼だけ見えてる部分があったが、それでもおれからしたら宗教的な面で本当にそうだろうかと思う部分もある。幼年時代の終わりとして、誰しも母親なるものの死が必要になる。しかしおれはトルストイが好きだ。アンナ・カレーニナなど他の作品では人の心をいきいき、時に残酷なまでに描き出すのに、この作品ではその文体のままあどけない主人公の目線をみずみずしく描いている。
再読。
Posted by ブクログ
どこを読んでも瑞々しい輝きに満ちた中編。
たくさんの愛すべき登場人物に囲まれてのびのびと暮らし、母から注がれる最上の愛と、それを渇望する少年の人生に於いてもっとも幸せな時代。
日常の小さな幸せのひとつひとつにこそ胸を締め付けられる想いがしたし、もうとっくに思い出す事もなくなっていた甘美な思い出も思い出させてくれた。
あの頃のような瑞々しい心や感動はどこへいったのか?
トルストイの言葉をそのまま自分に問いかけてみる。
「あの涙や歓喜が永久にわたしから離れ去ってしまうほど、
重い足跡を、はたして人生がわたしの心に残しただろうか?」
そんなはずはないと、思ってはいるけれど。