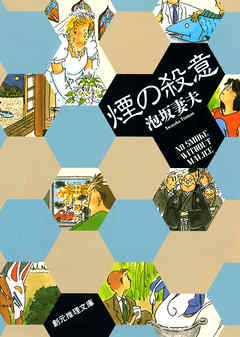あらすじ
問答無用の面白さ、騙される快感!泡坂ミステリのエッセンスが詰まった名作品集。困っているときには、ことさら身なりに気を配り、紳士の心でいなければならない、という近衛真澄の教えを守り、服装を整えて多武の山公園へ赴いた島津亮彦。折よく近衛に会い、2人で鍋を囲んだが……知る人ぞ知る逸品「紳士の園」や、加奈江と毬子の往復書簡で語られる南の島のシンデレラストーリー「閏の花嫁」、大火災の実況中継にかじりつく警部と心惹かれる屍体に高揚する鑑識官コンビの殺人現場リポート「煙の殺意」など、騙しの美学に彩られた8編を収録。/収録作=「赤の追想」「椛山訪雪図」「紳士の園」「閏の花嫁」「煙の殺意」「狐の面」「歯と胴」「開橋式次第」
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
一分の隙もない短編集。落語のようなとぼけた語り口と、何回も読者の予想や思い込みをひっくり返す展開が見事。虚実ないまぜのうんちくが効果的な『椛山訪雪図』、社会を外側から眺めているかのような登場人物達が十蘭っぽい『紳士の園』が特に好き。
Posted by ブクログ
泡坂氏初期の短編にはチェスタトン張りのロジックが愉しめる。それは歪んだ論理とでも云おうか、読後に奇妙な味わいを残す。
本作では「赤の追走」、「紳士の園」、「煙の殺意」、「開橋式次第」がそれに当たる。
しかし本作は先ほど「奇妙な味わい」と述べたようにエリンの『特別料理』を意識したに違いないと思われる作品がある。『閏の花嫁』はもうほとんどオマージュであろうし、『歯と胴』は一種のホラーとも云える(題名からすればバリンジャーか)。
恐らく雑誌掲載の短編を寄せ集めたものであろうが、この完成度は素晴らしい。
Posted by ブクログ
冒頭の「赤の追想」を読んですぐ、米澤穂信の『氷菓』を思い出した。淡々とした語り口、理路整然とした謎解きの明かし方が似ているように感じられたからだ。果たして、直木賞候補の『満願』を書く際に米澤氏がこの『煙の殺意』参考にしたという記事を読み、やはりと思ったのであった。こういう逸品に出会えた事を幸運に思う。「椛山訪雪図」はさながら芸術作品のようだ。『11枚のとらんぷ』も是非読んでみたい。
Posted by ブクログ
おもしろかった!スピーディーに読めた。短編ミステリだと、最後にどかんと返されたりして楽しい。美しいと言われていた「椛山訪雪図」ついに読めた。なるほど美しい。名前もきれい。「紳士の園」「閏の花嫁」好きだったな。「紳士の園」は出所したふたりの会話がなんだか好きだった。「閏の花嫁」みたいな書簡体小説結構好きみたい。
Posted by ブクログ
男女の恋愛模様、一幅の掛け軸、なんの変哲もない公園、殺人現場での風変わりな捜査など様々な趣向を凝らしたミステリーが八編収録された短編集で、筆致豊かな人物描写と情景描写、読み手の思い込みを利用したトリックの数々が今読んでも色褪せない名作だと感じられた。
Posted by ブクログ
創元推理文庫版で発売されたのが2001年なので、てっきり新しめの作品集なのかと思いきや、1976~79年と『亜愛一郎』シリーズと同じ時期に執筆されたものであるとともに、元のそれが入手し辛くなったことからの発売かもしれないと知り、内容に好みはあるかもしれませんが、ミステリファンならば、一度読んでおいて損はない作品だと感じました。
本書には、それぞれに趣の異なる8つの短篇が収められており、当時の時代背景も反映されているかもしれないと感じたのは、これまで私の中で抱いていた、泡坂妻夫に対する人柄の良さを思わせるイメージとは真逆のそれであり、それは人間には良いところも悪いところもあるのだろうなといった、漠然としたものというよりは、人間は時と場合によって、突拍子もなく平気で恐ろしいことを考えつく生き物であることを、ごく当然のように描いている、そこに感じられた容赦の無さであると共に、だからこそ見えてくる人間味もあった。
ここで冷静に省みると、亜愛一郎シリーズにも、確かにそうしたテーマは存在するが、作品全体を覆うユーモラスな雰囲気と亜自身の個性によって、大分和らいだ印象を抱かせる反面、この前読んだ「乱れからくり」には、本書と似たような人間の持つ闇の一面を垣間見たことから、泡坂妻夫も人間なのであることをようやく意識させられた、というよりは、そこに彼の作家性があるのだと思われたことに、実は騙しの美学だけではなく、思いの外、現実志向も強かったのではないかと感じられたのである。
となると、彼の中で思い描いているのは、物語がたちまち様変わりするようなミステリとしての面白さや陶酔感だけではなく、あくまでも、それを引き起こしているのは人間なのであるということも強く意識させられることにより、人間というものの得体の知れなさから考えさせるものもありながら、そこから派生する泣き笑いのような思いには、決して恐怖だけではない、そこに至るまでの気持ちがそうさせるのだと思わせるものもあった、そんな人間の不完全さに悲喜こもごもが宿っている点には、単なるミステリという枠だけでは収まりきらない、まるで人間自体が謎であるかのような書きっぷりに、泡坂妻夫の世の中の表と裏を見抜く、確かな眼差しがあるように感じられた。
思えば、最初の「赤の追想」から、いきなり後頭部を激しく叩きつけられたようなショックがあり、安楽椅子探偵仕立てなので直接的では無いものの、それでも彼の望みを叶えるための、その考え方には理解の範疇を超えた恐ろしいものがありながら、どこか哀愁も漂わせていた、それは人生のゴールが決して変わることのない、彼自身の悲劇とも思われる中、それに対して、人間の中に光と闇があることを当たり前に受け入れた彼女の言葉に、どこか爽やかさを感じられたのが一つの救いでもあった、生と死の対照性を、ある素晴らしいものに擬えて、人間の儘ならぬ様を見事なまでに描いている。
「椛山訪雪図」は、知識が専門的すぎて読み辛かったものの、最後は目にも鮮やかに、その意味するところを簡潔に見せてくれた、そこには「椛」の読み方から、実は最初からタイトルに全て込められていたことを思い知る、その正々堂々とした潔さと、死角を突いたような絶妙なバランス感が、泡坂妻夫の一つの持ち味だと思う。
「紳士の園」は、かなり闇志向が強い一品で、公園の奥でバーベキューパーティーさながらにあれを食べようとするのが、既に衝撃的だったが、それすらも些細なことに過ぎなかった最後の意外性には、それに対する並々ならぬ思いもあることから、単なる奇矯さだけではない、確かな説得力もあったのだが、それ以上に、この『大は小を兼ねる』的解釈の非人間性には、冷静に考えれば考えるほど空恐ろしいものがあった。
「閏の花嫁」は、最初と最後でがらりと景色が一変する、まさに泡坂妻夫の醍醐味を堪能しつつ、お伽話はお伽話だからこそ楽しいということも痛感させられ、人間も動物の一種であることを、改めて思い知る。
「煙の殺意」は、事件の捜査をしながらも、デパートの火事のテレビ中継から目が離せない望月警部と、屍体そのものが好きな斧技官の、ユニークなコンビだからこそ事件の真相に気付くことのできた、物語としての面白さとは対照的に、犯人の動機は本書の中で最も理解不能で恐ろしいものがあり、しかもそれを何の躊躇いもなく実行しながら、謝罪の一言も何も無く、これでも人間なのだろうかと思わずにはいられなかった、その衝撃は怒りよりも、どこか無関心風な望月警部と斧技官の様子も加わって、悲しくてやり切れないものへと変わり、確かにこうしたことも世界ではいくらでも起こっているけれど・・・といった、人間社会の闇の部分を深く抉り出しながら、「紳士の園」と見事な対照性を為した構成も心憎いばかりで、泡坂妻夫、恐るべしといった心境。
「狐の面」も専門的知識の読み辛さがあったものの、物語は心に響くものがあり、そこには奇術に対して奇術で対抗するといった、言葉は一緒であっても、そこへの拘りと思い入れには天と地ほどの差がある点に、泡坂妻夫の好きなものに対する真摯な情熱が、ひしひしと伝わってきながらも、それをユーモラスなタッチで描いたことに、彼の人間性が垣間見えた、それは最後の彼女に対する優しさもそうであった。
「歯と胴」は、犯罪者心理として起こり得る物語に斬新さは無かったものの、それを呼び起こす一つ一つの要素が、ゆっくりと明らかになっていく過程にあった、まるでホラー映画を観ているような恐怖には、思わず信じてしまいそうな臨場感で満たされているようであったが、これも人間に闇の部分がある故の思考法なのだと思うと、果たして人間とは、悲しい程に愛しい存在なのか、滑稽な程に愚かな存在なのか、よく分からなくなる。
最後の「開橋式次第」の、五代揃って一つ屋根の下で暮らしている家族の、人数が多すぎて名前を覚えられない面白さの裏で、くどい程に繰り返されるのは、人間は何かを拠り所にして生きていることであり、それが良くも悪くも、それぞれの人生に反映されている点を皮肉を交えて描きながら、どこか微笑ましさも感じられたのは、きっと完璧でないからこそ人間は特別に愛おしく思える存在なのだということを、改めて教えてくれたのだろうと、私は思う。
Posted by ブクログ
『ダイヤル7をまわす時』の解説で、櫻田智也さんが『煙の殺意』に言及していた記憶があったので、読んだ。(櫻田さんがどんな言葉でこれを紹介していたか失念した。あとで確認したら追加するかもしれない。)
必ずしも「事件→誰かが謎を解く」という構造の話ばかりではなく、最近読んだ岩波少年のホラー短編集とか、ウェストール短編集(こちらはホラーと銘打ったものではないが一応ホラーやスリラーが得意な作家とされている)のような、ちょっと不思議なぞくっとするお話集になんとなく読み心地が似ていた。
色気と、ユーモアと、トリック愛とは変わらず、短編集全体としてもバラエティ豊かで、とても良かった。
以下、備忘メモ。ネタバレはしてないはず。
・赤の追想→小柄で老け顔だが妙に色気のある男が安楽椅子探偵を演ずる。地の文の美しさも心に残った。「…堀があった。淀んだ都会の水は、夜になると水の心を取り戻していた。対岸のネオンが、水と恋をした。」
・椛山訪雪図→解説の澤木喬さんはこれを大絶賛していた。(私はちょっと固有名詞に混乱したせいか入り込めなかった。)
・紳士の園→刑務所帰りの島津。同じく刑務所帰りの先輩近衛に誘われ閉園後の公園での怪しげな酒宴を二人で開く。酒宴の前後で物語の様相が変わるのが面白い。
・閏の花嫁→彼、私の方に気があると思っていたのに、まさかあなたと結婚するとはね!という関係の女二人の手紙のやりとりからのまさかの展開。
・煙の殺意→お、表題作。殺人事件の現場で、デパートの火災事故のテレビ中継に見入る、無類のテレビ中継好きの望月警部。熱心に、執拗なほど熱心に現場、というか被害者の遺体の検証をするのは、無類の屍体好きの斧技官。この互いに相手を「変なやつだな」と思っている者同士のコラボで真相が解明される。
・狐の面→ヨギガンジーイズムを感じる一話。
・歯と胴→完全犯罪なるか。女のとある台詞が伏線だったことがあとでわかるのが見事。
・開橋式次第→大家族をおじいちゃんが一人で起こして回るドタバタ喜劇調の幕開けが楽しい。
Posted by ブクログ
ノンシリーズの短編集。
どれもこれもおもしろい、ハイクオリティな1冊でした。
【赤の追想】女の様子から推理された一人の男の真実。そしてそれと重なり明らかになる女の真実。
1ページの物語と思っていたものが、実は同じような内容のページが2枚重なっていてひとつの物語を作り上げていたというような結末。巧い。
【椛山訪雪図】一枚の掛け軸が事件を解決というわけではなく、あくまでも掛け軸に主眼を置き、事件が掛け軸の謎を明かしたというのが新鮮。
1枚の絵が見る人に何重もの意味を表し、それが持ち主の断腸の生き様とも重なってなんとも「粋」な1編でした。
【紳士の園】出所したばかりの二人の男が、公園の池で優雅に泳ぐ白鳥を捕まえてこっそり食べ始めるといういきなりの暴挙に驚き。
「スワン鍋」とか、何の冗談かと思ったら本当に公園の白鳥食べちゃうんだもんなぁ。こういうブラックでとぼけた会話など、著者の独特のテンポがとても楽しいです。
昨夜発見した死体が翌日なくなっているという謎をきっかけに、人間の自然な振る舞いについての捻くれた考察が思わぬ結末に。
他殺体を発見しときながら、追求するのはそこじゃないというのがおもしろい。
死体や、白鳥を食べた残骸などの非日常が人間の不自然さに覆い隠され、結末といい不気味さが漂います。
【閏の花嫁】女二人の往復書簡によって展開する物語。一人の男を巡る女同士のちょっとした嫌味の応酬とかが楽しい。
何となく胡散臭い結婚の話がどこに向かうのかわからずハラハラするのですが、からかいのネタだった大食いや太っていることがあんな結末の伏線になるなんて。
【煙の殺意】デパートの火災が気になり、殺人事件の現場でテレビを見だして片手間に捜査する刑事がおもしろい。
アリバイトリックが成された殺人ですが、じゃあ、そのトリックが何の為にという展開からの動機が凄い。話の持っていき方が楽しいです。
確かに犯人の思考と行動は合理的な気がする。恐ろしい考えではありますが。
【狐の面】マジシャンの著者らしく、山伏たちの奇怪な興行の種明かしが興味深く楽しかったです。
解決の仕方が洒落っ気と人情味があって良かった。
【歯と胴】女と愛人の男が夫を亡き者にしようと企むサスペンス。ところが、いざ決行!という時に思わぬ展開になりました。
「そっとされるのが好き」という女の本意がこんなところにあったとは!
【開橋式次第】大家族のどたばたがとっても楽しい。名前を覚えられず適当になったりとかが笑えました。
迷宮入りになった事件と同じ事件が発生するという魅力的な展開ですが、そんな理由で犯人と決め付けていいのか?
Posted by ブクログ
4+
独特なストーリーテリングで、変化球に見えても実はプロットはシンプル。故に早々に先が読める話も多いが、それでもその語り口の巧みさには舌を巻く。個人的には、キャラが立っている「狐の面」「開橋式次第」あたりが、先が読めても更に楽しめるので好みだが、やはり、特筆すべきは核心部で映像が華麗に反転する「椛山訪雪図」。思わず「おおー」と声が出た。お見事。
Posted by ブクログ
久しぶりに再読。
壮大なトリックではなく、視点変更を基軸とした騙しと意外性がやはり素晴らしい。
良作揃いの短篇集ですが、個人的ベストは「紳士の園」でしょうか。健全で安心できる世界が徐々に違和感をはらみ、やがて暗転するプロセスが絶妙です。
Posted by ブクログ
短編「椛山訪雪図」が面白かった。時間によって、紅葉や雪景色に変わるという不思議な絵によって殺人のボロが暴かれてしまうストーリが面白い。「紳士の園」も良い。出所者同士が公園で白鳥を食べたりする思いも着かないエピソードが可笑しい。泡坂の短編は少しコミカルでテンポもよく楽しい。
Posted by ブクログ
短編集です、それぞれの繋がりはなく純粋な短編です。それぞれに泡坂テイストが封じ込まれていて楽しめます。日本のチェスタトンの異名の通り、謎を置く位置が独特で予想外であること、その謎が明かされる時に、読者が見ていた場面、情景が、反転すること。つまり事象の見せ方、描き方が非情に秀逸であるということ。語る言葉にキリはないようです。
気になったのを挙げてみます。
「椛山訪雪図」紋章上絵師という伝統工芸の従事者でもあった氏ならではの作品だと思います。作中の椛山訪雪図、こんな絵があるなら見てみたい。
「閏の花嫁」いささか変わった作風、同じ味わいの海外有名作品があります。書簡のみの構成と最後の一行、フィニッシングストロークですね。
「紳士の園」「煙の殺意」「開橋式次第」いずれも、なぜ?どうして?の謎の置き位置が独特で、これぞ泡坂ミステリと言えるのではないでしょうか?見方を変えると全く違った風景が見えてくる騙し絵の世界、マジシャン泡坂の真骨頂でしょう。
Posted by ブクログ
70〜80年代に書かれた作品なのでちょっと古い感じがするのは否めない。しかし登場人物や舞台設定は短編とは思えないほど作り込まれている。
ミステリ好きなら読んでおくべき作品と言われているのもわかる。
Posted by ブクログ
当作品、泡坂妻夫著『煙の殺意』収録の「椛山訪雪図」のオマージュとなったののが、米澤穂信『儚い羊たちの祝宴』収録『北の館の罪人』(初出:『小説新潮』2008年1月号)
---
北森鴻氏推薦――「これまでもこれからも、僕の短編ミステリの大切なお手本です」
捜査そっちのけの警部と美女の死体に張り切る鑑識官コンビの殺人現場リポート「煙の殺意」を表題に、知る人ぞ知る愛すべき傑作「紳士の園」や、往復書簡で綴る地中海のシンデレラストーリー「閏の花嫁」など、問答無用に面白い八編を収める。
Posted by ブクログ
バラエティに富んだミステリー短編集。
表題作の真相には見事やられた。
そうきましたか!と。
『紳士の園』は奇妙な味みたいでちょっと不気味。
『歯と胴』の結末にはニヤリとする。
『開橋式次第』もなかなかユニーク。
予想外の展開が続くので、次はどんな結末になるんだと終始ワクワクした。
Posted by ブクログ
サクサク読める短編集。バリエーションがあって面白い。
泡坂さんは長編はもちろん、そして短い中でもしっかりと驚かせてくれる。
個人的には「紳士の園」が一番良かったかな。
Posted by ブクログ
短編集。どれも泡坂作品らしいテイストに満ちている。仕掛けのインパクトは長編には及ばないが、中でも恋愛ものには味わいがある。マイベストは最初の「赤の追想」。
Posted by ブクログ
70年代に書かれたミステリを集めた短編集、恥ずかしながら・・・初めての泡坂妻夫。
正確には、泡坂妻夫の作品自体は他のミステリ・アンソロジーで読んだ事はありますが、一冊の本としては・・・(^_^;)
米澤穂信の帯書き『世界最高のミステリ短編集です。』の一文に惹かれて読みました。
確かにミステリとしての読み応えは十分にありましたが・・・如何せん文体が古く、今一つ感情移入できない感じは否めませんでした!残念!!
Posted by ブクログ
つまらない本は途中でまだ終わらないのかなとつい思ってしまいますが、面白い作品は永遠に続いてほしいと思わせる力があります。
もちろん、本書は面白さ抜群です。
文章も格調高いものからユーモラスなものまで様々なバリエーションで読んでいて作者の芸の深さを堪能できますが、私は特に「狐の面」が昔の興行師のだましテクニックと童話のような雰囲気を持った作品として印象深かったのでおすすめです。
文庫本解説の澤木喬氏の文章もよかった、これだから文庫本はお得ですよね。
Posted by ブクログ
以下ネタバレ。
「紳士の園」の、スワン鍋を巡る不思議なやり取りから、この人らしい面白さが味わえるようになってきた気がする。
ラストシーンの飛躍が、個人的には好き。
あ、そう締めますか!みたいな。
「閏の花嫁」シボニスータ。気になる。シボニスータ。
「煙の殺意」も、犯行動機の奇妙さ、でも不意に犯したことによる死者の数に耐えられなくなる人間心理というのも、あながちあるように思えて、面白く読めた。
「歯と胴」は、二度面白い。
一度目は、死体を無茶苦茶にしたわりに歯を含んだ石鯛を彼が食べられなくなるというシーン。
二度目は、妻が殺されたことを知らず、教授が浸る幸せさえも滲んでゆくシーン。
こういう視点で描かれた話はまだ読んだことがなくて、なるほどと思わされた。
米澤穂信のお薦めらしい、と聞いて読んでみたものの、自分が生まれる前に書かれた作品とは思えないくらい、なんか発想や書き口が若い!
ちょっと驚いてしまう。
一人が殺されることのストーリーが組み立てられていくのに、その一人が突然パーツになるというか、俯瞰される構造が楽しかった。
Posted by ブクログ
ここに死体を捨てないでくださ
奇妙な論理というなら表題作が飛び抜けていますが、「紳士の園」「開橋式次第」の方が私好みでした。前者はスワン鍋が象徴するように、これから何が始まるのだろうと聴衆の心を大いに引き付け、手品の披露から種明かしに至るまで流れるように進んでいきます。後者はお得意の伏線祭りに加えて、ちゃっかり探偵役が入れ替わっているのも見逃せないポイント。いずれも賑やかでユニークな作風になっています。
「椛山訪雪図」はきっと私のセンスがないのでしょう。美しい情景がぼんやりと浮かびましたが、すぐに消えていきました。
Posted by ブクログ
1970年代後半に書かれた著者初期の短編集です。どれも騙しのテクニックが光りますが、作品の出来にはややばらつきがありました。
個人的ベストは、江戸時代の画家の描いた絵に隠された謎を解き明かす【椛山訪雪図】。騙し絵や玩具などに興味のない人にはピンと来ないかもしれませんが、鮮やかなトリックがとても印象的です。
その他【閏の花嫁】【煙の殺意】【歯と胴】も見逃せません。【閏の花嫁】はオチが見え見えなのは残念ですが、最後の一言でゾクッと来ました。
【煙の殺意】はアイデア自体には前例がありますが、点と点が繋がる瞬間は驚嘆しました。
【歯と胴】は完全に見えた殺人計画が思わぬところからバレてしまうという落とし方が綺麗でした。
Posted by ブクログ
泡坂妻夫の妙技を凝らした品々を堪能する、傑作短編を八編収録。
つくづく「泡坂さんはホワイダニットの作家さんなんだなぁ」と思った短編集であった。
なぜ、犯人はそのような犯行をしたのか? なぜ、そういう行動を取るに至ったのか?
ここらへんの心理的ロジックを描かせると、泡坂さんの筆は冴えに冴える。一見突飛過ぎるロジックも、不思議と動機としてしっくり来るのだ。まさに、「こんなの現実にはありえない」とわかりつつ、その「騙し」を堪能するトリックアートのような、めくるめく騙し絵の世界である。
この短編集のうち、ホワイダニット作品の白眉はやはり「紳士の園」と「煙の殺意」だろうか。読んでいて、泡坂さんのデビュー作「DL2号機殺人事件」を読んだときに抱いた、ロジックの鮮やかさが蘇ってきました。
しかし、やや難点も。
とてもバラエティーに富んだ作品であるし、ミステリーとしてロジックはどれも読み応えがあるのだが、いかんせん文章に膨らみがあまり感じられないため、読んでいて少々飽きてくる。
少なくとも、一気読みはおすすめできない。また、主人公達に感情移入できる、というわけでもない。
手品はただやってもらうだけでは、物足らない。いわくありげに、余裕を持って、たっぷり演出を利かせて、十二分に堪能したい、というのがわがままな観客の要望。
そして、それに応えてこそ、マジシャンは本当に「マジック」を使う人になるのだと思う。
そういう意味で、もうちょっと文章にも気を使って、お話にも膨らみを持たせてもらうと、ありがたかったのにな・・・というのが、わがままな客の、ショーのあとの寸評である。