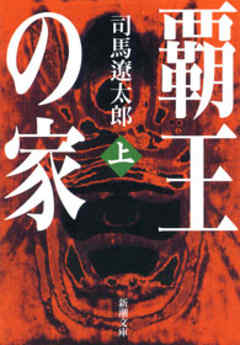あらすじ
徳川三百年――戦国時代の騒乱を平らげ、長期政権(覇王の家)の礎を隷属忍従と徹底した模倣のうちに築き上げた徳川家康。三河松平家の後継ぎとして生まれながら、隣国今川家の人質となって幼少時を送り、当主になってからは甲斐、相模の脅威に晒されつつ、卓抜した政治力で地歩を固めて行く。おりしも同盟関係にあった信長は、本能寺の変で急逝。秀吉が天下を取ろうとしていた……。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
司馬遼太郎の本は、いつもひとつの事柄から、違った方向にひろがっていったり、例え話をいれてくれたりしてわかりやすく、おもしろいです。本作は、大河を見て家康をもう少し知りたくなり読んでみました。三河衆の忠誠心の強さ、今川衆や織田衆の三河衆の見下し、信長より信玄の生き方を参考にしたこと、三河物語は大久保彦左衛門のひがみが書き込まれていること、信康が長篠の決戦前での退却戦で殿をつとめたことなど色々知ることができました。いちばんは、築山殿の話。10歳も家康より年上で、多淫であること、ヒステリックであることなどは大河で有村架純演じたものとは全く違い、私はどちらかというとこの作品のイメージでしたが、本来はどちらなんでしょうかな~と考えてしまいました。後半は、義理の叔父にあたる酒井忠次とのやりとりにも驚かされました。信康の非常識な行動からしたら仕方ないのかと思いますが、当時は当たり前のことなんでしょうかね。信長との同盟関係を20年続け、チャンスや恨みもあったろうに、ただの1度も裏切ることもなかったのも、辛抱強いとおもいました。長篠の戦いの後の勝頼との戦いは、色々テレビやら本やら読んでもあまり描かれておらず興味深かったです。勝頼は戦には、強かったが、内政をおろそかにしたこと、北条との同盟を破棄して、上杉と同盟したことなどが、衰退につながっていくことなどは始めて知りました。また、家康も本能寺の変後は強大な勢力である北条と敵対するが、暗愚の氏直と戦離れしている北条軍の弱さを見抜いていたことなどもすごいなと思いました。下巻も楽しみです。
Posted by ブクログ
~全巻通してのレビューです~
「関ケ原」「城塞」と共に家康三部作とされている本書。
家康が童だった頃の人質時代から天下を獲るまでを描いています。
ただし、関ケ原の合戦や大坂冬の陣、夏の陣には触れられていません。
具体的には信玄との三方ヶ原の戦い、本能寺の変後の上方脱出劇、秀吉との小牧・長久手の戦い、石川数正出奔劇などが中心に描かれています。
家康は信玄をよっぽど尊敬していたんですね。
井伊の赤備えもできましたし。
また、信長の後継者に名乗りを上げた秀吉に対して、圧倒的兵力差がありながらも引かなかったのは凄いなと思いました。
「関ケ原」「城塞」を読んだ後に読む本としてはいいのではないでしょうか。
家康を知ろうとしてこれを読んだだけでは物足りないと思います。
私は山岡荘八の「徳川家康」を読んでたので、おさらいの意味でも読みやすかったですね。
あと、司馬先生は家康を好きではないようですね。
江戸時代という太平の世が長く続きましたが、反面閉鎖的で世界から取り残されましたからね。
評価は難しいところだと思います。
Posted by ブクログ
徳川家康の本。司馬遼太郎は家康があまり好きではないようで、家康の劇的な人生の割にはページ数も少なく、小牧長久手の戦いで話が終わってしまう。まあその後の話は、「関ヶ原」「城塞」を読んで欲しいということなのでしょう。司馬遼太郎の考えでは、家康は全く新しいことをせずに人の真似のみで天下を取った、さらに本人は別に天下を欲していたわけではなく自分の領土である三河・駿河を守ることしか考えていなかったらしい。家康のすごいところは自分を人間としてではなく、殿様(社長)という部品であると定義し、人格を消してあくまで機械として一生を全うしたということ。現代のサラリーマン社長的な面があり、そこが個性で通した信長や秀吉と異なるところであり、徳川幕府という大きな会社が250年もの間存続することができた大きな理由なのだろう。また三河人は田舎者でそのために豪奢なことを嫌い、同族意識が強く外部のものを寄せ付けず、かつ我慢強く精悍な武士とのこと。信長、秀吉は三河人であり、明るく贅沢好きで経済感覚が非常に発達しておりお金を通して全てを考えていたので、三河人とは正反対であった。最終的に三河人(家康)が天下を取ったため、三河人の外部を受け入れないという気質が国全体に敷衍されて鎖国となったなどというのはとても面白い考えである。また、現代日本人の我慢強さや質素を好むような面(いわゆる武士道精神)も結局は三河気質によっているようだ。家康が現代に残した影響は相当大きいと改めて感じた。