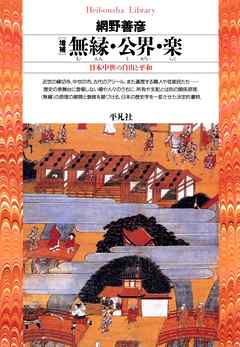あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
近代から古代まで遡り、駆込寺や楽市など多様な領域に、人間の本源的自由に淵源する無縁の原理の展開をよみとる。日本歴史学の流れを捉え換えた画期的名著。解説=笠松宏至
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
80年代頃の著作ということもあり、多少唯物史観的な観点はありつつも、一次史料を丹念に読み込み、中世世界の容貌を描き出している点で非常に素晴らしい。
特に面白いところは、無縁的な世界を為政者が取り込み自身の統治メカニズムに利用しようとしてきた経緯
Posted by ブクログ
宗教史の先生から必読と勧められて読みました。
中世の世界観を知る上でとても役に立った濃厚な一冊でした。
ただし一般向けに書かれた本ではないので文章は難しいです。
繰り返し何度も読みましたが読むたびにのめり込んでしまいます。
Posted by ブクログ
網野善彦は、間違いなく歴史学の天才でした。
この本は寺院と俗世、僧侶とその他の人々などの「縁切り状態」、つまり無縁を中心に、それが権力に取り込まれながらも形を変えて生き延びていく姿を文献資料を使って明らかにしています。
寺院に寄進された荘園もまた公権力の手の及ばないものになり、遍歴の芸能民も、一方では差別されながら、もう一方では力強く自由を持って生きていたことが分かります。
そして「無縁」は仏教的に肯定された語であることも網野氏によって証明されていく、歴史学の様々な前提を覆した名著です。
Posted by ブクログ
都市が村落との差異を持ちうる要因、市・盛り場などの都市のハレの場となりえた要因、これらは近世以降の概念では説明しえない、無縁の原理によって規定されている。
Posted by ブクログ
「公権力もしくは社会的関係が及ばない世界」でいいのだろうか。無縁の話で引き合いにだされるのが「縁切寺」で、ここに入ると夫婦関係(社会的関係)はナシになるし、「楽市楽座」の制は<座>の縁を無くした場所と説明できる。
Posted by ブクログ
本やさんで見かけて手にとり、あとがきを読んでそのまま購入した本。380ページのうち、初版についての批判を受けた「補註」と「補論」が108ページ。「無縁」という概念から主に中世の日本の社会を捉え直している、という理解でいいのかな。具体的な事例が次々と挙げられ、「無縁」の視点で語られていく。それが真実かどうかは置いておいて、純粋に面白い。
Posted by ブクログ
歴史書というよりも、思想、文化論。
西洋の自由、平等、平和に対して、日本文化としての「無縁、公界、楽」を対置しているわけで、生物学で言えばドーキンスに対するグールドの論を読んでいるような感覚を覚えた。
読みどころは本文よりも補注である。
Posted by ブクログ
乱暴なことかもしれないが、「有縁」の代表たる武士と「無縁」の代表たる朝廷。戦国時代までは住み分けが出来ていたが、徳川幕府による朝廷や寺社への法度、さらに明治の近代化により、社会全体の「有縁化」が進んだ。現代の差別問題は、一部、この有縁化がもたらしているのでは。
Posted by ブクログ
暴力のシステムが、ある程度の力を持つとき、それは少数者の保護を約束する。
道々の輩、異形異類と言われる特殊な技能を持つ人々が、かつては職農民同士で国のようなものを作り、他の組織あるいは国と交流していたと説く。
Posted by ブクログ
従来の、天皇と幕府の二重権力と農本主義に貫かれている日本史観を覆したというだけで、網野史観はスリリングだし、それだけで面白い。
その上、それぞれの時代のアウトローな存在たちに光を当てているのだから、学術書でありながらエンターテイメントの要素をはらんでいて、活劇を読むようにわくわくして読み進めた。
それが学術であれ、エンタメであれ、人の魂を揺さぶるものには、いつも無縁の原理が働いているという。
「無縁」というのは、現代的な意味での無縁とはちょっとちがう。
現代では「無縁仏」とか「無縁社会」とか、個人が社会の中で孤立している状態を指すのだが、網野史観による「無縁」の概念とは、「有縁」「有主」の対立物として浮かび上がる。
定住に対して移動。
国家に対して宗教。
…といった具合に。
しかもそれらは対立ばかりしているわけではなく、常に背中合わせで、密着しながら拮抗している。
具体的な無縁の原理というのは、
場としての市場、境界、社寺、山林、自治都市、関渡津泊、橋、河原、中洲などなど。
人々しての、供御人、職人、手工業人、海民、遊女、聖、山伏、巫女、勝負師、芸能民などなど。
それらは異界と異界の境界に発生し、異界と異界を行き来する人々によってもたらされる。
大阪に現れた最大の自治都市「堺」はまぎれもなく「境」だったのだ。
異界と異界の境とは、この世とあの世の境でもあった。
市には必ず死者が現れる。河原も中洲も浜も山野も、それらは神々と関わる聖域であり、交易芸能の広場であり、平和領域であり、葬送の地であり、刑場でもあった。
「無縁」の原理は階級社会に対しての自由・平和・平等の理想への本源的な希求が貫かれている。これはなにも日本に限ったことではない。
寺院に飛び込むと娑婆世界での縁が断ち切られる。
祭では日常社会の階級が解消される。
でも、このような無縁の原理は、国家(有縁の原理)の台頭によって衰弱してしまう。江戸時代の身分政策や寺請制度、明治以降の近代化によって人々はより権力の管理下に置かれ、無縁の原理は有縁の原理に取り込まれる。
60年代の学生運動などはこうした無縁の原理の希求がその根底に流れているのだろうし、この本が1978年に初出でベストセラーになったというのも興味深い。左翼やリベラルたちの支持を得たのは想像に容易い。
そしてインターネットの登場。
誰もが発信できる双方向のコミュニケーション空間は、それこそ有縁の原理がすみずみまで立ち入ることが困難な、無縁の世界の登場だったのだが、これもまたいつか有縁に取り込まれることになるのだろうか…。
********************
文学・芸能・美術・宗教等々、人々の魂を揺るがす文化は、みな、この「無縁」の場に生まれ、「無縁」に人々によって担われていると言ってもよかろう。
********************
Posted by ブクログ
ネットで見かけて。
面白かったし、読みやすかった。
中世に寄進関係や主従関係で結ばれていない
「無縁」のエリア、人々がいたらしいことは
納得できた。
その無縁所は
ただ神聖な場所ということではなく、
芸能に関係し、婚姻の無効に、借金の棒引きに有効なのはまだしも、
犯罪をも帳消しにできるエリアだということが、
今一つピンと来ない。
納得できないというか。
現代人の感覚なのか。
Posted by ブクログ
【読んだきっかけ】網野善彦氏の研究に興味があった。古本屋にあったので買ってみた。
【内容】縁切寺、中世の市、遍歴する職人や芸能民など、歴史の表舞台に登場しない場や人々のうちに、所有や支配とは別の関係原理、〈無縁〉の原理の展開と衰微を跡づける、日本の歴史学を一変させた書物。(カバー説明引用一部改)
【感想】網野氏の本はこれまで中世の遊女や非人について書かれたものなどを読んでいた。これまでの日本の歴史と呼ばれるものとは違う部分にフォーカスしており大変興味深かったが、この『無縁・公界くがい・楽』も期待を裏切らない内容だった。著者は大名や家臣の縁に繋がる場や人々ではなく、そこから逃避する者や逃げ込む場所、「有縁」の支配の外にある社会について語る。そこは遍歴する海民、山民、商工業者、科人、勧進聖、非人、芸能民らが存在する「無縁」の場で、そこには独自の関係原理と自由があった。中世の自治都市にもその性格があった。
読み間違いもあるかもしれないがこんな話である。私はこれを読んで、おサムライやお百姓中心の歴史・ドラマがいかに風景の一面だけを切り取ったものであるかを感じた。今で言えば政界や経済界だけを描くようなもの。これでは現代社会を正確に描いたとは言えない。
本書は発表当時異端の書とされ、また批判も多かった。著者はこの批判にも正面から対応し、その分の増補がまた長い。私もようやく一度読んだ程度で理解も浅いが、いろいろと創造力をかきたてられる良書だと思う。
Posted by ブクログ
江戸時代、夫と別れたい妻は縁切り寺に駆け込んだということは高校の日本史でも習う事実である。著者、網野善彦氏はこの縁切り寺のような世俗から断絶したアジール(=聖域)は日本に昔から存在したことを証明していく。そのような場は、タイトルである「無縁」「公界」「楽」などと呼ばれていた。そこでは例えば、世俗の身分から切り離されていた、犯罪者の駆込場となっていた、税金の徴収を免れていたなどの特徴を有していたことが示される。わたしたちは「自由」や「平等」といった西欧的価値観を深く深く内面化している。わたしはそれらヨーロッパ(もっといえばヨーロッパ近代)の価値観がどれほど普遍性を持っているのか、西欧と接触する以前、日本に自由、平等の精神と呼びうるものが存在したのかいなかに興味を持っていた。そのことについて考えるきっかけとなった。網野善彦さんの他の著作にもあたってみたい。
Posted by ブクログ
最初に「えんがちょ」とか「すいらいほうらい」という自分が育った藤枝でやっていた、子供の時の遊びから始まったので、簡単なエッセイかと思ったら、全然違う。
駆け込み寺のような公の権力の及ばない、世界、無縁・公界・楽などの視点から、日本の中世史を分析している。
(1)堺などの自由都市というのも、むしろ公の権力の及ばないところ、無縁の世界と考えることもできるらしい。
(2)市場、網野さんは市庭というのも、無縁性があった区域らしい。
(3)河原の中州、山林、寺院、墓所など、一種のけがれの空間から無縁の世界、人々が始まったという考え方は、おもしろい。
白川静先生が、孔子伝で、孔子は葬祭をあつかった下層の祭司という指摘をしていたが、そのような現世からの境目を扱うということに、なんらかの神秘性、宗教性を感じるというのは、世界共通かもしれない。
そこに、現世とは別の中間領域がうまれ、そこに駆け込む人がでてくるという発想、おもしろいな。
Posted by ブクログ
もののけ姫のタネ本と聞いて手に取った。内容は、日本中世(鎌倉〜室町)において、「無縁」「公界(くがい)」「楽」と呼ばれるアジール(世俗権力や権利義務関係から絶縁している場所)が存在し、そこでは有縁の関係から離れた無縁の人々が活発に生きていた、という事を資料に基づき説いていくというもの(読み込めてないので正しくないかも)。
自分は日本史にまったく明るくないので読むのには苦労したが、興味深い内容も多かったので楽しめた。
本書は著者が学生から発せられた「天皇はなぜ滅びなかったのか?」「なぜ平安末・鎌倉時代にのみ優れた宗教家が輩出したのか?」という問いに対するひとつの試論として書かれている(pp.5〜6)。
後者ついて、それまでの論理から多少飛躍した部分があるものの、その回答はとても面白い内容だった(「二十三 人類と「無縁」の原理」)。
それをかいつまんでまとめると以下の通りである。
西欧の自由や平和・平等という概念はキリスト教のアジールから出発し、宗教改革や市民革命などによる権力との格闘の末に獲得されていった。それに対し日本におけるアジールは、仏陀の教えとして捉えられる形で鎌倉仏教に組み込まれ深化し、室町〜戦国時代にかけて無縁・公界・楽として意識化されたものの、以降はそれを発展することができなかった。江戸時代を経て幕末明治に西欧の自由・平等の思想が流入し、ついには日本的な無縁の自覚化、つまり日本にとっての自由・平等の思想がが起こらずに来た、というのが著者の見立てである。
これは夏目漱石が説いた「外発/内発」の話とも通じる話であり、とても面白い。著者は「その過程が段階を画するためには、『有主』の世界から、『原無縁』を最初に組織し、その後も『無縁』の世界の期待を体現しつづけた王権ー天皇との酷烈な対決を経なくてはならなかったが、その課題に、ほとんど手をつけることなしに、日本の『近代』は始まる。」(p.247)と述べている。この言葉の意味を明確には理解していないが、とても重いテーマのように感じる。
ちなみにもののけ姫の関連としては、おそらくタタラ場の扱いがそうだろう。戦国大名(の走りだろう)アサノ公方と対抗し、また病人などの有縁から外れた人たちが住む無縁の場として、タタラ場がある。自治共同体としての無縁の原理も、この著書に惹かれる部分のひとつである。
Posted by ブクログ
こんにち子どもたちのあいだに残っている「エンガチョ」、江戸時代に妻が尼となり強制的に離婚するために駆け込んだ「縁切寺」、罪人がそこに逃げ込めば基本的に罪科を逃れられるという「駈込寺」などと列挙していき、主に戦国時代の「無縁所」という、世間との縁をいったん断ち切って内部での平和を保証する一種の聖域=アジールを浮かび上がらせる。
そしてこの無縁所は「公界」ともつながって、その場所の平和を土台として「市」=「楽市」が成立する。
タイトルだけだとなんだかよくわからないこの本は、知的興奮をよびさます名著である。
さらに「アジール」=「無縁性」は、どの文明・未開社会においても、普遍的に見られるものであると指摘し、とうとう人類学的な視野にまで到達するから壮観だ。
さて現代社会では、たくさんのお年寄りが所在不明になっていることがわかり「無縁社会」だと言われているが、この本に呈示されている「無縁」による「自由と平和」が、自由主義/資本主義としての「市場」を形成するのであってみれば、現在の社会はその無縁性・自由主義の到達点であると言えなくもない。著者はそんなこと、執筆時にはまったく考えていなかっただろうけれども。
ともあれこの本は面白かった。お薦め。
Posted by ブクログ
冒頭で筆者は、子供時代のエンガチョの遊びや、江戸時代の縁切寺などの「縁切り」の例を挙げ、縁切り=自由、縁切り寺=アジール(避難所)という捉え方を提示する。そしてそのような「自由」の原理が以前にはもっと生き生きと活動していたのではないか、という問題意識の下で、中世、古代、さらには未開社会における「自由」のあり方を探っていく。
その結果明らかにされるのが、本書の表題でもある無縁・公界・楽と呼ばれる原理である。それは無主・無所有の思想が貫徹されているという意味でアジール、さらには一種の理想郷であり、未開・文明を問わず、世界の諸民族に共通して見られる。そのようなアジールの形態には3段階の変遷があるという。
未開社会では、王などの特別な人間や寺院、神殿、あるいは森林などの場はそれ自体がアジールとされ、世俗の権限の及ばない神聖な領域であった。これが第一の「聖的・呪術的アジール」であり、この段階では無縁の原理もすでに見られるものの、まだ後の時代のように具体的な内容を伴ったものではない。いわば「原無縁」とも呼ばれる状態にある。
しかし人類が自然の開発を進める中で「所有」を基礎とする有主・有縁の原理が分化し、無主・無縁の原理を「国家」として取り込んでいく動きが顕在化する。無主・無縁の原理の衰弱はここに始まるが、同時にそれは、それらの原理が有主・有縁と対立するものとして自覚化し、明確な意識化を遂げていく段階でもあった。これによって現れるのが、第2段階としての「実利的アジール」であり、日本ではその勃興期が古代から中世前期までに相当する。ここにおいては、遍歴民、勧進聖、一揆や惣、非人などの人々や、都市、山林、関渡津泊、市や宿、寺社などの場は、世俗的な権利の働かない無縁の存在であるとされ、「無縁所」「公界」「楽市楽座」などの名称の下に様々な特権、具体的には不入権、地子・諸役免除、自由通行権、平和領域、指摘隷属からの解放、貸借関係の消滅・徳政の免除、連座制の否定、自然的な年齢階梯による組織などが与えられることになる。
これらの原理がもっとも完成させた姿を現すのが室町~戦国期にかけてのことであるが、同時にそれはアジールが第3段階の「終末」へと向かっていく過程でもあった。有主・有縁の関係を固めた戦国大名たちは、無縁の原理の取り込みを一層進行させていく。それまで潜在的に無縁の場所として認められていた寺社は、戦国大名の菩提所とされ、大名からの文書を受けることで無縁所としての形態を認められることになる。これは「無縁所」としての完全な自覚化であると同時に、大名の統制下に組み込まれていく動きであると見てよいだろう。その結果最終的に現れるのが、織豊政権、さらには近世幕府のような統一的な国家権力である。この段階では、無縁の原理は縁切り寺(鎌倉東慶寺、上野国満徳寺など)、遊郭などのごく限定された領域にのみ認められることになる。
一方のヨーロッパでは、これらの段階を経た後、宗教改革や市民革命などの王権との闘争を通じて、近代的な自由、平等、平和の思想を生み出したと思われる。その点日本における無縁の原理は、近世以降特にその歩みを遅めたようにも思われる。しかし、無縁の原理とその世界は、決して滅びることはない。その「無縁」の自覚化こそが、現代における日本人にとって重要であると最後に述べられている。
現在、エンガチョ遊びを知らない子供が増えている。これが「自由」「平和」の消滅と連携していることなのかは分からないが、いま末期症状を呈しているこの概念を、著者自身の経験から直観で捉えられるうちに形成期に遡って調べ上げた本書は、今後の歴史学研究に重用される文献となるだろう。
また、「末期症状」とは言いながらも、再生への展望が最後に示されている。ただ研究のみ行い、それを提示するだけの論文と違ってこの著者は、それを研究した者にしか為しえない、「確実に文脈に則った展望の提示」を行う。ここを特に評価したい。
さらに無縁の原理に関連して、従来の歴史学が軽視しがちであった非農業民的存在の人々や、都市的な空間に注目している。その点でも、後の歴史学に影響を与えたところは大きいだろう。
そして壮大な試みであるこの研究は、壮大な試みであるが故に発表以来様々な形で批判を浴びることにもなった。その中で筆者自身による再検討作業も進められ、1987年にこの『増補版』が出版されることになったが、2004年の筆者の死去にともない、その原理も未完成のままに終わっている。
また、本書では中世以前の「原始の自由」に生き生きとした生命力を見出し、それが近世以降に国家権力によって制限されていったとする点で、歴史認識としてはかなり悲観的なものがある。筆者によれば本書は、私的所有、有主的世界の進展を「人間社会の発展」ということができても、直ちに「進歩」と言い切ることができるのか、という疑問から出発し、「自然を人間と対立するものと見て、それを所有し、支配・管理することにのみに人間の本質を見出したときに、人間は破滅の道を進まざるをえない」と判断することにもなる。その上で、筆者は未開・文明を問わず世界の全ての諸民族の間に共通して存在し、作用し続けてきた無縁の原理を追求することで、従来の世界史の基本認識とは異なる、無所有の深化・発展に関する新たな人類史・世界史の基本法則を捉えようと試みているのである。それは、「進歩」や「自由」とは何なのか、という人間にとっての本源的問題とも関わってくる内容であるといえるだろう。しかし無縁の原理を追求するあまり視野が多少狭まるのだろうか、何から何まで無縁に関連づけることに、少し違和感を覚えた。
Posted by ブクログ
今年(2004年)2月27日に亡くなった網野善彦の代表作。縁切寺や子どもたちの「エーンガチョ!」に見られるような「無縁」の原理は、原始のかなたから生きつづけているものだという、人類学的な拡がりを見せる日本中世史の本。普通は「縁」こそが日本独自の共同体の論理だと思われているが、「無縁」もまた「公界」という公共の領域を作り、「楽」と言われるように一種の自由を享受していた。しかし、その自由は近世になるにつれて「縁」の論理のうちに取り込まれていき、差別として固定化されていく(つまりエタ・ヒニン)。網野善彦がこの「無縁」の論理に一種の「希望」を見出し「自由」と形容したことに、抵抗と共感の両方を感じる。つまり、「楽観的すぎる」「もっと社会構造の観点から攻めるべきだ」という批判と、その論理が現に生きられたものであったからには、それはあくまで一種の「自由」であり、ひとつの生き生きとした社会的現実ではないかということだ。どちらにしても、この本にさまざまな可能性を感じるし、単なる日本史の専門書としてだけでなく、ひとつの読み物として魅力的だ。