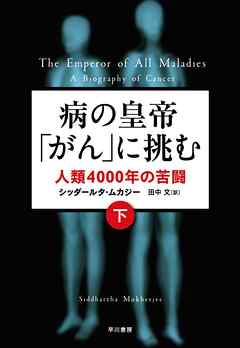あらすじ
20世紀に入り、怪物「がん」と闘うには「治療」という攻撃だけでなく、「予防」という防御が必要であることがわかる。かくて、がんを引き起こす最大の犯人として、たばこが指名手配されたが……人類と「がん」との40世紀にわたる闘いの歴史を壮絶に描き出す!
1964年1月、アメリカ公衆衛生局長官はひとつの報告書を発表した、「たばこはがんの主要な原因である」と。たばこ産業にとって、この報告書はまさに爆弾であった。この時から全世界に覇権を広げるたばこ会社と、「がんの予防」を推進する人々との熾烈な戦いが始まる。そしてまた、巨大企業、患者、医師、研究者とのあいだの壮絶なドラマは、がんを治す「新薬」をめぐっても行なわれていた。 その一方で、分子生物学の進歩は、がんの根本的な原因を明らかにする。異形の怪物の原因は、我々自身が体内に持つ遺伝子の突然変異の蓄積によるものだったのだ!
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
一通り読むことでがんの歴史の概要がつかめる良書である。医師である著者の個人的な体験とからめながら書かれており、現実味が増している。翻訳も素晴らしく、医学系の本にありがちな不自然な訳語は見られなかった。翻訳家は現役の医師とのことであり、納得した。繰り返し読んで知識を定着させたい。
Posted by ブクログ
現代に生きていて、"発がん性物質"という言葉を聞かずに一生を終えることは難しい。
『原因不明の不治の病を生じさせる』という空恐ろしい事実は、しかしその構造の不理解ゆえ、長らく見過ごされ、なんの対策もなされなかったどころか、明確な隠蔽にさえあった。
タバコのパッケージに警告文「喫煙は健康に害を及ぼします。」と記載されるようになったのはつい最近の出来事だと思いがちだが、ガンへの影響が初めて論文になったのが1761年、警告文の提案がなされたのは1964年、日本で記載されたのが2005年だ。
とはいえ、その因果関係を説明できないうえに、統計学すら発展途上であった時代の出来事とあっては、単純にその産業主義を責めることは難しい。
1976年に人間に備わったがんのもととも言える現がん遺伝子が特定され、この時ようやく喫煙者と非喫煙者に同じがんが生じる理由が明らかになる。
1983から次々とがん遺伝子やがん抑制遺伝子が同定され、遺伝子組み換えマウスでがんを人為的に発生させることに成功。
1986年には研究結果をもとに初のがん遺伝子標的薬剤が発見され、
1994年の病院は治験を待てずに新薬を求める人たちであふれかえった。
そして2005年、がんの死亡率は1990年と比較して15%近く減少した。
だが、同じ年に50万以上のアメリカ人ががんで亡くなっている。
上巻ががんの治療の物語だとしたら、本書はがんの研究の物語。
ひらめきと偶然と人の意志により、研究と治療がようやく結びついたがんと人との物語の終わりは、まだまだ見えそうにない。
治るがん、治らないが薬で抑制できるがん、未解明のがん、治療薬耐性がん、末期がん。
転移との戦い、副作用との戦い、治療費との戦い、そして代替医療との戦い。
がんの物語とは、医者と研究者と患者とその関係者。すなわち人類の物語と言っても過言ではないだろう。
Posted by ブクログ
現役の腫瘍医であるムカジーによるがんの治療と研究の歴史を描いた本。古代エジプトのパピルスに「この病の治療法は無い」とかかれてあったという。それほど昔から人類はがんと隣り合わせに生きてきた。がんは遺伝子の病と言われるようになった。がん遺伝子とがん抑制遺伝子の存在が明らかになり、それらの遺伝子が損傷して活性化、あるいは抑制遺伝子の場合は非活性化するとがんが発現するらしいという。それぞれの遺伝子を標的にした分子治療薬の開発が続けられている。がんはゲノムによるのであれば人類はがんからは逃れられない運命にある。
Posted by ブクログ
特に印象深いページは、上165pの科学者のスタンス、下260pのスレイモンの橋を架ける、下287pのドラッカーの「みんなはただ愛想よく振舞っていただけだった」
Posted by ブクログ
「ここ二十年間のあいだの驚くべきスパートのあいだに、科学者はすばらしい新世界 ― 悪性増殖を解き放つがん遺伝子やがん抑制遺伝子や、切れたり点座したりして遺伝子のキメラをつくる染色体や、細胞死を受けつけないシグナル経路からなる世界 ― のベールを取った。」
この後すぐに「しかし、がんの死亡率の減少につながった治療法の進歩はそうした新発見をまったく反映していなかった」と続くのだが、人間はがんとの闘いを着実に進めてきたは明白である。実際に、1990年から2005年にかけて、がんの死亡率は15%近く減少しているらしい。もちろん、その変化は、医学的治療の進歩だけではなく、ロビイングによる喫煙率の減少や、早期発見に向けたスクリーニングの効果も大いに寄与していると考えられる。
ーーーー
父ががんを患い、他界したのは、1992年のことだ。ちょうど先に挙げた二十年のスパートが起きる前のことだ。当時は、がんであることを医者が本人に告知することも躊躇われていた。本人よりも前に医者からその事実を告げられた母は、暫くそのことを本人にも子供である自分たちにも伝えなかった。同時に、もし自分がそう診断されたら、自分にも伝えてほしくないとも言っていた。がんになるということはそれだけ重く致命的な宣告であった。父は、外科手術も抗がん剤治療も行った。最後は丸山ワクチンも試していた。二十年後の今であれば、どうなっていたのだろうか、とどうしても考える。がんにかかるにはあきらかに早い歳であったから。
自分が父が死んだ歳になるのはまだ少し先だが、父が自分の歳にはおそらく初期のがん化は始まっていたであろう。目をつむると自分の体の中で、遺伝子による抑制を外れて増殖を繰り返す細胞が生まれているのを感じることさえできそうだ。がんは克服されるかもしれない。しかし一方、生物としてその規を超えて抵抗すべきではないようにも思うのだ。
Posted by ブクログ
「ある特定の果物(きのこだったりもする)だけを食べれば、がん(どこのがんか特定もしない)が消滅」、みたいな、素人目にみても無茶苦茶なタイトルや帯が付いた本、雑誌が、大手を振って、書店に並んでいる現状において、「がんリテラシー」というのは非常に重要だと思う。
本書は、その観点から、とても大切な「教科書」のひとつになるのではないか。
Posted by ブクログ
そして下巻はがんの予防、そしてついに来ましたがんのメカニズム解明。
細胞分裂の開始と終了を司る遺伝子が変異するのが原因、てことで分裂のアクセル踏みっぱなし、かつブレーキが壊れた状態になってまうらしい。そりゃワサワサ増えるわな。。。で、その遺伝子を標的にした、副作用の少ない分子標的薬がついに出回り始めました、という現状でこの大作は締めくくられとります。
最後まで読んでふと思ったのが、実は"がん"って病気とは違うんとちゃうか、と。もちろん発がん物質のような外部要因もあるけど、普通の細胞分裂でもDNAのコピーミスが発生して、そこからがん、ってのも確率的にありうる話やからなあ。
あらかじめ生命の設計図に記載されてる、自分の別バージョンみたいなもんとも言えるなあ、とそんなことを考えさせられました。もちろんできれば発症したくはないけど(-_-)
がんを知るにはホント最適な本やと思うので、あまねく人にぜひオススメ!
Posted by ブクログ
下巻は、予防の占める割合が多い。特に、喫煙と発癌の関連が今まで感じていたよりもはるかに強いことを知らされた。
その差の原因は政治的な情報制御としか考えられず、自分で情報収集しなければならないことを痛感した。
癌がいずれ克服されるというような薔薇色の夢は描けないが、個々の癌に対して治療法がみつかって行くことには率直に感動させられる。
Posted by ブクログ
とんでもなく面白かった。
疫学的、分子生物学的、
腫瘍遺伝学的アプローチのお話もわかりやすく、
他分野でもそうだが、
科学の進歩と人類の探究心のすごさを思い知った。
2011 年 ピューリッツァー賞一般ノンフィクション部門受賞作品。
Posted by ブクログ
がんはどうやってできるのか?最初のヒントは1775年のロンドン。クライミング・ボーイと言う煙突掃除夫に陰嚢がんが多発した。チムチムチェリーはすてきな歌だが実態は病気の温床だった。1761年素人科学者のジョン・ヒルは噛みタバコが口腔がんなどを引き起こすと発表した。タバコの消費は増え続け1855年頃クリミア戦争を契機に爆発的に拡がった。イギリス、フランス、ロシアの兵士が紙巻きタバコの習慣を持ち帰り、アメリカにも伝播した。1870年に一人当たり年間1本未満だったアメリカのタバコ消費量は30年後にはアメリカ全体で35億本のタバコと60億本の葉巻を消費した。しかしタバコと発がん性の関係が調査されたのは1948年ごろアメリカとイギリスの別のチームが同じ結論に達した。しかし喫煙と肺がんの相関関係がわかったとしても将来のリスクはわからない。1951年10月31日ロンドンのドールとヒルはついに追跡調査をすべき集団を見つけた。4万人を超える医者からのアンケートを回収し喫煙者と非喫煙者の仮想の集団を観察したのだ。集団内の死亡報告が上がるたびに集計し29ヶ月後789人の死亡が確認されその内36人の肺がん患者は全て喫煙者だった。1964年には臨床試験参加者数112万3千人と言うルーサー・テリーの報告書が提出され連邦取引委員会はタバコ会社にパッケージに「喫煙は健康に害を及ぼします」と表示するように提案した。政治的な力を持つタバコ会社の抵抗にも関わらず反タバココマーシャルはタバコのテレビコマーシャルを1970年末に中止させた。1983年に弁護士マーク・エデルは肺がん患者シポロンに勧めてタバコ会社に対して訴訟を起こした。シポロンがタバコのリスクを認識していたことは認めながら、重要なのは「タバコメーカーが喫煙リスクをどれだけ認識し、そのリスクを消費者にどれだけ公開していたか」だと。裁判自体はタバコ会社の勝利となった(責任は20%)がタバコ会社はその後も攻撃にさらされつづけた。
がん研究の重要な一歩はエイムズによるサルモネラ菌の変異の研究から生まれた。サルモネラ菌を様々な化学物質で曝露し、元の菌が増殖できない培地に置いたときにどれだけ増殖するかは菌の突然変異によって決まる。菌を突然変異させる化学物質はがんの原因物質にもなりやすいと言うことが研究で裏付けられた。これが変異原性試験ーエイムズ試験で今では新しい化学物質を登録する際には必須の試験になっている。しかし、アスベストなどはエイムズ試験では変異原性を判定できない、万能ではないのだ。
1960年代にはHBV(B型肝炎ウイルス)に感染すると、肝細胞がんのリスクが高まることが発見された。ブランバーグは遺伝子調査をしている際に血中タンパク質に注目し、HBVの感染を見分ける方法に気づいた。ウイルスが直接ガンの原因になることは証明できなかったもののブランバーグは発ガンウイルスの検査法とHBVのワクチンを開発することで伝染を止める方法を開発した。
1979年胃炎の原因を調べたマーシャルは未知の細菌をなかなか見いだせずにいたが、ある時放置したままの培養基からピロリ菌を発見した。細菌が胃炎の原因になることを証明するためには感染させる実験をしなければいけないが、ブタは感染しなかった。1984年7月マーシャルは行き詰まり、助成金の申請も難しくなり究極の実験を行う。絶食して培養されたピロリ菌を飲み込んだのだ。数日後に具合が悪くなり内視鏡検査をした結果、急性胃炎を起こしており胃壁は細菌の層に覆われその下に潰瘍ができていた。若年層に対しては除菌は胃がんの発生率を大きく下げたが、慢性胃炎の高齢者にはあまり効果がなかった。
1920年代に徹底的な細胞観察で子宮頸がんの異常細胞を発見したパパレンコウは発表時点では笑われた。子宮頸がんを診断するなら細胞塗抹なんて面倒なことをせずに、なぜ子宮頸部の生検をしないのか?パパレンコウのド録画実ったのは1952年、NCIの史上最大規模の臨床試験で15万人の女性がパップテストを受け、555人に浸潤性のがんがみつかり、そしてより大きな意味を持つ発見、557人のほぼ無症状の前浸潤がんが見つかった。そして前浸潤がんと診断された女性の平均年齢は浸潤がんと診断された女性より平均年齢が20才若かった。これにより子宮頸がんは治る病に変わった。そして、早期発見の可能性も拡がっていく。
1981年それまでは化学療法によって大多数の白血球を破壊されたがん患者によく見られたニューモシスチス肺炎がアメリカ中の若い男性患者に見つかる。後にAIDSと名付けられたこの病気は当初ゲイ関連免疫不全「GRID」と呼ばれた。この病気が変えたのは認証薬のあり方だった。エイズ活動家はFDAの承認プロセスを攻撃した。「二重盲検法をつくった者たちは、末期の病のことなど念頭に置いていなかった。何も失うもののないエイズの犠牲者達は、喜んでモルモットになりたがるだろう。」シュプレヒコールは「薬を体へ、薬を体へ」。がん患者も声を上げる。エイズが未承認薬を使うのならばなぜがんには使えないのか。転移性乳がん患者は効果が確認されていないにも拘らず大量化学療法と骨髄の自家移植へと殺到した。未承認の治療法への治療費支払いを拒否した保険会社は敗訴し、保険会社のその姿勢のために治療が遅れたと8900万ドルを賠償請求をされた。この時にはまだ臨床試験は続けられていたが、患者は臨床試験ではなく高額の治療を選んだ。しかし、この治療法を推進する強力なデーターであった南アフリカの治験データーは全てねつ造されたもので、1999年から5年間かけて実施された臨床試験では乳がんのリンパ節転移に対して超大量化学療法と自家骨髄移植は否定された。(その後ある種のリンパ腫を自家骨髄移植が完治させることが判明している)
がんの原因は何か?1970年代にはがん遺伝子が見つかった。srcと名付けられた遺伝子からつくられるタンパクがいくつもの細胞を活性化させ分裂加速状態へと陥らせる。では、がんは内在的な病気なのか。これまでの発がん物質との関係はどうなるのか?遺伝子の研究が進むと細胞分裂を進めるアクセル遺伝子(原がん遺伝子)と止めるブレーキ遺伝子(がん抑制遺伝子)があることがわかってくる。網膜芽細胞腫(Rb)遺伝子のケースでは正常なRb遺伝子は対になっていてブレーキとして働き、二つの遺伝子が両方変異して不活性化するとブレーキが壊れ分裂が止まらなくなりがん化する。発がん性物質は様々な理由で遺伝子を変異させ、結果としてアクセルを踏むかブレーキを壊す。また、細胞分裂を繰り返すと遺伝子のコピーミスが起こり変異した遺伝子ががんを発生させる。
がん細胞はタンパク質をスイッチにして次々と他の遺伝子を活性化することがわかってきており、その際がん遺伝子が特異的につくるタンパクと結合する物質が考えだされた、それが分子標的薬だ。組み替えDNAの技術によってジェネンテック社は薬としてタンパクを作れるようになっていた。乳がん組織のHer-2と言うタンパクに結合する特別なタンパクー抗体がわずか3年で合成された。92年に臨床試験が始まり、98年にFDAに認可されたハーセプチンだ。
1993年、6年前に乳がん手術と化学療法を受けていたマーティ・ネルソンは乳がんを再発しいろいろな文献を調べハーセプチンにたどり着く。しかし、健康維持機構はハーセプチンは未承認だからHer-2陽性かどうかを調べるのは無意味だと言い、ジェネンテックはHer-2陽性とわからなければ使用許可を出せないと言う。1994年10月手を尽くしてようやくハーセプチンの理想的な候補者だとわかったが遅すぎた。9日後ハーセプチンの使用承認を待ちながらネルソンは亡くなった。この事件がきっかけでジェネンテックは臨床試験は患者に対して行うのではなく、患者と一緒に行わなければならないと気づかされた。副作用に対するリスクを重視すれば未承認の薬をばらまくわけにはいかないが、一方で副作用がどうとかを待てない患者がいる。患者と製薬メーカーと行政がどう折り合いを付けるかは病気の種類や深刻さによっても変わるのだろう。
ヒトゲノムは解読されたががん遺伝子の解読はまだ始まったばかりで散発的にがん遺伝子と抑制遺伝子が見つかってきている状態だ。同じがんでも人により効く薬も違う。がんとの戦いはまだまだこれからだが、少なくとも進むべき方向はわかってきたようだ。
Posted by ブクログ
ガンがエジプト/ペルシアなど古代文明で認識(ペルシア王妃が乳がんを切除)されて、そのかにのような固さ、広がった形からcancerと名付けられてから、現代までの経緯を著者自身の臨床経験と交えて熱く語る今年一番の力作。
特に20世紀は寿命が伸び、タバコなどの発がん性物質もより一般化して来たガンの世紀となった。一方治療も手術は過激ともいえる、できるだけ切除する方法、化学療法は大量のカクテル療法を行い、正常細胞を死ぬまで追い込むあるいはがん化させるリスクを十分冒して対抗した。その背景は、遺伝子に異変を引き起こすガンの仕組みが明らかではなく、対処療法にとどまったことだ
21世紀の後半にかけて
1.増殖シグナルの自己否定、2.増殖抑制シグナルへの不応答、3.アポトーシスの回避、4.無制限な複製力、5.持続的な血管新生、6.組織への浸潤と転移
と行った特徴が明らかになった。がなかなかこれらの知見に対応する治療法が生まれず/認可されず、時間の限られた患者との間での摩擦が高まった(エイズも同様)。しかし1980年代後半から、増殖シグナルを抑制する分子標的薬ハーセプチンの研究/認可が進むなど局所疾患、急激な成長、生体の機能の利用(血管を持ってくるなど)へ対応した治療法が出て来ており、完治数がこの20年で毎年改善していることは医学の勝利への希望が高まっている。
)
Posted by ブクログ
がんの分子標的薬は、がん遺伝子を直せく不活性化するものと、がん遺伝子によって活性化されるシグナル経路を標的とするものがある。
現在は、がんゲノム解析プロジェクトが進んでいる。
がんゲノムの変異には、ドライバー変異とパッセンジャー変異がある。ドライバー変異はがんの増殖を直接誘発しており、当該がんの標本上で繰り返し起きている。パッセンジャー変異はランダムで無害だ。
また、これらの変異による繋がりを「がん細胞の活性化経路」として分類し直すと、11~15(平均13)種類の経路となる。
今後がんのメカニズムが明らかになると、がん医療には三つの大きな方向性がもたらされる。
一つめは治療の方向性で、13種類の経路のうちいくつかを標的とした阻害剤は既に臨床で利用されている。
二つめはがん予防の新たな方向性で、活性化経路への影響を調べることで新たな発がん物質の検出方法が発見される可能性がある。
三つめはがんの挙動全体の説明で、異常遺伝子と経路に関する知識を統合することで新たな知識と発見ひいては治療的介入のサイクルを一新させる可能性がある。具体的には、がんの不死性は造血幹細胞のような正常な生体の再生を真似ているという説がある。
Posted by ブクログ
・患者相手のトライアル&エラーがすさまじい。しかし著者は患者を埋もれさせず、臨床医として関わったがん患者の話を何度も織り交ぜていてすばらしかった。特に最終節。著者の温かい人柄が伝わった。
・個々の科学者も敗北し続けながらも、全体としては少しずつ謎が解明されていくのが壮大で感動した。ひとりの成果は小さくても、そのおかげで前進していると見なせる。まさに「何一つ、無駄な努力はなかった」。
・葉酸類似体や化学兵器マスタードガスやX線やラウス肉腫のように、別分野のことを端緒に新しい攻め方が開発されていくのもおもしろい。
・米国の科学政策も興味深かった。基礎研究が無いのにマンハッタン計画やアポロ計画のような目的指向型はだめだな。
Posted by ブクログ
後半は喫煙やアスベストなど、公衆衛生学上の知見によるがん予防、バップテストなどによる早期発見など、本格化するがんとの戦いが描かれる。
HBVなどのウイルスやピロリ菌などの細菌による、環境因など、様々な要因によってがんが起こる原因として、細胞の分裂をつかさどる遺伝子の変異(がん遺伝子)や、暴走を制御する遺伝子(がん抑制遺伝子)の変異が明らかになり、これらは数百も見つかる。がんを起こすのは通常、こうした遺伝子一つのみの異常ではなく、複数の遺伝子が障害されることによる。一つの遺伝子異常を抱えたまま静かに増殖する細胞群の中に、2つ目の異常が起き、3つ目がおき、、、がんになる。
タモキシフェン、ハーセプチン、グリベックなど、薬物療法の開発は進み、がんゲノムシークエンスにより、複数の遺伝子が障害されてがんが発生するメカニズムも明らかになっている。現状はまだ、がんは手強い存在であるが、今後は明るい(?)と思わせる書きぶり。
・がんのウイルス(鳥に肉腫をおこすウイルス)を最初に見つけたのはペイトン・ラウスであった。30歳の時に見つけたが、当時はその発見を冷笑され、87歳になってようやくノーベル賞を受賞した。
・乳がんの手術は時代とともによりラジカルな術式に移っていき、それはより広範で、身体的な代償を支払う手術であったが、1981年に大規模な臨床研究の結果が発表され、単純乳房切除術と長期予後は差がないことが示された。今日では、根治的乳房切除術が施行されることはほとんどない
・スクリーニング検査の指標として生存期間を設定するのはよくない。全く同じ時期にがんが発生した場合、鋭敏なスクリーニングでがんがみつかり、5年後に亡くなったケース、スクリーニングを受けずに同じ時期に亡くなったケース、二例を比較すると一見、スクリーニングにより5年、余命が伸びたように見えるがこれは間違い。このバイアスをリードタイムバイアスという。
Posted by ブクログ
癌と人間の壮大な歴史。上下700㌻と大部だが様々なエピソードを織り交ぜて退屈しないし,しっかりした通史として学べるので時間をつくっても読む価値がある。
下巻では癌の予防の発見,癌のメカニズムの解明,そして分子生物学の進展による分子標的薬の獲得を扱う。
医療といっても科学や技術一辺倒でないのは,人々の高い関心やどろどろした既得権益を反映していて,上巻同様政治運動の側面も見逃せない。強い発癌性が発覚した煙草をめぐる論争や,新薬を切望する末期患者たちによる「悠長な」臨床試験への批判,目覚ましい効果を挙げた化学療法が幻と消えた論文捏造事件などが読みどころ。
高齢化が進みより癌への関心が深まる中で,これからも様々な物語が語られるだろう。中にはこれまでの癌研究の流れや基本的な事実をねじ曲げるようなものもあるだろうが,そういったものへの免疫をつける上でも本書は役立つに違いない。
Posted by ブクログ
がんと人類の歴史。
がん「闘う」とは何か。
その言葉だけでは言い表せない。
治療により失うもの、得たもの。
あるいは、何か理由があって備わった機能なのか。
Posted by ブクログ
上巻同様の感想になりますが、患者さんや医師や研究者を交えたドラマとしても、科学医学の進化の歴史という話としてもとても興味深いものでした。やや難解さを伴うと感じることがあったので星3にしましたがほとんど星4の素晴らしい作品です。ゆっくりなようでやはりこの百年くらいの医学の進歩は凄いのだと気づかされます。一方でここに来て、他の科学もそうですが、本当の難題にぶち当たっていることは気がかりなことです。