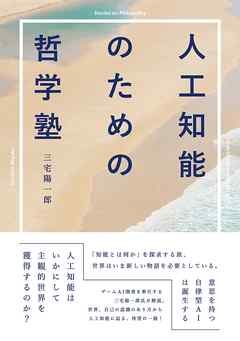あらすじ
「人工知能は、いつ主観的世界を持ち始めるのか?」
本書はこの問いを巡って、人工知能を成り立たせるための哲学・思想的背景(工学やコンピュータサイエンスではなく)について、ゲームAI開発者として数多くの実績のある三宅陽一郎氏が解説する一冊です。
人工知能は「私」というものを持ちうるのか? そうならばそれはいかにしてか? 「世界」とは何か? そして「身体」とは何か? 人間の世界認識/自己認識の軌跡を濃密に辿りながら、人工知能に迫ります。
Facebookで1,500人が参加するコミュニティ「人工知能のための哲学塾」にて開催されてきた連続夜話が待望の書籍化!
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
人工知能を理解するために、近代哲学の系譜を俯瞰して捉え、知能とは何か?自己とは何か?について考察している。どちらも、まだ明快な説明ができない自分のために読んでみた。読後もいまだに説明ができそうもない。
手元に置いておき再読したい一冊。
Posted by ブクログ
2020年の夏休み図書として購入。
2017年から社会人として博士後期課程に進学したことがきっかけで哲学的思考に興味を持ち始め、自身の研究を進める傍ら様々な西洋哲学の入門書も読み進んでいくなかで偶然本書を知ることとなった。
著者は国内におけるゲームAI開発者の第一人者ともいえる三宅陽一郎氏であるが、本書は三宅氏が「人工知能のための哲学塾」というイベントを5回に渡って開催した際の、いわば講義録的な内容となっている。
人工知能関連の書籍はサイエンスやエンジニアリングに偏った内容が多い中で、本書は人工知能に関する専門的な内容は最小限に留めつつ、人工知能開発における哲学的思考の必要性について、終始一貫して取っ付きやすい話し言葉と図解で綴られている。
そのため、"人工知能と哲学"という一見難解かつそれぞれの関連がなさそうなテーマにも関わらず、専門家でなくても読み進めることのできる構成となっている点が、本書の最大の特徴であるといえる。
個人的に興味はあるものの、何から手を付ければ良いのか分からなかった「現象学」について、人工知能という切り口でデカルトとフッサールの哲学を対比させながら冒頭で解説し、最終章でメルロ=ポンティの知覚論に繋げる展開は、非常に理解の助けとなった。
また、本書は現象学アプローチだけでなく、ユクスキュル、ギブソン、ベルンシュタインなどによる生物学的アプローチや、デカルト、ライプニッツ、ラッセルなどによる数学・記号学的アプローチ、そしてジャック・ラカン、ジャック・デリダなどによる構造主義的アプローチに関しても解説され、人工知能開発を下支えするための多角的・多面的なアプローチの必要性を説いている。
「ゲームキャラクターにAIを実装する」と聞くと軽い響きに感じるが、これは「コンピュータに知能を持たせる」ことと同義である。さらに言い換えると、文字通り"人工的に知能を創り出す"ことに他ならない。
そのためにはまず、プログラミングや開発以前に「知能とは何か?」という疑問が出発点となり、その解を足がかりとして構築していかなくてはならず、途方もない地平が広がっていることに気付く。
そしてその解を導出するために、哲学的アプローチが必要であると著者の三宅氏は主張する。
5回のテーマそれぞれが異なる学説やアプローチで展開され、時には哲学から離れる部分もあるが、図表がふんだんに使われ首尾一貫した構成であるため、困惑することなく読み進められた。
また本書を通じて、人工知能開発に対する現在の課題および将来の可能性だけでなく、新たに学んでみたい哲学者について知ることもできた。
最後に、本書を読み終わった時の率直な感想は、
『人間は、根源的に時間的・空間的存在である。』
Posted by ブクログ
AIが本物のAIになるための必要な要素のひとつとして著者が考える、哲学を解説してある、と思ってたら大間違いだった。
哲学塾とあるものの、実際は心理学や生物学も含めた幅広い分野をAIに絡めつつ、AIに主観を持るためには何が必要なのかを認知を中心として解説していくように自分には読めた。
本書の素晴らしいと感じたところは、例えば、さりげなく
「意識」を「注意」と置き換えて考えてみます。
といって(理由をくどくど説明することなく)、よどみなく読み進められるところか。
唯一残念だったのは、巻末に読書ガイドがあるとてっきり思い込んでいたのが、めくってみたら講義のディスカッションの記録だったことくらいか。読書ガイド、実在すると思ってたのだけど。。。
勉強不足が身にしみた一冊でした。
Posted by ブクログ
現象学の考え方が人工知能研究で大きな意味を持ちうるという事を初めて知りました。
分野横断的に人工知能に関わり得る思想を取り上げているので、哲学や人工知能の各分野の本を読むだけではなかなか触れ合うことのない考えに触れられた気がします。
Posted by ブクログ
講義録なので著者の他の本と内容がかぶるところはあるけれど、大きな筋での見通しが素晴らしくて、最後のメルロ・ポンティに得心する。ユクスキュルと環世界のところはあまり理解していなくて、なんでこれが2番めなんだろうとか思うのですが、最後まで読むとああそういうことねとなりました。エントロピー増大の話が量子力学から導出出来た日にこの本を読んだというのもなにかの縁な気がします。
Posted by ブクログ
哲学に全く馴染みがなかったが、人工知能の理論的側面で哲学のアプローチがあるという発想そのものは非常に面白かった。内容がやや難しいこともあり、消化不良でもあるがそれは自分の能力不足。
Posted by ブクログ
フッサール、ユクスキュル、デカルト、デリダ、メルロ=ポンティなどの偉大な哲人達の思想を基に人工知能への実装を考察、汎用的な人口知能へはこのようなアプローチも必要なのかと朧気ながら思いつつも私にはかなり荷が重い難解な書であることは否めない一冊でした。また、人間以外の動物や昆虫の世界観と身体感覚の遠心性コピーが印象に残りました。