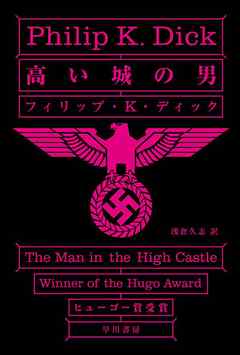あらすじ
第二次世界大戦が枢軸国側の勝利に終わってから十五年、世界はいまだに日独二国の支配下にあった。日本が支配するアメリカ西海岸では連合国側の勝利を描く書物が密かに読まれていた……現実と虚構との間の微妙なバランスを、緻密な構成と迫真の筆致で描いた、P・K・ディックの最高傑作!
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
枢軸国と連合国の勝利逆転if小説ですが、架空戦記ではなく人間関係や各各々の国の人間性を詳しく描かれ、敗戦国から全てを取る戦勝国などが詳しく描かれていてとても面白かった。恐らく史実のアメリカが史実の日本にソ連がドイツに置き換わっているのでしょう。
Posted by ブクログ
ディックの作品は「アンドロイドは〜」以来なのですが、作品設定として仮定した社会の描写力がすごい。この物語では「連合国が敗北した社会」でのアメリカの精神がどうなるか、人々がどのような生活を送っているかの描写が群像劇の中でリアリティを持って描かれています。
個人的にドキッとさせられたのはラストの易経「米国が勝ったのが真実である」でしょうか。今までフィクションとして読んでいた物語からこちらからを見る眼差しがある、ということに新鮮味を感じました。何度でも読み直す価値がある作品です
Posted by ブクログ
初めてフィリップ・K・ディックの作品を読んだ。ストーリーははっきりしている。登場人物の関係性もわかる。緊張感をはらんだシーンも続いて飽きることなく読み進むことができる。度々現れる卦の部分も物語を進める装置としてうまく働いている。ではこの小説全体としてどういう意味なのか?と問われると、うまく答えられる自信はない。
歴史の逆転する仮説そのものを細かく書き出すことには、例えそれが一つの重要な要素であるとしても、最も大きな意味があるということではないだろう。その小説の中で、その小説のなかの現実とは逆の世界を描いた小説、つまり本当の歴史に近いものが登場人物によって書かれて、読まれているというのはさらに大きな意味はあるのだろうけどそれ自体は小説の構造を成しているという意味で重要であるが、描かれた世界の持つ意味はなんだろう?
「イナゴ」を書いたアベンゼンの空虚さはどう理解すれば良いのか。バイネスと矢田部の意味のありそうで空虚な会談は田上の心を揺らすための仕掛けなのか。最後まで会うことのないフリンク夫妻が混沌とした世界の良心のように見えるけど、結局のところ易経に依存して生きているようにも見える。とはいえフランクフリンクとチルダンはアメリカ人としての良心のようなものを自分たちが作り出して世の中に出していくアクセサリーの中に見出しているように感じられて、それがこの世界の希望のようにも見える。
高い城は結局現れず、そこには底の知れない空虚さが口を開けている。わずかながらの良心のようなものが風に吹かれて偶然のように過ぎ去っていく。
理解を超えた部分で心に残る作品。
Posted by ブクログ
舞台は、第二次大戦が史実と異なる結果を迎え、ドイツと日本が戦勝国となった世界。敗戦国アメリカの国民は自尊心を失い、両国との狭間で翻弄されていく。
舞台設定的には、ifモノの歴史が好きな層に受けそうだし、それだけでワクワクしてしまうが、本質としてこの物語が訴えたかったことは、「今、生きているこの世界こそが真実であり、懸命に、前を向いて生きていくしかない。」(つまりあの時ああだったら、本当はこんなはずじゃなんて考えたところで無駄。)ということだと思う。
そのメッセージを表現するのに、劇中劇として登場人物たちが虜になる「身重くイナゴ横たわる」という本が大きな役割を果たしている。この本は「もし連合国側が勝っていたら」を描いているが、史実と微妙に異なる内容である(真珠湾攻撃が失敗する、チャーチルが90歳まで首相を務めている等)こと、終盤に主人公の一人であるジュリアナに、この本の世界こそが真実である(つまり劇中の世界は嘘である)とメタフィクションを告げていることから、物語は「結局どの世界が真実かなんて重要じゃない、知ったところでどうなる?」と読者に問いかけている。
Posted by ブクログ
第二次世界大戦で枢軸国側が勝利した世界に生きる人々の群像劇。
北米は3つに分断され、日本支配地域、ドイツ支配地域、中立地域となっている。
ドイツは水面下で、日本を破壊して世界を征服しようと画策している。(タンポポ作戦)その矢先にボルマン首相が死去。タンポポ作戦の賛成派であるゲッペルスが次の首相として有力視されている。一方、タンポポ作戦反対派のハイドリヒが盛り返しているという話もある。小説で描かれているのはこの辺までで、その後どうなるのかは分からない。
ホーソーン・アベンゼンが書いた「イナゴ身重く横たわる」という歴史改変小説が流行している。この本では(現実の歴史とは詳細が異なるが)連合国が勝利したことになっている。
登場人物の多くが易を行い、自らの行動を決定する。
設定はあくまで設定で、その中での複数の登場人物の行動がそれぞれ独立して描かれているのが面白い。各登場人物の行動は絶妙に交錯している。
ジュリアナの最後の結論「ドイツと日本が負けたのが事実」というのと、田上が見た幻覚がよく分からない。架空の登場人物が動く世界(高い城の男)が虚構で、ジュリアナと田上は現実(高い城の男の読者がいる世界)を一瞬垣間見たということなのか。
Posted by ブクログ
独日がWW2に勝った世界線という事、アマプラのドラマ版のPVでちらっと見た事があるくらいなので、読んだ感想としては思ったより地味
易経に何度もメインキャラクター達が頼っているが、日本人が易経をやるというイメージはどこから来たのだろうか笑
易経の難しい漢字とか読み方にはルビが欲しい、、笑
章の中で登場人物が行ったり来たりするので少しだけ分かりにくい
田上とチルダンが個人的にはお気に入り
たんぽぽ計画は結局どうなるんだろう?
結構大事な所なのに、曖昧にされちゃってそこは残念でした
Posted by ブクログ
設定は最高。手に取った時ワクワクした。
展開と中身は。。。なんか気が散る文章で生成AIとウィキペディア駆使してなんとか読んだ。
易経が万能すぎる。易経本だこれは。
Posted by ブクログ
不思議な力強さのある作品でした。
本当にそっくりそのまま世界が反転していのは凄かったです。確かに日本とドイツが世界大戦で勝っていればこんな世界になっていたのだろうと想像ができます。陰鬱で秩序や差別が厳しい世界。
日本タイムズなどは、読んでいて言葉が面白かったです。西海岸は日本が占領しているなど、ありえなさそうで、でも勝利していたらありえそうで、白人が日本人にあんなにオドオドする姿はある意味新鮮でした。アメリカと日本の立場が見事に逆転していていました。
内容はかな。哲学的、人とは何なのか、人種とは何なのかという自問自答が多い。国家とは何なのか、そういった思想に近いモノを一人一人が抱えており、その思想が正しいのかどうか、自分の判断を占う為に、易経という占い(おみくじに近いかな)みたいなモノで、自分の指針を定めるきっかけにしている。そこはかなり古典的で物理的な方法だなと拍子抜けしましたが、日本が勝利し、日本の占い文化が西洋でも根付いた結果、易経が広く浸透していたのかもしれません。
個人的には、ドイツは勝利してもヒトラーがいなければ、ナチスは機能しないと思いました。、ヒトラーがいなくなれば、ナチはうまく機能しないと思っていた。たとえどれだけ優秀な人がいたとしても、内輪揉めで崩壊する、いや、この作品はその崩壊する一歩手前を描いていたのかも知れない。
かなり現実的な作品、というより、登場人物にすごく軍の中枢の人達ではなく(そういう人もいたが)1人の商人やただのお金持ちなどが登場するため、その辺りが自分達とある意味変わらず、心情を理解しやすかったです。
第二次世界大戦後期あたりの知識がないと、世界観をうまく掴めないかも知れないです。特にドイツに関する知識は必要かも。YouTubeの簡単な解説をご覧になってからこの本を読む事をオススメします。
Posted by ブクログ
アベンゼンは『易経』を使って小説『イナゴ身重く横たわる』を書いていた。ジュリアナが「なぜその本を書いたか、我々はその本から何を学ぶべきか」という問いを立てて易を行うと、「真実」という回答を得る。ジュリアナは、本に書かれていることが真実であるというメッセージとして受け取る。これが、本作の幕切れ直前、結論のような位置に置かれているシーンだ。
ここから読者は何を読み取ればいいのだろうか?
(a)彼らの世界で起こった出来事は真実ではないということか? それとも、(b)これからドイツ帝国の崩壊や、日本への水爆投下が起こり、プロセスこそ違えど、最終的には本に書かれた世界と同じような結果にたどり着くという予言なのか? あるいは、(c)幾千幾万もの偶然の積み重ねにより、無数の可能世界が生じているという視座を暗示しているのか(この解釈は弱い。もしそうならば、彼らの世界も、本に書かれた世界も同等に「真実」なのだから)。しかし、(d)そもそも『易経』は単なる占いであり、占いは信じなければ無意味だし、信じる人には、曖昧な示唆のレベルで意味を持つものだ。アベンゼンの本が占いの結果の集積であるなら、その本が価値を持つのは、それを真摯に受け止める場合のみである。だから、アベンゼンの本から学ぶべきことは、「戦勝国となった枢軸国がアメリカを支配する現状を宿命と受け止めて、その現状に馴致するような生き方をするな。彼らの勝利は確率的なものでしかないし、彼らは勝ちながらにして実質、負けていることすらあり得る」といったメッセージだ。
本作では、個人がさまざまな選択を迫られ、よくわからないままにどれかを選択しながら生きている様子がしばしば描かれている。田上にしろ、フランクにしろ、ロバートにしろそうだ。その都度選択をし、そして人生が展開していく。そのことを肯定的に書いていると思う。反対に、「あり得たかもしれない世界」「選ばなかった世界」についてあれこれ考えを巡らせることは停滞でしかない。だから、パラレルワールドの存在を示唆しているといった解釈は、本作の場合、そぐわないと思う。ロバートは、日本人たちに表面的に媚びへつらう商売をしながら、やがて西欧文明を受け継ぐものとして自信を取り戻していった。戦争に負けても、そのことを絶対視する必要はなし、ましてや卑屈になる必要はない、という価値観を示すためにロバートというキャラクターは作られたのだと思える。だから、私は解釈(d)こそが一番もっともらしいと思う。
負けは負けとして認める。けれど、そのことを絶対視して卑屈になるべきではない。戦争の話じゃなくて、個人の人生の教訓。
「ディック作品にありがちなプロットの破綻が見られず」(訳者あとがき)という点が高評価(1963年ヒューゴー賞受賞)の一因らしいが、私はプロットが破綻しているディック作品のほうが断然スリリングだと思う。プロットをあまり決めずに書くようになった『OUT』以後の桐野夏生のほうが、彼女の初期作品より素晴らしいように。
Posted by ブクログ
第二次世界大戦が枢軸国側の勝利で終わったという世界。
日本やドイツに統治されている米国。
ドイツが統治する地域では禁書となっているという小説が、それ以外の地域では話題になってヒットしている。内容は、第二次大戦が連合国側の勝利で終わった世界を描いたもの。
登場人物の多くが自らの進むべき道を「易経」で占っている。
本作は1962年に執筆されているが、この時代には易経が流行っていたのだろうか…。1978年に出版された『宇宙船とカヌー』でも、ジョージ・ダイソンが旅の出立をいつにするか易経で占うべきかなぁ、なんて言うくだりがあった。
この世界で売れているという小説の作者も、ストーリーの展開を易経で占っていたと告白する場面があるが、実はP.K.ディック自身が本作を書く上で実際にそうしたことがあると解説にあった。
作中の小説の内容と、現実の歴史と、登場人物の振る舞いとディック自身の振る舞いと、最後の平行世界的どんでん返しで目くるめく感覚に陥る。
骨董品屋と贋作メーカーとの関係など、本物とレプリカをめぐる物語などもディックの真骨頂と思わせる。
なかなか面白かった。