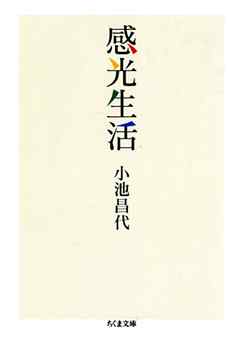あらすじ
「その日も、呼び鈴は、いつにもまして、権力的に鳴った。その瞬間、わたしは神経を逆なでされ、理由もなく押したひとに反感を抱いた」(「隣人鍋」)。日常と非日常との、現実と虚構との、わたしとあなたとの間の一筋の裂け目に、ある時はていねいに、ある時は深くえぐるような視線をそそぐ15の短篇。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
自分と他者との関係を、感覚的に詩的に捉えた表現が卓越している。それでいて哲学的といってよいほど深く突きつめられてもいる。
例えば、『石を愛でる人』の一節。手のひらの中で石ころをころがす場面。
「石とわたしは、どこまでも混ざりあわない。あくまでも石は石。わたしはわたしである。石の中へわたしは入れず、石もわたしに、侵入してこない。その無機質で冷たい関係が、かえってわたしに、不思議な安らぎをあたえてくれる」
ここに収められた15本の短編小説は、15通りの「人との関わり」を描いている。
主人公は全て「こいけさん」だが、不躾に入り込もうとして「こいけさん」に拒絶される迷惑な隣人。知らぬ間に入り込んできて「こいけさん」を発情させてしまうが、期待に反して通り過ぎてしまう男。絶対にこちらから入いりこめないにもかかわらず、新たな何ものかを触発させる子ども達。思い出として「中に」刻み込まれているのに、形としては消え去ってしまったものへの郷愁。
入ってこようとして拒絶されたり、入ってきて欲しいのにすり抜けられる。あるいは、既に中にあるのに失われてしまったり、産み落としたつもりはないがなぜか通じたり。すべては、自己と他者との関係について突きつめた思いの詩的な表現である。また、常に「こいけさん」は受身である側からさらりと表現している。
この連休中に読もうと小説ばかり四冊購入した。その中で読みやすいという点ではこの本が群を抜いていた。他は川端康成の名作、藤沢周平の短編集、小川洋子のベストセラーである。同時に何冊か読み進み、読みやすくて面白くて「読めてしまう」ものから読んでいくのが私流だ。2位以下を大きく引き離してゴールしたのが小池昌代のこの本だった。
いつも「なぜだかわからないが」読みやすい。といい続けてきたが、秋以降矢継ぎ早に読んだ小池さんの小説本も3冊目である。いいかげん「わからない」ままではと思い、今回大真面目に分析してみた。その結果だから理屈っぽくて難しい話になってしまった。
まあ、わかりやすくいっちゃえば、女のエロスでしょう。だからといって今回の15編には肉体的に「入って」こられた話はない。そういう意味で官能ではありえなくて、あくまで「感光」であって、「入って」きたのは外界から射し込んできた光である。
『感光生活』とは、光になる経験です。光となって事物を照らす、その目がつくる経験の世界です。と著者自ら説明してくれています。
ですが私は、全く逆じゃないかと感じます。あたかもピンホールカメラの針穴から射す光に、フィルムが「感光」して画像を刻むかのように、その時々様々な他者との関係という光に「コイケさん」が感応して、その時々の色に自由自在に染まって像を定着させている。その自在さ軽やかさこそが著者ご自身もお気づきじゃない「読ませる」魅力なのではないかと思う。
何事も言い切らぬ軽やかさ、なんの解釈も強要してこない気安さ。何の引っ掛かりも感じず読み始め、読み終わってもなにか物足りないにもかかわらず、常に爽やかな読後感。すべては小池さん自体が「感光材」だからでしょ。
ただし、15編のうち唯一『蜂蜜びんの重み』だけは例外とみた。
この1編だけは軽やかな感光材としてではなく、追いつめられながらも作家として生きていく「決意」が、『重み』として込められた物語だと私は見抜いた(あくまでつもり)。
当たってるかどうか、小池さんに聞いてみたいものだ。
Posted by ブクログ
そのももの本質にまっすぐ根ざした、適切な重み。
そのときわたしは、日常のなかで、わたしたちの生にに、
気づかないほど微量に付加されている、
さまざまなものの、
さまざまな重みのことを思っていた。
(「蜂蜜びんの重み」より)
小池さんの目ににじむ光は、
やわらかい、のか、あいまい、なのか。
遮蔽物と投影面が近ければ近いほど鋭敏さを持つ光と影のコントラスト。
すべての作品において、人と人との関係や、感情、そして虚構性までもが、その境界線をゆらめかせている。
小池さんのファインダーは気まぐれか、確信的か。
物語の襞の中で、くっきりと浮かび上がるかにみえる思想や感情は、
単に読み手であるわたしの補正技術(願望)ゆえか。
老齢の写真家は言った。
「光の輪郭だけではないのだ。
重さ。
重さを撮ることが、写真というものなのだ。」
読み終わって思い返すと、
どの写真も、
すべて、ぼんやりしている。