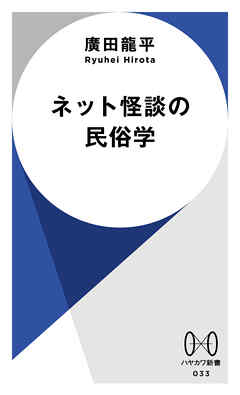あらすじ
空前のホラーブーム、その源流がここにある。
ネット怪談はどのように発生し、伝播するのか。きさらぎ駅、くねくね、リミナルスペース……ネット民たちを震え上がらせた怪異の数々を「共同構築」「異界」「オステンション(やってみた)」など民俗学の概念から精緻に分析、「恐怖」の最新形を明らかにする
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ドストライク世代なので、懐かしい感情が1番大きかった。
類書が乏しいジャンルと時間軸なので、貴重なまとめだと思います。
都市伝説解体センターのカバーがとても良い。
Posted by ブクログ
2000年代、オカルト板やまとめサイトを深夜まで読み耽っていた当時が懐かしく思い出された。
著者は今後、ネット怪談の流れは因習系(コトリバコなど)から異世界系(バックルームなど)へと移行していくと見ている。
「恐怖の根源には自分は違うともの、自分の知らないものへの漠然とした不安や警戒があるとはよく言われることである。だが、そうした不安や警戒が、現実に存在する具体的な人々・集団や、それをモデルにした登場人物に直接向けられる怪談やホラー作品の体験談あるいは新作は、今後、ゆるやかに減っていくのではないかと思われる」
怪談索引、参考文献、注が充実。
Posted by ブクログ
きさらぎ駅やことりばこ、リアルなどいわゆる「洒落怖」系怪談や、スレンダーマンなど海外産のクリーピーパスタ。さらにはバックルームなどの今なお様々な派生がある作品や動画系など幅広いネット怪談をまとめ、分析していく一冊。
民俗学的視座を用いてはいるものの、読んだ時の楽しみとしては怪談の幅広い網羅性が面白かった。
まさに洒落怖の流行当初からネットに浸かっていた身としては懐かしさを感じる本だ。
Posted by ブクログ
発売されてすぐくらいに手に入れてたんだけど、雰囲気で手に入れたということもあって、なかなか読む気になれずにいました。書影にもある、帯の梨さんの言葉で読んでみようと思ったんじゃないかなと思う、多分…もうその辺のことも忘れてしまってるくらい積読してました ごめんなさい。。
私の2000年代は仕事中心時代だったから、PC漬けの毎日だったにも関わらず、ネット怪談やネットホラーにはほとんど馴染みがなく。
リゾートバイトやきさらぎ駅とかも映画が先で後追いでネットという、順序逆の触れ方をしていたので、本書でその経緯やらが知れたのはありがたかったです(特に、コトリバコにおける差別的歴史が云々のくだりを読んで、映画「樹海村」を観て感じた違和感というかなんか違う感は ここから来たのかと思いました)。
ネタから始まったものが時間経過とともに真実であるかのような様相を帯びてくる、確かにそうかもしれないですよね。
その話題に途中参加したとか、更に馴染みのない地域だったりしたら、「ぇ~ネタじゃない 笑」って思う反面ほんとも隠されてるかもと思ってみたり。
特に村系のお話に関しては、心のどこかにそうだったら面白いというか凄いよねという腹黒い気持ちがあって(極端な話、因習村系のお話の読者は皆そうじゃないかと思ってる)、罰当たりなうちらにはいつかほんとの恐怖がやってくるんじゃなかろうかと…
本の感想とは関係ないことやけど。
Posted by ブクログ
ホラーのゲーム実況などをよく観る。最近は物語らしい物語がないものが多いなあ、と漠然と思っていた。どうしてそうなったのかが書かれていて納得したし、すっきりした。
掲示板など文字だけの情報から、画像や動画が出てきてネット怪談の有り様が変わっていくのが分かって面白い。
「田舎の因習を都会の人間が楽しむ」「田舎なら何でもあり」という文化が忌避されるようになり、物語のない「感覚的で曖昧な不穏さ」のものが多くなっている。
とはいえ「因習もの」が完全に無くならないのは、「怪異の原因をつきとめて、それを解消する」という筋立てがあるとすっきりするからなのかな…
Posted by ブクログ
インターネット時代の到来で、誰もが気軽に情報発信できるようになった現代。空前のホラーブームはそんな時代の産物と言える。本書はネット怪談、ネットホラーを民俗学的観点から追いかけ、その空気感を丁寧に解説している。
日本におけるネット怪談、ネットホラーというものが旧2ちゃんねる由来が多いせいか、ところどころ読みにくさと理解しづらさがあったが、概ね理解することはできた。取り上げられている個々の都市伝説や怪談のほとんどを知らなかったため、それに対する解説が少なかったのはちょっと残念だったが、少しずつ変化していく様や共同体が(ネット上で)形成されていく様は非常に興味深く読めた。
Posted by ブクログ
最近の出版業界で最も勢いがあるとされているジャンルはホラーである。また、それは出版業界に限らずインターネット、SNSでも大きく注目を集めている。その代表例としては雨穴さんや背筋さんが該当するだろう。彼ら以外にも、いわゆるモキュメンタリーホラーというジャンルが注目されている。モキュメンタリーとはドキュメンタリーのようなリアリティを持つフィクションである。そして本書はそういった現代のホラーのルーツや2024年までの変遷について民俗学の観点から迫ったものである。
先ほど民俗学の観点という言葉を用いたが、残念ながら私に民俗学の知識なんてほとんどなく、柳田國男という名前を知っている程度だが、本書は民俗学の専門用語はあまり用いられず、仮に使われたとしてもその意味について解説がなされている。また、ネット怪談の知識がない人にも、話の中で大きく取り上げられているものや怪談のタイトルが分かるような仕組みになっておりとても読みやすかった。
本書では、オステンション(やってみた)という、肝試しなど噂の現場に実際に訪れてみる行為に対し、その逆をいく逆行的オステンションがインターネット上で行われていると述べられている。逆行的オステンションとは、特定の画像や写真に対して、人がその写真についての物語を後付けするものである。本書の中では、スレンダーマンが例として用いられていた。そして、衝撃的なことにこの逆行的オステンションが進むことで、文字がデータとして残るインターネットという媒体でありながら、本来のネット発の創作という文言が失われるという事が行われているというのだ。そして文言が失われた事でスレンダーマンのように事件も起こってしまったというのも衝撃だった。
この本では終盤に2020年代のホラーの流行についても述べられている。TikTokやYouTubeの縦型スライド動画の流行により、逆行的オステンションが行われなくなり、物語を持たない写真のみのホラーが発展している。そういった写真には不穏さや不気味さがや懐かしさなどの答えのない異質なものを味わうホラーが生まれている。それは、普段TikTokなどを使わない私としては衝撃的な事実であった。
本全体を通して、民俗学という特定の地域の風習を取り扱う学問なのにアメリカなどの他国の怪談が出てくるのはかなりグローバルなものを感じた。本書で語られているが、ネット怪談について語られている論文などは多くないという。ネット怪談においては、民俗学という観点だけでなく、グローバルな視点でも取り扱う必要があるのではないかと個人的に思った。
きさらぎ駅やくねくね、マンデラ効果や検索してはいけない言葉、バックルームなどの定番を取り扱う一方で、日本のインターネットを語る上で欠かすことのできない淫夢についても少ないながら記述がある点が個人的に好印象だ。
また、民俗学的観点からの考察だけでなく、ネットホラー史を辿れることがこの本の素晴らしい点の一つである。ネット怪談が好きな人は買って損はないと思う。また、ネット文化が大好きな身としては、こういった本が出てくれてとても嬉しいので、今後こういった本が増えて欲しい。
Posted by ブクログ
きさらぎ駅、リアル、本当に危ない場所を見つけてしまった、などから果ては近年のホラー映画や小説などまで網羅し、この30年ほどの間ネットでホラーを見てきたものなら誰もが知っていると思われる、代表的な「ネット怪談」をいくつも取上げ、その成立の過程を具に追い、オステンション/逆行的オステンションなど、民俗学的見地から解剖した1冊。取り上げる対象が多いためか1件1件のボリュームは浅めだが、「この話知ってる!」という親近感が本書の面白さを底上げしている。著者は終盤で「リミナルスペース」の台頭流行を取り上げ、「ネット怪談はもはやナラティブ(物語)を必要としなくなった」と述べており、非常に興味深い分析だと感じた。
Posted by ブクログ
懐かしいワードがいっぱい出てきてよかった、平成1桁ガチババアだからショート動画とかTikTokとか全く見ないのだけれど、そういう土壌でもあの頃と似たようなオカルトの隆盛があると知れてなんだかホッとした(?) 現代の差別意識やジェンダー観のアップデートに伴って怪談からもそういう要素が排されて(より無機質なものが面白がられて)いるの、なるほどという感じだ。
インターネット独自の文化のソースを調べるのってどんな分野であれ労力を要するが、本文で言及があった通り怪談やホラーは特に創作であっても人伝に聞いたとか転載したかのように書かれることが多いので、裏取りがマジで大変だろうな……。発刊がもう少し遅かったら都市伝説解体センターなんかも触れられていそうだ。
Posted by ブクログ
ネット怪談がどのように生まれ、広まっていくかを、民族学的視点から書いているのだが、それはともかく──
初めて聞くネット怪談を一つ一つ読むだけでも充分面白い。
「きさらぎ駅」「犬鳴村」は映画のタイトルになっているから知っていたけど、それ以外は全然知らなかった(個人的には、「おつかれさま」は、誰かに言いたくなるほど心に残った)。
昨今話題の「ある近畿地方について」や、「TRICK」「光が死んだ夏」なんかも、ネット怪談の系統、とりわけ因習系怪談の側面があると感じた(「8番出口」に関しては、異世界系)。
心霊スポットから怪村、
そして異世界系、今後はAIなど、
ネット怪談の行く末がこれからどうなっていくか、少し興味をもった。
Posted by ブクログ
こういう題材の本待ってた‼︎
巻末の索引や参考文献、URLの量が筆者の研究に対する真摯な姿勢と熱意の証。
ネット怪談は投稿者の匙加減で情報量をコントロールされたり、共同で構築され続ける性質があるなど。普段この手の怪談に触れる度に感じていたものが言語化やカテゴライズされて、なんだか新鮮な気持ちで本書の内容に向き合うこととなった。
ネット怪談の歴史を振り返る中で、忘れていたあの番組や懐かしの怪談に出会ったり、ごく最近の作品にも言及していて驚いた。ジャンルや言葉の壁すら超えていて、兎に角研究対象が幅広い。
データだから紙媒体よりも元を辿りやすいと思い込んでいたが、ネット怪談も口承と同様に変容すると聞き、納得とともに調査の困難さを垣間見た。
本書を読んでいて、ネット怪談は時代とともに特徴が変わっていくものと感じたので、これからまた誰もが見聞きしたことがあるようなビッグタイトルが新たに生まれるのかどうか、楽しみでもあり怖くもある。
Posted by ブクログ
インターネットで発現し、広がりを見せている特有の怪談・ホラーをまとめた本。参考文献のページが充実しており、このテーマを深掘りしたいと思った時の足掛かりになりそうな一冊。
Posted by ブクログ
かつて「洒落怖」を読み漁った人間として、ずっと読みたかった一冊。懐かしすぎる怪談のオンパレードに、よくぞまとめてくださった!と拍手を送りたいです。
筆者自身が1983年生まれで2ちゃんのオカルト板と共に育ってきただけあり、当時の空気感を味わった方ならではの豊かな解説に安心感を覚えました。「専ブラ」や「クソスレ」が当たり前に文中に出てくる新書、私は初めて読みました。
私自身は映像としての「怖い話」がどうにもダメで、そのくせ学級文庫に置いてあった「学校の怪談」シリーズなどは怖い怖いと言いながらよく読んでいた記憶があります(これも文中に登場して嬉しかった!)。
携帯電話を持つようになってからは、本書でいうところの「再媒介化」された怖い話まとめに夢中に。ネット掲示板特有の「たぶんネタだけど本当かもしれない」絶妙な境界線上に作られたお話を楽しんだものでした。
本書によると、2000年代によく投稿されたいわゆる「因習系怪談」は、インターネット環境の普及により舞台とされる地方のユーザーも増えたことや、似た系統の話が乱立したことで勢いをなくしていったとか。
近年は主に画像や動画で形作られる「異世界系」が人気のようで、こちらで取り上げられるバックルームやリミナルスペースは全く知らなかったので勉強になりました。でも私はやっぱりネットホラーの方に惹かれるなぁ。
しかし、かつて隆盛を誇ったオカルト板で育った若きクリエイター達により、ホラーブームは息を吹き返しているとのこと。背筋さんとか梨さんとかですよね。
私は幽霊系の怖い話は本当に苦手なのですが、それでもほんのり背筋が怖くなる話を求めてしまうのは、自分が安全地帯にいることを確認したいからなのかもしれません。……なので、見聞きした人にも災いが及ぶ系の話をうっかり踏むとヒエッとなってしまうのですが(^^;
くねくね、八尺様、コトリバコ……このあたりの単語にピンと来た方には、ぜひおすすめの一冊です!
(でも200ページの画像には心臓止まりかけました)
Posted by ブクログ
そんなんあったなのラッシュ
2chのホラー的な話のまとめを読み漁ってた時期があったから感慨深い
本著ではサラッと書かれていたが初投稿が何処なのか調査するのビビるくらい大変だったろうな
Posted by ブクログ
文字通り、ネット怪談について民俗学の視点から歴史、成り立ち、立ち位置について整理した本。
インターネット老人会の人ならば、そんなコピペあったなーと思えたり、え?これってネット怪談だったの?
と驚いたりできるニッチな内容が書かれている。そんなキャッチー?なテーマを民俗学者が真面目に解説しているのだから面白い。真面目すぎてたまに読みにくいのがちょっと辛い。
付帯効果だが、民俗学入門書として良いかも。
怪談コピペの歴史を知りたい人、民俗学者がどんな研究をしているか知りたい人におすすめ。
Posted by ブクログ
インターネットで語られる怪談を、民俗学の視点から読み解いた一冊。
きさらぎ駅やくねくねなど、一度は聞いたことのある怪談の成り立ちが詳細に解説されており、非常に読み応えがありました。
クリーピーパスタなど海外のネット怪談にも触れられており、新たな学びを得ることができましたね。
Posted by ブクログ
いわゆる「ネット怪談」、記録しておかないと消えてしまうものだなあということを再認識した。そういう巷の一つひとつの話を拾い、記録し、後世に残すことも、ひとつの学問(それが民俗学かはわからないけど)なのだなあと感じた。
村の古老に話を聞くように、インターネット老人会に話を聞く必要があるというのには笑いつつも、そうか!と膝を打った。私は当時その話を聞いてたけれど、何かの事情でいまはそのログがないということはあるだろうし。それこそが老人から受け取る伝承になってるんだ、いまは。
Posted by ブクログ
しまった!恐かった!(いや、そりゃそやろ!)
というわけで「民俗学」です
「民俗学」と言えば怪談ですよ
そして本書はネット上で生まれた怪異の数々”ネット怪談”を「民俗(民間伝承)」の一種としてとらえ、その生態系を描いています
との触れ込みなんで、まぁ考察メインでそんな恐くないと思って読み始めたんだけど…
そりゃあ紹介するわな
実際のネット怪談を紹介しながら、話進めるわな
そりゃそう
そしてどうしたって検索しちゃうよね
スマホあるもの
手を伸ばせばそこにスマホがあるもの
本書でも紹介された有名なネット怪談を挙げるので、興味ある強者は各々検索するがよい
「八尺様」「くねくね」「きさらぎ駅」「時空おっさん」「コトリバコ」「犬鳴村」「杉沢村」
短いやつをひとつ
二〇二三年四月、あるクリエイターがChatGPTに「15文字のひらがなでなにか怖いこといって」と尋ねたところ、「わたしはにんげん ここからだして」と返ってきた
どう?ゾワゾワした?
Posted by ブクログ
『リミナルスペース 新しい恐怖の美学』と共に購入し読み進めた本。ネット怪談は誰かが連綿と作り上げてきたもの。そのような話を掬い上げる民俗学と相性がいいということで作られた。きさらぎ駅、SCP財団、ジェフ・ザ・キラー、そしてリミナルスペースも取り上げられている。個人的に印象に残ったのは、フォークホラーや因習ものの流行り。これはたしかに地方を悪とするイメージをつけすぎている。いつの時代も理解しにくいものを拒否する捉え方があるなと感じます。他にも死者は書かれていましたが、精神疾患もありそうですね。
Posted by ブクログ
ネット怪談とネットホラー。私は本書を読むまで、その違いを気に掛けたことはなかった。「ネット怪談」は特定の作者への帰属が意識されず、投稿者は報告者として認識される。一方の「ネットホラー」は投稿者は作者として意識され、創作の一種として恐怖が楽しまれる。この二つは別々のものだけど、ネットホラーとして生まれたものがいつしか不特定の人々によって構築されていく中でネット怪談として認識されるようになったり、あるいはその逆もある。その話が真実であるかどうかは本質ではなく、境界も曖昧であるというのが面白いなと思った。
それにしてもネット怪談は、口承で伝わる怪談よりは収集しやすいとはいえ、リアルタイムで見ていなければ後からログを辿るのは困難な例もあったりするので、マイナーな怪談や有名な怪談でもその源流を辿るのは大変であることは想像に難くない。しかし本書ではさまざまな怪談の初出が丁寧に調べられており、素直に感嘆した。新書には珍しいくらい索引や出典もまとめられているので、本書自体が貴重な資料になるのではと思う。
Posted by ブクログ
主に2ちゃんねるで流行ったホラーの内容、広まり方についてまとめられている。世代の方は懐かしい!と思うのでは。今やあまりない、嘘を嘘と知りながらみんなでブラッシュアップしていくあの感じがよかったなあと懐古厨になってしまった。
Posted by ブクログ
えええのえ!
八尺様とか巨頭ォとかホラゲーだと思ってたら元になった話があったのか!
ただのえっちなねーちゃんと毛深い男梅かと思ってたわ!失敬失敬!
ばけたん(WARASHI)やっっっば!
「周囲に霊がいると発光し、さらに光の色によって危険度がわかる」www
やべぇ!くそほしい!!
深夜時間帯、テレビが放送休止した後に表示されるものっつったらブリキンホテルの宣伝じゃないん?
Posted by ブクログ
『ネット会談の民族学』を読んで、どのようにしてネット上の怖い話が広まっていったのかがとても分かりやすくまとめられていると感じた。作者が不明なまま別の人が話を引き継いだり、スレッドでの会話がそのまま物語として発展していくという構造はとても興味深かった。普段なんとなく読んでいるネットの怖い話にも、こうした「語りの連鎖」や人々の関わりがあるのだと知り、ネット文化の奥深さを改めて感じた。
Posted by ブクログ
多少、小難しいが、「ネットの怖い話」の知識がつく。
あと、突然、「ジェフ・ザ・キラー」の画像が載ってる箇所があるので(P200)、ページめくる時は注意!(笑
Posted by ブクログ
ネット怪談・ホラーの発生と拡散の過程を振り返ったり分析したり。確かに「きさらぎ駅」はネタがネットに初めて上がった頃から広まるまでに間があったね。インターネット老人会にも価値がある。
因習系は地方への差別が問題視されて下火になった、とか、小説投稿サイトの隆盛によってネットホラーが生まれづらくなった、という話はなるほどなぁと思ったよ
Posted by ブクログ
本作では膨大な量の「ネット怪談」あるいは「ネットホラー」に触れられており、自分が知っているものよりも、知らないもののほうが圧倒的に多かったです。自分は特にバックルームスなどの異界について触れられた章が面白かったです。
現在、「実話怪談」の怪談ブームが来ていると聞きましたが、そんな新作怪談達もいつしかネット怪談と同じように推測や考察、逆行的オステンションによって肉付けや添削をされて名作になっていくのかなと思いました。
Posted by ブクログ
ノリで借りたけど面白かった。因習系から異世界系、なるほど。2000年代に暇にあかせてサーフィンしまくっていた際に結構ネット怪談読んでたんだなと懐かしく思い出しました。出てくる話の半分くらいはうっすら覚えてる、きさらぎ駅、ことり箱、くねくね、巨頭オ、リゾートバイト、、、、懐かしかった。